
021. 認知的不協和(Cognitive Dissonance)
現状とゴールのギャップが大きければ大きいほど不満が溜まる。この状態を心理学用語で認知(的)不協和(cognitive dissonance)という。認知的不協和理論は、心理学の分野で有名。1957年にレオン・フェスティンガーが命名した。
認知的不協和を起こせば、その不満が大きければ大きいほどエネルギーが生まれる。輪ゴムの理論で説明できる。
ただし、不満だけがつのっていく状態ではまずい。使い方次第ではストレスが溜まっていくだけである。
日々の充実感と不満の平衡感覚のようなものがなければ、心が折れてしまう。
エネルギーを産むには良質なストレス(不満)が必要。すべてのストレスから逃げていたら無能な人になってしまう。一方で、やりたくないことばかりやっていては奴隷になってしまう。
そのバランス感覚が大切だなぁと思う。
現状維持は生物に埋め込まれた生存戦略だからそれをいかに克服するかが求められる。
ゲシュタルトは複数持つことができるが、一つしか維持できない。
つまり、ゴール側のゲシュタルトと現状のゲシュタルトの二つを同時に維持することはできない。よって、ゴール側のゲシュタルトを選ぶように臨場感を高めなければならない。その方法論がアファメーションである。
アファメーションをして、自己イメージを再度変えていこう。
最後に、補足的な内容。認知的不協和を利用して人に好かれる方法が解説されているメンタリストDaiGoの本があるので下記に紹介しておく。
今日も読書!!!

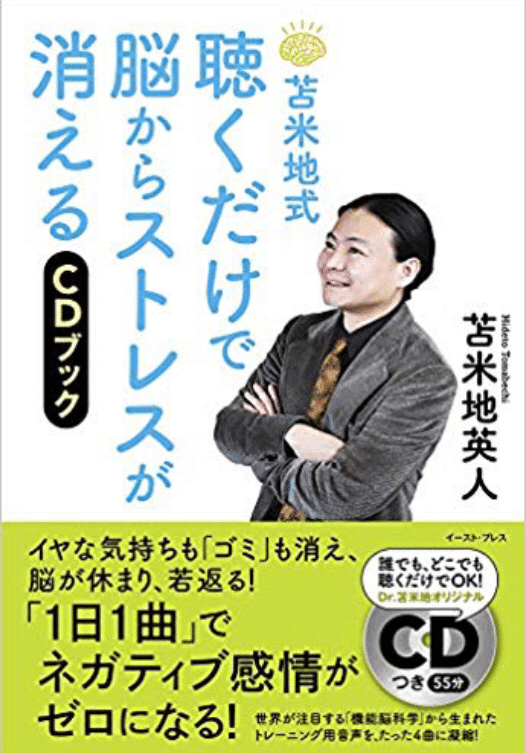


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
