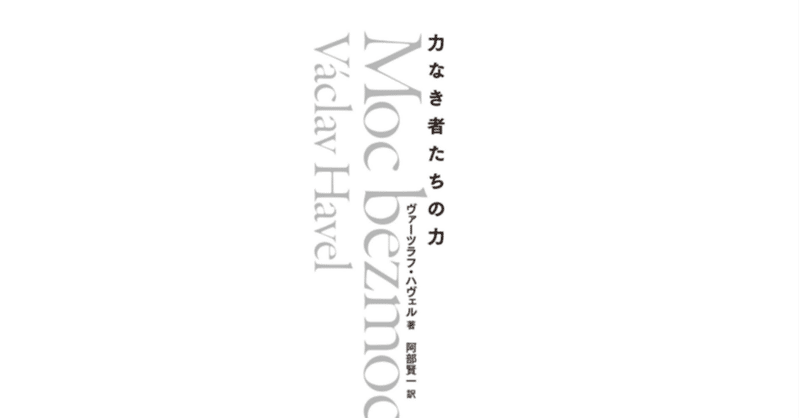
力なき者たちの力
著者 ヴァーツラフ・ハヴェル
訳 阿部 憲一
出版 人文書院 2019年8月30日 初版第1刷発行 2020年6月20日 初版第4刷発行
全体的な感想
現代では表向き当たり前となっている「個人の尊厳」や「自由」を抑圧された体制下で、信念を貫き、体制に抵抗し、回復を目指すこと、その後の政治に対して誠実であろうとした著者チェコ元大統領のヴァーツラフ・ハヴェル。
本書は、プラハの春の崩壊後1978年に、彼が一市民として書いたエッセイである。
彼の誠実さがよく表れていた内容に思える。文章は非常にストレートであり、彼の確固たる信念がにじみ出ているようであった。
劇作家らしく、文章そのものは飽きさせることなく、とても分かりやすい。また、だからこそ、体制下での言葉の持つ扇動性という恐ろしさと、それに対抗すべく市民たちの言葉のもたらす希望の光や可能性をも考えさせられた。
それと同時に、ここ数ヶ月に渡り、ハマって読んだミラン・クンデラの『笑いと忘却の書』、『存在の耐えられない軽さ』、『無意味の祝祭』でいくつか印象に残った言葉たちや、現代社会における見えにくい問題が脳裏に甦る。そして、現代における、真実に生きる、真の自由とは何なのか、再度考えさせられる。
本書を読むに至った動機
チェコ出身のフランス亡命作家、ミラン・クンデラ。彼の多くの作品は1968年の『プラハの春』前後などの旧チェコスロバキア政治情勢を背景にした人間模様が描かれている。クンデラ作品が好きになり、当時の彼が過ごした激動の時代や古くからのビザンツ帝国など含め、東欧の歴史をもう少し良く知りたいと思ったのはごく自然なことだった。ある日、プラハの春についてインターネットで調べていると、チェコの標語とビロード革命のスローガンに辿り着いた。『真実は勝つ』と『愛と真実は憎しみと虚偽を征服しなければならない』。
革命という言葉が現代の日本にいると、ピンと来ないが、中二病の俺の心を掴むには充分すぎるほどの熱いスローガンだった。
『愛と真実は憎しみと虚偽を征服しなければならない』
スローガンを提唱したのはヴァーツラフ・ハヴェルという、のちのチェコスロバキアとチェコの大統領となった、ひとりの不条理劇作家だった。
情熱的で愛によって自由を市民たちのものとして再生しようとするようなこのスローガンに惹かれて、ハヴェルのエッセイに辿り着いた。
プラハの春と一市民としてのハヴェル
現代におけるヨーロッパの代表的作家、ミラン・クンデラ。
1968年の『プラハの春』を文化面から支えようとしてきた人物でもある。
そのような行動をとってきた人物はクンデラだけではない。
当時、不条理劇作家だったヴァーツラフ・ハヴェルらもそうした人物である。
かつてはローマ帝国ともいえたビザンツ帝国が侵略主義的、帝国主義的色彩に塗り替えられ、ついには旧ソ連の影響が強まり、民族主義的な汎スラブ主義ではなく、労働者の国際主義を無理やり標榜とされたチェコスロバキア。
プラハの春を率いたのは当時のリーダー、アレクサンドル・ドゥプチェク共産党第一書記であった。ドゥプチェクは『人間の顔をした社会主義』を訴えて「自分の意見を恐れずに言えるようにすること」現代では当たり前のことを実現しようとしていた。
プラハの春が旧ソ連の軍事介入によって、鎮圧された、いわゆる『正常化』前後、ドゥプチェクは旧ソ連当時の書記長ブレジネフらに追求され、遂には旧ソ連へ連行されてしまう。
失脚させられたドゥプチェクに代わって、フサークが党第一書記となる。その後、フサークらによって「プラハの春」に参加した知識人や文化人らは厳しい弾圧下にさらされた。
そうした中で、ハヴェルは政治家へ転向し、クンデラはフランスへと亡命する。
ハヴェルはその後、何度も投獄されながらも、一貫して祖国の自由化のために活動しつづけた。旧ソ連のゴルバチョフの登場とペレストロイカにより、東ヨーロッパの共産圏諸国は大きく変わっていく。そうした気運の中、1989年11月の『ビロード革命』によって、当時のフサーク大統領は辞任に追い込まれ、ハヴェルがチェコスロバキアの大統領へとなる。
当時、日本国内では、竹下登首相が政権のトップであり、昭和天皇が崩御し、昭和というひとつの時代が終わり、平成へと変わった。1989年は遠く離れた日本でも時代が大きく変わった年とも言えよう。
クンデラ同様に、作家であったハヴェルは、表現者として様々な制約や弾圧を受けていた中で1978年、一市民としての視点からある著書を書く。
それが、『力なき者たちの力』である。
現代における全体主義を考える
序盤から「ディシデント」、「ポスト全体主義」、「自発的な動き」といったキーワードが飛び交う。ハヴェルは青果店店主の例え話を出して、読者にわかりやすくこれらを伝えようとしている。
ディシデントやポスト全体主義、自発的な動きといったキーワードを俺なりにそれらを現代に置き換えて考えてみた。
ハヴェルは、古典的独裁と当時のチェコスロバキアにおける全体主義とを「体制」と「権力」における性質で大きな差こそあれ、外側から見ると、些細な差であるとし、当時の全体主義を「ポスト全体主義」とした。
ハヴェルの言う「ディシデント」とは当時、「力のーない」人々のことであったかもしれないが、現代における「ディシデント」とはGAFAらに対して無抵抗極まりない我々ユーザーすべてが当てはまるのではないか?
これに関して、ドイツ人哲学者マルクス・ガブリエルは中島隆博との対談『全体主義の克服』(集英社新書)で革命を起こすべきだと言っている。
インターネットのために働く人々は、デジタル・プロレタリアートです。わたしが提案したのはデジタル革命が必要だということでした。デジタル生産物はあるのに、デジタル革命はありません。「シリコンバレーの魔女たち」に奪われたコントロール権を、市民は取り戻さなければならないのです。
『全体主義の克服』マルクス・ガブリエル; 中島隆博 (集英社新書)
奇妙なことに、青果店店主のように日常生活の維持と引き換えに、「真実の生を犠牲にし、イデオロギーを忖度する」というのは、あからさまな全体主義に限ったものではない。現代の日本でも同じようなことが起こっている。日本だけではなく、世界中がそういう風潮になっている。
人間の位置をめぐる惑星規模の危機は、我々の世界と同じく、西側でも進行している。異なるのは、別の社会形態、別の政治形態を有している点である。ハイデッガーは、はっきりと民主主義の危機を唱えている。西側の民主主義、つまり、伝統的な議会制民主主義が、我々よりも深遠な解決法をもたらしていることを示すものは現実には何もない。そればかりか、生が真に目指すものという点において、西側には我々の世界以上に多くの余地があり、危機は人間からより巧妙に隠れているため、人びとはより深い危機に直面している。
『力なき者たちの力』ヴァーツラフ・ハヴェル 人文書院
一見、個人の自由が保障されているようで、実は、「トレンド」に左右され、真の自由、自らが考え、選択した自由ではないことがややもするとほとんどである。「ニュースを見る」⇒Twitterのトレンドを見る、「政治家たちの考えを知る」⇒Twitterのトレンドにあがっていた、「本を読む、映画を観る」⇒Amazonなどのランキングやレビューを気にする。
トレンドに流されることなく、自分の意志で、フラットな視線で出所のきちんとしたところから情報を得ることの大切さと、それができる言論の自由、表現の自由はとても大切である。それと共に、自らよく考え抜き、コントロール権をきちんと我々ユーザーに取り戻すことが、現代の、構築されつつある監視社会のような中での、真の自由への一歩とも言えなくもない。
ポスト全体主義体制は、人間が一歩 踏み出すたびに接触してくる。もちろん、 イデオロギーという手袋 をはめて。 それゆえ、 この体制内の生は、 偽りや嘘ですべて 塗り固められている。官僚政府は人民政府と呼ばれる。労働者階級という名前の下で、労働者階級が隷属化される。人間に対する徹底的 な侮辱は、人間を完全に解放するものとしてなさ れる。情報の隔離は、情報へのアクセスと呼ばれる。権力の操作は、権力の公的な統制とされ、権力の恣意的な利用は、法規の遵守とされる。 文化を抑圧することは、文化 の発展とさ れる。 帝国主義の影響が拡大することを、抑圧されている者に対する支援と呼ぶ。表現の不自由は、自由の最高の形態とされる。選挙の茶番は、民主主義の最高の形態とされる。独自の考えを禁止することは、もっとも科学的な世界観とされる。占領は、同胞による支援 である ─ ─。 権力は みずからの嘘に囚われており、そのため、すべてを偽造しなければならない。 過去を偽造する。 現在を偽造し、未来を偽造する 。統計資料を偽造する。 全能の力などないと偽り、何でもできる警察組織などないと偽る。人権 を尊重していると偽る。誰も迫害していないと偽る。何も恐れていないと偽る。何も偽っていないと偽る。
『力なき者たちの力』ヴァーツラフ ハヴェル 人文書院
ハヴェルのポスト民主主義への問いかけ
後半、「ポスト民主主義」の本質について問いかけをするハヴェル。
「 ポスト 民主主義」の構造のヴィジョンは、いくつかの要素において、 私たちの近くにいて知っているような、グループや 独立した市民のイニシアチブ による「 ディシデント」のヴィジョンを想起させるものではないか?
(中略)
無関心な社会の真っ只中での、「 真実の生」を表現し、「 高次の責任」という感情を一新しようとするかれらの試みは、倫理 の再建が始まっている 兆候なのではないか?
『力なき者たちの力』ヴァーツラフ・ハヴェル 人文書院
正直言って、悲しい事に、無関心極まりない超個人主義社会の中で、目に見えない全体主義が始まり、また、心のない資本主義的経済によって、ハヴェルらの激動の時代よりも、彼らの目指した真の生とは程遠い現代になってきている気がしてくる。無関心という個人の自由に身を委ねた結果、他者との交わりがない現代社会の構造の事に関しては、ミシェル・ウェルベックが小説のテーマとして取り上げている。
本書を現代の今、読む価値は十分にある名著だと感じた。俺は読んでいて、終始、GAFAらによる見えざる全体主義のことが頭に過った。この現代こそポスト全体主義といって過言ではないかのように思えてくる。
見えざる全体主義、ポスト全体主義で問題提議していた人物として、ドイツ人哲学者マルクス・ガブリエルも挙げておきたい。彼の新実在論は、20世紀という過去と21世紀という現在の全体主義への批判に基づいている。単に政治的に批判するだけでは不十分で、その哲学的構造自体を把握しなければならない。すなわち、普遍に関わる問題だということだ。全体主義が想定した普遍は決して普遍的なものではなく、ある種の悪しき相対主義を許すことで、きわめて暴力的なものになったといえよう。だからこそ、我々は新しい普遍を、グローバルに、時には、哲学的概念に求め、向き合う必要がある。
※機会があったら、マルクス・ガブリエルの著書を数冊読んでみて欲しい。
また、イスラエルの歴史学者、ユヴァル・ノア・ハラリも見えざる全体主義に警鈴を鳴らしている。
本人に意識させない形で思考と行動を操作する未来です。人間の自由意思を否定する未来。
自由民主主義という大きな物語の失墜は、破壊的技術革新とも関係しています。自由経済と民主政治は人間の自由意思を根幹としているのです。
それでも私は民主主義の自己刷新能力を信じます。民主主義は自らの過ちを認め、修正できる。脆弱ですが適応力もある。 人類は物事を決定する力を手放してはならない。歴史の流れを定めるのは私たち人間です。
引用『自由の限界 世界の知性21人が問う国家と民主主義』(中公新書ラクレ)
ミラン・クンデラが著書『笑いと忘却の書』の中でこんなことを言っているのをふと思い出した。
「文明という牢獄の向こう側では魂と肉体をめちゃめちゃにする社会の偽善」(集英社文庫 p372)
旧チェコスロバキアは旧ソ連の影響を強く受けることによって魂も肉体をめちゃくちゃにされたが、現代では、無関心さと他者との関わりの極めて少ない超個人主義、そして、目には見えない全体主義によって、人間らしい温かい社会、真に生きるということが阻害されてはいないだろうか。
真に生きる、自由への道
体制によって自由を抑圧された内側から激しく抵抗しつづけたハヴェル。同じく自由という視点で、大衆社会嫌いな傾向ではあるが、自由と責任を追及しようとした人物に、俺の最も敬愛するサルトルがいる。
旧ソ連を「プラハの春」までは擁護していたサルトルだが、彼の望んだ姿だったのか、勉強不足のため、よくわからない。ハンガリー暴動やプラハの春を通して、サルトルは旧ソ連から手を引いたように見える。それまではアメリカ的帝国主義を擁護することになってしまうから、旧ソ連や共産主義を批判してはならぬというスタンスであった。
真に生きる、というのは当然ながら己の意志、選択の自由と責任を持って、生きる、すなわち、主体性を持って生きるということとも言えよう。あたかも当たり前のことのようであるが、現代ですら、「主体性」を持って物事を考え、責任を負って判断するというのは、時に、社会風潮などに流されがちな危うさを持っているのではなかろうか。
では、主体性とは一体何なのか?
サルトルは1961年ローマ講演「マルクス主義と主体性」にて、ルカーチの主体性をあらかじめ決定された過程の目撃者という役割に閉じ込める観念論を主意主義的観念論と批判する形をとりながら、主体性について述べている。
意志が自由との関係性において二次的なものであり、存在と無において、
意志に価値を大きく与えることは自由を犠牲にしてしか行えない
『存在と無』J.P.サルトル 人文書院
と結論づけており、主意主義は空虚なものであるのは自明である。
人間にとって主体性にはいくつか次元があり、主体性とはそれら次元の全体化であるとしている。
そしてそれらを認識することなく再全体化されねばならないとしている。
「社会的実在〔現実〕は、機械ではなく、機械を操り、給料をもらい、結婚し、子どもをもつ人のことです。言い換えると、人は、労働者であれブルジョワであれ、おのれの社会的存在になるべきであるということです。そして、人は、まずは主体的な仕方で、おのれの社会的存在になるべきであるということです。」
主体性とは何か? J.P.サルトル 白水社
選択の自由の中、主体性と責任を持って己の意志で判断、行動することこそが真の自由であり、真実に生きることのひとつの条件ではないかとも俺は思える。ユダヤ人哲学者ハンナ・アレントがホロコーストにおけるナチSSを鋭く洞察しているが、その中で、思考を停止させている状態こそ凡庸な悪を生み出すと主張している。
現代ではどうだろう。情報が氾濫し、GAFAらのマイニングやトレンドに乗っかり、自身の意見の主張とすり替えてしまってはならない、とここ最近思うのだが、うっかりしていると、主体性なき意見を持ちかねない危うさを俺自身も持っている。
また、サルトルは未完の大作、著書『自由への道』でこんなことを言っている。
おれの手、このほんのわずかな距離が事物をおれに啓示し、永遠にそれから引き離している。おれは何者でもない、おれは何も持っていない。光と同じくらい、世界と密接につながっているが、それでも光と同じように、そこから追放され、石や水の表面を滑っていく、決してひとつとしておれにひっかかることも、おれを埋めることもない。外部だ。外部。世界の外、過去の外、自分の外、自由とはこの追放のことだ、おれは自由の刑に処せられている
『自由への道』J.P.サルトル サルトル全集 人文書院
これは、サルトルの思想をよく反映した第4部でのシーンだ。サルトルは1980年に亡くなり、1989年のチェコスロバキアにおける「ビロード革命」を見ることはなかった。
彼がゴルバチョフによるペレストロイカ、旧ソ連崩壊と1980年後半の東欧における共産圏諸国の大きな方向転換を見ていたら、また、現代における大衆社会の見えざる全体主義によって、ややもすると自分の意志による自由が無意識のうちに奪われかねない状況に対し、どう思うのだろうか。
おわりに
当初、これまで読んできた作家クンデラのいくつかの著書を引用したり、そこから本書を探ってみようと考えていたが、やはり、俺はサルトルが好きなのだろう。結局は後半、サルトルの著書を読み返していた。
すこし時間をおいて、ハヴェルの本書をサルトルとは切り離して、クンデラの作品からもう少し当時の歴史を探ってみたり、ハヴェルの作品、ドゥプチェクの自伝などをよく読んでそれらをベースにもう一度本書を考えてみたいと思えた。
ヴァーツラフ・ハヴェル 略歴
1936年 プラハの名家実業家の息子として生まれる
1948年 共産主義体制に全財産を欧州されたため、勉学を止めて働き始める
プラハのカフェで働きながら、文学の土台を習得する
1957年ー1959年 兵役
除隊後、演劇批評活動
1963年 『ガーデン・パーティ』
1965年 『通達』
1967年 『集中の妨げられた可能性』
1968年以降
プラハの春を「正常化」によって潰された時代、反体制運動の指導者として活躍。
1977年 「憲章77」を起草する。以降、幾度となく逮捕/投獄される。
1989年 反体制勢力を結集した「市民フォーラム」を結成、共産党政権を打破(ビロード革命)
1989年 12月チェコスロバキア最後の大統領に選出される
1993年 チェコスロバキア解体後、1月にチェコ初代大統領に就任
1998年 再選
2003年 任期満了に伴い退任
2011年 12月18日 75歳にて生涯を閉じる
Wikipediaより引用
本書以外の参考文献
『ビザンツとスラブ』井上浩一、栗生沢猛夫 中公文庫
『証言 プラハの春』アレクサンデル・ドプチェク 岩波書店
『民主主義とはなにか』バートランド・ラッセル 理想社
『主体性とは何か』J.P.サルトル 白水社
『自由への道』J.P.サルトル サルトル全集 人文書院
『責任と判断』ハンナ・アーレント ちくま学芸文庫
『新実存主義』マルクス・ガブリエル 岩波新書
『全体主義の克服』マルクス・ガブリエル/中島隆博 集英社新書
『自由の限界 世界の知性21人が問う国家と民主主義』エマニュエル・トッド、マルクス・ガブリエル、ジャック・アタリ、ユヴァル・ノア・ハラリら 中公新書ラクレ
『世界の多様性 家族構造と近代性』エマニュエル・トッド 藤原書房
『冗談』ミラン・クンデラ 岩波文庫
『笑いと忘却の書』ミラン・クンデラ 集英社文庫
『存在の耐えられない軽さ』ミラン・クンデラ 河出書房新社
『セロトニン』ミシェル・ウェルベック
いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。
