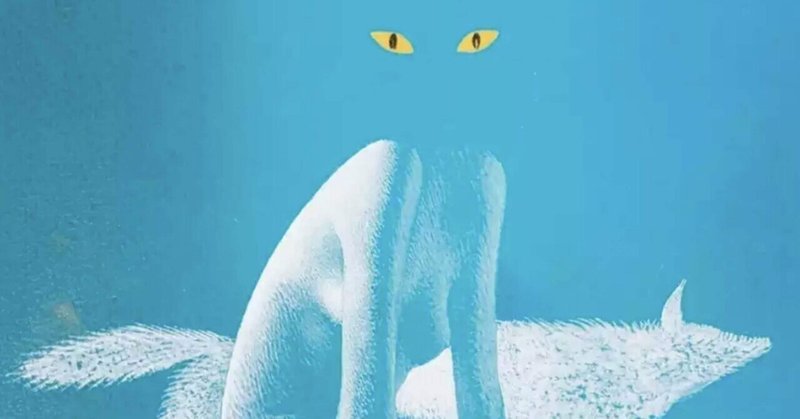
好き嫌いについての思索 1
人に向かう/向けられる「好き嫌い」とは、まず、偏見の一つの形態ではなかろうか。
粗削りながら書き起こしてみると
「主観的に判断あるいは断定する」偏った知覚の状態が、意識を介してほぼ反射的に、他者に向かって起こされる。
それに対してさらに、私たちが同調したり拒絶したりする反応が起こる。
それが、好き嫌いとして意識に上ってあらわれるのではと思った。
容姿、嗜好、価値観、性質/性格、物言い、所作、習慣、行動等々において、「私」が「主観的に」見たり感じたりする。
主観的に。事実とされる情報からだとしても、その情報をどのように受け止めるのかは「私」である。
例
遅い → のろい 鈍い → 鈍感、無神経
早い → せっかち、落ち着きない
冷静 → 冷たい
大らか → おおざっぱ、雑
清潔、優しい、気さく、懐っこい
親切、切れ者、センスいい
汚い、しつこい、ださい
いじわる、きつい、偉そう
ずるい、大げさ、話聞いてない
…
これらの反応に気づくとき、気づいたままその反応を認め続けるのは不快なので、心が「とりつくろう何か」を作ったり、意識的・無意識に関わらず「そう感じていないように」振舞うこともあれば、
何らかの理由づけをして、その反応を妥当なものと「私」が決めて、その妥当性に満足し、好き嫌いの感情をさらに増幅させることもよくある。
そのようにそれらを覆ったり、そこから逃げようとすること、反対に助長させることのどちらからでも、矛盾が生まれる。
それらは、反応が起きたときの自然のままでないから。
そしてこの矛盾によって、葛藤が発生するのではないだろうか。
一方で社会では個人的な感情をとりつくろわず開放しっぱなしで集団の中にいるのは困難なので、社会性というものが生まれたのかもしれない。
人間が集団で何かを為す、組織が機能するために、この社会性は当然の条件のように要求されてきた。
道徳観や倫理観は、社会性より後でできたのではないだろうか。社会性は狩猟や農耕の時代に、必然的に生じていただろうけど、道徳や倫理は、人間の精神の領域を人間自身が発見して以降の時代から、発達していったと想像する。
社会性、道徳、倫理などが混ざり合って通俗化したもののなかに、礼儀や社交性、愛想などが発達していったのだろうか?
ここらへんは文化とも関わるだろうし、思索の主題から離れるのでここまでとします。
続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
