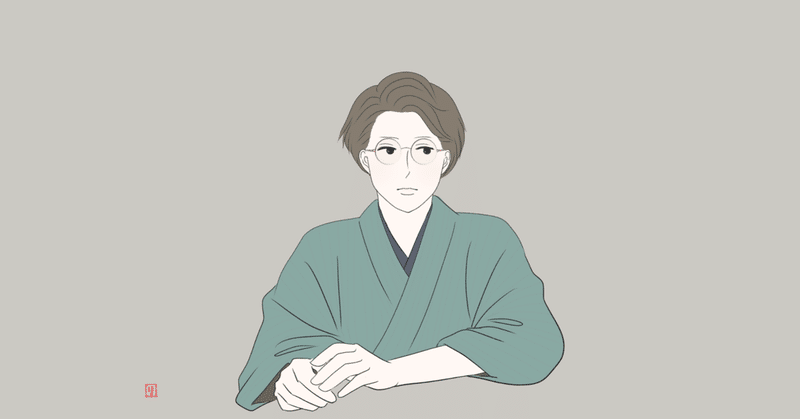
#RTした人の小説を読みに行く をやってみた【33作目〜37作目】
【33作目】盛田雄介『サイドステップストーリー』 評:タイムリープのリアリズム
タイムリープを根幹に据えた物語は多く、特に近年の日本ではノベルゲームの発達とともにその文脈は大きく更新されたのではないか、とぼくはおもいます。そこで重要になるのが「誰かの死を防ぐために世界をやりなおす」という強いフィクションの想像力です。本作『サイドステップストーリー』もまた、その文脈を踏襲したものだと読みました。
たとえばkey『CLANNAD』は、プレイヤーと登場人物がおかれたシチュエーションをつなぎ、「繰り返しプレイする」ことに意味づけがなされています。そしてニトロプラス『STEINS;GATE』でも同様に「ヒロインの死」を回避すべく、作中で科学技術として扱われるタイムマシンを使用し何度も世界をやり直します。また、ニトロプラスは『君と彼女と彼女の恋。』でメタ的な手法を用いてプレイヤーによる「都合の良い反復」を否定する野心的な試みを行なうなど、「ループができてしまうこと」に対して批判的なスタンスをとることにより、「一回性の生」ともいうべき尊さへ訴求する制作も行なっています。
別の方への批評でも行いましたが、メディアが違えば情報の次元が異なります。2000年代以降、日本ではノベルゲーム作品のアニメ化が大量に行われましたが、ひとつなぎの12〜26話程度の構成のなか、ノベルゲームが持つ多世界的な世界描像を余すことなく示すのは不可能です。ほとんどの場合、特定のエンディングへむかう物語がアニメ版として選びとられるなか、「繰り返しの生」が見事に12話の物語で表現されたアニメ作品がありました。シャフト制作の『魔法少女まどか☆マギカ』(以下まどマギ)です。
まどマギでは、時間を操る能力を持つほむらが、主人公であるまどかの現在進行形の記憶にはない世界を何度も生きている。ほむらは時間を何度も戻ることで、世界のだれとも一致しない時間を生き、そのなかでまどかへの想いを育む。繰り返すことで得られる特有の質感を、まどかへの想いの堆積がもたらす世界構造の変化として処理することで、「世界を何度もやりなおす」という質感をひとつなぎのテレビアニメという媒体で表現することに成功しました。
本作で重要になるのは、美樹にこの質感をどれだけ持たすことができるかという点につきるでしょう。三部構成で、最初は歩視点、次に美樹視点、そして最後に三人称と語りを変えていますが、これはあまり良い手法とはいえなかった気がします。「繰り返される世界をそのまま書くこと」と「世界を繰り返している質感を与えること」は似て非なるものです。この短い小説のなかに3つも視点を入れてしまうのはそれぞれの内容が薄くなるだけでなく、悪い意味で視界が開けすぎてしまう。こうなると「質感」にとってもっとも重要というべきカタルシスが損なわれているようにおもいました。
しかし「じゃあ三人称で全部かけばいいのか?」とか「歩視点に限定して書けばいいのか?」とか、そういう話は表層的な問題でしかないです。解決方法は表現が自由である限りそれこそ無限にあるとおもいます。それでもひとついうとしたら、「世界の繰り返し」を書くならば、その繰り返しを容易に描出できないような「制限」を加えた設定で書いてみることをオススメします。その「制限」を乗り越えてなおも「時間が繰り返されている」という質感が得られれば、それはその世界におけるリアリティに他ならないはずです。
【34作目】葵すもも『君との恋愛に占める相性の割合』 評:ふたりの恋愛を阻むもの
ビッグデータということばが景気良く使われる昨今ではありますが、大量のデータを対象に力づくで演算を進めていけば一定の成果が挙げられるだろうことはかなり前から定説ではありました。しかしながら、それを実現できるだけの計算資源がないまま数十年の時間が経ち、最近になってようやく理論に対して技術が追いついてきた…という背景があります。
「マッチング」ということばは今やあらゆるビジネスシーンにおいて広く使われるようになり、需要と供給が合致する組み合わせを楽に作れる環境をつくり、市場を最適化することが現在のイノベーションの定跡といえるかもしれません。
マッチングアプリは、まさにそのひとつの例であり、「マッチング」という概念のもっとも根源的にあるものとさえいえるでしょう。
本作『君との恋愛に占める相性の割合』は、マッチングアプリで「ミスマッチ率」なるものが導入され、そして社会的にその信頼性が広く理解されている世界が舞台となっています。主人公とヒロインのあいだには「ミスマッチ率100%」という壁がたちはだかり、それを乗り越える恋愛小説という構成をとっているのですが、作品の世界とふたりの恋愛の「壁」をつくるにしても重要であるはずの「ミスマッチ率」のディテールがまったく説明されていないのは科学技術をベースとした作品作りとしてはさすがに厳しいのではないか、と感じました。
たしかに実在のマッチングアプリには「マッチング率」に似たようなものが設定されています。それは趣味や休日の過ごし方など、提示されるいくつかの項目のアンケートに答えることでユーザーを特徴化し、他のユーザーと「どれくらい近いか」の重み計算によって算出されています。ただ、それは性格診断とかそのレベルでしかない(つまり「娯楽」の域をでない)ものであり、作品世界中にあるような「親が高いマッチング率の異性を結婚相手としてすすめる」レベルの信頼性を持つにはいたっていません。つまり、この小説が想定している社会においての「ミスマッチ率」は、オーウェル『1984』ぐらいのレベルの管理社会が実現された世界でなければちょっと説明がつかないようにかんじます。そのレベルでミスマッチング率を計算できるならば、かなりのディテールで個人の情報を明け渡さないといけないだろうはず。そのわりに、「顔が好みだったから」という恋愛において最もありがちな動機があるにもかかわらず「ミスマッチング率100%」という結果が出るのはかなり不可解だと、素朴におもいました。
こうしたことは、この作品がもっとも重視している「二人の関係を否定するシステムとの戦い」としての恋愛をまったく読んでいないように思われるかもしれませんが、決してそうではないとぼくは考えます。起承転結を大事にするタイプの小説であれば、「ふたりの恋愛を阻むもの」の巨大さはかなり具体的に描く必要があります。どんな障壁を乗り越えなければならないのか、それはどんな不可能をもたらし、どのような手法でならば乗り越えられるのか。その徹底した具体性が、描かれる恋愛のリアリズムとなります。この小説は理想化された恋愛はあっても、恋愛のリアリズムが存在していないのが大きな問題に思えます。
また、マッチングアプリなんですけれど、多くの男性ユーザーは「イケメン風の自撮り」と「いい感じに笑えるファーストコンタクトのメッセージ力」がなければまず会話をはじめることができない一方で、女性は男性からの(卑猥なものを含む)メッセージが毎日大量に投げ込まれてくる非対称があります。ミスマッチ率0%という数字が社会的に信頼にたるものだとしたら、あらゆる手を使っても会話などそもそも始まらないのではないか…とおもうのですが、相手がどんな人間かを知る前にこの障壁を乗り越える手段があるとするならば、それはかなり大きな小説になるとおもいます。
【35作目】藤宮南月『愛なんて知らない』 評:恋愛のエコシステムとその「生きづらさ」
http://hypergraphia.vivit-official.com/novel/love/
先の葵すももさん『君との恋愛に占める相性の割合』にひきつづき、恋愛マッチングアプリを題材とした作品のため、引き続き取り上げさせていただきました。
ひとが出会うための手段が多様化し、かつ出会いのニーズに対する供給方法が発明されることにより、「恋愛」はシステマティックに市場化されるようになったとおもいます。「1(わたし)対1(あなた)」の恋愛から「1(わたし)対多数(異性一般)」の恋愛のような構造がうまれ、恋愛そのものを最適化するような行動をユーザーそれぞれが自発的にとることで、そこにはこれまでになかった(あるいは顕在化されてこなかった)エコシステムが現れました。それは「恋愛工学」と呼ばれることもあります。
とはいえ、ひとが出会いを求める動機は細かく細分化されます。恋愛を求めなくても「承認されたい」「性的な関係を持ちたい」「暇つぶしの相手が欲しい」など様々にあり、共通しているのは「相手」が必要だということ。「欲望を最適化する」ことは「出会い数」で定量化され、それはじぶんの欲望がどれだけ満たされたかを自身で査定する指標にもなります。より視野を広げるとTwitterのフォロワー数にしかり、小説投稿サイトのレビュー数にしかり、根本的にはおなじ構造を持っているとさえいえます。
本作『愛なんて知らない』はそうしたエコシステムに依存しながらも、そのエコシステムのなかで自由に呼吸できないでいる閉塞感がよく書かれていると感じ、特に前半部はおもしろく読みました。特に良いとおもったのは2点。まずは書き出しです。
渋谷が嫌いだ。
昔、ティンダーでマッチングした男と、渋谷のハチ公前で待ち合わせをしたが、連絡もなしにドタキャンをされた。それだけではない。渋谷に行くたびに雨が降り、そのたびに傘が壊れる。ヒールの底が抜けたこともあった。
この短い文章は、前述のエコシステムの所在が具体的な感触をおぼえました。「ティンダーでマッチした」という実在の固有名詞とアプリ内用語を生活感を与えつつ提示し、かつその後に続くのはティンダーや恋愛、そして表面上の嫌悪の対象とされる「渋谷」からも直結しないエピソードがさりげなく配置されています。論理を経由せず具体的な事象を並べ、それにより語り手が置かれる閉塞感と足掻きが文章表現として馴染んでいるとおもいました。
そしてもう1点はこの小説でもっともフィクションが込められている「不老不死の男」です。この小説の大枠はマッチングアプリによって異性からの承認欲求を求めつつも満たせない、そしてそうした生活に対して焦りと自己懐疑を抱く「あたし」による生活に根ざした語りで構成されていますが、その重心をズラすものとして「不老不死」や「人魚の肉」はちょうど良いアクセントになっています。現実から遠い位置にある寓話的なエピソードがカジュアルな会話のなかに挿入されることにより、恋愛工学的なシステムの閉塞感に風穴をあける想像力として機能しています。これが語り手の感慨に大きなカタルシスを与えることになり、小説としてのまとまりがよくなっています。
ただ、序盤の良さに比べ、自称「不老不死」の男・紫からの告白を受けたあとは文章の密度がガクンと下がった印象もありました。断章的なエピソードを重ねるならば厚みが足らず、「あたし」をとりまくエコシステムの巨大さや重さを浮き上がらせるにはいたっていなかったように感じます。作中ではティンダーとペアーズが取り上げられていますが、それぞれのアプリの機能的差異のディテール、あるいはタップル、ハッピーメール、ワクワクメール、TwitterなどのSNS、裏LINEともいわれる「カカオトーク」のやりとりなど、同じ系列のシステムでありながら微妙にことなる空間も同様の断章としてさらに積み重ねることができたなら、物語の最後で生じるカタルシスはより大きなものになったとおもいます。
もちろん、「短編だからこその良さ」というのはあり、限られた字数によって扱える世界の規模も変わるでしょう。しかし、だからこそ短編でより大きな世界を扱うための技巧について、腰を据えて考えてもらいたいと感じました。そして同時に、せっかく「不老不死」という寓話性の高いモチーフを使うなら、話をきれいに着地させようとせずもっと荒唐無稽な方向に向かっても良い気がしました。
【36作目】夕月檸檬『赤い星の住民になった』 評:どこまで説明が必要か?
うろ覚えで恐縮なのですが、たしかSFショートショートの名手・星新一が「短編で『世界一の美女』と書けばそれでもうその女性は『世界一の美女』になる」というようなことを言っていたという話を聞いたことがあります。そしてそれは限られた文章のなかでフィクションの想像力を顕在化させるために必要な技術であり、説明をすっ飛ばして「ありえない状況」を素早くつくりあげることができれば、その小説のなかでなければぜったいに感じたり考えたりできないことを描出できます。その恒例としてぼくはよくカフカの『変身』の冒頭を取り上げます(ほかの方への評でも何度か言及した記憶があります)。
本作『赤い星の住民になった。』はアンタレスへの移住を前提としながら、現代の実在のメディアへの言及、そしてほかの記事へのリンクを使うなど、WEBメディアの特性を活かしながら現実と虚構をハイパーリンクを用いて混在させ、独自のリアリズムを作り上げようとする意思が見られます。言い方は悪くなりますが、「ただの身辺雑記に終わりそうなこと」を公開メディアや実在するサービスや文章と接続させることで、小説たる創意を保っていると読みました。
ただ、本作が自立してフィクション作品であるための想像力の強度については疑問が残ります。それは「アンタレスAへの移住」なのですが、これはたとえば「私は火星に移住した」と書くのとは異なる問題が生じるとぼくはおもいます。例に挙げた火星は惑星ではありますが、自ら発光するアンタレスは恒星です。「恒星に住む」となると現在ぼくらが生活をする地球とは根本的な性質も大きく異なるため、冒頭で挙げた星新一のことばの射程外にあることを考える必要があるのではないか…とおもいました。変わったのは星か、それとも人類か?
とりわけ特異な状況下で日常的なものをとりあげる「一人語り」の作品を書く上では、たとえ小さなものであっても、現実の感覚とその世界独自の感覚との差異を浮き上がらせなければ成立しない、言い方を変えれば「差異が認知されなければ土台としているフィクションの想像力が活かされない」ようにおもわれます。この小説では、物理的距離や言語的差異などひとを隔てるあらゆる距離が解体されるようなフラットな語りを志向していると認めつつ、その距離に具体的な手触りが得られないのがもったいないところです。解体されるべき距離の像はどんなものなのか、じっくり時間を割いて考え、作り込んでもらいたいと感じました。
【37作目】Takeman『死がふたりを』 評:アンバランスさの魅力
本作を読んで思い出したのは『ガリバー旅行記』の以下の部分でした。ちょうど手元に角川文庫版がありましたので引用します。
政党間の抗争が激化した場合についても、この医師はすばらしい融和政策を編み出している。ざっと説明すると、まずそれぞれの党から主だったもの百人ずつを選び出す。そして、頭の大きさが似ているものどうしを両党からひとひずつ選び、全員をふたり組に分ける。そして、腕のいい外科医をふたり連れてきて、各組の党員の後頭部を、ちょうど脳みそも二等分になるよう同時にのこぎりで切らせ、切りとった後頭部を交換して相手の頭にくっつけてやるのだ。たしかに精密さを要求される手術ではあるが、みごと成功の暁には、めざましい効きめが約束されているのだという。医師の解説によると、この半分ずつの脳みそが、争点となっているさまざまな問題について頭蓋骨の中で議論を重ね、まもなくお互いの合意にいたるばかりか、以後は節度ある、中庸を踏み外さない思考ができるようになるのだそうだ。
––––ジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』
まさにこれは本作の根幹にある「脳を半分移植する」という話そのものです。ひとりの身体にふたりの人間(ないし意識)を同居させるというところまでガリバー旅行記も本作も同じですが、ちがうのはその後。ガリバー旅行記は「A+B→C」であるのに対し、本作は「A+B→A+B」。ふたりの意識がそれぞれ独立に共存しているというアイデアが参照されています。
脳摘出についてぼくにまったく知識がなかったので少しですが調べてみましたが、「脳が半分なくてもそうとはわからないように生活できる」という事例があったのにはおどろきました。
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/11/post-13447.php
作中の大部分を脳摘出に関する説明が割かれているのですが、一部ぼくが知っていることもあり(記憶は脳の特定の部分が担うのではなく、全体で分散的に担うとか)、おそらくはかなり事実ベースで作られているのではないかとおもいました。作中の説明でこんな胡散臭くて前例もなければ法的に余裕でアウト、人権的に大きな問題を抱えている手術を受けようとはとうていおもえませんが、それでもこの「うんちく」の部分は大変おもしろく、かなり興味深く読みました。
この小説の良さは、このリサーチというか事例をコラージュする手つきにあったとおもいます。ただ、設定の説明に大きな魅力を持ちながらも、ストーリーがベタなだけじゃなくめちゃめちゃ浅いのは頭を抱えたくなるレベルです。最初のシーンから、物語を進めるシーンの切り替え、描写のディテール、脳移植が行われている社会全体を俯瞰できる視点の挿入、そしてなにより肝心の「ふたりの意識が同居する身体」を持ってからの起こるできごと、ラスト––––あえていうと、そのどれをとっても0点にちかいくらいホントに全然ダメで、もうまったく書けていない。それでもそのダメさをチャラにする…とまではいきませんが、それなりにリカバリーできるほど脳摘出の説明をしているところだけ異様におもしろい。このアンバランスさがぼくにとっては好感でした。こういうアンバランスなやつが読みたかった!というよろこびがありました。
たぶん、この小説からいっそ物語要素を剥ぎ取ってしまって、脳摘出・脳移植についての虚実入り乱れた研究・ニュースを徹底的にコラージュするような(動物実験やら臨床研究やらそういうものを扱えばエピソードは無限に湧いて出てくるはず)血も涙もない小説を書けばめちゃめちゃ傑作になる気がしました。そういうアンチロマン作品はお好きじゃないかも……とはおもうのですが、特定の部分への執着心を昇華できる作風が見つかれば大きく化ける気がしました。たとえばこの評の冒頭で挙げた『ガリバー旅行記』の引用みたいなことだけで原稿用紙100枚、200枚……と書ければ、長所が活かされると。機会があればまた読みたいです。
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。
