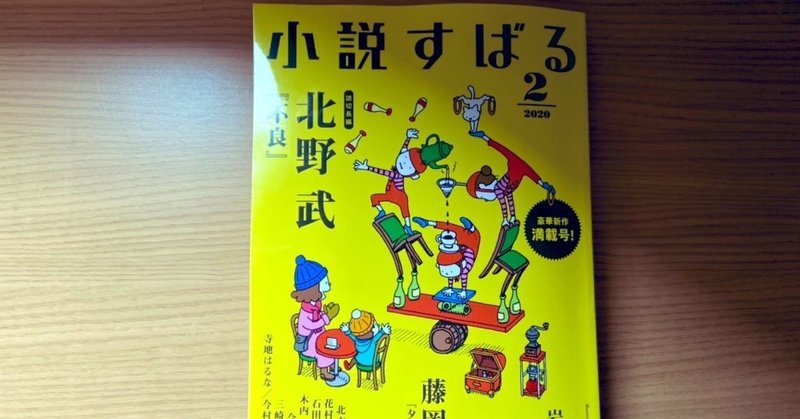
「黒い森見登美彦」としての佐川恭一/名もなき男たちの肖像
※はてなブログを閉鎖したため、こちらに転載します。ちなみに小説すばる2020年2月号に佐川恭一の短編『スターライトパレスパート2にて』と、わたくし大滝瓶太のエッセイ『佐川恭一に近づく女性編集者について語るとき我々の語ること』が掲載されています。どちらもひどめなパロディ(笑)なのに掲載してくださる寛大な編集部には感謝してもしきれません。
秋ごろだったか、かねてから仲良くしていた小説を書く友人たちが偶然東京で集まれる日があった。知人の結婚式に出席したのちに合流した佐川恭一(もんもん文学賞受賞)はそのときもうすでにいい感じに酔っ払っていて、ほぼ文章でしかかれの存在を認知していなかった友人たちは「実在したんですね!」と歓喜の声をあげた──
あたたかく迎え入れられた佐川恭一は一人ひとりに挨拶したのち、「大先生」と崇拝さえする参加者のうち最年少のK(文藝賞最終候補)に握手を求め、
「おれめっちゃK大先生の小説が好きで、笑いでゆうたらぜったい勝てへんと思ってるんですわ!」
と賛辞を送り、そしてKの勤務先を確認すると、
「そこにな、おれの高校(洛南高校)の同級生の◯◯って奴がおって、そいつ京大やってんけど同志社落ちてんやんか。そんで散々みんなで『同志社落ちた』ってイジり倒してたんよ」
という作品とかれのペルソナ認証が一瞬で可能なエピソードトークを繰り広げていた。その後、また別の友人M(すばる文学賞最終候補)にグイグイ絡んでいくと、
「関西弁が強い」
とやや距離を置かれていた。
そんなこんなで一部初対面でありながらも同窓会のカラーを強く帯びた会合は終始たのしくおわり、ぼくは宿泊先である荒川区町屋で欠席していたR(1年後に芥川賞受賞)と落ち合う。
「きょう佐川さんも来てたんだね」
というかれに上記のような一部始終を伝えると、
「やれやれだね~」
とふたりで笑った。
そう、佐川恭一の作品群について、この「やれやれ」がなんとなくつきまとっていた。読むとたしかにおもしろいんだけど、続けざまに読んでいくとその感覚は「はいはいおもしろいおもしろい」みたいな感じに変わってゆく。
かつて佐川恭一とは共に同人誌を使った経験があり、そのときに文学を学問として専攻する友人Sに解説をお願いしたのだが、佐川作品に対してはその実力を認めながらもどこか古臭い「ありきたりな」筋書きに対してやや否定的な評価を下していた。
この「古臭さ」については後述するとして、しかしそれでもぼく(ら)は、ときどき思い出したかのように佐川作品を求める傾向はあった。具体的には年に1回くらいである。
しばらくしてある友人とちょっとした合評をやろうという流れになった。
そこで佐川恭一の作品『受賞第一作』を題材にすることにしたのだが、見知った間柄ばかりだとあらたに得るものはなかろうという話になり、ぼくは当時親交を深めつつあった樋口恭介(ハヤカワSFコンテスト受賞)に声をかけた。ありがたいことに、樋口はこの申し出を快諾してくれた。
佐川恭一の了承を得て、その「怪文書」を樋口へ転送すると、すぐさまかれはその作品を読み始めた。当初、
「文学かぶれの学生のヌーヴォーロマンの真似事のような感じがある」
「リーダビリティが低いものの、エピソードやキャラクター、文章はおもしろい」
など読みながら気づいたことを逐一TwitterのDMでぼくに知らせてくれたかれであったが、まもなくDMは途絶えた。それからおよそ2時間の空白を経て、
「感動しました。かれは天才です」
「かれの作品をもっと読みたいのですが、どこで読めますか?」
というDMを受け取った。その後われわれはSkypeで議論を行ったのだが、やはりおもしろさを認めつつもどこか「やれやれ」といった辟易を抱いていたぼくらに対し、樋口は「ベタ」ともいえる展開にこそ強いエンターテイメント性があるのだと主張した。熱弁を振るうかれにぼくらは、「佐川作品はやはり読むひとが読めばきちんと評価されるものなのだ」という今更感はあるものの、当時としては新鮮な意見を得たのだった。
個人的にはそれ以上に、ひとりの読者が特定の作家に強烈な熱意で入れ込むという過程をすべて見れたこの「事件」は、とても希望的なものだった。柄にもないことをいえば、「価値」としての具体的な定義づけが困難な小説というものにおいて、このように「心が動かされる」瞬間に立ち会えることは、このさきも長く小説を信じていくことに不可欠なものだ。
「黒い森見登美彦」として
以上のような顛末を経てTwitterのTLで「佐川恭一」が頻出するようになったが、佐川恭一が「知る人ぞ知る作家」となったのはやはり樋口恭介による功績が大きい。かれの熱烈な佐川作品の紹介により、佐川はぼくらの仲間内や小説投稿サイトのユーザーを超えたひとびとにも認知されるようになり、「小説すばる」でのエッセイ連載を得るまでに活動の幅を広げた。
佐川恭一はこの連載で童貞やニンフ的な女性のポートレートをつくりあげるような作風を展開しているが、これは佐川の名を一部に強く印象付けることとなった短編集『サークルクラッシャー麻紀』の延長線上に位置づけることができるだろう。
※破滅派から出ている佐川恭一の電子書籍はKindle Unlimitedで読めます。
『サークルクラッシャー麻紀』は京都大学を舞台とした自己顕示欲と性愛が渦巻く混沌を、フェミニズムが高まりつつある昨今の潮流に逆らった、コンプライアンスなどおかまいなしの過激な下ネタと偏見で作られたほとんど狂気じみたユーモアで埋め尽くされた作品である。ただ、そのユーモアには不思議と「暗さ」がなく、むしろ「底抜けの明るさ」が宿っており、この明るさが多くの読者を惹きつけているのではないだろうか。
この短編集に収録された作品や最新作『童Q正伝』では、京都大学内の小規模コミュニティに所属する奥手な男性が、性的ないざこざに巻き込まれるなか大きな(しかし定型的な)人格変貌を遂げるという筋書きがフォーマットになっている。
佐川作品の強力なペルソナとして「京都大学」という記号がある。これは「偏屈な分析力と女性に対する免疫の低さ」として象徴化され、この点において森見登美彦を想起させるキャラクターが多数配置される。
しかし、佐川作品は森見登美彦を想起させるといっても、森見登美彦とはまったく似ていない。どう似ていないのかを説明するのはひどく面倒なので実際に読めばわかるので各自勝手に読んでもらいたい。ひとことだけ言っておけば、森見登美彦は「ちんこ」も「まんこ」も「フェラチオ」も言わないし、「童貞のまま平成の30年を通過した人間を『ふなき』と名付ける」なんてことはしないのである。
※これもKindle Unlimitedで読めます。
名前を与えられない男たち
佐川作品における「京大生」は上記よりもさらに細分化された構造を持つ。厳密には、「京都大学に入学する経緯」が登場人物のペルソナを強く規定しているのである。
佐川作品の特徴のひとつに、男性の登場人物のほとんどは名前が与えられない。名前を与えられない男たちは「洛南」、「東大寺」、「灘」といった出身高校や、「一次通過」や「三次通過」といった文学賞の戦績がそのまま人物の固有名詞として採用され、その偏差値や実績に基づくヒエラルキーとして男たちは作品内に配置され、また、「男子校」と「共学校」のあいだにも恋愛経験の有無といった階層化が施されている。
一見して人物造形としてはかなり解像度が粗いようにも感じられるのだが、強いステレオタイプを持って多数登場する名もなき男たちがコミュニティを形成することによって小説は戯曲の様相を帯び、「個」ではなく「群」としての運動が過剰に表面化しているのである。
三島由紀夫と佐川恭一
上記のような階層化の手つきについての議論を深めるにあたって参考になるのが佐川恭一がどのような作品の影響下にあるかということである。
実はそれについて、ぼくはかれと初めてあったときちらっと聞いたことがある。好きな作家を尋ねるとかれは、
「ぼ、ぼきはですね!三島ですね。三島由紀夫」(※意訳)
と答えた。なかでもかれは『金閣寺』の影響を大きく受けているとのことで、この作品について佐川は「老母で童貞を捨て、そのことを武勇伝にして童貞の友人をめっちゃマウントする」というところに痺れたといった。
ぼく自身は三島の良い読者ではなかったのだが、この証言を参考に佐川作品を読み進めていくとこの「経験による変貌」と「童貞マウント」が構造の骨格をなしているのがわかる。しかし、佐川本人は件のシーンを「ギャグとして読んだ」という訳ではない。一般的な美意識から距離をおいた、側から見れば醜悪とさえ映りうる情景に固有の耽美を感じとっていたようだ。
ここからはぼくの推測になるが、経験によって一般的な美意識から離脱し、個人と他者の差異に生じる強い自己肯定を得るという局所的な物語にかれは美意識を抱いている。そしてその美が顕在化するのが「マウント」により生じる構造だ。
耽美的経験の前後の間には「物語」というトンネルが存在し、そのトンネルの出口に立つ者がトンネルの入り口に立つ者へと声をかける。ラベリングによりなされた人格造形は、自己と他者の関係性を解体・再構築する機能を果たしており、名もなき男たちは小説的存在の次元に置いてそれぞれのアイデンティティを持ちながらも「京大生」という同一性を持っている。「京大生」とは他者であり、「私」であるのだ。佐川作品には三島のような流麗な情景描写は排除され、耽美的経験が怒涛のごとく押し寄せる。これはかれの三島の読み方が反映された実作態度であるだろう。
佐川は三島以外にも昭和の名作におけるヒューマニズム的潮流を汲んだ作家である。しかしそれゆえにか、「一般的な感性では了解されづらい経験」にセックスや暴力を多用する傾向があり、その手垢まみれのモチーフに「古臭さ」を感じにはいられないことも否定できない。 これが冒頭で述べた「はいはいおもしろいおもしろい」的な辟易に繋がるものなのだが、この点については今後どのような飛躍を遂げるかを楽しみにしている。
おわりに
さて、ぼくはそんな佐川恭一と数ヶ月に1回の頻度で酒を飲みながら長々と話をするのだが、酔いが深まるとかれはいつもこんなことを口走る。
「10代後半の頃、小説を書くやつをバカにしていたじぶんが、20代で小説を書きはじめ、30代になっても小説という魔物に取り憑かれている」
佐川恭一という作家の真髄はそこにあるのだ。
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。
