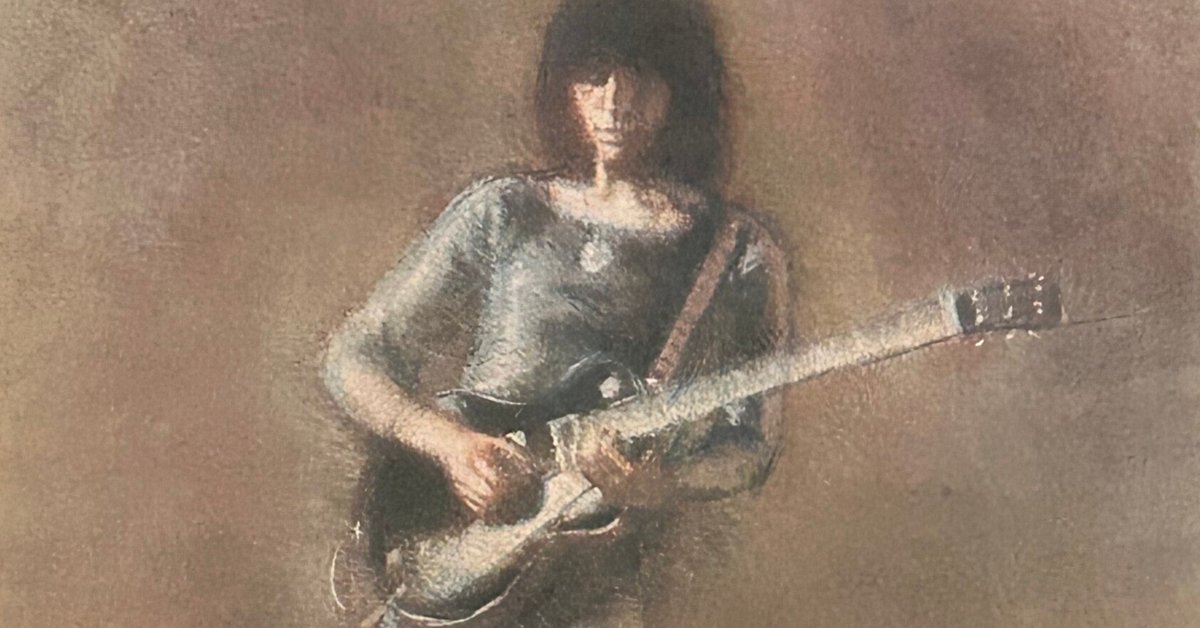
名盤と人 第18回 インスト・ロックの傑作 『Blow by Blow』 ジェフ・ベック
70年代、次々とバンドを作り解散し迷走したかに見えたJeff Beck。
1975年にリリースした『ブロウ・バイ・ブロウ』 (Blow by Blow)はギター・インストという新境地に挑戦して、見事にセールス的にも成功。さらにはジャズやファンクを取り入れた新しいサウンドの先駆者となる。成功の裏に「孤高の人」に見えるベックの意外な適材適所の人使いを発見した。
『ギター殺人者の凱旋』
『ブロウ・バイ・ブロウ』 (Blow by Blow) は、1975年にリリースされたJeff Beckのアルバム。発表当時の邦題が『ギター殺人者の凱旋』と言うタイトルでサウンドよりも、まずその奇妙な題名が子供心に刻まれた。当時は珍しいロックのインストルメンタルながら、ビルボード・チャートで4位を獲得しておりJeff Beckの代表作となった。
歌を入れずに自分の得意なギターで勝負する新しいチャレンジで、今後の彼の道筋を作ったエポックメイキングな作品となる。

Jeff Beckの変遷
1965年、Jeff BeckはEric Clapton脱退後のヤードバーズに参加。
ヤードバーズ脱退後、1967年「Jeff Beck Group」を結成。
当時は無名だったRod Stewartがボーカル、BassがRon Wood、ピアニストがNicky Hopkins 、ドラマーがAynsley Dunbar(マザーズ、ジャーニー)と言う今から見ればすごいメンツだ。
交通事故で休養後、再び「第2期Jeff Beck Group」を始動。このグループはドラマーにCozy Powell、キーボードにMax MiddletonにボーカルにBob Tench、ベースにClive Chamanという2人の黒人を含むメンバー。
この第2期はソウル/ファンクのエッセンスをふんだんに取り入れた新しい路線で、それまでのブルース路線とは異なるものだった。
1971年にアルバム『Rough And Ready』、翌年『Jeff Beck Group』を発表、ベックと黒人音楽との融合が始まる。
その後はカクタスで活動していたTim BogertおよびCarmine AppiceとBeck, Bogert & Appice(BBA)を結成。翌1973年2月、アルバム『Beck, Bogert & Appice』発売してツアー。1973年5月には日本ツアーを行う。しかし1974年1月26日、ロンドンでのコンサート中、ジェフとTim Bogertが衝突しBBAは自然消滅する。
ベックは「第2期Jeff Beck Group」にいたMax Middletonに相談し、Middletonはレコーディングに参加した。必然的にBBAではなく「第2期Jeff Beck Group」のソウルやファンクなど黒人音楽の影響を受けた路線を想定して録音が始まる。
そして、Middletonの推薦で、当時は無名のPhil Chen(Bass)とRichard Bailey(Drums)が参加する。
カリブ出身の2人のリズムセクションの貢献は大きかった。
そして『Blow by Blow』は1974年12月にレコーディングが開始される。
Stevie Wonderのお返し
『Blow by Blow』のSide2-1の「哀しみの恋人達」(Cause We've Ended as Lovers)は、本作で最も知られた曲でセールスに貢献した。
1972年Stevie Wonderの『Talking Book』のレコーディングにベックは「Lookin For Another Pure Love」にギター・ソロで参加した。
そしてそのお礼に、Stevieはジェフに「迷信」(Superstition)という曲を書き下ろしてBBA用にプレゼント。
BBAはヨーロッパとアメリカのツアーを行った後に、アルバムのレコーディングを予定しており、このツアー中にも「迷信」は演奏されていた。そして、彼らの強力なデビューシングルとして発売予定だった。
だが、モータウンはアルバム『Talking Book』からのファース ト・シングルとして、「迷信」を同年11月に強引に発売し、全米チャート1 位の大ヒットとなるが、これはベックには寝耳に水だった。
結局は迷信はBBAのアルバムには収録されたが、シングル・カットされることはなかった。
ジェフは不満を漏らし、Stevieは謝罪の印としてかつての妻であったシリータ・ライトの2枚目のアルバム『スティーヴィー・ワンダー・プレゼンツ・シリータ』(1974年)に収録されたバラードである「哀しみの恋人達」を提供した。
この曲はベックによりRoy Buchananに捧げられている。
また、クレジットにはないがSide2-1「Thelonius」ではStevieがクラヴィネットを弾いている。
第2期から継続するファンクへのこだわりは絶頂期を迎える黒人シンガーStevieの参加で明確化し、さらにヒットの弾みとなる。
ジョージ・マーティンの起用
インストルメンタルながら、アメリカで4位を獲得したのは、プロデューサーにビートルズで著名なGeorge Martinを起用したことも一つの要因である。
George Martinは当時ジョン・マクラフリン率いるMahavishnu Orchestraの『黙示録 Apocalypse』をプロデュースをしていた。
のちにベックとタッグを組むJan Hammerも在籍していたMahavishnu Orchestraのフュージョン(ジャズロック)的なサウンドに影響を受け、Martinにプロデュースを依頼したのであった。
「俺は彼は王室の人なんじゃないかって思ってたんだ」と語るように、ベックとGeorge Martinの見た目の組み合わせには違和感はある。
だがべックは「あんな才能ある人と取り組めたなんて。彼がキャリアを与えてくれたんだ。彼なしでは、どうなってたか誰にも分からない」とも語っている。
アルバムのラスト『Diamond Dust』でMartinがメロディーの盛り上がりを強調するために弦楽器パートを加えることを提案したという。
ベックでは思いつかないようなポップな味付けとMartinの知名度は売行きに好影響を与えた。
Side2-2ではビートルズの「She's a woman」をカバーしている。これもMartinの提案だと思ったが違った。
ベックはトーキング・モジュレーターを使用して歌パートを代用する。
そしてMartinが反対したレゲエのリズムを取り入れており、ジャマイカ出身のベーシストPhil Chenとガイアナ出身のRichard Baileyのカリブ海コンビの存在が自然とレゲエテイストに導いたと思われる。
東洋人のベーシスト
ここで話は変わる。
2015年10月24日(土)と10月25日(日)に開催されたPeter Barakan氏がキュレーターを務めるフェス「LIVE MAGIC!」(恵比寿ガーデン)で意外な人物に遭遇する。
ここに参加した沖縄に住むDavid Ralstonというギタリストである。
Ralstonはデラニー&ボニーのデラニー・ブラムレットからボーカルを学び、彼のプロデュースで「Nail It Down」を1999年に発表。さらに本作のベーシストPhil Chenが参加したアルバム『LA SESSIONS』もリリースしていた。
公演後に彼と立ち話をしていると、Phil Chenの話題に及んだ。
その名前を久しぶりに聴いて思い出したのが、1979年のRod Stewartの来日公演でのベースを弾く姿。
その時の演奏の素晴らしさを彼に話すと、早速Face BookでChenに連絡を取ると、すぐに返事が帰ってきた。
Real Live Magic!
Hey Tatsuo Domo arigato the truth is dat success is in every one of us , regardless of race ,talent is secondary it is how hard we work at it n we must think POSITIVE KI!! For ANYTHING IS POSSIBLE IF ONLY WE BELIEVE IN OURSELVES! I thanx you again .
One luv de Bassman Phil Chen OD
(成功は私たち一人一人の中にある。人種に関係なく、才能は二の次で、私たちがどれだけ一生懸命に努力するかです 。ポジティブに考えましょう!!
Bassman Phil Chen )
と言う、励ましのメッセージが即座に返って来て、感激したものだった。
「人種に関係なく」、と言うように「Blow By Blow」では白人と黒人さらに東洋系のChenと人種を超えたコラボレーションが展開されていた。
当時人気絶頂のRod StewartのLIVEは抽選となり、友人と武道館の二階から眺めた。
メンバーで著名だったのはドラムのCarmine Appiceだったが、1人の東洋系のベーシストがステージ狭しと動き回り気になった。
それがPhil Chenだった。
前年78年の「Da Ya Think I'm Sexy?」でのイントロのベースも彼のもので、「オクターブ奏法」といわれるディスコでも有名な、「ンッタタ、ンッタタ、ンッタタ」「ン、ぺぺ、ン、ぺぺ」のような感じのテクニックがこの曲の独自のノリを形成している。このベースラインのテイストは、その後のディスコ系アレンジなど多くのロックで取り入れられ、更に進化しながら世界中を席巻した。
その彼について調べたところ、何と1940年ジャマイカのキングストン生まれの中国系ジャマイカ人であることが判明。
その後、英国に渡るとアフリカ、カリブあたりから来た移民ミュージシャンたちと交流を深め、リンダ・ルイス、ドノヴァン、ジョーン・アーマトレイディング、レゲエの伝説シャロン・フォレスターらをサポートし、「Blow by Blow」やRodのバンドへの参加で名声を高めた。
クイーンのJohn Deaconは尊敬するベーシストとしてChenの名前を挙げているのは、ブラックミュージック好きの彼らしい。
当時はロックの世界で東洋人は珍しく、記憶にあるのは山内テツくらいか。
その彼が「Blow by Blow」に参加していたことを知り、再度このアルバムに辿り着いたのだ。
Ralstonには「RalstonとRichard Baileyと組んでBlow by Blow再現ライブを日本でやりたい」とまで提案してくれたが実現していない。
そのPhil Chenも癌との闘病生活の末、2021年12月14日に80歳で亡くなったため、その約束も果たされていない。
UKファンクの立役者
その後、さらにドラマーRichard Baileyの名前を聞くことになる。
2017 年に発売されたSteve Winwoodの名作LIVE「GREATEST HITS LIVE」のメンバーにRichard Baileyの名前を久しぶりに見つけたのだ。
Richard Baileyはガイアナ生まれでトリニダッド・トバゴに移住。
12歳の時ロンドンに移り、ジョニー・ナッシュやボブ・マーリーなどと活動をし、そして若干18歳でほぼ無名ながら「BLOW BY BLOW 」のドラムに抜擢されたのだ。
当初は「BLOW BY BLOW」 はCarmine Appiceがドラムを担当し録音が開始されたが、何らかの理由でBaileyに変更されている。
Carmine Appiceについては「ハードロック色が強くて硬くて柔軟性がない」とBaileyは語る。
Baileyは「腕に力を入れずにリラックスして叩く」と語り、きめの細かいロールを決めまくり、自然で流動的で自由なリズムを展開した。
BBAなど過去のベックのバンドとしては軽めのリズムセクションだが、全く違和感がない。
「孤高の人」のイメージが強いベックだが、人を抜擢する力と聞く耳を持つ柔軟性の高い人物だったことが伺える。
その後、Richard Baileyは英国のジャズ/ロック/ソウル/フュージョン集団であるIncognito に"POSITIVITY"より参加している。
Incognitoのリーダー、Blueyは「演奏を終えたリチャード・ベイリーがパブから外に出てくると、僕は彼に近寄って『大ファンです! いつか僕がバンドを作ったらドラマーになって下さい!』なんて伝えた」と語る。ジェフ・ベックの『Blow By Blow』を聴いて、「リチャード、あの曲で使ってるスネアは何?」なんて聞いたりもした。
「他のドラマーにはない彼特有のグルーヴが絶対にほしかったから。多くのドラマーはエネルギーやスピードを落とそうすると、同時にグルーヴもなくしてしまう。それをなくさずに生かし続けられるのがリチャードなんだよ。ボリュームを落としながらも人々を踊り続けさせるという技を極めているからね。」と絶賛する。(rolling stone japan)
『Blow By Blow』のキーマン
このリズムセクションを招聘して成功に導いた立役者がキーボードのMax Middletonである。
第2期においては、ファンクをベースとした黒っぽい音づくりで、Middletonによってジャズ的な味付けもされていた。
とはいえ、第2期よりはずっとタイトで、ファンキーで、ローズ・ピアノの音がジャズを強く感じさせる。
このリズセクション2人とMax Middletonとの接点はどこなのか?
Linda Lewisの1973年の作品『Fathom Deeps』(1973年)には、Max Middleton(key)がBob Tench(g)、Clive Chaman(b)という元Jeff Beck Groupメンバーと共に参加。さらにPhil Chen(b)、Richard Bailey(ds)などが参加しており、3人の接点が垣間見える。
Linda Lewisと言えば、90年代のレア・グルーヴ~UKソウルのムーヴメントの流れの中で、クラブDJにより再評価された。『FREE SOUL』コンピなどにも選ばれクラブシーンで人気を博した。
この辺りはRichard Baileyが所属したIncognitoとも結びつく。
Linda Lewisの1975年の『Not a Little Girl Anymore』にも参加。「I Do My Best To Impress」はフリーソウル・クラシックとして人気の高い1曲。Max MiddletonのエレピとLindaのヴォーカルがメロウなサウンドを形成する。
作曲面での貢献も大きく、今もベックのLIVEの定番である「Freeway Jam」もMax Middletonの作品。
オープニングナンバーのYou Know What I Meanもベックとの共作。
ミーターズやLittke Featの影響も伺えるニューオリンズファンクテイストとなり、Middletonのクラヴィネットも効果的だ。
この時のツアーでもBernardPurdie(drums)やWilbur Bascomb(bass)という超ファンクのリズム隊と共に日本にも来日。伝説のワールドロックフェスで演奏している。
ジャズに向かうベック
1976年にはさらにフュージョンに寄った「Wired」をリリースし、その後にはスタンリー・クラークと活動。
よりクロスオーバー的な展開な突入し、78年には共に来日する。
ベックの抜擢上手は今も継続し、2007年には21歳の女性ベーシストTal Wilkenfeldをバンドのレギュラー・ベーシストに抜擢。
元々はピノ・パラディーノがCrossroads Festival 2007でベースを弾く予定だったがその代役での大抜擢だった。
「ジェフは性別でミュージシャンを選んだりしないのだと思う。」とTalも語るが、性別も人種も超越したジェフは多様性の先駆者でもある。
2015年のBlue Note JAZZ FESTIVALにベックがヘッドライナーで登場した時は「なぜ」と感じたが、この足跡を辿ると彼こそがロックからジャズへアプローチした先駆者と感じ違和感はない。
Jeff Beckというと、「唯我独尊」「孤高の人」と1人で我が道を行くイメージがあったが、本作を通じてイメージは変わる。
無名でも若手を抜擢して育成したり、足りない部分を持つ人の意見を聴いてコラボレーションするのに長けている人物像と言う発見。
だからこそ「Blow By Blow」でギターインストという未踏の地で大衆の支持を広く受けつつも、マニアにも説得力のある新しさも提示できたのだろう。
本作の試みが、ジャイルス・ピーターソンなどの90年代のアシッド・ジャズ等のUKクラブシーンに流れ着き、今のUKジャズ等にも受け継がれている。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
