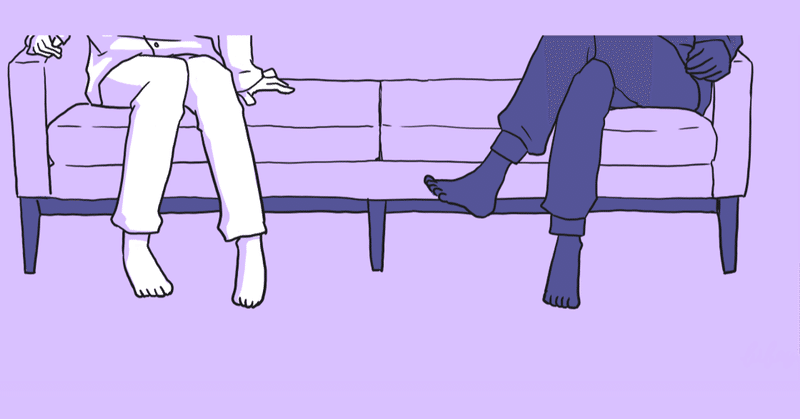
ゲームにおける「2人」のあり方(Couple's Gaming)
本記事は、Alexandre Santos氏が2021年12月15日に投稿した「Couple's Gaming」の翻訳である。長文なので、ほとんど読まれることのない記事と想定される。訳者の興味関心を元に翻訳したものであるが、ボードゲームという趣味とパートナーとの関係性について、悩みを持つ人も少なくないだろう。
本記事で触れられている事柄は多岐にわたる。パートナーとゲームをすることだけでなく、それと関連して、2人用ゲーム、RPG、ゲーム会、ビデオゲームを取り上げている。パートナーとの非対称な関係性から生ずる様々な事柄について述べた記事ということになる。
タイトルは相当な意訳をしている。直訳すれば、「カップルのゲーム(カップルがゲームすること)」とでもなろうか。ただ、カップルにも色々な形があるものだし、もう少し多岐にわたる本文の内容が捉えられるようなタイトルがいいなと考えた。そこで、タイトルを「ゲームにおける「2人」のあり方」とした。
原文は以下のリンク先を参照されたい。ヘッダー画像はみんなのフォトギャラリー機能を利用させていただいた。

作者: Jan Sanders van Hemessen
1969年、多作なゲームデザイナーでありコレクターでもあったSid Sacksonは、大きな影響を与えることとなった彼の著作「シド・サクソンのゲーム大全」(A Gamut of Games, ※邦訳はNew Games Orderから出版されている。)を妻のBerniceにささげました。その理由は、ゲームデザインや本の編集に関する彼女のサポートと「……何よりも、彼女は長年にわたり1人のゲームオタクに我慢してきてくれた」ことにあるようです。このことには、ゲームという趣味に大切な人(significant other)が関与することの複雑さがはっきり示されています。
ゲームで遊ぶことは、非常に開かれた(open)社会的活動であることが多く、いつもの人たちと繰り返されてきた集まり(recurrent meetings of regulars)や、知らない人たちとのオープン会が含まれます。ロマンス語圏では、ボードゲームが社会全体に関係している(involve)ことから、"社交(社会)ゲーム"(society game)と呼ばれることも多いです。他方、「2人」のゲームは、恋愛関係にあるパートナーと一緒に遊ばれるものです。パートナーの参加の仕方によってではありますが、それには特別な経験となるような親密さという側面(aspects of intimacy that give it specific characteristics)が含まれています。

クレジット: spelfoto
ボードゲームに対する熱の入り具合
当たり前ですが、「2人」でゲームをすることは、パートナーの熱の入り具合(the level of engagement)によって、その在り方が決定されます。ゲームをひどく嫌うパートナーであれば、どんなに意味のある「2人」のゲームであっても、(※その関係性から)締め出そうとするのは明らかですし、時として、家族でゲームをすることさえも制限されます(limited allowances)。ゲームで遊ぶことは、パートナーが人生を豊かにする"秘密の花園"を持つことができるようにする、一連の自立的な活動に付き合うことですので、「2人」の関係性にも良い影響を与えることも多いはずです。
私の最も頻繁に同卓していたゲーム仲間の2人が、このような状況に置かれています。その結果、1人は、ソロゲームをメインにしたコレクションという方向に舵を切りました。反対に、もう1人は、ゲームをコレクションしなくなりました。彼のパートナーはゲームで遊ばないし、ソロゲームも好きではないので、ゲーム会に参加して他の人たちが持ち寄ったゲームで遊ぶようになりました。
パートナーの熱の入り具合が高いと、2人で遊ぶゲームは、小さいゲーム会やいつものメンバーでのゲーム会に近いものになります。つまり、2人一緒になってコレクションの管理やゲームを探究すること(game exploration)に等しくお金を出すようになります。ゲームで遊ぶことは、"一緒に過ごす時間"の重要な一部になるでしょう。一緒にイベント(conventions)に参加したり、ゲームを中心とした(game-oriented)旅行をしたりするでしょうし、共通の興味に家庭の都合を合わせられるように配慮するようになるでしょう。

クレジット: Steve Huckabee
ゲームを遊ぶことが広まっていくにつれて、このような関係(this configuration)がより頻繁にみられることでしょう。しかし、このような2人であっても、そうではない2人の関係と同様に、パートナーがだんだんと他の趣味や優先事項に関心が移るにつれて、周囲の環境(circumstances)を変えるよう交渉しなければならなくなるかもしれません。
パートナーの熱の入り具合が異なる「2人」のゲームについてみると、この非対称な関係性によって2種類のゲーマーの状況が生み出されます。まず、活動型ゲーマー(the active gamer)は、率先してゲームを入手し、ルールを覚え、どのゲームを遊ぶべきか提案することが多いです。参加型ゲーマー(the participatory gamer)は、遊ぼうとするが、滅多にゲームを探したり、自分でルールを覚えたりすることはありません。参加型ゲーマーは、とても競争好きで、経験豊かで、1年間に何百ものゲームを遊んでいることもありますが、ゲームに対する関与は、活動型ゲーマーの積極的な行動(initiative)に付随(※依存)したものとなります。

クレジット: Daniel Indru
この構図が「2人」のゲームが社交ゲームと最も異なる点になります。"社交(社会)"ゲームのゲーム会では、全てのプレイヤーが、他のレジャー活動よりもゲームを優先しています。そして、プレイヤーは、自分の家から人と会う場所まで移動して、対等な関係性のもとで時間を費やすのです。「2人」のゲーム、特に参加型ゲーマーの場合には、ゲームをすることは、パートナーと共有された時間を過ごすための導管(conduit, ※道具的な意味合い)であることが明らかで、その関係性という状況下で育まれるのです。
その結果、「2人」のゲームでは、活動型のパートナーが、ゲームの"コーチ"としての役割を担うことが多くなります。趣味における知識や興味の非対称性は、活動型ゲーマーが遊ぶゲームを選定し、参加型ゲーマーの体験を見て適切に対応し、それを評価した上で、ゲームの予定を提案することになります。

クレジット: Jeffrey Nolin
解き放たれたガラテイア
社交ゲームと比較すると、その差が大きいことから、私は、非対称的な関わり合い(※熱の入り具合が異なる場合)における「2人」のゲームを主に論じようと思います。私の個人的な場合をいうと、私の妻は明らかに参加型ゲーマーですので、彼女にゲームを紹介するに当たっての失敗談を役立てることができます。
こうは言っても、具体的なケースを見るに当たっては、状況が微妙に異なることも留意すべきです。例えば、ゲーマーがそのパートナーに趣味を紹介したが、そのパートナーがその趣味に没頭してしまって、最終的に立場が逆転することも起こり得ます。先ほど論じたように、熱の入り具合は時間経過により変化し、「2人」の関係性もある状況から別の状況に移り変わることもあるのです。

クレジット: Brian B.
参加型ゲーマーと一緒にゲームをする際の具体的な状況を考慮すれば、いくつかの要素が浮かび上がってきます。参加型ゲーマーは、定例会に参加しているゲーマーと比較して、より強い意思を持って(decisive)はっきりと、ゲームが面白くなかったと表明したり、そのゲームを否定したり(dismissing)します。また、参加型ゲーマーは、よりわかりやすく講義的なルール説明を要求しますし、初回プレイで良い体験が得られないゲームに対する許容度は低いものです。
彼らにゲームを紹介するには、ゲームに習熟するという観点からだけではなく、教えること自体の用意や、ゲームを紹介する機会を慎重に検討するといった観点から、より一層入念な準備を要することがわかります。私は、妻にゲームを紹介するに当たり、ゲームに参加してもらうための都合の良い事情を辛抱強く待つことがあり、1年かそれ以上の時間をかけて待っていることも多いです。

クレジット: Carlos Ferreira
つまり、時として、パートナーに新しいゲームを紹介することは、就職の面接に合格することと同じように感じられます。しかし、当然ですが、うまく受け入れられたゲームであれば、リプレイされる可能性が高くなるという利点があります。
気のない返事がされたゲームがローテーションに入ることは稀です。その稀な例外は、具体的にいえば、ゲームにあまりにも多くの新しいコンセプトが搭載されていて、1つにまとめることができず(※1つのゲームとしてまとまっていると認識できず)、ゲーム体験が損なわれている時です。この場合、パートナーがもっと経験を積んで、そのゲームを正当に評価できるようになれば、数か月後に再度試してみることができるかもしれません。私の場合をいうと、あまりにも早い段階で、「レース・フォー・ザ・ギャラクシー」を紹介するという失態を犯してしまい、結果として大失敗となりました。しかし、妻の好みをより理解するにつれて、「レース・フォー・ザ・ギャラクシー」が彼女の好みであるとますます確信するようになりました。そして、一、二年後に再度試してみると、大成功を収めたのです。

クレジット: Prashant Maheshwari
パートナーのゲームの好みを理解するようになることは、彼らのゲーム体験を向上させるのに重要なのは明らかです。しかし、パートナー自身を表現をするためのツールを与えて、その結果、ゲームで遊ぶことに関してもっと自覚的(※能動的)にさせることも大事です。ゲーム体験を議論することや、ゲームの専門用語(jargon)を紹介したりすることが有益でしょう。プレイヤーは、特定のゲームが他のゲームよりも優れたゲーム体験だったと自発的に言うことができます。しかし、もし、これがより正確に表現することができたら、例えば、どんなタイプのインタラクションやメカニズムが、良い又は悪いゲーム体験を引き起こしたといったような表現ができて、感想を交換するための共通言語を作れたのであれば、有益なことでしょう。

クレジット: John Lee
一般的に自己認識の向上は、「2人」のゲームに有益です。それは、参加型プレイヤーだけでなく、活動型プレイヤーにとってもです。例えば、自分のプレイを記録することは、妻と一緒に遊ぶ際のパターンに気付くために有益でした。それにより、私は、妻が年間に100ゲームほど遊んでいることに気づくことができて、私は完全に低く見積もっていたことがわかりました。
参加型のプレイヤーは、自己認識を高めるのにも役に立つことがあります。結局のところ、自分のパートナーは、大抵の場合、最も観察している片割れ(companion)であり、これまできちんと評価していなかった趣味の重要性に気付くのに有益なのです。ゲームは、余暇の時間、予算、生活空間、「2人」のライフバランスに影響し、双方が満足できるような合意に至る必要がある全ての問題に影響を与えます。これは、ニーズが正しく認識されて表現された時のみ可能になります。いつもどおり、こういった問題について定期的に話し合うことが、最善の解決策です。そして、パートナーが、多くの場合、実際にうまくいく提案をしてくれる最善の人(the source)なのです。一旦、オープンに話し合えば、棚のスペースやプレイの頻度のような問題は、環境が変化したせいで整頓について見直しの必要が出てきた時でさえ、お互いの摩擦の原因にはならなくなります。

クレジット: mrbass
2人用ゲーム
長い間、多くのボードゲーム、特にユーロゲームにおいては、主にプレイヤー数の多いゲームが発表されており、プレイヤー数が2人のものは選択肢が少ない(dearth)ままでした。この状況は、2010年代に、このプレイヤー数に特化したスピンオフのゲームに伴って変わり始めました。例えば、「アグリコラ:牧場の動物たち」、「世界の七不思議:デュエル」はプレイヤー数が2人の場合に合わせてドラフト要素を調整しています。

クレジット: 上からQuijanoth、Rudy Priecinsky
興味深いことですが、長い間にわたり、「Glen More」でみられるような、ゲームプレイを引き締めるためにダミープレイヤーを使用することは、滅多に活用されず、敬遠されていた(shunned)解決策でした。しかし、ソロゲームが台頭したことや、ゲームをソロに適応するために自動化された対戦相手が普及したことにより、2人用ゲームにおけるダミープレイヤーの活用がより確立したものとなりました。「Concordia: Solitaria」の場合をみると、自動化された対戦相手であるContrariusは、ソロと2人用ゲームの双方で使用されています。

クレジット: Alexandre Santos
こうは言っても、プレイヤー数が2人に限定して明確にデザインされたゲームも製造され続けています。例えば、「Mr. ジャック」は推理要素のあるチェス風味のゲームで、「タルギ」はドラフトとワーカープレイスメントを組み合わせたゲームです。

クレジット: 上からGregory Duff、Jakub Niedźwiedź
「パッチワーク」はドラフトとポリオミノを組み合わせています。「コードネーム:デュエット」は推理系の単語連想ゲームを2人用ゲームにうまく調整したゲームで、「2人」のゲームにおける素晴らしい選択肢となっています。

クレジット: Jon Enns、John Gentry
他方、シミュレーションゲームや歴史ゲームは、伝統的にプレイヤー人数が2人となっているゲームが支配的でした(privileged)。そして、より手に取りやすいバージョンが今では入手可能となっています。具体的には、「13 Days: The Cuban Missile Crisis」、「ウォーターゲート」、「Blitzkrieg!: World War Two in 20 Minutes」があります。

クレジット: 上からJakub Niedźwiedź、Tim P.
こういった2人プレイヤーゲームの要望(offering)の高まりは、このプレイヤー人数に特化したオンラインリソースが増加することによっててこ入れされています。BGG上の「A Couple of Gamers」のギルドでは、2人用ゲームに関する議論を集約し、最も人気のある2人用ゲームの年間ランキングを主催しており、Ira Perkinsが今年のランキングを執り行いました。「You and me . . . and coffee make three」では、限られたテーブルスペースにおいて、2人で遊べるゲームをリストアップしており、出先で「2人」のゲームをするのにとても便利です。
協力ゲーム
協力ゲームは、いくつかの理由から「2人」のゲームにぴったり合います。まず、対戦ゲームの対立的な要素を避けることができます。対立要素は、時として幼い頃の嫌なゲーム体験を思い出したり、負けたことによって低く評価されたように感じるのを避けられない新規プレイヤーにとって心配の種になりかねないものです。協力プレイにおいては、チームの一員となって、勝利や敗北を分かち合うのです。

クレジット: Adam Carney
協力ゲームが有益である第2の理由は、卓でのおしゃべり(table talk)や戦略に関する話し合いをすることができることが多いからです。実際に、パートナーと話す時間をもつことは、特に「2人」のゲームで重要ですし、一緒にいる時間というのが、一緒に遊ぶことよりも重要視されることが多いです。

クレジット: eruntalon
協力プレイが良い3つ目の理由は、一緒に戦略について話すことによって、より段階的でわかりやすい方法で、ゲームのコンセプトを学ぶことができます。誤った理解にも容易に気付けますし、対戦プレイの妨げになるほどの失望の原因にはならないので、完璧なルール説明の必要性が低まります。

クレジット: Ronny Alexander
とはいえ、「花火 / HANABI」や「Bridge」のようなチーム戦のあるゲームを遊んだ人なら誰でもよく知っていると思いますが、プレイヤーは、自分のアクションが敗北の原因となることに対する恐れを伴うプレッシャーを感じることがあるので、協力要素が常に衝突や緊張感を避けられるとは限りません。そこで、協力ゲームであってさえも、勝つことよりもゲーム体験を優先することを頭の片隅に入れておいたほうがいいでしょう。

クレジット: Aldo Ojeda
対戦ゲーム
そうは言っても、全ての人が協力ゲームが好きなわけではありませんし、対戦ゲームは、ある種のプレイヤーにとって、より心躍るように感じられるものです。プレイヤー数が2人の対戦ゲームは、特定の性質があります。そういったゲームは、より一層バチバチの殴り合いとなって(confrontational)、ゼロサムゲームであるということです。3人以上のゲームでは、1人の対戦相手の順位を落とすことは、自分自身の順位を上げることよりも有益でないことがあります。2人プレイヤー間では、対戦相手を攻撃することは、自分の立場を上げることと同じくらい有益です。そして、対戦相手を攻撃することが容易であれば、より多くのプレイヤーがいる場合よりも更に多い頻度で、それが起こってしまうでしょう。

クレジット: Ryan Cross
他方、2人でのゲームでは、ゲームの流れをよりコントロールしやすくなり、プレイヤー人数が多い場合にはより混沌として変動しやすくなるゲームにおいて、より戦略的な体験を得られるという利点となります。

クレジット: Henk Rolleman
また、2人で遊ぶことは、ダウンタイムを最小限にして対戦ゲームを遊ぶのに最適で、特に、インタラクションが小さいゲームにとっては都合が良くなります。そういうゲームでは、プレイヤーの追加によって増加したダウンタイムを補う要素は滅多にないですし、ゲームの総時間当たりの各プレイヤーの手番時間(on-time)を減らすことができます。

クレジット: 上からCasey Lee、Mike Toner
もちろん、2人プレイのゲームは、外交や交渉という面では劣っており、「デッド・オブ・ウィンター」の囚人のジレンマバリアントのように、そういったメカニクスをブラフに置き換えることがかなり多いです。

クレジット: Sean
まさしく、プレイヤー人数が2人というのは、相手プレイヤーの心理を読んだり、その裏をかいたりするのが決定的なゲームにおいて本当に機能するのです。その裏を読み、さらに裏の裏を読むということが楽しくなります。

クレジット: Henk Rolleman
深くゲームをすること
参加型ゲーマーと一緒に遊ぶ「2人」のゲームは、ゲームの宣伝や一過性の流行(churn)から隔離された島であるということが、利点としてあまり認識されてないことが多いです。例えば、「ウイングスパン」の見栄えは魅力的なのですが、私の妻に"もっと早いペースで進むタブロービルドのほうが良い"と言われて、遠慮なく片付けられてしまい、このゲームは妻の前に無惨にも散ってしまいました(fell flat)。
一過性の流行について、多くのゲーマーは、ゲーム界における過剰なゲームの入れ替わりに不満を持っており、懐古的なゲーマーは、同じゲームを何回も遊ぶことができた、年間発売数の少なかった昔を恋しく思っています。しかし、参加型ゲーマーは、目新しさには興味がなく、別のゲームのルール説明を受けるよりもむしろ、何百回とは言わないまでも何十回と同じゲームを遊んで、習得したスキルを磨くことを好むことが多いです。そのゲームがそれを可能とする深さがあればの話ですが。
こういう理由と、参加人数も問題にならないことから、「2人」のゲームは、じっくりと豊かな物語が展開される(deploy its richness)「グルームヘイヴン」のような、長く、濃密な(dense)キャンペーンゲームにはうってつけです。

クレジット: Martin Mudrak
この文脈において好まれる他のゲームといえば、そのラインナップに大きな多様性をもたらすゲームになります。多くの固有能力があるという点では、例えば、「Summoner Wars」や「Neuroshima Hex! 3.0」があります。「2人」のゲームは、拡張要素や、「センチュリーシリーズ」や「Pyramid Arcade」のようなゲームシステムを探究することも好まれます。

クレジット: Gregory Duff, Alexandre Santos
「2人」のゲームは、「アーカムホラー ザ・カードゲーム」のようなライフスタイルゲームにも適応します。そういったゲームでは、ゲーム自体のプレイと同じくらい、デックビルド要素がゲーム体験や卓上での会話の話題の大部分を占めることになります。

クレジット: Alexandre Santos
このような深いプレイと、率直で無愛想な(abrupt)フィードバックのおかげで、「2人」のゲームは、Sid Sacksonの場合と同様に、時としてデザイナーにとって重要なリソースになることがあります。しかし、例えば、「アグリコラ」のUwe Rosenbergや、「デウス」のSébastien Dujardinといった他のデザイナーも、同じような経験を報告しています。
実質的にも、「2人」のゲームで実現する深いプレイは、時折遊ぶようなプレイヤーが適当なプレイ(casual play)をして大勝ちしてしまう(outskilled)ことがあるので、そういった出来事に対してゲームを控えめに調整することがあります。他方、普段からより規模が大きくて多様なゲーマーと競っているプレイヤーと比較して、ゲーム全体(game space)の探索が限られてしまっていることから、「2人」のゲームは、トーナメントでのプレイの準備に役立つことは滅多にありません。
それにもかかわらず、このことから、数点の興味深い考察につながります。専門的な努力をした「2人」がとても優れた者となるのと同じように(科学分野におけるキューリー夫妻を参照してほしい。)、「2人」のゲーム経験を積むことで、「コンコルディア ・ヴィーナス」でみられるような、優れた対戦相手のチームになることがあります。

クレジット: Govind Krishna
「2人」が社会に関わること
より大きなサークルにおいて、「2人」がゲームすることについて言及しますが、このことが、とある問題を引き起こす可能性があります。単独で活動しているゲーマー(isolated gamers)は、過去のゲーム経験を通して、遊ぶ際のエチケットを学んでいますが、参加型ゲーマーは、そのパートナーが自分たちのゲーム習慣を過度に尊重してしまっていると(overcompensate)、ゲームを遊ぶことに関して抱いていた予想を裏切られる(crossed expectations)かもしれません。
準備や撤収を手伝うといったようなわかりやすいこともありますので、「2人」でゲームを遊んでいる間におそらく(※習慣として)取り入れられることもあるでしょう。しかし、わかりにくいこともあります。絶対にルールブックを読まないプレイヤーは、ルールを覚えたり、ルール説明の方法をデザインしたりする努力に無関心かもしれず、そうなると、活動型のプレイヤーがルールを詳しく説明しなければならなくなってしまいます。
また、知ってか知らずか(knowingly or unconsciously)ですが、活動型のプレイヤーは、オープンなゲームイベントで遊ぶ際に、参加型のプレイヤーが予期しない手厳しい仕打ちを受けることになってしまう、「カルカソンヌ」の熾烈なプレイのような、ある種のプレイスタイルを、パートナーと一緒に遊ぶ時には避けるべきだと学んでいるかもしれません。

クレジット: Andi
時には、経験の浅いカップルが、普通の多人数用ゲームにおいて、お互いに情けをかけたり贔屓したり、又はその反対に不必要なほど攻撃的になったりして、そんな一方的な勝利を望んでいない別のプレイヤーを有利にすることでゲームにわざと負けるといった、混乱を引き起こすこともあるかもしれません。時には、こういったことが、普段のパートナーを標的にすることが感情的に容易く(comfortable)、馴染みのないプレイヤーに対して同じことをするのに抵抗があることが原因で起こることもあります。かつて子供と遊んでいた親は、子供たちをそっちのけにして、お互いに競い合っていることが多いわけですが、通常のゲーム会ではそんなうまくいかないのは当然でしょう。
このような問題は、普通は一時的なものであり、他の人と数回遊べば、徐々に適応して解決するものです。
対話を続けること
オープンなゲームグループでは、参加者の環境が変化するとともに、出席者が増えたり減ったりしますが(ebbs and flows)、「2人」でのゲームは、パートナーが抜けたり入ったりすることがないので、長い期間で行われる柔軟性に欠けた性質となります。このことから、ゲームをすることについてこれからどうやっていくのかについて話し続けたり、継続的に環境に合わせたりすることが何よりも重要となるのです。
私の経験では、疲れていると、ゲームをすることに興味を失ってしまうのが必然(logically)ですから、仕事に関係する問題が「2人」のゲーム環境に影響を与える主要な要因となります。そこで、コミュニケーションをとって、可処分時間の(availability)変化に気を配ることが大切なのです。

クレジット: Brian M.
このことは、それぞれの好みや状況によりけりですが、私自身は、毎月どのゲームを遊ぶかについて話し合うことが有用だということがわかりました。私たちは、1か月を1つのゲームや1つのゲームシステムに打ち込むことが多いです。こうすることで、多様なゲームに触れることと(achieving diversity)、限られた時間でのルールの習得との間で、ちょうど良い妥協点を探ることができるのです。
ロールプレイングゲーム

「2人」で行うロールプレイングも固有の利点と欠点があります。「2人」のロールプレイングにおいては、かなり実験的なことが許容されます。例えば、私は、こんなように(※実験的な感じで)、始まったばかりの恋愛関係を題材にしたRPGである「Breaking the Ice」を遊んでみました。また、「2人」のロールプレイングは、「Dread」や「Ten Candles」といったホラーRPGにもうまく機能します。

クレジット: Stephen Dewey
しかし、他方で、「2人」のロールプレイングは、参加型プレイヤーであるほど、負担が大きすぎる(too taxing)ことが多いのです。その理由は、演じる時間("on" time)が多いものの、創造性に富んだ演技の引き出し(creative input)が少ないので、プレイヤーが疲弊した状態に早く陥ってしまうからです。要するに、同じくらいの熱意と創造性のある演技の引き出し(creative output)の双方が揃わないと、より大きなグループで遊ぶことが、より良い選択となることが多いです。

この問題に対するあり得る解決策は、専任のGMなしで遊ぶことです。そうすれば、双方のプレイヤーが同じレベルで一緒に遊ぶことができますし、お互いのアイディアを出し合いながら、GMの仕事をより手続的なものにしておけるのです。「Ironsworn」のような協力して作り上げるRPG(Collaborative RPGs, ※ジャンルの和名は不見当であった。)は、このような可能性を追求しています。
別の方策として、行えることを制限した(constrain bandwidth)RPGを使用することです。RPGの中には、1日当たり一、二通のショートメッセージだけのような固有の制約を設けるものもあり、興味深い実験的な空間となるかもしれません。
ビデオゲーム
ビデオゲームに関していえば、「2人」の体験として最高だったのは、カウチゲーム(couch gaming, ※現実の友達グループと遊んで、ワイワイ盛り上がるのに最適なゲームのことで、スマブラとかが典型例らしい。)でした。「ダンジョン・シージⅢ」のようなカウチRPGを遊んでると、お互いを補い合う能力をもったキャラクターの作成や、敵と戦う際に相乗効果を発揮する戦術を学ぶことが面白いと思います。

クレジット: Alexandre Santos
悲しいですが、カウチゲームは減少の一途を辿っているように思われます。以前より選択肢がなくなり、オンラインのマルチプレイヤーモードが支持を集めています。こうは言っても、コントローラーを共有するなどして、「2人」でゲームするために、1人用ビデオゲームをうまく遊べるようにすることが多いですよね。

クレジット: Alexandre Santos
「マックス・ペイン」において、私が移動キーを操作して、妻が狙いを定めて打つためにマウスを操作することがあります。私のほうは空間移動がしやすくなり、妻のほうは私以上に反射神経が良いので、このアレンジは完璧でした。このことにより、気分転換を楽しむことにもなります。このようなゲームでは、私は、堅実で(conservative)、ステルス行動を好み、弾薬を節約する傾向がありますが、妻は、やたらと銃を撃ちたがり、全ての敵が押し寄せてくる状態になります。妻がやると、狂乱して、全ての弾丸を撃ち尽くすプレイスタイルになり、爽快で、私とは大きく性質の異なったものになります。
最終的な考え
「2人」のゲームは、長い間共有されることが多く、「2人」の歴史の一部となるような思い出深い瞬間を伴う、非常に個人的で、本物の体験となり得るものです。

クレジット: Jon Enns
ゲームは、時間と場所を必要とする(hungry)趣味かもしれません。だからこそ、「2人」にとって摩擦を生み出すものではなく、結び付きを深めるものにするのは私たち次第ということになります。人間関係ではいつもそうですが、コミュニケーションと信頼が、当初予想していた以上に素晴らしい解決策に至る基礎となるのです。

クレジット: Alexandre Santos
以上
※他のAlexandre Santos氏の記事として、以下のようなものがある(なお、意訳している関係でわかりにくいが、「ソロゲームの類型とその分析」は本記事の続きものである。)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
