
子育て×コーチング 子どもたちの可能性を信じて、100%味方でいること。~やってみた編~
こんにちは。nako*です。
前回の記事から1週間が経ちました!
"コーチングマインドで子どもたちにかかわる"
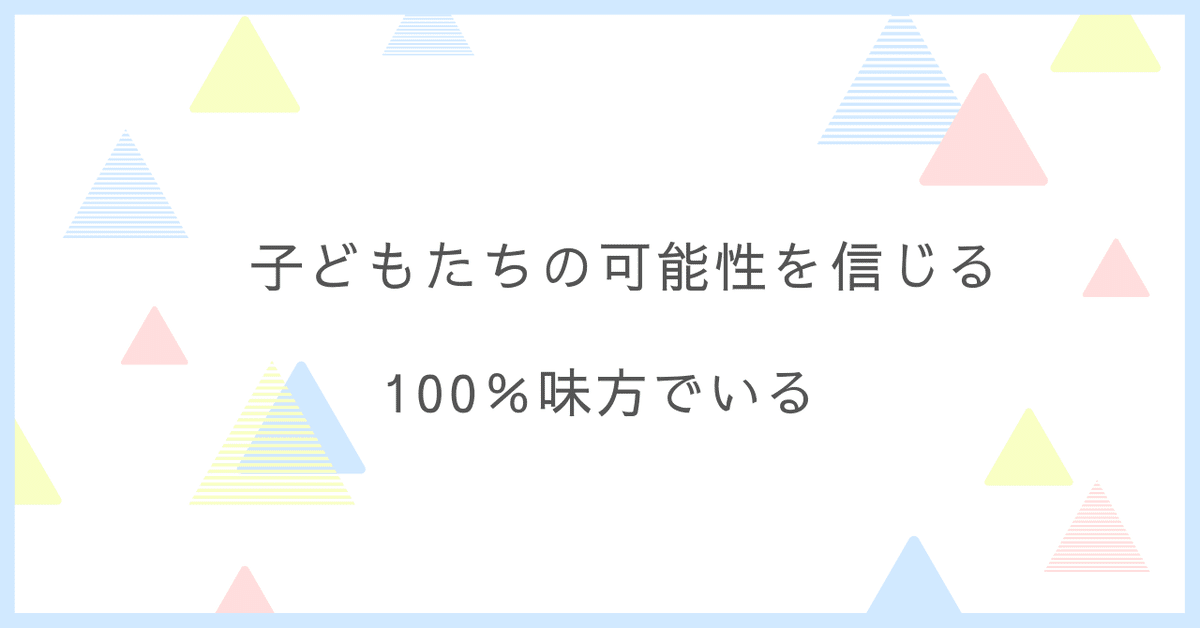
1週間意識してみて、感じたことや、子どもたちの変化をつづります。
"子どもの可能性を信じる=できる前提で接する"
を心がけました。
長男の変化
・宿題をきちんとするようになった
今までは、私が仕事から帰ってくるまでの間に「宿題終わった」とあきらかにウソをついて、私も追及していませんでした。
そこで、一旦「宿題終わったんだね」とやっている前提で受け止めて、「音読ママも聞きたいからもう1回聞かせてよ」と"一緒に"やることに。
すると、自分から「書く宿題はもう終わったから、音読とかけ算カードはママとやる」と言うようになりました!
"宿題をやっていると信じているよ"、"ママはあなたのことを見ているよ"という気持ちが伝わったのかなと思います。
・自分で考えて行動するようになった
ここ1週間ほど、3年前の誕生日プレゼントのスマホロトム(ポケモンのキャラクター)が復活。
目覚まし機能を設定して、自分で朝起きようとするようになりました。
ある日、私よりも早起きして、私が起きると既に制服に着替えていてびっくり!
「早いね!」と言うと、「だってこの方がゆっくり朝ごはん食べられるもん」とのこと。
ちゃんと自分で考えて行動してる!と感動…!
口うるさく「早く〇〇しなさい」と言わず、今の時間は何をしないといけないか自分で考えてほしかったので、
「6時50分だね」と時間だけを伝えるようにしました。
・やりたいこと、言いたいことが言えるようになった
これは、いちばんの変化でした!
今までは、やりたいことやほしいものがあっても、自分からはもぞもぞして言うことができませんでした。
そんな長男が、「メルタンのモンコレ(ポケモンのフィギア)がほしいから、週末100マンボルト(お店)に行きたい!」「ポップコーン作りたいから、ポップコーンのもとを買ってほしい」など、自分の思いを言葉にするように!!
夫もびっくりしていたほど!
子どもと向き合う姿勢が伝わって、
"自分の思いを伝えても受け止めてもらえる"と思ってくれたのかな。
次男の変化
・自分で着替えるようになった
4月で5歳になる次男。
毎朝ぎりぎりまでウルトラマンショーのDVDを見て、「着替えなさい」と言うと、「着替えさせてー」と時間がないので仕方なく着替えさせていました。
でも、"「ヘルプ」ではなく「サポート」"を意識!
まずは早い時間から、「お着替えできるかな?」と何度か予告。
そして、「〇〇のお着替えしてるところ見たいな~」とのせて、
「まずはズボンからやってみよう!」と少しずつ声掛けをしていきました。
すると、だんだん自分で全部着替えるように!
今では、お風呂上りも「もうシャツの着方わかったよ!」と言って楽しそうに自分で着替えています。
自分でやりたくない日は、「今日だけ特別だよ」と言ってお手伝いする日もあります。
自分自身の変化
・子どもの気持ちを考えられるようになった
日々、仕事や家事に追われて子どもに対してイライラすると、子どもの気持ちを考えずに怒り散らしていました…
怒ってる間も、「あぁ、大きい声出してる、でも止まらない」と頭では分かっていても、自分の感情をコントロールできず、後で後悔するの繰り返し。
でも、"コーチングマインドで子どもとかかわる"と決めたことによって、
イライラしたら、「どうやってかかわるんだっけ」と考えることで落ち着くことができました。
「目の前にいるこの子は、今どんな気持ちなんだろう」
「私のことばかけで、どんな風に変わるんだろう」
と自分に問いかけるようにしました。
・子どもを待てるようになった
子どもが何かに迷っているとき、ほかのことが気になってもたもたしているとき、すねて言葉につまっているとき、
子どもではなく自分を優先させて、「早く〇〇しなさい」「早く決めなさい」と急かしてばかりいました。
"子どもを信じる"を考えたとき、
"「すぐに答えを求める」のではなく、「答えは持っている、子どもの中にある」から待とう"
ふと、そんな風に思えるようになりました。
子どもがすねたり、言葉につまったりしている時間。
きっと、子どもなりに気持ちを整理したり、考えたり、必要な時間なんだろうな。
待っていると、すねていた子どもがにやっとしてやってきます^^
・自分自身が勇気づけられた
仕事でものすごくやりたくないことがあったとき、
“子どもの可能性を信じる”→“自分の可能性を信じる”に置き換えて、
「大丈夫、できる!」と頑張ることができました!
子どもたちだけでなく、自分自身を勇気づける言葉にもなりました。
ピグマリオン効果
教育心理学における心理的行動の1つで、教師の期待によって学習者の成績が向上することである。
ちなみに、教師が期待しないことによって学習者の成績が下がることはゴーレム効果と呼ばれる。
Wikipediaより
コーチングの講座で学んだ心理学のことば。
子どもの可能性を信じる=子どもは答えを持っている、できると信じること。
このマインドをいつも心の中に置いておきたいと思います!
次回は、また違うテーマで1週間やってみます♩
それではまた!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
