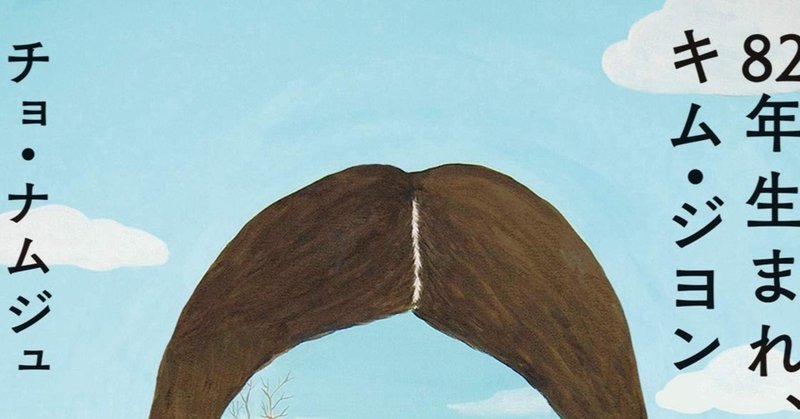
『82年生まれ、キム・ジヨン』、読書感想文と映画ポスター
■はじめに
昨年7月に読んだ『82年生まれ、キム・ジヨン』。
発売当時も話題になっていたが、このたび映画が公開されるとのことで映画ポスターが話題となっている。私の中では悪い方向で。
日本の映画界あるあるなのか、あるいは日本のデザインあるある(ローソンのパッケージ然り)なのか。
それにしたって、今回の映画ポスターは書籍の内容を鑑みるに、あまりにも違うのではないかと思うのである。
ということで、読書感想文と映画のポスターについて。
■韓国で書かれた『82年生まれ、キム・ジヨン』
最初に本屋さんの新刊ゾーンで見かけて表紙が目についた。
そのあとこの記事を読んで、内容もなかなかパンチが効いているようなので、手にとってみることにした。
●重要ではない(ということが重要である)あらすじ
あらすじはこんな感じ。(ちょっと長い)
ある日突然、自分の母親や友人の人格が憑依したかの様子のキム・ジヨン。
誕生から学生時代、受験、就職、結婚、育児……キム・ジヨン(韓国における82年生まれに最も多い名前)の人生を克明に振り返る中で、女性の人生に立ちはだかるものが浮かびあがる。
「キム・ジヨン氏に初めて異常な症状が見られたのは九月八日のことである。(……)チョン・デヒョン氏がトーストと牛乳の朝食をとっていると、キム・ジヨン氏が突然ベランダの方に行って窓を開けた。日差しは十分に明るく、まぶしいほどだったったが、窓を開けると冷気が食卓のあたりまで入り込んできた。キム・ジヨン氏は肩を震わせて食卓に戻ってくると、こう言った」(本書p.7 より)
「『82年生まれ、キム・ジヨン』は変わった小説だ。一人の患者のカルテという形で展開された、一冊まるごと問題提起の書である。カルテではあるが、処方箋はない。そのことがかえって、読者に強く思考を促す。
小説らしくない小説だともいえる。文芸とジャーナリズムの両方に足をつけている点が特徴だ。きわめてリーダブルな文体、等身大のヒロイン、ごく身近なエピソード。統計数値や歴史的背景の説明が挿入されて副読本のようでもある。」(訳者あとがきより)
この小説において、さほどあらすじは重要ではない。
個人的に要約するならば、以下の通り。
「主人公であるキム・ジヨンは子育て中の専業主婦。ある日、精神的な不調をきたし、病院へかかる。治療にあたって、病院のカルテに書き留められていく彼女の幼少期から現在に至るまでのストーリーを読者はともに追いかけていく。」
さて、なぜこのあらすじがそれほど重要ではないか。それは人生の時々で起こる出来事ではなく、現在に至るまでの時間の中で自然と繰り返されてきた(抑圧されてきた)ことが重要であるからである。
ひとつの事件で何かが変質することを書くのではなく、ホコリが静かに、音を立てずに、満遍なく積もっていく過程のように、ある女性が積み重ねてきた人生について滾滾と綴られている。
恐るべきことに、こういう静かに降り積もってきた抑圧や不満というのは、一人の女性が体験したことではなく、韓国の多くの女性が「これはあのときの私だ」と感じたという。
(韓国の女性全員が賛同したというのは誇張しすぎているのかもしれないが、この本が売れた理由のひとつとして、確実に「共感」があるのだろう。)
一昔前であっても、ここまで自分を投影できることが理由で読まれた小説というのはあったのだろうか。小説は非日常や部分的な感情移入によって成り立つことがほとんどだと思っていた私にとっては驚きであった。
●不自然な統計数値や歴史的背景の説明
本書の特異な点として、統計数値や歴史的背景の説明が挟まれる点があげられる。
世界的な男女格差についてのデータなど、小説らしさを損なうことを恐れずに、何度も不意にデータや数字が差し込まれている。
主人公の名前である「キム・ジヨン」でさえも、本当に82年に生まれた女の子の中でいちばん多かった名前にしたという。
しかしながら、論文などの表記に則った正しい書き方をしているわけではないし、統計データが必ずしも必要であるとは思えない。(場合によっては、小説を読んでいるのに堅苦しい統計データが出てくることに嫌悪感を示す人さえいるのではないか。)
それでも、統計データを差し挟むことの意味は?
小説=フィクションであるが、それでもこの小説で起こる出来事は現実に存在しているのだということを示したかったのではないだろうか。
100人の実在する女性のインタビューをまとめたものではないけれど、それでも、私たち女性はこんな人生を送ってきたのだということを表明するために、フィクションの中に何度も現実の統計データを挟み込んだのではないか。
●名前をなくした男たち
あとがきでも触れられている通り、本書には男性の名前がほとんど出てこない。
キム・ジヨン氏の夫の名前以外は、「キム・ジヨン氏の弟」「キム・ジヨン氏の父」といった具合である。男性の名前が文中には登場しないことに対して、女性の名前については何度も表記されている。
本書での主人公は女性で、男性はあくまでも男性としたくくりで書き表したかったのだろうか。
不思議なことに、さいごに「あとがき」でこの特異点について語られるまで特に違和感を覚えなかった。「少し堅苦しい文体だ」としか思わなかった。
このようなさりげない徹底した文体が作品自体に及ぼす影響は定かではないが、こういう工夫がこの作品らしさを作り上げるひとつの要素になっているのであろう。
●救いはあるのか
本書の終わり方については、特に救いがあるわけではない。
むしろ、「これからも救われないのではないか?」と絶望するような終わり方であるようにさえ思う。
結末を仔細に語るのは控えるが、抽象的に書くならば、「この本を読んで男性の中にも理解者が出てくるかもしれないけれど、それでも男性は(無意識のうちに)私たちのことを抑圧しているのだ」と言わんばかりの結末であった。
問題提起をして解決策を書かないというよりも、「それでも私たちは今日に至るまで救われていないのだ」と叫び続けた内容であったように思う。
昨今の小説にありがちな、曖昧なところで突然終わってあとは読者に委ねます〜という書き方ではなく、最後まで悔しさとジレンマを書ききったことがとても印象的であった。
●おわりに
フェミニズム論争なんてネットを開けばいくらでも転がっている。
「私は20代だけど、もう差別なんてないと思う。すでに平等、あとは自分たちの腕っぷしで頑張っていきたい。」といったバリキャリぶって斜に構えた意見だとか(なんか見た)、こういう差別があったとか、いろんな意見が転がっている。
私自身は別にフェミニストではないと思っているけれど、だからといってこういう問題が自分に無関係であるとは思わない。
先日放送された情熱大陸で上野千鶴子氏が「その都度、”ムカつく”って言うことを1つ1つその時その場で言っていくことの蓄積の結果、今日の私達がある。いちいち目くじら立てて面倒臭い女になっていく」と言っていたが、少なくとも、いちいち意識するべきトピックではあるように思う。そう考えたときに、あまり対峙したくない現実を小説という形で摂取できるというのは、すごく良いのではないか。
■祝!映画化!ポスター・・・?あー。
もともと、韓国の映画ポスターはおしゃれだと話題になっている。
(おしゃれというよりも、作品の雰囲気をコピーではなくデザイン全体の雰囲気で伝えようとするスタンスなのだと思う。)
カンヌで話題をさらった『パラサイト』のポスターなどは特に記憶に新しい。
この意味不明な改変が日本映画界の敗北そのものって感じ。 pic.twitter.com/hFVkqQqd3Y
— いーえく (@aqilaEX) February 10, 2020
さて、パラサイトを経た、『キム・ジヨン』の映画ポスターはどうだろうか?
●韓国版ポスター
「誰もが知っているが誰も知らなかった あなたと私の話」

●日本版ポスター
「大丈夫、あなたは一人じゃない 共感と絶望から希望が生まれた」

(こちらのツイートから翻訳をおかりしました↓)
82年生まれキムジヨンのポスター、オリジナルの韓国版と日本版で夫の側に添えた言葉が全く変わってる。韓国版「誰もが知っているが誰も知らなかった あなたと私の話」日本版「大丈夫、あなたは一人じゃない」いやいや…日本版の妻に寄り添う夫の言葉みたいなコピーは、原作の内容とかけ離れすぎだろ pic.twitter.com/AxR390Yfm4
— Kちゃん (@lovebtsgold) June 18, 2020
●ポスターのデザインっていうかコピ〜〜〜〜〜!!!
韓国版:誰もが知っているが誰も知らなかった あなたと私の話
日本版:大丈夫、あなたは一人じゃない 共感と絶望から希望が生まれた
そして極めつけがこちら。
『82年生まれ、キム・ジヨン』
— 映画『82年生まれ、キム・ジヨン』 (@KimJiyoungJP) June 18, 2020
予告映像も到着しました📽️
誰かの妻で、母で、娘である”あなた”の人生を生きるジヨン。どうしようもない絶望を抱えながら、それでもなお、「全力でいきますよ」と笑顔を見せる彼女が出した答えとはー?#これは私の物語 #82年生まれキムジヨン pic.twitter.com/pBCRYTzJUF
「誰かの妻で、母で、娘である」ことへの抗えなさについて、本書籍は声なき声をあげていたのである。女性への悪意なき無言の抑圧は当然の風景となり、もう違和感さえ抱くことができていないのだと、本書籍は叫んでいたはずなのである。
抗えない大小の環境や出来事の蓄積によって、「誰かの◎◎」ではなく「私」であることを大切にできない人生を、キム・ジヨンに仮託していた。
どうしたら、
大丈夫、あなたは一人じゃない 共感と絶望から希望が生まれた
というコピーになるのだろうか。
どうしたって一人だったし、共感を得られなくて、どうしようもなかった話なのである。終わり方さえも、「それでも私たちは今日に至るまで救われていないのだ」と言わんばかりであったのに。
希望なんてないのだ(現時点では)と言う締め方をした小説が、映画化されて希望が付与されたのだろうか?
それはそれで絶望的な話である。
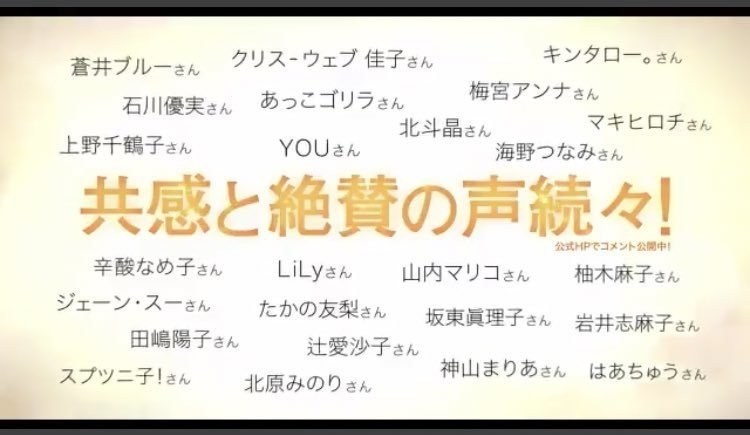
宣伝動画の中では、共感の嵐として大量の女性有名人の名前が登場する。
全部、女性である。男性はいないのである。
あえて女性だけを選んだのではなく、最初から男性が必要かどうかも検討されていないものだろう。皮肉でも何でもない、ただの単細胞である。
●救いはあるのか
ポスターにも写っている俳優のコン・ユさんが、とても出演する作品を選ぶ人らしいので、毎度こだわって映画に出演する人なのであれば、きっと、たぶん、大丈夫なのだろう・・・か?
作中では、主人公であるキム・ジヨンのいちばん近くにいながら何も理解できなかった人として描かれている彼に現実世界で一縷の望みを託すとは随分な皮肉である。(あるいは、作品をよっぽど慎重に選んで出演している彼でさえ、そもそもの前提としてこの作品になにも絶望を抱くことができていないのだとしたら?それこそ大層な悲劇である。)
●筑摩書房にのぞみを託して
いまのところいちばん筑摩書房さんの宣伝がしっくりきている。
映画、見に行くべきかどうか。
絶望を突きつけることで希望を探そうとするきっかけになるはずの小説が、絶望の上塗りをしてくる映画にならないよう願うばかりである。
映画『82年生まれ、キム・ジヨン』が10/9より新宿ピカデリー他全国ロードショー!
— 筑摩書房 (@chikumashobo) June 20, 2020
原作小説『82年生まれ、キム・ジヨン』の人物相関図、西村ツチカさん描き下ろし絵付きでの本編抜粋、著者からのメッセージ等を収録した📕ストーリーブックを無料公開中。試し読みもできます↓https://t.co/ZRghbl4Iv1 pic.twitter.com/t1Dwprqc5S
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
