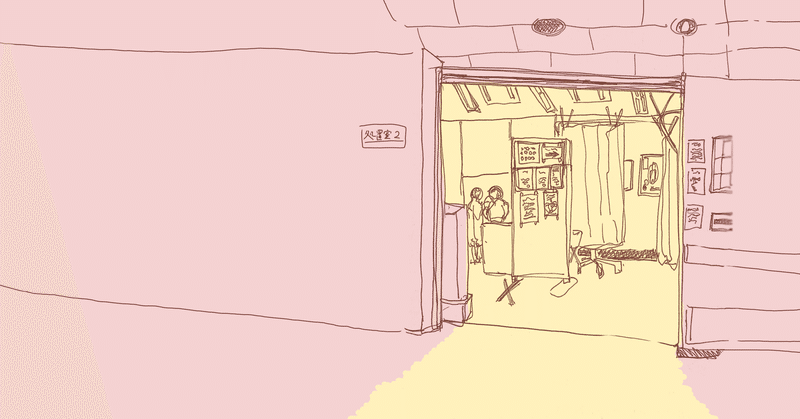
アスペルガーは消えて行く
発達障害やうつ病のような目に見えない病気を診断するとき、その基準は誰が決めているのか。医者が長年の経験と勘で、この人は発達障害で、この人は単なるなまけ癖だと当てているのか?と言うと、もちろん違う。
現在、臨床の現場で精神疾患を診断する際の基準としては、アメリカ精神医学会が刊行したDSM:精神障害の診断と統計マニュアル(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)が標準的に用いられている。最新版は2013年に改訂された第5版で、DSM-5と称されている。
そこに記載されている診断基準に当てはまるかどうかを見きわめて、医者は患者の病名を推測しているわけだ。
ちょっとややこしいのは、DSM-5に基づいた見立てで治療をしていても、障害年金や自立支援医療などの申請の際に行政機関に提出する診断書においては、WHOが制定したICD:国際疾病分類(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)の第10版による分類が適用されることだ。ICDも最新の第11版はDSM-5に即した分類になっているのだが、現行で使用されている第10版は一つ古い版になるため、病名や分類の仕方にDSM-5とは違っているところがある。
たとえば、ICD-10には広汎性発達障害という分類があり、その下位分類として旧来の自閉症とアスペルガー症候群が置かれ、別々のものとして区別されているのだけれど、DSM-5とICD-11ではそれがなくなった。知的障害がともなう自閉症と、そうではない自閉症との間に明確な境界線が引けるわけではないという考え方のもと、どちらも同じASD:自閉症スペクトラム障害に統一されたのだ。
スペクトラム(連続体)と言うのは、重い自閉症から軽い自閉症、さらには健常者までが、境目なく一つに繋がっていることを示す概念だ。
私の場合で言うなら、診察室で医師に告げられたのはDSM-5に準拠した「ASDとADHD」だったが、(ちなみに、ASDとADHDの併存が認められたのもDSM-5以降のこと)障害年金申請のために提出した診断書には、ICD-10に基づいた病名「広汎性発達障害」の方が記載されることになった。
このように、病態が変わったわけではないのに、場合によって疾患名が違ったりすることが、現段階では割とよくある。
ただ、ICDの方もすでに各国で移行の準備が進んでおり、遠からず行政手続きでも第11版の方が適用されるようになるはずだ。
それにともなって「ASD」がスタンダードになっていくのは、個人的にいい傾向だと思う。
私は、アスペルガー症候群という名称がどうしても好きになれない。
と言っても、アスペルガーの名前の元になったドイツの医師、ハンス・アスペルガーがナチスに加担していたから嫌だ、というわけではない。(全く関係なくはないけれど)
私が嫌なのは、わざわざ古い疾患名を用いてまで「アスペルガー」と自称するときや、他称するときの、「我々は(あなた方は)知的障害者とは違う」と言う、特権意識みたいなものだ。たとえ無意識的にでも「知的障害の有無」を区別することがそれほど重要であると思うのは、知的能力、生産性の有無で人に序列を付ける社会の価値観を、あまりにも自然に内面化しすぎているんじゃないだろうか。
知的に低い自閉症者と、知的に高い我々は違う。そんな差別を、私はしたくもされたくもない。
2018年に翻訳されたジュリー・ダシェの漫画『見えない違い 私はアスペルガー』も、原題はもともと『La différence invisible(見えない違い)』のみだった。そこにあえてアスペルガーという「わかりやすい」疾患名を入れたのはなぜか。そこにあるのはマーケティング上の都合と、「自閉症では恰好がつかないから」くらいの軽い考えなんじゃないだろうか。
私はその「軽さ」が、どうしても喉に引っかかってしまう。
アスペルガーではなくて自閉症では、なぜ「恰好がつかない」のか?
アスペルガー症候群という診断名が消えて行く社会で、私たちはそろそろそのことについて考えなくてはならないんじゃないだろうか。
私はアスペルガーじゃない。私は自閉症スペクトラムだ。同じ自閉症圏の住人の中には、知的障害がある人もいれば、知能テストで高いスコアを出す人もいるらしい。私は多分、その真ん中くらいのところにいる。あなたも近くにいるだろうか。もっと遠くにいるのだろうか。どちらにしても、誰も変ではないし、特別でもない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
