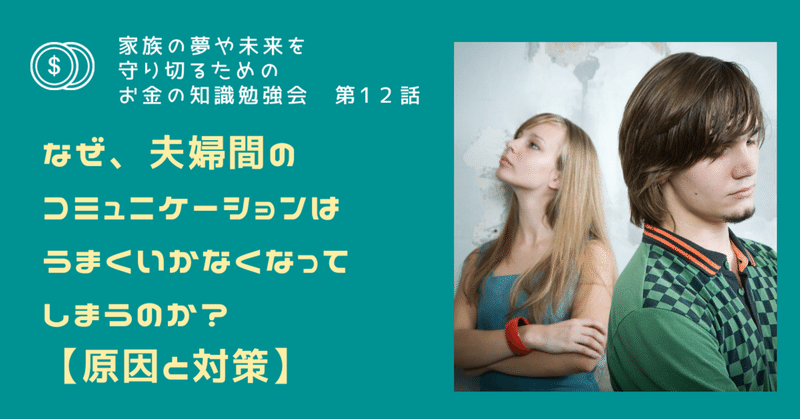
【だからぼくはお金の知識を届けたい #12】なぜ、夫婦間のコミュニケーションはうまくいかなくなってしまうのか?【原因と対策】
こんにちは、「自殺者ゼロの生きるに値する社会をつくること」を目的に活動しているカウンセラー・コーチ・作家の水樹ハル(@harumizuki423)です。
今回は、
「なぜ、夫婦間のコミュニケーションはうまくいかなくなってしまうのか?」
というテーマでお話をしていきたいと思います。
先日ファイナンシャルプランナーの金山さんと「家族の夢や未来を守りきるためのお金の知識勉強会(第3回)」を開催したんです。
そのテーマが「子どもへのお金の教育」で「なぜ、子どもの頃からお金の教育を受けておいた方が良いのか?」という内容だったんです。
▼第3回勉強会の様子
この勉強会の中で、金山さんが、
「子どもへのお金の教育って、夫婦間のコミュニケーションを豊かにするんですよー!」
と話していたんです。
こう聞くと、最初は、
「え??どういうこと?」
と思われるかもしれません。
これが今回の「なぜ夫婦間のコミュニケーションはうまくいかなくなってしまうのか?」という問いにも関係するんですけど、、、結論からいうと共同作業が減るから夫婦間のコミュニケーションはうまくいきにくくなるんですね。(コミュニケーション習慣が弱るという方がニュアンスが近い)
「共同作業」が減ると、人間関係にズレが生じてくる
例えば、日本って「ワンオペ育児」という言葉がありますよね。
女性が育児をして家事をして場合によっては共働きだったら仕事までするわけで・・やることがいっぱいある。
「夫・家族に相談したらいいじゃん」
と言われたとしても、
「全部自分でやらなきゃいけないと思ってしまうんです」
「つい、なぜか自分でやっちゃうんですよね・・・」
というふうに頼ったり相談することが苦手な方がめちゃくちゃ多いんです。
(ぼくがこれまでカウンセリングの活動をさせてもらっていての肌感ですが)
▼ちなみにカウンセリング経験からこんな本も出しています
「つい、なぜか、なんとなく」
ってことは、これまでずっと一人でやってきた習慣から無意識のうちにそう思い込んでしまってるわけです。
このように、
・うまく相談できない
・うまく話を聞けない
というコミュニケーション不足が、夫婦の関係が冷え込んでいくわけです。
ぼくは、その思い込みをを切り替えるためにカウンセリングやコーチングをさせていただいてるんですが、今回の金山さんの、
「子どもへのお金の教育って、夫婦間のコミュニケーションを豊かにするんです」
という全く違う視点からの話がすごく面白かったので紹介させてください。
どうすれば「共同作業」を増やせる?
「大事なことなのに話を聞いてくれない」
「関心を持ってもらえない」
という時って寂しいですよね。
でも、忘れがちなんですが人間は脳を持つ生き物ですよね。その脳は「重要だ!」と思っていない情報に興味を持ったりキャッチするのは難しいんです。
なので、まずは、夫婦ともに「これは重要なことだ!」と思えるものを設定すれば良いんです。
そのテーマが、「子どもへのお金の教育」!
親としては、
「子どもが経済的に困らないようにしてあげたいな」
と思っていませんか?
ここで、正直、
「まぁ、そりゃそうだけど・・・」
と思われているかもしれません。
なので、もう少し具体的に話をさせてください。
ファイナンシャルプランナーの金山さんの家(金山家)では、「靴をキレイに並べたら10円ゲット」というように家事のリストがあって、銀行口座2つと貯金箱も2つあります。
この環境を用意することで、2人の小学生の男の子は、
「これを毎日すれば、1ヶ月で300円か・・・」
というように考えるようになったり、
「他にやってほしいことない?」
というように交渉したりするようになるんです。
なので、家事を家族に「手伝って」といえないママも、「手伝って」と言わなくて良いし、子どもからしても「やらされ感」がない。例えば、子どもがお風呂掃除やお米をといで炊いてくれたら、ママさんが家事をやる時間が減り、心に余裕も生まれますよね。(もちろん、やり始めはやり方を教えたり見守る必要がありますが)
この、「やってほしい家事のリスト」や「銀行口座2つと貯金箱2つ」を用意したり、、、そのことについて話す「共同作業」が増えて、コミュニケーション習慣がつくんです。
子どもの頃の習慣が、大人になってからも影響する
もちろん、
「子どもとお金の話をするのは抵抗がある」
「お金を渡さないと何もやらなくなるんじゃ?」
という意見もあるかもしれません。
でも、子どもが「お金の取り扱い方」を考えたり、お金に向き合う際には「自分自身」と向き合うことにもなるんです。「稼いだ後、何にどう使うのか」の部分です。
例えば、
「500円のうち150円は将来のために口座に貯めておこうかな・・・」
「あと100円は今度おじいちゃんが誕生日だから、人のために使う貯金箱に貯めておこう」
というふうに、自分と向き合いながら考えることになるんですね。この習慣が、のちに社会で働いて報酬をもらった時のお金の取り扱い方に繋がっていきます。
また、家族というコミュニティーの中で役割を持って、プロセスを評価してもらえると、努力する子どもにもなっていきます。そうしてコミュニケーションをとる習慣ができてくると、お金以外のテーマでもコミュニケーションが生まれやすくなって1人で悩みにくくなる。
だから家族間のメンタルケアにもすごく良いなーと感じました。
この「家族の夢や未来を守り切るためのお金の知識勉強会」をやっている金山さんは、
「チャレンジできる家族を増やす」
という目的で活動していますので、「たしかに!自分も子どものチャレンジを見守れる親でありたい!」と興味のあるあなたはぜひ、今回のテーマに関連する動画をご覧ください。
↓↓
「第3回お金の知識勉強会」の振り返り動画
▼勉強会オープニング価格:390円!
「家族・子どもの夢や未来を守り切るためのお金の知識」に興味のある方は、ぜひ勉強会で一緒に学んでいきましょう!過去のアーカイブ動画は全て公開しています!(このプロジェクトの始まり「第1話」)
次回
次回は、第4回勉強会の打合せ!
「なぜローンを学んでおくことが重要なの!?」
※noteマガジン「月刊水樹ハル」で順次お届けしていきます。
このプロジェクトが始まった経緯(第1話)
▼note「月刊水樹ハル」で配信しているプロジェクト
水樹ハルの著書
水樹ハルのSNS
ここから先は

水樹ハルの「まだ世には出せないお話」
ストーリー制作専門のWebライター、カウンセラーとして、「チャレンジを応援しあえる世界」を実現することを目指す、水樹ハルのnoteマガジン…
いただいたサポートは、ありがたく活動費にさせていただきます😃
