
安全に必要な専門知識? ~◯×が判断できるように~
こんにちは! あたたけ です。
前回、『Safety-Ⅱ』を実現するためには、
人に『専門知識』と『倫理観』が必要という話をしました。
※前回記事はこちらです。
今回はどのような専門知識がSafety-Ⅱの実現に必要かを考えていきます。
おさらいですが、Safety-Ⅱに関する解説論文には、
『4つの能力』と『補完的要件』が示されています。

で、前回記事では以下のようにまとめました。
専門知識:正しいことがわかる、適切な判断のベースとなる
⇒4つの能力『対処できる、監視できる、予見する』に繋がる
ということは、専門知識(技能も含む)としては、
・異常に対処できる
・異常を監視できる(現在の異常に気づくことができる)
・異常を予見できる(今後、起こりうる異常に気づくことができる)
の3つが出来るための知識が必要だと考えられます。
組織全体で考えると、部門や役職で『異常』の範囲が変わってきますが、
ここでは、『食の安全』を『現場』で実現することに絞ってみましょう。
1.異常とはなにかを知る!
判断基準を明確にしないと判断できません。
また、判断基準がわかれば、『監視』『予見』に繋がります。
単純に考えれば『安全ではない状態、安全をおびやかす状態』が
異常となるでしょう。
わかりやすいのが『食中毒とは、食中毒に繋がる状態とは』ですね。
金属片の混入などまで考慮すると、
食中毒ではなく『食品事故』とするのが良いかもしれません。
ここまでは、まぁ、わかりやすいです。
あいまいになりがちなのが『事故ではないが世間が要求すること』です。
例えば、『毛髪』とか『行政機関による細菌検査基準』とかですね。
毛髪ってイヤなのはイヤですけど、
人によってけっこう、捉え方が違うんですよね。
ちなみに、私はこんな仕事のわりにそこまで気にしてないです。
入っていても、自分で取り出して終わりですね。
虫は、、、、、モノによりますね。
人により捉え方が違うと、当然、判断基準も変わってきます。
ですので、組織にとっての異常(≒会社の品質基準)をまずは明確にし、
それを教育することが必要なのではないでしょうか。
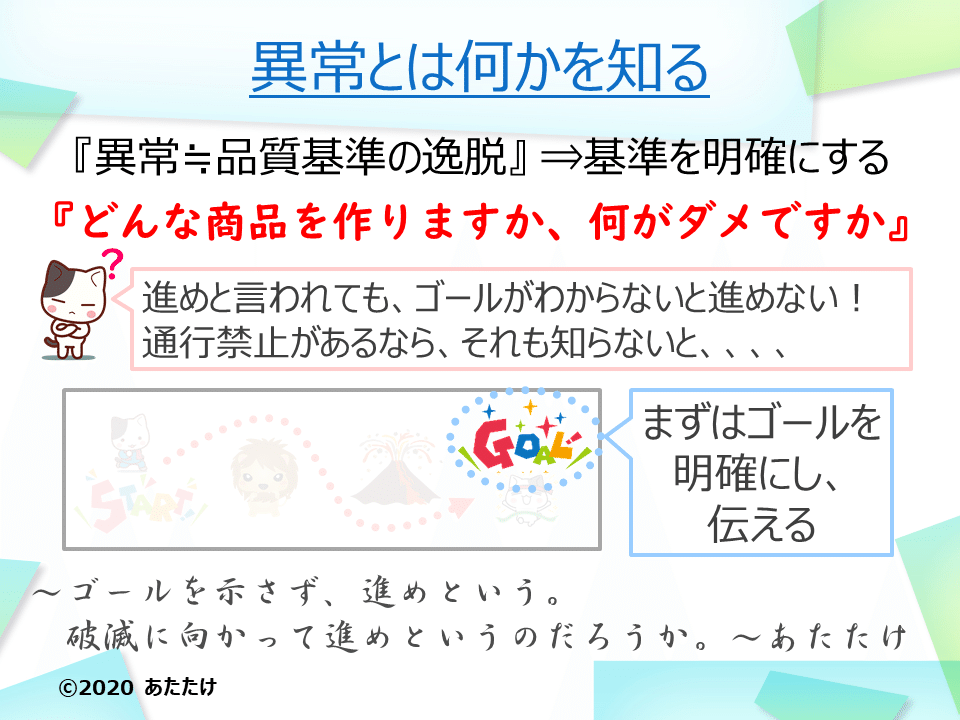
2.異常がなぜ起こるか&異常への対応方法を知る!
異常を監視、予見しても正しく対処できなければ異常は防げません。
なぜ異常が起こるのかがわかれば正しい対処に繋がりそうですね。
ここで問題となってくるのが、『異常の原因をどこまで想定するか』です。
Safety-Ⅰの場合は、限りなく想定して対応方法を事前に決めます。
が、その『限りなく想定する』ことが難しいというのが
Safety-Ⅱを考えるきっかけですので、ここのさじ加減が
Safety-Ⅱにうまく取り組む重要なポイントになりそうですね。

ちなみに、あたたけ的には、食の安全については
『食中毒予防3原則』に関連する知識で良いのかなぁと思っています。
食中毒とは⇒食中毒はなぜ起こるのか⇒どうすれば防げるのか(=3原則)
という感じですね。
この辺りに興味がある方はこちらの記事もご覧ください。
『菌を食品につけない(汚染防止)』だけ考えても、
汚染経路は細かく見ると限りなくありそうですが、
汚染源(≒食中毒菌がいるところ)と対象(≒そのまま食べる食品)は
ほぼほぼ明確になっているので、
それら、『異常の最初と最後』を伝え、途中はうまくやってもらう、
みたいなイメージです。
ダメなことを考えている時点でSafety-Ⅱから逸れている気もしますが、、
個人的には3原則という基本を理解してもらい、
各自で応用(臨機応変な対応)をしてもらうのが良いのかなと思います。
3.まとめてみると?
さて、ここまでは『Safety-Ⅱを実現する(≒柔軟に対応する)』ための
理想的な姿を考えてきましたが、
実際のところは、既に(Safety-Ⅰに基づいた)ルールがあります。
それとの兼ね合いを考えると、まず考える&教育することは、
『既存のルールの目的・意味』ではないでしょうか?
目的・意味を知ることは単純にルールを守る意欲に繋がります。
で、それを継続することが、『専門知識の蓄積』に繋がっていく。
ついでに言えば、『目的・意味が不明確なルール』は
惰性で行っているだけの不要なルールかもしれません。
ということで、
『あたたけ的今後の食品安全マネジメント 最初の一歩』は
以下をご提案します。
①既存のルールの目的・意味を改めて整理する。
目的・意味が不明確なものは、本当に継続が必要か検討する。
(目的・意味が明確になっても、有効性まで含め検討が望ましい。)
②上記の『ルールの目的・意味』と『食中毒予防3原則(+α)』を
今後の教育項目とする。

次回は、あたたけが考える『倫理観』の話の予定です。
それでは、今回はこの辺りで!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
