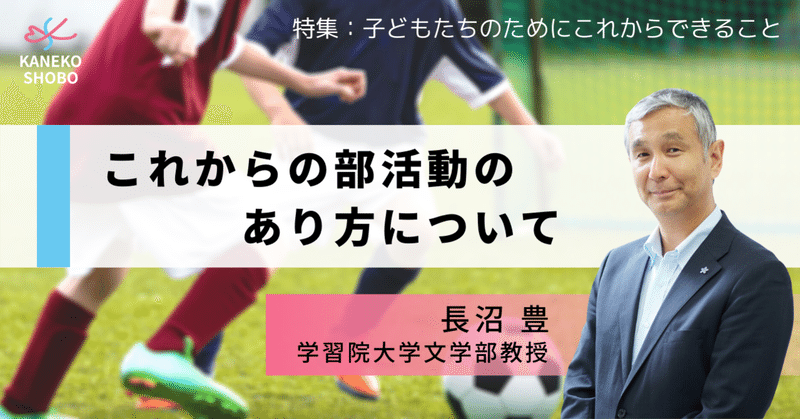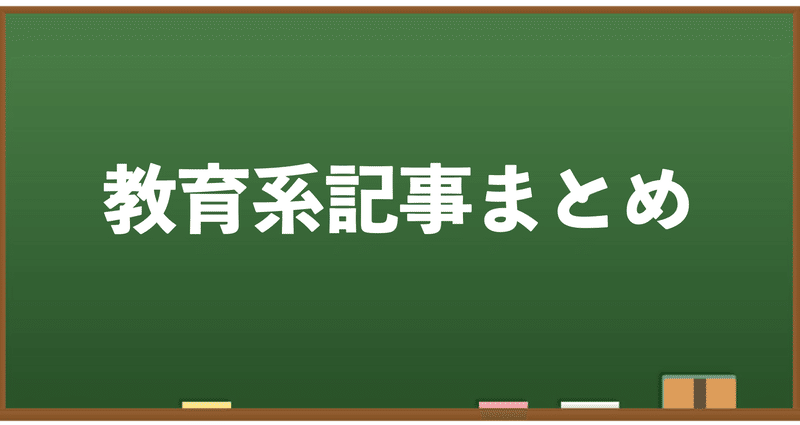
教育に関して自分なりの考えや、思ったことを書いていきます。
自分が今の教育に関して正直に思ったことを書きますので、もし、違う意見等ありましたらコメントいただけるとありがたいです。…
- 運営しているクリエイター
2020年8月の記事一覧

Google meet、Google classroomを利用されている学校教育機関の皆さま、ご活用ください 〜無料資料も添付しています〜
🕛この記事は3分で読めます🙌 久しぶりに遠隔ツールについて投稿します、いえやすです☺️ 様々な学校教育機関が、外部講師の授業対応、就職・進学説明会、その他の説明会でどのようなリモートツールがよいのか、判断しかねる部分があるかと思います。 リモートで外部の先生に授業を開催頂く、または授業ではなくても何かしらの行事で外部の方とリモートで接続する際にzoomやteams等があるかと思いますが、 既に「Google Suite」を使用されている学校教育機関であれば、先方に「学