
緑肥栽培の講習会で農業とエコを学んだ
2022年11月6日
地元の農業振興会主催の「緑肥を活用した野菜づくりの講習会」に参加してきた。講師の米倉賢一先生は「伊豆陽なたビオファーム」代表
緑肥を使いこなして10年間無農薬無施肥で農業をやっているらしいです、めっちゃすごい、憧れます。

今までどう考えても無施肥栽培の仕組みが理解できなかったんですよね。だって必ず作物を収穫したらその分の栄養素が畑の外に出ていくわけですから、その分を肥料として畑に補給しないとなくなっちゃうじゃないですか。でも講習を聞いてると何となく仕組みが分かってきたように感じました!
先生の畑は4面の畑を1年ごとに隣にずらしながら栽培することで連作障害を回避しており、4年で一周します。
主にナバナ、ニンジン、ジャガイモ、タマネギ、キュウリ+αで作物を作っているのですが、作物を植え付ける半年前には必ずイネ科とマメ科の緑肥を栽培しすき込むんです。
イネ科は根っこを土深く伸ばし、畑に散らばっている栄養分を吸収してくれて、水はけのいい畑に整えてくれます。
マメ科は、根っこの根粒菌が大気中にあるチッソを根っこにためてくれるので、土壌に栄養を蓄えてくれるんです。
それらをトラクターで土にすき込むことで、先生の畑は10年以上も無施肥で栽培できるんですね。
緑肥ってすごく面白くて、土をむき出しにしているところには生き物が見えないけど、枯れ草が敷いてあったり、草で日影ができているとそこにはダンゴムシやワラジムシをはじめいろんな虫たちが暮らしていることに気付きます。それらの土壌動物(虫)にも生態系があり、枯れ草を食べて分解して、それをたべる土壌微生物がいて、それらの死骸も栄養分として土に帰る、奥が深いですね。
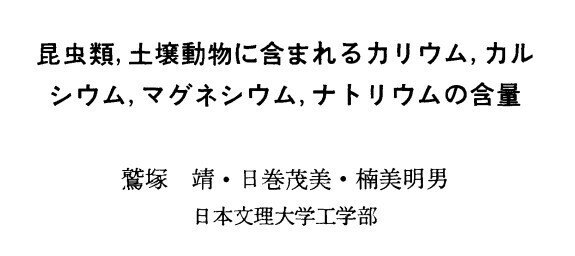
これらを使いこなしたら実は肥料も農薬もいらない栽培が、理論上はできるんです。
米倉先生は緑肥栽培は地球温暖化削減にも貢献できることを教えてくれました。先生調べだと、化学肥料1トン作るのに約760Lの原油を使用し、CO2にすると2.07トンを排出するそうです。
緑肥を肥料の代わりにすることで、化学肥料を作る分と、それを輸送する分のCO2 排出をなくすことも可能です。また、大気中のCO2を吸収した植物は炭素として土壌に吸収されるため、実は土壌には森林よりも多くのCO2が閉じ込められているんです!・・・って先生が言ってました。

米倉先生のように、化学肥料を使わなくていい栽培をして、いずれは地域の農家さんの手本になれるような農家になりたいとおもった。私一人の小さいエコから、周りを巻き込んだ大きなエコになるんだ”!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
