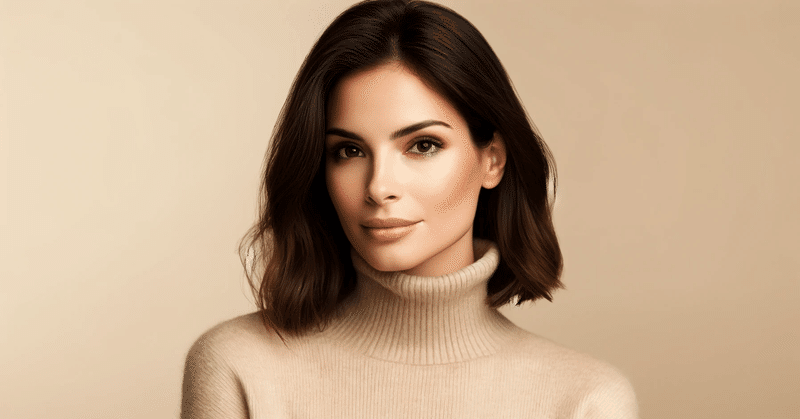
論文まとめ356回目 Nature Twitterによる1月6日の暴動後の大規模凍結アカウント措置は、デマ情報の拡散を抑制した!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなNatureです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
A disease-associated gene desert directs macrophage inflammation through ETS2
炎症性疾患関連の遺伝子砂漠領域はETS2を介してマクロファージの炎症を制御する
「この研究は、複数の炎症性疾患のリスク因子である遺伝子ETS2に着目しました。マクロファージでETS2の発現が増えるとさまざまな炎症応答が亢進することを明らかにしました。ETS2は炎症性サイトカインの産生や活性酸素の放出など、炎症性マクロファージの機能を統合的に制御する中心的な役割を果たしていました。ETS2の働きを抑えることで病気に関わる過剰な炎症を抑制できる可能性が示されました。」
Post-January 6th deplatforming reduced the reach of misinformation on Twitter
1月6日以降のTwitterによるアカウント凍結措置は、デマ情報の拡散を抑制した
「2021年1月6日の米国議会議事堂襲撃事件後、Twitterは事件に関わったアカウント7万件を突然凍結しました。この大規模措置は、凍結されたアカウントだけでなく、それらのフォロワーによるデマ情報の拡散も大幅に減少させました。これは、ソーシャルメディアプラットフォームが公共の議論をコントロールする力を持っていることを示す重要な出来事でした。」
Observation of 2D-magnesium-intercalated gallium nitride superlattices
2次元マグネシウム挿入窒化ガリウム超格子の観察
「窒化ガリウムは青色LEDなどに使われる半導体ですが、原子1層分のマグネシウムを挟み込むことで、規則正しい層状の「超格子」構造ができることを発見しました。窒化ガリウムの結晶が大きく圧縮されて物性が変化し、電気を流しやすくなるなどの効果が見られました。金属と半導体の複合超格子は珍しく、応用にも期待が持てる成果です。」
Scaling neural machine translation to 200 languages
200言語に対応するニューラル機械翻訳の拡張
「Facebookの研究チームが、200もの言語間で翻訳できる巨大な機械翻訳モデルを開発しました。今まで翻訳が難しかった低リソース言語にも対応しており、人工知能による自動翻訳の可能性を大きく広げる成果です。訓練データを増やす工夫や、言語間の知識移転を促進する新しいアーキテクチャの採用により、既存の最先端モデルを大きく上回る性能を実現しました。この技術により、言語の壁を越えたコミュニケーションがより身近なものになるかもしれません。」
Visualization of oxygen vacancies and self-doped ligand holes in La3Ni2O7−δ
La3Ni2O7-δにおける酸素欠損と自己ドープされたリガンドホールの可視化
「La3Ni2O7-δは高圧下で80K付近で超伝導を示す物質です。最新の電子顕微鏡技術を用いて、原子レベルで酸素欠損の分布を直接観察することに成功しました。さらに分光測定から、化学量論組成の物質中ではNiサイトから酸素サイトにホールが自己ドープされていること、酸素欠損量が増えるとそのホールが消失することを明らかにしました。超伝導の理解に重要な知見を与える研究です。」
MYCT1 controls environmental sensing in human haematopoietic stem cells
MYCT1はヒト造血幹細胞の環境感知を制御する
「ヒトの造血幹細胞をうまく培養して増やすことは難しい課題でしたが、MYCT1という因子を発見しました。MYCT1は細胞のエンドサイトーシス(物質の取り込み)を適度に抑制することで、造血幹細胞が周囲の環境からのシグナルを適切に感知し、幹細胞性を維持することを可能にします。MYCT1の発現を保つことで、培養した造血幹細胞の機能が改善されることもわかりました。」
要約
炎症性疾患の遺伝的リスク因子ETS2が炎症性マクロファージを制御する
多くの炎症性疾患のリスク因子が集中する21番染色体長腕22領域(chr21q22)に注目し、その領域がETS2遺伝子の発現を制御することで炎症性マクロファージの機能に影響を及ぼすメカニズムを明らかにしました。chr21q22領域の遺伝的多型がパイオニア転写因子PU.1の結合に影響し、ETS2遺伝子の発現を増加させることを示しました。ETS2の発現増加は炎症性サイトカインや活性酸素の産生など、炎症性マクロファージの主要な機能を亢進させることがわかりました。このメカニズムの抑制が新たな炎症性疾患の治療標的となる可能性が示唆されました。
事前情報
chr21q22は複数の炎症性疾患のリスク領域だが、どの遺伝子に作用するかは不明だった
ETS2はマクロファージの炎症に関与すると考えられるが、詳細な役割は不明だった
行ったこと
CRISPR-Cas9によるchr21q22領域やETS2遺伝子の編集
ETS2のmRNA過剰発現実験
マクロファージの遺伝子発現や機能の解析
ETS2結合部位の同定(CUT&RUN)
炎症性腸疾患の腸管組織や原発性硬化性胆管炎の肝臓でのETS2の役割の検討
検証方法
MPRA(massively parallel reporter assay)によるchr21q22の機能的なSNPの同定
アリル特異的なChIP-seqやATAC-seqによる転写因子PU.1の結合の解析
RNA-seqやChIP-seqによるETS2の下流遺伝子の同定
マクロファージのサイトカイン産生や活性酸素産生、貪食能の測定
炎症性腸疾患の腸管や原発性硬化性胆管炎の肝臓のsingle-cell RNA-seqやspatial transcriptomicsの解析
分かったこと
chr21q22のrs2836882がPU.1の結合に影響し、ETS2の発現を制御する機能的なSNPである
ETS2はマクロファージにおいてサイトカイン産生、活性酸素放出、貪食能など炎症応答全般を統合的に制御する
ETS2はマクロファージのHIF1AやPFKFB3の発現を制御し解糖系の活性化にも関与する
炎症性腸疾患や原発性硬化性胆管炎の病変部ではETS2の発現が亢進している
ETS2の下流で発現変動する遺伝子群は炎症性腸疾患のリスク遺伝子に有意に濃縮されていた
研究の面白く独創的なところ
chr21q22のようなGWAS疾患リスク領域に機能的に迫った点
転写因子PU.1とETS2の協調的な作用を明らかにした点
ETS2が多様なマクロファージの炎症応答を統合的に制御することを示した点
実際のヒト炎症性疾患の病変部でETS2の役割を実証した点
MEK阻害剤がETS2の下流で炎症を抑制することを示した点
この研究のアプリケーション
chr21q22-ETS2経路を標的とした新たな炎症性疾患の治療法開発の可能性
MEK阻害剤による炎症性腸疾患など炎症性疾患の新たな治療選択肢の可能性
ETS2の下流遺伝子群を利用した炎症の新たなバイオマーカーの開発の可能性
著者と所属
C. T. Stankey (The Francis Crick Institute) C. Bourges (The Francis Crick Institute)
L. M. Haag (Charité–Universitätsmedizin Berlin) (他39名、主要著者のみ記載)
詳しい解説
この研究は、複数の炎症性疾患のゲノムワイド関連解析(GWAS)で同定された遺伝的リスク領域である21番染色体長腕22領域(chr21q22)に着目し、その領域内の遺伝的多型がどのように疾患リスクに関与するのかを解明しました。
chr21q22領域はいわゆる「遺伝子砂漠」と呼ばれるタンパク質をコードする遺伝子の乏しい領域ですが、炎症性腸疾患、強直性脊椎炎、原発性硬化性胆管炎、高安動脈炎など複数の炎症性疾患のリスク領域として知られていました。しかし、その領域内のどの遺伝子多型が、どのようなメカニズムで疾患リスクに関与するのかは不明でした。
研究チームは最初に、chr21q22領域内の遺伝的多型rs2836882に注目しました。MPRAという解析から、rs2836882がマクロファージ特異的なエンハンサー活性を持ち、疾患リスクアリルで転写活性が上昇することを見出しました。さらに、rs2836882リスクアリルではパイオニア転写因子PU.1の結合が増加することを明らかにしました。クロマチン相互作用の解析から、rs2836882を含むエンハンサーはETS2遺伝子プロモーターと相互作用し、ETS2の発現を正に制御することがわかりました。
次に、ETS2の炎症性マクロファージにおける役割を明らかにするため、CRISPR-Cas9によるETS2遺伝子のノックアウトやmRNAによる過剰発現実験を行いました。ETS2の発現低下により、炎症性サイトカインの産生、活性酸素の放出、貪食能など炎症性マクロファージの主要な機能が広範に抑制されることがわかりました。逆にETS2を過剰発現させると、これらの炎症応答が亢進しました。RNA-seqの解析から、ETS2は多数の炎症関連遺伝子の発現を直接的に制御していることが明らかになりました。さらにETS2は解糖系の律速酵素の発現も制御しており、マクロファージの代謝リプログラミングにも関与していました。
炎症性腸疾患患者の腸管や原発性硬化性胆管炎患者の肝臓のシングルセルRNA-seqの解析からは、病変部の炎症性マクロファージでETS2の発現が亢進していることがわかりました。spatial transcriptomicsの解析からは、ETS2の下流遺伝子群の発現が病変の中心部で上昇していることが示されました。また、ETS2の下流遺伝子群は炎症性腸疾患のGWASで同定された疾患感受性遺伝子と有意に重複していました。
最後に、NIH LINCSのデータベースを用いた解析から、MEK阻害剤がETS2の下流の遺伝子発現変化を最も強く模倣することを見出しました。MEK阻害剤は炎症性腸疾患患者の腸管の炎症を抑制し、抗TNF-α抗体と同等の効果を示しました。
以上のように本研究は、chr21q22領域の遺伝的多型がETS2の発現上昇を介して炎症性マクロファージを活性化するメカニズムを明らかにしました。そしてETS2の下流シグナルを標的とすることで、過剰な炎症を抑制し炎症性疾患を治療できる可能性を示しました。炎症という複雑な生体応答の背景にある遺伝的な仕組みに迫った研究として大変意義深いものです。
Twitterによる1月6日の暴動後の大規模凍結アカウント措置は、デマ情報の拡散を抑制した
Twitterは2021年1月6日の米国議会議事堂襲撃事件への関与が疑われる7万件のアカウントを突然凍結した。この研究では50万人以上のアクティブユーザーを分析し、この大規模凍結措置がデマ情報の拡散に与えた影響を自然実験デザインにより評価した。その結果、凍結されたアカウントだけでなく、それらをフォローしていたアカウントによるデマ拡散も減少したことが分かった。また、多くのデマ拡散アカウントがこの措置後にTwitterから離れたことも判明した。これらの知見は、ソーシャルメディアプラットフォームが公共の議論を規制する力を持っていることを示している。
事前情報
21世紀のソーシャルメディアプラットフォームは、米国や世界中の言論を規制する巨大な役割を担っている。
プラットフォームによる言論への大規模な介入の効果についてはほとんど研究されていない。
行ったこと
2021年1月6日の米国議会議事堂襲撃事件(1月6日事件)を受けて、Twitterが突然7万件のデマ拡散アカウントを凍結した決定の影響を評価した。
50万人以上のアクティブなTwitterユーザーのパネルデータと自然実験デザインを用いた。
この介入が、Twitterにおけるデマ情報の拡散に与えた影響を調べた。
検証方法
凍結されたアカウントをフォローしていたグループとフォローしていなかったグループの行動変化を比較する差の差分析を行った。
1月6日の前後でデマ情報のリツイート数がどのように変化したかを回帰不連続デザインで分析した。
分かったこと
凍結措置により、凍結されたアカウントによるデマ拡散が減少しただけでなく、それらをフォローしていたアカウントによるデマ拡散も減少した。
凍結を免れた多くのデマ拡散アカウントが、この措置後にTwitterから離れた。
これらの結果は、ソーシャルメディアプラットフォームが、デマ情報の拡散をコントロールし、より広く公共の議論を規制する力を持っていることを示唆している。
研究の面白く独創的なところ
1月6日の事件とその後のTwitterによる大規模アカウント凍結という歴史的な出来事の影響を分析した点。
50万人以上のアクティブユーザーデータを用いた大規模な実証分析を行った点。
自然実験的な状況を活用して因果推論を行った点。
この研究のアプリケーション
プラットフォーム上の有害コンテンツへの対策を検討する際の重要な知見を提供。
ソーシャルメディア上の言論規制の是非を議論する上での実証的根拠を提示。
1月6日事件の歴史的記録に貢献。
著者と所属
Stefan D. McCabe (ジョージワシントン大学) Diogo Ferrari (カリフォルニア大学リバーサイド校)
David M. J. Lazer (ノースイースタン大学)
詳しい解説
2021年1月6日、ドナルド・トランプ支持者らによる米国連邦議会議事堂襲撃事件が起きました。この事件を受けて、Twitterは1月6日から12日にかけて、事件に関与したとされる約7万のアカウントを突如凍結するという大規模な措置を取りました。
この研究では、この前例のないアカウント凍結措置が、Twitterにおけるデマ情報の拡散にどのような影響を与えたのかを検証しました。分析には、50万人以上のアクティブなTwitterユーザーのパネルデータを用いました。
まず、凍結されたアカウントをフォローしていたユーザーグループと、フォローしていなかったグループの行動変化を比較する差の差分析を行いました。その結果、凍結アカウントをフォローしていたグループでは、1月12日以降のデマ情報のリツイートが大幅に減少したことが分かりました。これは、凍結措置が凍結アカウント自体だけでなく、それらのフォロワーによるデマ拡散も抑制したことを示しています。
次に、回帰不連続デザインを用いて、1月6日前後のデマ情報のリツイート数の変化を分析しました。すると、1月6日以降、突如としてデマ情報のリツイートが激減したことが判明しました。また興味深いことに、凍結を免れた多くのデマ拡散アカウントが、この大規模凍結後にTwitterから離脱したことも分かりました。
これらの知見は、ソーシャルメディアプラットフォームが、デマ情報の拡散を直接的にコントロールできるだけでなく、より広範に公共の議論をも規制する力を持っていることを示唆しています。米国史に残る重大な事件の記録としても、また、プラットフォームによる言論規制の是非を議論する上でも、この研究は重要な実証的根拠を提供するものです。
窒化ガリウムに原子層レベルでマグネシウムを挿入することで、独特の超格子構造と物性の変化を発見
金属マグネシウム(Mg)を窒化ガリウム(GaN)上で熱処理すると、MgがGaNの原子層間に自発的に挿入され、規則的な超格子構造が形成されることを発見した。Mgの単原子層がGaNの数原子層の間に挟み込まれた層状構造で、金属が半導体にこのように挿入された例は初めてである。Mgの挿入によりGaNが大きな一軸圧縮ひずみを受け、電子バンド構造が変化して正孔の移動度が大きく向上した。またMg層により結晶の極性が周期的に反転し、分極電荷が生じた。これらの特性は半導体のドーピングや伝導性向上、ナノ材料の弾性ひずみ制御、金属・半導体超格子の物性解明などに新たな知見を与えると期待される。
事前情報
窒化ガリウムへのマグネシウムドーピングによりp型伝導が初めて実現され、青色LEDなどの発展につながった
窒化ガリウムとマグネシウムの相互作用の詳細はよくわかっていなかった
行ったこと
窒化ガリウム上の金属マグネシウムを大気圧下で熱処理
高角度環状暗視野走査型透過電子顕微鏡(HAADF-STEM)、積分型微分位相コントラスト(iDPC)-STEM、エネルギー分散型X線分光法(EDS)による構造解析
理論計算による窒化ガリウムの電子バンド構造の解析
テラヘルツ時間領域分光エリプソメトリー(THz-TDE)による電気伝導特性の評価
検証方法
走査型透過電子顕微鏡(STEM)による原子レベルの構造観察と元素マッピング
第一原理計算による高ひずみ下の窒化ガリウムの電子バンド構造シミュレーション
テラヘルツ時間領域分光エリプソメトリーによる面内・面直方向の伝導率計測
分かったこと
マグネシウムが窒化ガリウムの原子層間に単原子層で規則的に挿入され、超格子構造が形成される
窒化ガリウムが12%以上の大きな一軸圧縮ひずみを受け、価電子バンドの形状が変化
正孔の有効質量が大幅に減少し、c軸方向の移動度が6倍に向上
マグネシウム層により窒化ガリウムの極性が周期的に反転し、分極電荷が生じる
研究の面白く独創的なところ
金属原子層が半導体に挿入された珍しい超格子構造を発見
窒化ガリウムが10%を超える巨大な弾性ひずみを示すことを実証
マグネシウム層による結晶極性の反転と分極電荷の発生を見出した
半導体中の伝導性向上に新たな知見を与えた
この研究のアプリケーション
金属/半導体超格子の物性制御と応用
半導体へのドーピングと伝導性向上の新たな手法
ナノ材料における超弾性ひずみ設計
高効率パワーデバイスや発光デバイスへの応用
著者と所属
Jia Wang, Nagoya University Institute for Advanced Research
Hiroshi Amano, Nagoya University Institute for Advanced Research Wentao Cai, Nagoya University Institute of Materials and Systems for Sustainability
詳しい解説
窒化ガリウムは青色発光ダイオードなどに用いられる重要な半導体材料ですが、マグネシウムをドープすることでp型伝導を示すことが1989年に初めて報告され、この分野の発展の礎となりました。しかし、窒化ガリウムとマグネシウムの相互作用については不明な点が多く残されていました。
今回、研究グループは窒化ガリウム基板上に金属マグネシウムを蒸着し、大気圧下で加熱処理することで、マグネシウム原子が窒化ガリウムの結晶の原子層間に単原子層の形で規則的に挿入され、独特の超格子構造が自発的に形成されることを発見しました。STEMによる原子レベルの構造解析から、マグネシウム層1枚が窒化ガリウム数層ごとに交互に積層した構造をしていることが分かりました。金属原子層が半導体結晶中に挿入されるというのは非常に珍しい現象です。
マグネシウムの挿入により、窒化ガリウムには面直方向に12%以上におよぶ巨大な圧縮ひずみが生じています。第一原理計算の結果、このひずみにより窒化ガリウムの価電子バンドの形状が大きく変化し、正孔の有効質量が大幅に減少することが示唆されました。テラヘルツ時間領域分光により、実際にc軸方向の正孔移動度が6倍に向上していることが実証されました。
さらに、マグネシウム層を挟むことで窒化ガリウムの結晶の極性が周期的に反転し、それによって分極電荷が生じることも見出されました。これは半導体中のキャリアドーピングに新たな機構を提供する可能性があります。
本研究で発見されたマグネシウム挿入窒化ガリウム超格子構造は、ナノスケールで金属と半導体を複合化した新しいタイプの人工構造として、基礎と応用の両面から大きな意義を持つと考えられます。伝導性の向上は半導体デバイスの性能向上に直結しますし、巨大な弾性ひずみ状態は材料物性制御の新たな自由度になります。結晶極性の制御も新機能創出に役立つでしょう。今後、超格子構造の作製プロセスの最適化と物性の更なる探索が期待されます。
200の言語に対応した大規模な多言語ニューラル機械翻訳モデルを開発
ニューラル技術の発展により、機械翻訳の研究に新たな道が開かれた。今日のニューラル機械翻訳(NMT)システムは、非常に多言語な能力を活用し、ゼロショット翻訳も行うことができ、言語のカバー範囲と品質の点で有望な結果をもたらしている。しかし、世界の7,000以上の言語のうち、比較的少数の高リソース言語の翻訳品質を向上させることに集中することで、低リソース言語の研究に注意を向けることができなくなり、長期的にはデジタル不平等が悪化する。この問題を解決するため、ここでは、言語間の転移学習を活用した単一の大規模多言語モデル「No Language Left Behind」を紹介する。Sparsely Gated Mixture of Expertsアーキテクチャに基づく条件付き計算モデルを開発し、低リソース言語用に調整された新しいマイニング技術で取得したデータで学習させた。さらに、何千もの課題で学習する際の過適合を防ぐため、複数のアーキテクチャと学習の改善を考案した。このモデルの性能を、この目的のために作成されたツール(自動ベンチマークFLORES-200、人間評価指標XSTS、モデルのすべての言語をカバーする毒性検出器)を使用して、40,000の翻訳方向で評価した。先行研究の最先端モデルと比較して、このモデルはBLEUで測定した翻訳品質が平均44%向上した。NMTを200言語にスケールアップする方法を実証し、この努力で得られたすべての成果を非商用目的で自由に利用できるようにすることで、普遍的な翻訳システムの開発に重要な基礎を築いた。
事前情報
ニューラル機械翻訳(NMT)は、高い多言語能力を発揮し、ゼロショット翻訳も可能。
しかし、高品質なNMTには大量の対訳データが必要で、7000以上ある世界の言語すべてに十分なデータがあるわけではない。
高リソース言語の翻訳品質向上に注力することで、低リソース言語の研究がおろそかになり、デジタル不平等が悪化する恐れがある。
行ったこと
言語間の転移学習を活用した大規模多言語モデル「No Language Left Behind」を開発。
Sparsely Gated Mixture of Experts アーキテクチャを採用し、低リソース言語に特化したマイニング手法で取得したデータで学習。
過適合を防ぐため、アーキテクチャと学習方法に複数の改良を施した。
自動ベンチマーク、人間評価指標、毒性検出器など、評価用のツールも新たに開発。
検証方法
新たに開発した自動ベンチマークFLORES-200、人間評価指標XSTS、毒性検出器ETOXを用いて、40,000の翻訳方向でモデル性能を評価。
自動評価指標としてBLEUスコアを使用し、先行研究の最先端モデルと比較。
分かったこと
先行研究と比べ、BLEUスコアで平均44%の翻訳精度向上を実現。
200言語をカバーしつつ、先行モデルを大きく上回る性能を達成。
モデルや関連ツール、データセットを非営利目的で公開することで、普遍的翻訳システム開発の基盤を提供。
研究の面白く独創的なところ
言語間知識転移の促進と干渉の最適化を両立する新アーキテクチャを採用。
過適合対策として、言語ペアを段階的に学習するカリキュラム学習を導入。
低リソース言語のデータ収集に特化した手法を新たに開発。
人間評価の言語間較正など、大規模多言語モデルの評価手法にも工夫。
この研究のアプリケーション
機械翻訳の言語カバー範囲が大幅に拡大し、これまで翻訳が困難だった言語の可用性が向上。
提供されるモデルやツールを活用することで、低リソース言語の機械翻訳研究が加速。
言語の壁を越えたコミュニケーションの促進により、教育や情報アクセスの機会が拡大。
低リソース言語のコンテンツ創出が活発化し、多様な文化や知識の交流が進む。
著者と所属
Marta R. Costa-jussà (Foundational AI Research (FAIR), Meta, Paris, France)
James Cross (Foundational AI Research (FAIR), Meta, New York, NY, USA)
Onur Çelebi (Foundational AI Research (FAIR), Meta, Paris, France)
詳しい解説
この研究では、Facebookの研究チームがニューラル機械翻訳(NMT)モデルを200もの言語に拡張するための新しいアプローチを提案しています。従来、NMTには大量の対訳データが必要で、多くの低リソース言語では十分なデータが得られず、翻訳が困難でした。
この問題に対処するため、研究チームは言語間の知識転移を活用した大規模多言語モデル「No Language Left Behind (NLLB)」を開発しました。このモデルは、Sparsely Gated Mixture of Expertsというアーキテクチャを採用しており、関連する言語間の知識転移を促進しつつ、無関係な言語間の干渉を最小限に抑えられるのが特長です。
また、低リソース言語に特化した新しいデータマイニング手法を用い、ウェブ上の大規模なコーパスから効率的に対訳データを収集しました。さらに、数千もの言語ペアで学習する際の過適合を防ぐため、言語ペアを段階的に学習するカリキュラム学習など、複数のアーキテクチャ改良や学習手法の工夫も施しています。
モデルの評価においては、200言語すべてに対応した自動ベンチマークや人間評価指標、毒性検出器など、多言語モデルの評価に必要なツールも新たに開発。40,000もの翻訳方向について性能を評価した結果、先行研究の最先端モデルと比較して平均44%もの翻訳精度の向上を達成しました。
この研究のインパクトは大きく、これまで翻訳が困難だった多くの低リソース言語の可用性が格段に向上します。教育や情報アクセス、文化交流の機会が世界中で拡大することが期待されます。さらに、提案手法やツール、データセットを非営利目的で公開することで、低リソース言語の機械翻訳研究の発展にも大きく貢献するでしょう。
機械翻訳の新たな可能性を切り拓いたこの研究は、NLP分野のみならず、言語サービスを介した社会課題の解決においても大きなブレイクスルーとなりそうです。言語の壁を越えたコミュニケーションを、より身近で当たり前のものへと変えていく大きな一歩になるのではないでしょうか。
高圧下で超伝導を示すニッケル酸化物La3Ni2O7-δの酸素欠損と自己ドープされたリガンドホールを可視化
La3Ni2O7-δは最近高圧下で80K付近の超伝導転移が発見された物質である。本研究では、新しいエネルギーフィルター化マルチスライス電子プティコグラフィー法と電子エネルギー損失分光法を用いて、酸素欠損が主に内側のアピカルサイトを占有していることを直接可視化した。さらに、化学量論組成のLa3Ni2O7ではNiサイトからOサイトにホールが自己ドープされているが、酸素欠損濃度の増加とともにそのリガンドホールが消失していくことを明らかにした。これらの知見はニッケル酸化物超伝導体の理解に重要である。
事前情報
La3Ni2O7-δは高圧下で80K付近で超伝導を示す。
超伝導発現機構の理解のためには、最も関連する原子軌道と原子欠損の役割を明らかにする必要がある。
行ったこと
新しいエネルギーフィルター化マルチスライス電子プティコグラフィー法を開発し、電子エネルギー損失分光法と組み合わせて測定した。
ナノスケールでの化学量論比と酸素K端スペクトルの相関を精密に決定した。
検証方法
La3Ni2O7-δ単結晶試料の電子顕微鏡観察と分光測定を行った。
電子回折パターンの多次元データを用いてプティコグラフィー再構成を行い、原子像を得た。
酸素K端の電子エネルギー損失スペクトルを測定し、電子状態を調べた。
分かったこと
酸素欠損は主に内側のアピカルサイトを占有している。
化学量論組成のLa3Ni2O7は強い電荷移動の性質を持ち、NiサイトからOサイトにホールが自己ドープされている。
リガンドホールは主に内側アピカルOと面内Oに存在し、外側アピカルOの密度は無視できる。
酸素欠損濃度が増加すると、両サイトのリガンドホールが同時に消失する。
研究の面白く独創的なところ
原子欠損を定量的に可視化できる新しい電子顕微鏡法を開発した点。
酸素欠損とリガンドホールの分布を直接観察し、超伝導発現機構の理解に重要な知見を与えた点。
この研究のアプリケーション
本研究で開発した原子欠損の定量イメージング技術は、材料科学や凝縮系物理学の様々な分野に応用可能。
ニッケル酸化物超伝導体のさらなる発展と理解に役立つ。
著者と所属
Zehao Dong, Yayu Wang - 清華大学
Mengwu Huo, Meng Wang - 中山大学
Zhen Chen - 中国科学院物理研究所
詳しい解説
La3Ni2O7-δは、高圧下で転移温度約80Kの超伝導を示すことが最近発見された物質です。超伝導発現機構を理解するためには、最も関連する原子軌道と原子欠損の役割を明らかにすることが重要な課題でした。
本研究では、エネルギーフィルター化マルチスライス電子プティコグラフィーという新しい手法を開発し、電子エネルギー損失分光法と組み合わせることで、この問題に取り組みました。La3Ni2O7-δ単結晶試料の電子顕微鏡観察と分光測定を行い、酸素欠損が主に内側のアピカルサイトを占有していることを直接可視化することに成功しました。これは超伝導発現に重要だと提案されていたサイトです。
さらに、試料内のナノスケールでの化学量論比のばらつきと酸素K端スペクトルの相関を精密に決定しました。分光の結果から、化学量論組成のLa3Ni2O7では強い電荷移動の性質を持ち、NiサイトからOサイトにホールが自己ドープされていることが明らかになりました。リガンドホールは主に内側アピカルOと面内Oに存在し、外側アピカルOの密度は無視できるほど小さいことが分かりました。酸素欠損濃度が増加すると、両サイトのリガンドホールが同時に消失していくことも判明しました。
本研究で開発した原子欠損の定量イメージング技術は、材料科学や凝縮系物理学の様々な分野に広く応用できます。今回得られた知見は、ニッケル酸化物超伝導体のさらなる発展と理解に役立つでしょう。
ヒト造血幹細胞の機能を制御する新たな因子MYCT1の発見
ヒト造血幹細胞を培養して増やすことは困難だが、それらの機能を制御する重要な分子メカニズムは不明だった。この研究では、MYCT1が造血幹細胞特異的に発現し、エンドサイトーシスを適度に抑制することで、幹細胞が周囲の環境からのシグナルを適切に感知し、幹細胞性を維持することを可能にすることを明らかにした。MYCT1をノックダウンすると幹細胞の機能が失われ、逆にMYCT1の発現を維持すると培養した幹細胞の機能が改善された。MYCT1は培養中に発現が低下するため、MYCT1の発現維持が幹細胞の体外増幅の鍵となる可能性がある。
事前情報
ヒト造血幹細胞を試験管内で増やすことは難しく、その機能も培養により低下してしまう
造血幹細胞の自己複製と分化の運命決定に関わる分子メカニズムには不明な点が多い
行ったこと
ヒト造血組織のRNA-seqデータ解析により、MYCT1が未分化な造血幹細胞に特異的に発現し、培養により発現が低下することを見出した
MYCT1をノックダウンまたは過剰発現させ、造血幹細胞の機能への影響を解析した
MYCT1の細胞内局在や相互作用因子を調べ、エンドサイトーシス制御における役割を解明した
培養した造血幹細胞のエンドサイトーシス活性と幹細胞性の関係を調べた
検証方法
ヒト臍帯血またはFL由来の造血幹細胞にMYCT1のノックダウンまたは過剰発現ベクターを導入し、細胞数の変化や表面マーカーの発現をFACSで解析
MYCT1ノックダウンまたは過剰発現造血幹細胞をマウスに移植し、ヒト細胞の生着率と分化能を評価
免疫染色やIP-MSにより、MYCT1の細胞内局在や相互作用因子を同定
細胞内に取り込まれる蛍光色素の量をFACSで定量化し、エンドサイトーシス活性を測定
分かったこと
MYCT1は造血幹細胞の培養中に発現が低下し、エピジェネティックに抑制される
MYCT1のノックダウンにより、造血幹細胞の培養中の増殖とマウスへの生着能が失われる
MYCT1の発現を維持すると、培養した造血幹細胞の数が増加し、マウスでの血液再構築能が向上する
MYCT1はエンドソームに局在し、エンドサイトーシス関連因子と相互作用する
MYCT1の欠損により幹細胞のエンドサイトーシス活性が亢進し、シグナル応答が過剰になる
エンドサイトーシス活性の低い幹細胞ほど、幹細胞性の指標となる遺伝子発現プログラムが保たれている
研究の面白く独創的なところ
造血幹細胞の運命制御において、環境からのシグナル感知を司るエンドサイトーシスの重要性を示した点
エンドサイトーシス活性の制御因子としてMYCT1を同定し、幹細胞の培養による機能低下のメカニズムの一端を解明した点
MYCT1による適度なエンドサイトーシスの抑制が、幹細胞の環境応答性や自己複製能の維持に必須であることを示した点
この研究のアプリケーション
MYCT1の発現維持が、造血幹細胞の体外増幅効率を高め、移植治療に用いる細胞ソースの確保に貢献する可能性
MYCT1とエンドサイトーシスが制御する幹細胞制御メカニズムの解明が、再生医療等への応用に繋がることが期待される
著者と所属
Júlia Aguadé-Gorgorió - カリフォルニア大学ロサンゼルス校
Vincenzo Calvanese - ロンドン大学ユニバーシティ・カレッジ
Hanna K. A. Mikkola - カリフォルニア大学ロサンゼルス校
詳しい解説
本研究は、ヒト造血幹細胞の培養による機能低下のメカニズムを解明し、それを克服する方策を提示した画期的な内容となっている。まず筆者らは、ヒト造血組織のRNA-seqデータを解析することで、MYCT1が未分化な造血幹細胞に特異的に発現する一方、幹細胞の培養によりその発現が低下することを見出した。さらに、MYCT1をノックダウンすると造血幹細胞の培養中の増殖能とマウスへの生着能が失われることを示し、MYCT1の重要性を明らかにした。
次に筆者らは、MYCT1がエンドソームに局在し、エンドサイトーシス関連因子と相互作用することを免疫染色やIP-MSにより突き止めた。MYCT1を欠損させるとエンドサイトーシス活性が亢進し、増殖因子受容体のシグナル応答が過剰になることも明らかにした。一方、MYCT1の発現を維持すると、エンドサイトーシス活性が抑制され、培養した造血幹細胞の数が増加し、マウスでの血液再構築能も向上した。さらに、エンドサイトーシス活性の低い幹細胞ほど、幹細胞性の指標となる遺伝子発現プログラムが保たれていることも示された。
以上の結果から、MYCT1は造血幹細胞のエンドサイトーシスを適度に抑制することで、幹細胞が周囲の環境からのシグナルを適切に感知し、自己複製能や未分化性を維持することを可能にしていると考えられる。本研究は、造血幹細胞の運命決定における「環境感知」の分子基盤を初めて明らかにしただけでなく、幹細胞の体外増幅効率を高める上でのMYCT1の有用性も示唆しており、幹細胞研究や再生医療への応用が大いに期待される。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
