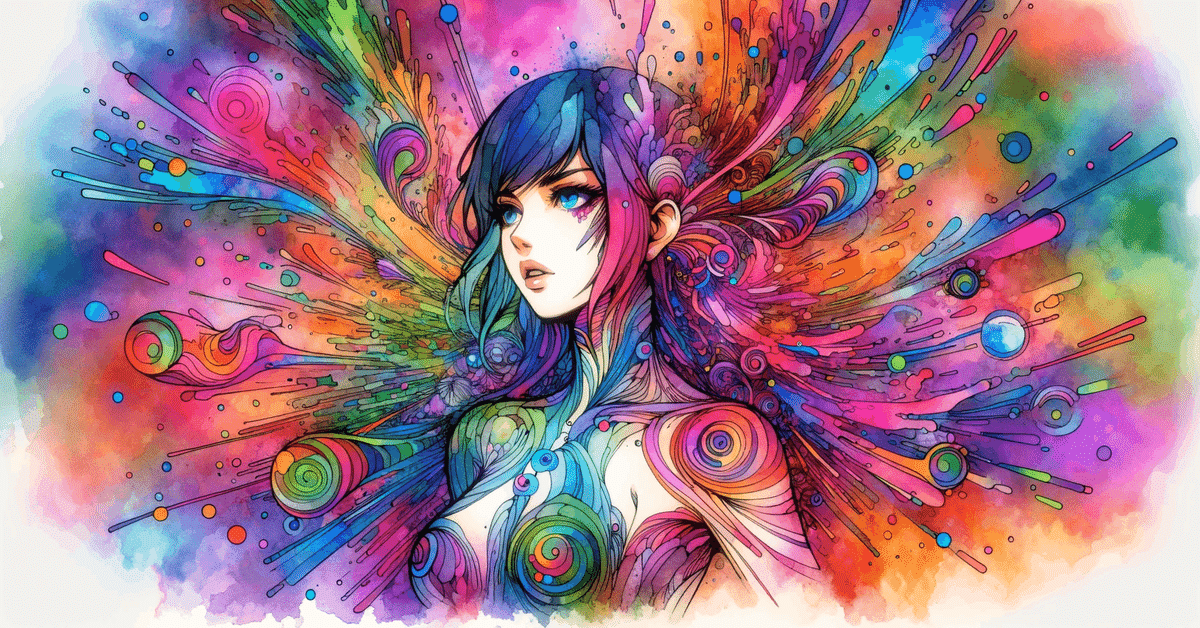
論文まとめ319回目 SCIENCE 自然保護活動のプラスの効果!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなSCIENCEです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
Expansive discovery of chemically diverse structured macrocyclic oligoamides
化学的に多様な構造のマクロサイクルオリゴアミドの網羅的発見
「マクロサイクルは環状ペプチドの一種で、生理活性物質によく見られる構造です。本研究では、深層学習を用いて130種類のアミノ酸を組み合わせ、1490万種類ものマクロサイクル構造を予測しました。そのうち18種類を合成したところ、15種類が予測通りの立体構造を取ることが確認されました。さらに、この手法で設計したマクロサイクルが、3つのタンパク質に選択的に結合することを示しました。本研究は、創薬のための新しいマクロサイクル設計法の開発につながる画期的な成果です。」
Vitamin D regulates microbiome-dependent cancer immunity
ビタミンDは腸内細菌叢を介してがん免疫を制御する
「ビタミンDががんに対する免疫応答を高めることは知られていましたが、そのメカニズムは不明でした。本研究では、ビタミンDが腸の上皮細胞に作用し、腸内細菌の組成を変化させることで、がんに対する免疫を活性化することを明らかにしました。特に、ビタミンDの存在下で増えるバクテロイデス・フラジリスという菌が、がん免疫の活性化に重要な役割を果たすことがわかりました。これらの発見は、ビタミンDと腸内細菌を標的とした新しいがん免疫療法の開発につながる可能性があります。」
Food perception promotes phosphorylation of MFFS131 and mitochondrial fragmentation in liver
食物の感知が肝臓のMFFS131のリン酸化とミトコンドリア分裂を促進する
「食事の匂いや見た目などの感覚情報は、食欲を刺激するだけでなく、体の代謝も変化させます。この研究では、マウスを使って、食物の感知が肝臓のミトコンドリアというエネルギー工場に与える影響を調べました。すると、食物を感知するだけで、視床下部のPOMCニューロンが活性化し、肝臓のミトコンドリアがすぐに分裂することがわかりました。この反応には、MFFというタンパク質のリン酸化が関わっており、インスリンによる肝臓の糖産生の抑制に重要だと示唆されました。食事の準備段階から代謝が変化するメカニズムの一端が明らかになった研究です。」
Nitrate reduction enables safer aryldiazonium chemistry
亜硝酸塩の還元により、より安全なアリールジアゾニウム化学が可能に
「有機合成で重宝されるサンドマイヤー反応は、19世紀に開発されて以来ほとんど変わっていません。この反応は、ジアゾニウム塩という不安定な中間体を経由するため、爆発の危険性がありました。今回、亜硝酸塩をゆっくり還元することで、ジアゾニウム塩が蓄積しない新手法を開発。より安全に、しかも効率よくハロゲン化アリールを合成できるようになりました。130年来の有機合成の常識を覆す画期的な研究です。化学者の創造力と洞察力のたまものですね。」
The positive impact of conservation action
自然保護活動のプラスの効果
「世界中で毎年何十億ドルもの資金が自然保護に投じられていますが、その効果は十分に検証されていませんでした。この研究では、保護区の設定や保全管理など様々な自然保護活動について、何もしなかった場合と比べてどれだけ生物多様性の保全に役立ったかを分析しました。その結果、保護活動を行った方が、行わなかった場合に比べて生物多様性の損失を抑制できることが明らかになりました。ただし損失を完全に止められるわけではなく、保護活動をさらに拡大することが必要だと示唆されました。」
要約
深層学習により、42,000種類以上の多様な構造のマクロサイクル化合物を網羅的に発見
https://doi.org/10.1126/science.adk1687
本研究では、αアミノ酸、βアミノ酸、γアミノ酸など、22種類のアミノ酸骨格化学を組み合わせた、4つ以下のアミノ酸からなる小さなマクロサイクルを同定する計算手法を開発しました。この手法を用いて、42,000種類以上のモノマーの組み合わせからなる1490万種類の閉環マクロサイクルを予測しました。そのうち、単一の低エネルギー状態をとると予測された18種類のマクロサイクルを化学合成し、X線結晶構造解析またはNMRで立体構造を決定したところ、15種類が設計モデルと非常に近い構造をとることが確認されました。さらに、3つのタンパク質標的に対する選択的阻害剤を開発することで、これらのマクロサイクル設計の治療応用の可能性を示しました。本研究の成果は、容易に合成可能な薬物様マクロサイクルの巨大な空間を切り開くもので、構造ベースの創薬を大いに促進すると期待されます。
事前情報
4つ以下のアミノ酸からなる小さなマクロサイクルは、最も強力な天然物の一つだが、系統的に生成する方法はない。
マクロサイクルは分子認識に有利な構造的特徴を持つため、創薬ターゲットとして注目されている。
行ったこと
αアミノ酸、βアミノ酸、γアミノ酸など、22種類のアミノ酸骨格化学を組み合わせたマクロサイクルを同定する計算手法を開発した。
この手法を用いて、42,000種類以上のモノマーの組み合わせからなる1490万種類の閉環マクロサイクルを予測した。
単一の低エネルギー状態をとると予測された18種類のマクロサイクルを化学合成した。
検証方法
合成した18種類のマクロサイクルについて、X線結晶構造解析またはNMRで立体構造を決定した。
3つのタンパク質標的に対する選択的阻害活性を評価した。
分かったこと
合成した18種類のマクロサイクルのうち15種類が、設計モデルと非常に近い構造をとることが確認された。
設計したマクロサイクルの一部が、3つのタンパク質標的に対して選択的な阻害活性を示した。
本手法により、容易に合成可能な薬物様マクロサイクルの巨大な空間を探索できることが示された。
この研究の面白く独創的なところ
22種類ものアミノ酸骨格化学を組み合わせ、1490万種類もの多様なマクロサイクルを予測した点が画期的。
深層学習を活用し、マクロサイクルの立体構造を高精度に予測できた点が独創的。
設計したマクロサイクルが実際にタンパク質に選択的に結合することを示した点が興味深い。
この研究のアプリケーション
本手法により、創薬ターゲットに特化したマクロサイクル阻害剤のデザインが可能になる。
深層学習を活用した効率的なマクロサイクル設計プラットフォームの開発につながる。
多様なマクロサイクルライブラリの構築により、新しい生理活性物質の発見が期待される。
著者と所属
Patrick J. Salveson, Adam P. Moyer, Meerit Y. Said, Gizem Gӧkçe, Xinting Li, Alex Kang, Hannah Nguyen, Asim K. Bera, Paul M. Levine, Gaurav Bhardwaj, and David Baker (Institute for Protein Design, University of Washington, Seattle, WA, USA; Department of Biochemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA; Department of Medicinal Chemistry, University of Washington, Seattle, WA, USA)
詳しい解説
本研究は、深層学習を活用して化学的に多様な構造のマクロサイクル化合物を網羅的に発見した画期的な成果です。マクロサイクルは、環状ペプチドの一種で、生物活性物質の中に多く見られる重要な構造モチーフです。特に4つ以下のアミノ酸からなる小さなマクロサイクルは、強力な活性を示すことが知られていますが、そのような化合物を系統的に生成する方法はこれまでありませんでした。
研究チームは、αアミノ酸、βアミノ酸、γアミノ酸など、22種類ものアミノ酸骨格化学を組み合わせたマクロサイクルを同定する計算手法を開発しました。この手法では、130種類のアミノ酸から4つ以下を選んで環状に連結し、深層学習を用いてそれぞれの構造のエネルギー状態を予測します。その結果、42,000種類以上のモノマーの組み合わせから、実に1490万種類もの閉環マクロサイクルが見つかりました。
さらに、予測されたマクロサイクルの中から、単一の低エネルギー状態をとると予想された18種類を選び、実際に化学合成しました。そしてX線結晶構造解析やNMRを用いて立体構造を調べたところ、15種類が設計モデルと非常に近い構造をとることが確認されました。これは、深層学習によるマクロサイクルの構造予測が高い精度で行えることを示しています。
次に研究チームは、設計したマクロサイクルの応用可能性を探るため、3つのタンパク質標的に対する選択的阻害剤の開発を試みました。ペプチド断片に基づくモチーフ足場を用いて、2つの酵素に結合するマクロサイクルを生成したほか、予測されたマクロサイクルの仮想スクリーニングにより、タンパク質間相互作用の阻害剤も開発しました。これらの結果は、本手法で設計したマクロサイクルが、実際に生体内の標的に選択的に結合し、生理活性を発揮できる可能性を示唆しています。
本研究の意義は、深層学習という最先端の技術を活用し、これまでにない規模と多様性のマクロサイクル化合物ライブラリを構築した点にあります。マクロサイクルは分子認識に有利な構造的特徴を持つため、創薬ターゲットとして大きな注目を集めていますが、その化学空間は十分に探索されていませんでした。本研究では、22種類ものアミノ酸骨格化学を組み合わせることで、構造と物性の異なる膨大な数のマクロサイクルを発掘することに成功しました。
さらに、深層学習モデルにより立体構造を高精度に予測できたことで、望みの構造や機能を持つマクロサイクルを効率的に設計できる可能性が開けました。実際に予測通りの構造を持つマクロサイクルが合成され、標的タンパク質に選択的に結合することも確認されました。このような構造ベースのマクロサイクル設計プラットフォームは、今後の創薬研究を大いに加速すると期待されます。
本研究は、計算科学と合成化学、構造生物学を見事に融合させた学際的な成果であり、マクロサイクル化合物の可能性を大きく押し広げるものです。深層学習により膨大な化学空間を俯瞰し、望みの構造と機能を持つ分子を自在にデザインする̶̶本研究はそんな創薬の未来への扉を開いたと言えるでしょう。新しい生理活性物質や薬のタネの発見につながることが大いに期待されます。
ビタミンDが腸内細菌叢を介してがん免疫を制御することを発見
https://doi.org/10.1126/science.adh7954
本研究では、ビタミンDががん免疫を促進する新たなメカニズムを明らかにした。マウスモデルにおいて、ビタミンDの利用能が高いマウスは、移植がんに対する免疫応答が強く、免疫チェックポイント阻害療法の効果も高かった。ヒトにおいても、ビタミンD誘導性遺伝子の発現ががん免疫や生存率と相関していた。この効果は、ビタミンDが腸上皮細胞に作用し、腸内細菌叢の組成を変化させ、特にバクテロイデス・フラジリスを増加させることで、がん免疫を正に制御することによるものだった。本研究は、ビタミンD、腸内細菌叢、がん免疫の関連性を示し、ビタミンDレベルががん免疫や免疫療法の効果を左右する可能性を示唆している。
事前情報
ビタミンDは免疫調節や抗がん作用に関与することが示唆されている。
腸内細菌叢ががん患者の治療応答性を調節することが示されているが、正確なメカニズムは不明である。
行ったこと
ビタミンD利用能の異なるマウスモデルを用いて、がん免疫応答と免疫チェックポイント阻害療法の効果を評価した。
ヒトにおいて、ビタミンD誘導性遺伝子の発現ががん免疫や予後と相関するか解析した。
ビタミンDががん免疫に及ぼす影響における腸内細菌叢の役割を調べた。
検証方法
移植がんモデルを用いた免疫応答と免疫療法効果の評価
ヒト患者データを用いたビタミンD関連遺伝子発現の解析
無菌マウスや抗生物質処理マウスを用いた腸内細菌叢の影響評価
腸内細菌叢のメタゲノム解析
分かったこと
ビタミンDの利用能が高いマウスは、がんに対する免疫応答が強く、免疫チェックポイント阻害療法の効果も高い。
ヒトにおいて、ビタミンD誘導性遺伝子の高発現は、がん免疫の活性化や生存率の向上と相関する。
ビタミンDの抗腫瘍効果は、腸内細菌叢、特にバクテロイデス・フラジリスに依存する。
ビタミンDは腸上皮細胞に作用し、腸内細菌叢の組成を変化させることで、がん免疫を制御する。
この研究の面白く独創的なところ
ビタミンDががん免疫を制御する新しいメカニズムを発見した点が画期的。
ビタミンDと腸内細菌叢の関連性を介したがん免疫制御という新しい概念を提唱した点が独創的。
ビタミンDレベルががん免疫療法の効果予測因子になる可能性を示した点が臨床的に重要。
この研究のアプリケーション
ビタミンDや特定の腸内細菌を標的とした新しいがん免疫療法の開発。
ビタミンDレベルに基づくがん免疫療法の個別化医療への応用。
ビタミンDサプリメントによるがん予防や治療効果増強の可能性。
著者と所属
Evangelos Giampazolias†, Mariana Pereira da Costa†, Khiem C. Lam†, Kok Haw Jonathan Lim†, Ana Cardoso†, Cécile Piot†, Probir Chakravarty, Sonja Blasche, Swara Patel, Adi Biram, Tomas Castro-Dopico, Michael D. Buck, Richard R. Rodrigues, Gry Juul Poulsen, Susana A. Palma-Duran, Neil C. Rogers, Maria A. Koufaki, Carlos M. Minutti, Pengbo Wang, Alexander Vdovin, Bruno Frederico, Eleanor Childs, Sonia Lee, Ben Simpson, Andrea Iseppon, Sara Omenetti, Gavin Kelly, Robert Goldstone, Emma Nye, Alejandro Suárez-Bonnet, Simon L. Priestnall, James I. MacRae, Santiago Zelenay, Kiran Raosaheb Patil, Kevin Litchfield, James C. Lee, Tine Jess, Romina S. Goldszmid, and Caetano Reis e Sousa (Immunobiology Laboratory, The Francis Crick Institute, London, UK; Cancer Immunosurveillance Group, Cancer Research UK Manchester Institute, The University of Manchester, Manchester, UK; Inflammatory Cell Dynamics Section, Laboratory of Integrative Cancer Immunology (LICI), Center for Cancer Research (CCR), National Cancer Institute (NCI), Bethesda, MD, USA; Department of Immunology and Inflammation, Imperial College London, London, UK; Bioinformatics and Biostatistics STP, The Francis Crick Institute, London, UK; MRC Toxicology Unit, University of Cambridge, Cambridge, UK; Basic Science Program, Frederick National Laboratory for Cancer Research, Frederick, MD, USA; Microbiome and Genetics Core, LICI, CCR, NCI, Bethesda, MD, USA; National Center of Excellence for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease, PREDICT, Faculty of Medicine, Aalborg University, Department of Gastroenterology and Hepatology, Aalborg University Hospital, Copenhagen, Denmark; Metabolomics STP, The Francis Crick Institute, London, UK; Cancer Inflammation and Immunity Group, Cancer Research UK Manchester Institute, The University of Manchester, Manchester, UK; Experimental Histopathology, The Francis Crick Institute, London, UK; Department of Pathobiology and Population Sciences, The Royal Veterinary College, North Mimms, Hatfield, Hertfordshire, UK; AhRimmunity Laboratory, The Francis Crick Institute, London, UK; Tumor Immunogenomics and Immunosurveillance (TIGI) Lab, UCL Cancer Institute, London, UK; Genetic Mechanisms of Disease Laboratory, The Francis Crick Institute, London, UK; Institute of Liver and Digestive Health, Division of Medicine, Royal Free Hospital, University College London, London, UK)
詳しい解説
本研究は、ビタミンDががん免疫を促進する新たなメカニズムを明らかにした非常に興味深い成果です。ビタミンDは骨の健康維持に重要なホルモンとして知られていますが、免疫系の調節にも関与することが示唆されてきました。また近年、腸内細菌叢ががん患者の治療応答性に影響を及ぼすことが明らかになってきました。しかし、ビタミンDと腸内細菌叢の関連性や、それががん免疫にどのように影響するかは不明でした。
研究チームは、まずビタミンDの利用能が異なるマウスモデルを用いて、がんに対する免疫応答と免疫チェックポイント阻害療法の効果を比較しました。その結果、ビタミンDの利用能が高いマウスでは、移植がんの増殖が抑制され、免疫療法の効果も増強されることがわかりました。同様に、ヒトのがん患者データを解析したところ、ビタミンD誘導性遺伝子の発現レベルが高い患者では、がんに対する免疫応答が活発で、予後も良好であることが示されました。
これらの結果は、ビタミンDががん免疫を促進することを強く示唆するものでした。そこで次に、その機序における腸内細菌叢の役割を調べるため、無菌マウスや抗生物質処理マウスを用いた実験を行いました。すると、ビタミンDの抗腫瘍効果は、腸内細菌叢の存在に依存することが明らかになりました。さらにメタゲノム解析により、ビタミンDの存在下では腸内細菌叢の組成が変化し、特にバクテロイデス・フラジリスという菌が増加することがわかりました。
バクテロイデス・フラジリスは腸内の常在菌の一種ですが、炎症性腸疾患での減少や、免疫調節作用が報告されています。本研究では、バクテロイデス・フラジリスをマウスに投与すると、ビタミンD欠乏状態でもがん免疫が活性化されることを見出しました。つまり、ビタミンDは腸内細菌叢、特にバクテロイデス・フラジリスを介して、がん免疫を促進することが示唆されたのです。
ではビタミンDは腸内細菌叢にどのように作用するのでしょうか?研究チームは、ビタミンDが直接的に腸の上皮細胞に働きかけ、腸内環境を変化させることで、バクテロイデス・フラジリスの増殖を促進すると考えています。実際、上皮細胞特異的にビタミンD受容体を欠損させたマウスでは、ビタミンDの抗腫瘍効果が消失することを確認しました。
本研究は、ビタミンD、腸内細菌叢、がん免疫というこれまで独立に研究されてきた分野を見事に結びつけた点で非常に価値があります。ビタミンDと特定の腸内細菌を標的とすることで、がん免疫療法の効果を高められる可能性が期待されます。また、ビタミンDレベルががん免疫の活性化や免疫療法の効果を予測するバイオマーカーになるかもしれません。
一方で、ビタミンDの至適レベルや、腸内細菌叢への長期的な影響など、まだ不明な点も多く残されています。また、ヒトとマウスでは腸内環境が異なるため、本研究の知見がそのままヒトに当てはまるかは慎重に検証する必要があります。今後は、より大規模な臨床研究や介入試験により、ビタミンDとバクテロイデス・フラジリスを軸とした新たながん免疫療法の開発が進むことが期待されます。
本研究は、ビタミンDという身近な栄養素ががん治療に役立つ可能性を示した点でも注目に値します。がん患者さんの中には、ビタミンD不足の方も少なくないと言われています。本研究の成果は、ビタミンDの重要性を再認識させるとともに、がん治療における栄養管理の大切さを示唆するものとも言えるでしょう。「腸内細菌を整え、免疫力を高める」という言葉を、ビタミンDを介して科学的に裏付けた画期的な研究だったと言えます。
食物の感知が肝臓のミトコンドリア分裂を促進することを発見
https://doi.org/10.1126/science.adk1005
この研究は、マウスにおいて、食物の感知が肝臓のミトコンドリアの形態と機能に与える影響を調べたものです。実験の結果、食物の感知は視床下部のPOMCニューロンを活性化させ、肝臓でのAKTキナーゼ依存的なミトコンドリア分裂因子(MFF)のセリン131のリン酸化を介して、速やかにミトコンドリアの分裂を誘導することがわかりました。リン酸化されないMFFS131Gノックインマウスでは、インスリン刺激による肝臓の糖産生抑制が損なわれました。これらの結果から、視床下部-肝臓軸の急速な活性化が、栄養状態の予測的な変化に適応してミトコンドリア機能を調節し、肝臓の糖代謝を制御していることが示唆されました。
事前情報
食事に関連する手がかり(匂いや見た目など)は、末梢の代謝を準備する。
視床下部のPOMCニューロンは、食事関連の手がかりで活性化される。
肝臓のミトコンドリアは、栄養状態の変化に対する代謝適応に重要な役割を果たす。
行ったこと
マウスで食物の感知が肝臓のミトコンドリアのダイナミクスに与える影響を調べた。
POMCニューロン特異的な光遺伝学的活性化の効果を検証した。
MFFのセリン131のリン酸化が及ぼす役割を解析した。
リン酸化されないMFFS131Gノックインマウスの表現型を調べた。
検証方法
肝臓のミトコンドリア形態の電子顕微鏡解析
超解像顕微鏡を用いたミトコンドリアの形態計測
POMCニューロンの光遺伝学的活性化実験
MFFのリン酸化部位特異的抗体を用いたウェスタンブロット解析
MFFS131Gノックインマウスの作製と代謝表現型の解析
分かったこと
食物の感知は、肝臓のミトコンドリアを速やかに分裂させる。
この反応は、POMCニューロンの活性化を介している。
MFFのセリン131のAKT依存的なリン酸化が、ミトコンドリア分裂に重要である。
MFFS131Gノックインマウスでは、肝臓のミトコンドリアダイナミクスが変化し、インスリン刺激性の糖産生抑制が損なわれる。
この研究の面白く独創的なところ
感覚情報が肝臓のミトコンドリアに急速に影響を与えることを示した点
視床下部-肝臓軸による予測的な代謝制御の新しいメカニズムを明らかにした点
MFFのリン酸化という分子メカニズムを突き止めた点
遺伝学的なアプローチで因果関係を証明した点
この研究のアプリケーション
食事の感覚刺激を利用した代謝疾患の予防・治療法の開発につながる可能性がある。
MFFのリン酸化を標的とした新しい糖尿病治療薬の開発が期待される。
肝臓のミトコンドリア機能を調節する新たなアプローチとなるかもしれない。
食欲や代謝を制御する脳-肝臓連関のメカニズム解明に役立つ。
著者と所属
Sinika Henschke, Hendrik Nolte, Judith Magoley, Tatjana Kleele, Claus Brandt, A. Christine Hausen, Claudia M. Wunderlich, Corinna A. Bauder, Philipp Aschauer, [...], Jens C. Brüning (Max Planck Institute for Metabolism Research, Department of Neuronal Control of Metabolism, Cologne, Germany; Policlinic for Endocrinology, Diabetes and Preventive Medicine (PEDP), University Hospital Cologne, Cologne, Germany; Excellence Cluster on Cellular Stress Responses in Aging Associated Diseases (CECAD) and Center of Molecular Medicine Cologne (CMMC), University of Cologne, Cologne, Germany; [...])
詳しい解説
この研究は、食物の感知という感覚入力が、脳を介して肝臓の代謝をどのように制御するかを明らかにした興味深い成果です。食事の匂いや見た目は食欲を刺激するだけでなく、消化管ホルモンの分泌や自律神経系を介して、摂食前から代謝を変化させることが知られていました。しかし、その詳細なメカニズムは不明な点が多く残されていました。 著者らは、マウスに食物を提示するだけで、肝臓のミトコンドリアが速やかに分裂することを見出しました。ミトコンドリアは細胞のエネルギー工場であり、その形態と機能は栄養状態に応じて動的に制御されています。絶食時には融合したネットワーク状になり、エネルギー基質が十分にある時には分裂した状態になることが知られていますが、食物の感知という感覚刺激でも素早く変化することが明らかになりました。 この反応は、視床下部の摂食中枢であるPOMCニューロンの活性化が引き金になっていました。POMCニューロンは、レプチンなどの代謝シグナルを感知して食欲を抑制する働きがあり、肝臓の糖代謝も制御することが報告されています。光遺伝学を用いてPOMCニューロンを人為的に活性化すると、ミトコンドリアの分裂が起こったことから、感覚刺激とミトコンドリアをつなぐ重要な中継点だと考えられます。 さらに著者らは、AKTキナーゼによるミトコンドリア分裂因子MFFのリン酸化が、この反応に必須であることを突き止めました。MFFの131番目のセリン残基をリン酸化できないようにしたノックインマウスでは、食事や感覚刺激に応じたミトコンドリアの分裂が起こらなくなり、インスリン作用による肝糖産生の抑制も減弱しました。MFFは、ミトコンドリア外膜上でDrp1を呼び込んで分裂を誘導する因子ですが、その活性がリン酸化で制御されていることを示した重要な発見と言えます。 本研究は、脳が感覚刺激に応じて末梢の代謝をダイナミックに制御する仕組みの一端を分子レベルで解明した点で価値があります。食物の感知という日常的な現象が、視床下部-肝臓軸を介してミトコンドリアに作用し、インスリン感受性など代謝の鍵を握る反応を引き起こすことがわかりました。この知見は、今後の肥満や糖尿病の研究に新しい視点を与えるものと期待されます。 例えば、食欲を刺激する匂いや見た目の工夫が、肝臓の代謝を改善する可能性も考えられます。一方で、過剰な感覚刺激が代謝を撹乱する悪影響も懸念されます。また、MFFのリン酸化を阻害する化合物が、インスリン抵抗性を改善する新しいタイプの糖尿病治療薬になるかもしれません。 本研究は、摂食行動が単なる栄養摂取ではなく、感覚や脳を介して全身の代謝制御に関わる入り口であることを教えてくれます。今後、ヒトを対象とした研究への展開や、他の代謝臓器への影響の解明などが進めば、肥満症や糖尿病の克服に向けた新しいアプローチが開かれていくことが期待されます。
亜硝酸塩の還元を利用することで、より安全なアリールジアゾニウム化学を実現した。
https://doi.org/10.1126/science.adn7006
本研究では、亜硝酸塩をチオ硫酸塩やジハロクプラートで還元することで、アリールジアゾニウム塩の蓄積を避け、より安全な脱アミノハロゲン化反応を単一工程で達成した。亜硝酸塩の還元が律速段階となるため、アリールジアゾニウムは不安定な中間体として一過的に生成するのみである。これにより、従来のサンドマイヤー反応のプロトコルで問題となっていた爆発の危険性を回避しつつ、しばしばより効率的にアニリンから直接アリールハライドを合成できることを示した。
事前情報
アリールジアゾニウム塩は有機合成の重要な試薬だが、19世紀に開発されたプロトコルがいまだに使われている。
アリールジアゾニウム塩は高い反応性を示すが、窒素ガスの発生により爆発の危険性もある。
これまでにも事故が報告されており、より安全な手法が求められていた。
行ったこと
亜硝酸塩をチオ硫酸塩やジハロクプラートで還元する新しい反応系を開発した。
反応機構を分光学的手法や理論計算で解析した。
様々なアニリンから対応するハロアレーンを合成し、適用範囲を検討した。
従来法との安全性と効率を比較検討した。
検証方法
EPR測定による反応中間体の解析
密度汎関数理論計算による反応機構の解析
様々なアニリン誘導体を基質とした基質適用性の検討
示差走査熱量測定と加速率熱量測定による安全性評価
分かったこと
亜硝酸塩の還元によりアリールジアゾニウムが定常的に低濃度で生成する。
反応系内のジアゾニウム濃度が低いため、爆発の危険性が大幅に低減される。
電子供与性/求引性置換基を持つ多様なアニリンに適用可能である。
従来法に比べて収率が向上する基質も多い。
この研究の面白く独創的なところ
有機化学の古典的な反応を、まったく新しい着想で改良した点が画期的。
亜硝酸塩の還元を鍵とすることで、爆発性中間体の蓄積を避ける点が独創的。
EPRや理論計算など物理化学的な解析により反応機構を詳細に解明した点が面白い。
収率向上と安全性向上を両立させた点が実用的にも意義深い。
この研究のアプリケーション
工業的なアリールハライドの製造プロセスの安全性向上に貢献しうる。
医薬品や機能性材料の合成におけるジアゾニウム化学の適用範囲が広がる。
反応機構の理解に基づく他の爆発性中間体を経る反応の改善につながる。
有機化学の教科書的な反応の新しい見方を提示し、化学教育にも影響を与えうる。
著者と所属
Javier Mateos†, Tim Schulte†, Deepak Behera, Markus Leutzsch, Ahmet Altun, Takuma Sato, Felix Waldbach, Alexander Schnegg, Frank Neese, and Tobias Ritter* (マックス・プランク石炭研究所、アーヘン工科大学、マックス・プランク化学エネルギー変換研究所)
詳しい解説
本研究は、有機合成化学の重要な反応の一つであるサンドマイヤー反応の安全性を飛躍的に高める新手法を開発した画期的な成果です。サンドマイヤー反応は、アリールアミンからアリールハライドを合成する反応で、19世紀末に開発されて以来、基本的なプロトコルは変わっていませんでした。 この反応は、まずアリールアミンを亜硝酸でジアゾ化してアリールジアゾニウム塩とし、これをハロゲン化銅などで処理することでアリールハライドを得ます。アリールジアゾニウム塩は窒素ガスを放出しやすく、非常に不安定で爆発性の化合物です。そのため、サンドマイヤー反応では、ジアゾニウム塩を低温で注意深く合成し、速やかに使用する必要がありました。それでも、事故が後を絶たず、工業的にも実験室でも大きな問題となっていました。 著者らは、この問題を根本的に解決する着想を得ました。それは、亜硝酸ナトリウムのような亜硝酸塩を、チオ硫酸ナトリウムやヨウ化銅のような還元剤の存在下でゆっくりとアリールアミンと反応させるというアイデアです。亜硝酸塩の還元が律速となるため、系中のアリールジアゾニウムの濃度は常に低く保たれます。生成したジアゾニウムは速やかにハロゲンと反応するため、爆発の危険はほとんどなくなります。 この新反応系の開発には、反応機構の綿密な解析が不可欠でした。著者らは、EPRスペクトル測定により、反応系中にチオ硫酸ラジカルアニオンが生成していることを突き止めました。さらに密度汎関数理論計算により、チオ硫酸ラジカルアニオンによる亜硝酸の一電子還元が鍵段階であることを明らかにしました。また、ヨウ化銅を用いる系でも、同様にヨウ素ラジカルアニオンが亜硝酸を還元することがわかりました。 様々なアリールアミンを基質として検討した結果、この新手法は電子供与性、求引性の置換基を持つ基質に幅広く適用可能であることが示されました。芳香族アミンのみならず、複素環アミンにも有効でした。収率は概して従来法と同等以上で、基質によっては大幅な向上が見られました。 安全性の評価のため、示差走査熱量測定と加速率熱量測定を行いました。その結果、新手法では、従来法で見られた爆発的な発熱が完全に抑制されていることが確認されました。また、圧力の急激な上昇もほとんど観測されませんでした。 本研究は、有機化学の教科書に必ず登場する古典的な反応を、斬新な視点で改善した点で特筆に値します。反応機構の詳細な理解に基づき、爆発性中間体の蓄積を避ける巧みな反応系を設計した点は、有機合成化学者の創造力と洞察力の賜物と言えるでしょう。 長年の懸案であったサンドマイヤー反応の安全性の問題を解決しただけでなく、収率の向上も達成した本手法は、今後、工業的にも実験室的にも広く用いられるようになると期待されます。医薬品や機能性材料の合成ルートの改善にも大きく貢献するでしょう。さらに、反応機構の理解は、他の爆発性中間体を経る反応の改善にも役立つと考えられます。 本研究は、有機合成化学における新しいブレークスルーであると同時に、基礎研究の力を示す好例とも言えます。130年来の常識を覆したこの成果は、有機化学の教科書を書き換える可能性を秘めています。研究の原動力となったのは、安全な合成法を追求する化学者の熱意だったのでしょう。
自然保護活動は生物多様性の損失を軽減する効果がある
https://doi.org/10.1126/science.adj6598
生物多様性の損失を食い止め、生態系の深刻な劣化を防ぐためには自然保護活動が不可欠です。毎年何十億ドルもの資金が世界中の自然保護に投じられています。これらの保護活動が生物多様性にプラスの効果をもたらしているのかを評価することは、今後の取り組みを方向づけるために必要不可欠です。 私たちは186の研究(665の試行を含む)のメタ分析を行い、保護区の設定や管理などの保護活動が、何もしない場合と比べて良好な結果をもたらすかどうかを検証しました。その結果、保護活動は半数以上のケースで生物多様性の状態を改善するか、少なくとも悪化を遅らせる効果があることがわかりました。 具体的には、外来種の駆除、生息地の損失の削減と再生、保護区の設定、持続可能な管理など、種や生態系を対象とした介入は非常に効果が大きいことが示されました。 この研究は、様々な種類の保護活動が概ね有効であり、生物多様性の損失を抑えるためにはこうした活動を拡大することが必要だということを示す、これまでで最も強力な証拠となります。
事前情報
政府は生物多様性の損失を阻止し、生態系の劣化を防ぐための新たな世界目標を採択した。
毎年1210億ドル以上が世界の生物多様性保全に投資されている。
2011-2020年の愛知目標は十分に達成されなかった。
行ったこと
自然保護活動の効果を比較対照試験で評価した186の研究(665試行)のメタ分析を行った。
種、生態系、遺伝子の各レベルの生物多様性への影響を評価した。
保護区の設定と管理、生息地の損失削減、持続可能な利用など7つの介入タイプを検討した。
検証方法
試行ごとに「介入下での変化率」と「対照下での変化率」から効果量を算出。
全体および介入タイプ別、生物多様性レベル別に平均効果量を計算。
感度分析で方法論の影響を検証。出版バイアスも評価。
分かったこと
保護活動は全体として生物多様性に有意な正の効果がある。
3分の2の試行で、保護活動が生物多様性を改善するか、少なくとも悪化を遅らせていた。
外来種対策、持続可能な生態系管理、生息地消失対策、保護区が特に効果大。
近年の研究ほど保護活動の効果が大きい傾向にあった。
この研究の面白く独創的なところ
100年以上に及ぶ様々な保護活動の効果を網羅的に定量評価した点が画期的。
種だけでなく生態系や遺伝的多様性への効果も評価した点が独創的。
対照試験のメタ分析により保護活動の因果効果を実証的に示した点が重要。
保護活動の有効性が近年高まっている可能性を示唆した点が興味深い。
この研究のアプリケーション
生物多様性条約の新目標達成に向けた保護活動の立案と資源配分の最適化に活用できる。
生物多様性保全の効果的手法の特定と実施の促進に役立つ。
保護活動のモニタリングと順応的管理に evidence を提供する。
様々なセクターによる保護活動の拡大の必要性を訴える根拠となる。
著者
Penny F. Langhammer, Joseph W. Bull, Jake E. Bicknell, Joseph L. Oakley, Mary H. Brown, Michael W. Bruford, Stuart H. M. Butchart, Jamie A. Carr, Don Church, Rosie Cooney, Simone Cutajar, Wendy Foden, Matthew N. Foster, Claude Gascon, Jonas Geldmann, Piero Genovesi, Michael Hoffmann, Jo Howard-McCombe, Tiffany Lewis, Nicholas B. W. Macfarlane, Zoe E. Melvin, Rossana Stoltz Merizalde, Meredith G. Morehouse, Shyama Pagad, Beth Polidoro, Wes Sechrest, Gernot Segelbacher, Kevin G. Smith, Janna Steadman, Kyle Strongin, Jake Williams, Stephen Woodley, Thomas M. Brooks
詳しい解説
本研究は、自然保護活動が生物多様性の損失を抑制するのに効果があることを、大規模なメタ分析により実証した重要な成果です。生物多様性の危機が深刻化する中、保護活動に投じられる巨額の資金が実際に生物多様性保全に役立っているのかを評価することは極めて重要な課題でした。
研究チームは、世界中の186の研究から665の試行データを収集し、保護区の設定や管理、生息地の損失削減、外来種対策、持続可能な利用など、様々な保護活動の効果を定量的に分析しました。その際、保護活動を行った場合と何もしなかった場合とを比較する対照試験のデータに着目することで、保護活動の因果効果を適切に評価しました。
メタ分析の結果、保護活動全体としては生物多様性に有意な正の効果があることが示されました。保護活動を行ったケースの3分の2では、生物多様性の状態が改善するか、少なくとも悪化のペースが遅くなっていました。介入手法別に見ると、外来種の駆除、生息地の損失削減と再生、保護区の設定と管理、生態系の持続可能な管理などが特に効果的であることが明らかになりました。
ただし、分析には地域的な偏りがあり、汚染対策や気候変動適応、種の持続可能な利用などについてはデータが不足していました。また、保護活動を行っても、なお5分の1のケースでは生物多様性が対照よりも悪化していました。これは保護活動の実施方法の改善が必要なことを示唆しています。
興味深いことに、研究の発表年が新しいほど、保護活動の効果が大きい傾向が見られました。これは保護活動の手法が向上していることを反映しているのかもしれません。一方、研究期間の長さと効果の大きさには一定の関係は見られず、短期の研究でも適切な計画と実施によって有効性を評価できることが示唆されました。
本研究の意義は、長期間にわたる様々な保護活動の効果を包括的に定量評価し、全体としての有効性を実証的に示した点にあります。特に、生物多様性への影響を種だけでなく生態系や遺伝的多様性のレベルで評価した点は新しい視点だと言えます。対照試験のメタ分析によって因果効果を確かめた点も説得力があります。
その一方で、結果は保護活動の拡大が喫緊の課題であることも浮き彫りにしました。自然保護活動は生物多様性の損失を抑える効果があるものの、それだけでは損失を完全に食い止められないことが示唆されたからです。保護活動の効果を高めるためには、より戦略的な実施と、社会の様々なセクターによる取り組みの拡大が不可欠と言えます。
本研究は、生物多様性条約の2030年目標の達成に向けて各国が効果的な保護活動を立案し、限られた資源を最適に配分する上で重要な知見を提供するでしょう。また、事業者や市民など幅広い主体による自然保護への参画を促す根拠にもなります。保護活動のモニタリングと順応的管理を通じて、より効果的・効率的な手法を改善していくことも大切です。
生物多様性の危機に歯止めをかけるには、社会全体で自然保護活動を拡大し、効果を最大化することが鍵を握ります。本研究は、保護活動がその鍵の1つであり、絶滅の波を食い止める希望の光であることを示したと言えるでしょう。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
