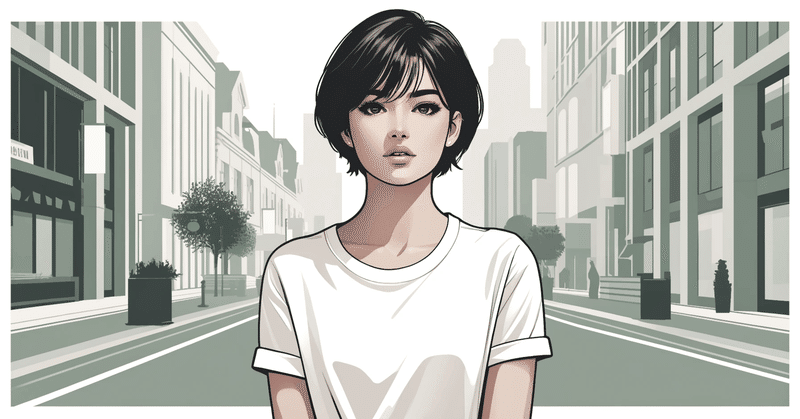
論文まとめ332回目 SCIENCE ヒト側頭皮質の1立方ミリメートル分を電子顕微鏡で撮影し、シナプスレベルの解像度で神経回路を丸ごと再構築することに成功!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなSCIENCEです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
Coexistence of superconductivity with partially filled stripes in the Hubbard model
ハバード模型における部分的に占有されたストライプと超伝導の共存
「高温超伝導を示す銅酸化物の本質を理解するため、「ハバード模型」という簡単だが難解な理論モデルが研究されてきました。今回、最先端の数値計算手法を駆使し、このモデルで超伝導とストライプ(しま模様)と呼ばれる電子の密度の濃淡が共存することを発見。超伝導の強さはドーム型に、ストライプはホール濃度0.6-0.8程度まで広がることがわかりました。この結果は、銅酸化物超伝導体の特徴をよく再現しており、その機構解明に大きな前進をもたらすと期待されます。」
A petavoxel fragment of human cerebral cortex reconstructed at nanoscale resolution
ヒト大脳皮質の1ペタボクセルの断片をナノスケール解像度で再構築
「人の脳のわずか1立方ミリメートルの中に、神経細胞は5万7千個、血管は230ミリメートル、シナプス結合は1億5千万個も詰まっています。研究チームはこの超微細な構造を1ナノメートルの解像度で丸ごと可視化することに成功。1.4ペタバイトにおよぶ膨大な電子顕微鏡画像を解析し、神経細胞や血管、シナプスの立体マップを作製。新しいタイプの神経細胞や特殊なシナプス結合も発見。ヒトの脳の設計図の理解が飛躍的に進みそうです。」
Catalog of topological phonon materials
フォノン系トポロジカル物質のカタログ
「10,000以上の結晶構造データベースを用いた大規模計算から、約半数の物質で非自明なフォノンバンド構造が発見された。その起源は空間群対称性に由来する。実験的検証が有望な物質も1000種類以上同定。フォノンのトポロジーが熱伝導や機械特性に影響し、新規デバイス応用への道が開けた。」
Future malaria environmental suitability in Africa is sensitive to hydrology
アフリカにおける将来のマラリア伝播適地は水文条件に敏感である
「気候変動によるマラリアの分布変化を予測する上で、蚊の発生源となる地表水の変化を正しく理解することが鍵です。今回、複数の気候モデルと水文モデルを組み合わせることで、2100年までのアフリカ大陸のマラリアリスクを予測。降水量のみに基づく予測と比べ、河川流量などを考慮することで、マラリアリスクの変化がより局所的かつ顕著になることが明らかに。特に人口の多い河川周辺で、マラリアのホットスポットが形成される可能性が示唆されました。」
The odd-number cyclo[13]carbon and its dimer, cyclo[26]carbon
奇数の環状炭素分子cyclo[13]carbonとその二量体cyclo[26]carbon
「炭素原子だけでできた奇数の環状分子cyclo[13]carbonを、初めて表面上で合成することに成功しました。高性能の顕微鏡で観察したところ、環がゆがんだ形をしていて、電子のスピンが特殊な状態になっていることがわかりました。さらに、2つのcyclo[13]carbonが結合した巨大な環状分子cyclo[26]carbonも作ることができました。奇数の炭素環は不安定で合成が難しいとされてきましたが、表面上での特殊な手法により実現できたのです。この発見は、炭素だけで作られる新しい物質の可能性を大きく広げるものと期待されます。」
要約
ハバード模型で、超伝導とストライプ秩序の共存を発見-銅酸化物高温超伝導体の理解に大きく前進
https://doi.org/10.1126/science.adh7691
本研究では、2次元ハバード模型において、次近接ホッピングt'を含めた場合の基底状態を、密度行列繰り込み群法(DMRG)と制約条件付き経路補助場量子モンテカルロ法(CP-AFQMC)という2つの数値計算手法を用いて調べた。その結果、電子ドープ側とホールドープ側の両方で超伝導が現れ、その超伝導オーダーパラメータがドーム型の構造を示すことがわかった。ホールドープ側では、0.6から0.8程度までドープされたストライプ秩序と強い超伝導が共存していた。一方、電子ドープ側の低ドープ領域では、反強磁性ネール秩序と弱い超伝導が共存していた。これらの結果は、銅酸化物高温超伝導体の特徴をよく捉えており、ハバード模型がその本質を記述できることを示唆している。
事前情報
ハバード模型は強相関電子系の代表的な理論モデル
銅酸化物高温超伝導体の超伝導メカニズムを理解するために盛んに研究されてきた
モデルの基底状態は、パラメータの微妙な変化に非常に敏感
ストライプ秩序の存在により、熱力学的極限への外挿に大きなサイズが必要
行ったこと
次近接ホッピングt'を含む2次元ハバード模型の基底状態をDMRGとCP-AFQMCを用いて計算
電子ドープ側とホールドープ側の両方で超伝導オーダーパラメータを評価
ストライプ秩序と超伝導の共存を調べるため、スピンと電荷の相関を解析
ツイスト平均境界条件を用いて熱力学的極限への外挿を行った
検証方法
密度行列繰り込み群法(DMRG)と制約条件付き経路補助場量子モンテカルロ法(CP-AFQMC)という相補的な数値計算手法を使用
DMRGは狭いシリンダー形状で、CP-AFQMCは広いシリンダーとトーラス形状で適用
ツイスト平均境界条件を用いて低エネルギー状態をサンプリング
分かったこと
電子ドープ側とホールドープ側の両方で超伝導が現れ、超伝導オーダーパラメータはドーム型の構造を示す
ホールドープ側では0.6から0.8程度までドープされたストライプ秩序と強い超伝導が共存
電子ドープ側の低ドープ領域では、反強磁性ネール秩序と弱い超伝導が共存
ストライプの出現は長距離位相コヒーレンスと超伝導を促進
これらの特徴は銅酸化物高温超伝導体の相図とよく一致
この研究の面白く独創的なところ
次近接ホッピングを含むハバード模型で超伝導の出現を確認した点
電子ドープ側とホールドープ側で超伝導の性質が大きく異なることを見出した点
ストライプ秩序と超伝導の共存を明確に示した点
銅酸化物の特徴をシンプルなハバード模型でよく再現できたこと
この研究のアプリケーション
銅酸化物高温超伝導体の超伝導メカニズム解明への重要な手がかり
ハバード模型の基底状態の理解を深め、強相関電子系の物理の理解に貢献
ストライプ秩序と超伝導の関係性の理解を通じ、新奇超伝導体の探索や設計に示唆
著者と所属
Hao Xu, Chia-Min Chung, Mingpu Qin, Ulrich Schollwöck, Steven R. White & Shiwei Zhang
(College of William and Mary, National Sun Yat-sen University, Shanghai Jiao Tong University, Ludwig-Maximilians-Universität München, University of California, Irvine, Flatiron Institute)
詳しい解説
銅酸化物高温超伝導体の発見以来、その超伝導メカニズムの解明は物性物理学の大きな目標の一つとなってきました。銅酸化物の超伝導を理解する上で、最も単純化された理論モデルとして注目を集めてきたのが、「ハバード模型」です。このモデルは、格子上の電子の運動エネルギー(ホッピング)とオンサイトのクーロン斥力のみを考慮した一見シンプルなモデルですが、実は非常に難解で、厳密に解くことは困難です。
特に、銅酸化物の超伝導を再現するためには、次近接サイト間のホッピング(t')を考慮することが重要だと考えられていますが、t'の導入によってモデルの基底状態は微妙なパラメータ変化に極めて敏感になることが知られていました。また、ストライプ秩序の存在により、熱力学的極限への外挿には大きなサイズが必要となります。こうした困難から、t'を含むハバード模型の基底状態、特に超伝導の有無については、長らく決着がついていませんでした。
本研究では、密度行列繰り込み群法(DMRG)と制約条件付き経路補助場量子モンテカルロ法(CP-AFQMC)という、近年発展した2つの強力な数値計算手法を組み合わせることで、この難問に挑みました。DMRGは狭いシリンダー形状で、CP-AFQMCは広いシリンダーとトーラス形状で適用することで、両者の長所を活かしつつ、それぞれの近似に起因する誤差を最小限に抑えることができます。
その結果、電子ドープ側とホールドープ側の両方で超伝導が現れることが確認されました。超伝導オーダーパラメータは、ドープ量に対してドーム型の構造を示し、これは銅酸化物の超伝導転移温度のドーム型の振る舞いに対応していると考えられます。ホールドープ側では、0.6から0.8程度までドープされたストライプ秩序と強い超伝導が共存していることがわかりました。一方、電子ドープ側の低ドープ領域では、反強磁性ネール秩序と弱い超伝導が共存していました。この電子・ホールドープの非対称性も、銅酸化物の相図の特徴をよく捉えています。
本研究の重要な発見の一つは、ストライプ秩序と超伝導の共存です。ストライプは電荷密度の濃淡が縞状に現れる秩序ですが、従来はこれが超伝導を阻害すると考えられてきました。しかし本研究では、ストライプの出現が長距離の位相コヒーレンスを促進し、超伝導を強めている可能性が示唆されました。これは、ストライプと超伝導の関係性について新たな視点を提供するものです。
これらの結果は、シンプルなハバード模型が、銅酸化物高温超伝導体の本質的な物理を捉えられることを示しています。もちろん、モデルに含まれていない他の相互作用の効果も定量的には重要かもしれません。しかし、超伝導のドーム型の振る舞いやストライプとの共存など、銅酸化物の特徴的な振る舞いが、t'を含むハバード模型で再現されたことの意義は大きいと言えるでしょう。
本研究は、長年の懸案であったハバード模型の超伝導の問題に決着をつけただけでなく、ストライプと超伝導の関係性について新たな知見をもたらしました。この成果は、銅酸化物高温超伝導体の機構解明に向けた大きな前進であり、強相関電子系の物理の理解を深める上でも重要です。さらには、ストライプ秩序と超伝導の共存という新たな概念は、新奇超伝導体の探索や設計にも示唆を与えるかもしれません。本研究を出発点に、ハバード模型と銅酸化物超伝導体の研究が新たな展開を見せることが期待されます。
ヒト側頭皮質の1立方ミリメートル分を電子顕微鏡で撮影し、シナプスレベルの解像度で神経回路を丸ごと再構築することに成功
https://doi.org/10.1126/science.adk4858
本研究では、てんかんの外科手術で切除されたヒト側頭葉の1立方ミリメートル分の組織を、電子顕微鏡を用いて1ナノメートルの解像度で撮影し、コンピュータ処理によって神経回路を丸ごと三次元再構築することに成功した。約5万7千個の細胞、230ミリメートルの血管、1億5千万個のシナプス結合が含まれる1.4ペタバイトの超大規模データセットを生成。グリア細胞が神経細胞の2倍存在すること、深層の興奮性ニューロンに樹状突起の向きに基づく新しいタイプが見つかったこと、ごく一部の軸索終末が50個もの多数のシナプスを形成することなどが明らかになった。ヒト脳の微細構造と結合様式の理解に資する貴重なリソースであり、脳の働きの解明に道を開く画期的な研究といえる。
事前情報
ヒト脳の微細構造や神経結合様式はほとんど分かっていない
これまでの方法では脳組織の限られた領域しか解析できなかった
ヒト脳由来の高品質な組織サンプルの入手が困難だった
行ったこと
てんかんの外科手術で得られたヒト側頭葉の1立方ミリメートルを解析
連続切片の電子顕微鏡撮影により1ナノメートル解像度のデータセットを取得
機械学習などを用いてニューロン、グリア、血管、シナプスを三次元再構築
1.4ペタバイトの膨大なデータを保存、共有、分析するためのツールを開発
検証方法
連続切片透過型電子顕微鏡による超微細構造イメージング
機械学習を用いた自動セグメンテーションとプルーフリーディング
シナプスの自動検出と興奮性・抑制性の分類
ニューロンの三次元形態の定量的解析と新規サブタイプの同定
分かったこと
5万7千個の細胞、230ミリメートルの血管、1億5千万個のシナプスが含まれる
グリア細胞が神経細胞の2倍存在し、オリゴデンドロサイトが最多
深層の錐体細胞に樹状突起の向きに基づく新規のサブクラスが見つかった
数千の弱いシナプス結合に加え、50個もの多数のシナプスを形成する軸索終末が稀に存在
髄鞘化の程度や血管との位置関係など、様々な組織学的特徴が明らかに
この研究の面白く独創的なところ
従来の1000倍以上の体積をシナプスレベルで三次元再構築した点
1ペタバイト超の超大規模の電子顕微鏡データセットを取得・解析した点
組織学的特徴を丸ごと定量的にマッピングできた点
新規の神経細胞サブタイプや特異的なシナプス結合様式を発見した点
この研究のアプリケーション
ヒトの脳の微細構造や神経回路の全容解明に道を開く
脳のシミュレーションや疾患メカニズムの解明に役立つ基盤情報を提供
本研究で開発されたデータ取得・解析ツールは他の脳領域の解析にも応用可能
得られたデータセットは世界中の研究者に公開され様々な研究に利用される
著者と所属
Alexander Shapson-Coe, Michał Januszewski, Daniel R. Berger (ハーバード大学)
Viren Jain, Tim Blakely, Peter H. Li (グーグルリサーチ)
Jeff W. Lichtman (ハーバード大学) ほか
詳しい解説
本研究は、ヒトの脳のごく一部である1立方ミリメートルという微小な領域を、電子顕微鏡を駆使して1ナノメートルの解像度で徹底的に調べ上げ、神経細胞やグリア細胞、血管、シナプス結合などの微細構造を丸ごと三次元再構築することに成功した、画期的な成果です。
てんかんの外科手術で切除されたヒト側頭葉の組織を用いて、これまでにない規模とレベルでの脳の微細構造の解析を実現しました。連続切片の電子顕微鏡イメージを人工知能で解析することで、約5万7千個もの細胞と230ミリメートルにおよぶ血管、そして驚くべきことに1億5千万個ものシナプス結合の立体マップを作製したのです。
この1立方ミリメートルには1.4ペタバイトもの膨大な画像データが詰まっており、従来の1000倍以上の情報量を誇ります。さらに、この超大規模データを保存・解析するためのコンピュータツールも開発。他の研究者もアクセス可能な形で公開されており、今後様々な分野で活用されることが期待されます。
データ解析の結果、ヒト脳の組織学的特徴が定量的に明らかになりました。グリア細胞が神経細胞の2倍存在し、特にオリゴデンドロサイトが最多を占めること、深層の錐体細胞に樹状突起の向きの異なる新しいサブタイプが見つかったこと、ごく一部のシナプスが驚くほど多数の結合を形成することなどが分かったのです。
本研究は、ヒトの脳の設計図ともいえる微細構造の全容解明に向けて大きく前進する成果といえます。このビッグデータは脳の動作原理の解明やコンピュータシミュレーション、脳疾患の理解など、様々な分野に影響を与えるでしょう。今回開発された手法を応用すれば、他の脳領域や発達段階、疾患サンプルなどの分析も可能になります。ヒトの脳の理解が飛躍的に進む日が来るかもしれません。
フォノン材料のバンド構造にも、電子系と同様にトポロジカルな性質が存在することが明らかに。
https://doi.org/10.1126/science.adf8458
本研究では、10,000以上の結晶構造データベースを用いて、フォノンバンド構造のトポロジーを網羅的に調べた。その結果、約半数の物質で非自明なトポロジーが存在することが明らかになった。トポロジカル量子化学の手法により、各フォノンバンドの表現や位相幾何学的性質を同定。さらに実験的に検証可能な有望物質を1000種類以上リストアップした。フォノンのトポロジーは熱伝導や機械特性に影響を及ぼすことから、新規デバイス応用への道筋が示された。本研究成果は、電子系と並ぶ新しいトポロジカル物質群の発見とも言え、フォノン工学やフォノニクスの発展に大きく寄与すると期待される。
事前情報
電子バンド構造にはトポロジカルな性質が存在し、新奇物性や応用に結びつく
フォノンにもトポロジカルな性質が存在する可能性はあるが、まだ系統的な研究は少ない
電子系のトポロジーを網羅的に調べる手法(トポロジカル量子化学など)が発展してきた
行ったこと
10,000以上の結晶構造データベース(PhononDB@kyoto-u, Materials Project)を対象
各フォノンバンドの既約表現、適合条件、位相幾何学的不変量を計算
バンド表現に基づき、原子的/障害原子的/非原子的バンドに分類
3つの代表的な表面についてフォノン表面状態を計算
実験的に有望なトポロジカルフォノン物質を抽出
検証方法
トポロジカル量子化学の手法を用いたフォノンバンドの分類
第一原理フォノン計算と組み合わせた表面状態の計算
データベース全体の傾向分析と個別物質の詳細解析
分かったこと
調べた物質の約半数で、何らかの非自明なフォノンバンド構造が存在
そのうち1780種類(PhononDB@kyoto-u)、151種類(Materials Project)でワイル点やノーダル線などのトポロジーが同定された
フラジャイルトポロジーはほとんど見られなかった
代表的な6種類のトポロジカルフォノン物質の特徴を詳細に解析
実験的に検出可能な表面フォノンモードの存在を予言
この研究の面白く独創的なところ
電子系で発展したトポロジカル物質の概念をフォノン系に適用し、網羅的に探索した初めての研究
調べた物質の半数近くでトポロジカルフォノンが存在することを発見
空間群対称性に基づくトポロジーの起源を解明
実験的に有望な候補物質を多数同定し、フォノン工学への指針を与えた
この研究のアプリケーション
トポロジカルフォノンに起因する新奇な熱電変換特性
フォノンダイオードや音響導波路などのフォノニクスデバイスへの応用
トポロジカルフォノンを介した超伝導などの探索
トポロジカル電子フォノン結合系での新奇量子現象の予言
著者と所属
Yuanfeng Xu (Center for Correlated Matter and School of Physics, Zhejiang University; Department of Physics, Princeton University)
M. G. Vergniory (Donostia International Physics Center, Spain; Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Germany)
B. Andrei Bernevig (Department of Physics, Princeton University; Donostia International Physics Center, Spain; IKERBASQUE, Basque Foundation for Science, Spain)
詳しい解説
本研究は、結晶中のフォノン(格子振動の量子化)のバンド構造にもトポロジカルな性質が存在し、物性や応用に大きな影響を及ぼすことを示した画期的な成果です。
これまで電子系では、トポロジカル絶縁体やトポロジカル半金属など、バンド構造のトポロジーに起因する新奇物性が次々と発見され、基礎・応用両面で大きな注目を集めてきました。一方、フォノン系についてはトポロジーの研究はまだ限定的でした。しかし近年、フォノンにおいてもトポロジカルな性質が存在し、熱伝導特性などに影響することが理論的に指摘されるようになってきました。
そこで本研究では、電子系で発展したトポロジカル物質探索の技術を応用し、10,000以上もの結晶構造データベースからフォノンのトポロジーを網羅的に調べ上げました。トポロジカル量子化学と呼ばれる手法を用いて、各フォノンバンドの既約表現や適合条件、位相幾何学的な不変量を計算することで、バンドのつながり方のトポロジーを数学的に分類したのです。
その結果、驚くべきことに調べた物質の約半数で何らかの非自明なトポロジーが存在することが判明。ワイル点やノーダル線などのトポロジカル特異点が1,000種類以上の物質で同定されました。トポロジーの起源が結晶の対称性に由来することも明らかになりました。さらに、第一原理計算を組み合わせることで、トポロジカルフォノンに伴う特徴的な表面状態の存在も理論的に予言しました。
フォノンのトポロジーは、バルクの格子熱伝導特性に加え、表面での熱輸送にも大きな影響を及ぼします。したがって、熱電変換や熱制御、フォノンコンピューティングなど、フォノンの性質を利用した様々なデバイス応用が期待できます。トポロジカルフォノンを介した新奇な電子フォノン相互作用の探索など、基礎物理の観点でも興味深い研究対象となるでしょう。
本研究で構築された「フォノン系トポロジカル物質のカタログ」は、新しい物質開発指針を与えるだけでなく、ありとあらゆる既知物質のフォノン物性を見直す契機になると期待されます。21世紀の物質科学を切り拓く重要な成果と言えるでしょう。トポロジーという数学の力を結晶物理学に持ち込むことで、私たちの物質観を一変させる可能性を秘めているのです。
アフリカにおけるマラリア伝播の将来予測に、河川の影響を考慮することが重要
https://doi.org/10.1126/science.adk8755
本研究では、複数の全球水文モデルと気候モデルを組み合わせることで、現在から2100年までのアフリカ大陸におけるマラリア伝播の適地を予測した。その結果、降水量のみに基づく予測と比べて、河川流量などの水文過程を明示的に考慮することで、将来のマラリア適地の変化がより局所的かつ顕著になることが明らかになった。特に、ナイル川などの大河川周辺や標高の高い地域で、マラリアリスクが集中する可能性が示唆された。一方で、西アフリカを中心に、マラリア適地が全体的に縮小する傾向も予測された。本研究の知見は、気候変動下でのマラリア対策を考える上で重要な示唆を与えるものである。
事前情報
マラリアは蚊が媒介する感染症で、アフリカで流行している
マラリア伝播は気温や降水量などの気候条件に影響される
従来の予測では降水量のみに基づくことが多かった
行ったこと
7つの全球水文モデルと4つの全球気候モデルを組み合わせた
河川流量や蒸発散量などの水文過程を明示的に考慮した
1986-2005年を基準とし、2025年以降の将来変化を予測した
検証方法
1875-1900年の予測結果を、介入前のマラリア分布と比較
モデルの精度を検証し、将来予測に使う重みづけを決定
複数シナリオ・期間で予測し、不確実性を評価した
分かったこと
降水量のみの予測より、水文過程を考慮した方が変化が局所的
ナイル川など大河川沿いや高地で、マラリアリスクが上昇
西アフリカを中心に、マラリア適地が縮小する傾向
温室効果ガス排出シナリオによって、変化の程度が異なる
この研究の面白く独創的なところ
初めて大規模アンサンブルで水文過程を考慮した将来予測
従来の降水量ベースの予測とは異なる変化パターンを示した
人口が集中する河川周辺のリスク上昇を定量的に示せた
不確実性を考慮しつつ、気候変動の影響を具体的に示した
この研究のアプリケーション
気候変動に適応したマラリア対策の立案に役立つ
水文過程を考慮した感染症予測手法の発展につながる
他の水媒介感染症の将来予測にも応用可能
人口分布の変化などを加味することで、影響評価が可能
著者と所属
Mark W. Smith, Thomas Willis, Elizabeth Mroz (School of Geography and Water@Leeds, University of Leeds, UK) William H. M. James (School of Geography and Water@Leeds, University of Leeds, UK ; 現所属 School of Geography and the Environment, University of Oxford, UK) Megan J. Klaar (School of Geography and Water@Leeds, University of Leeds, UK) Simon N. Gosling (School of Geography, University of Nottingham, UK) Christopher J. Thomas (School of Geography and Lincoln Centre for Water and Planetary Health, University of Lincoln, UK; University of Namibia, Namibia)
詳しい解説
本研究は、気候変動が引き起こすアフリカ大陸でのマラリア伝播リスクの変化を、これまでにない大規模なモデルアンサンブルを用いて予測した画期的な研究です。マラリアは蚊を媒介として伝播する感染症であり、アフリカではいまだに大きな健康被害をもたらしています。気候条件、特に気温と降水量がマラリア伝播を大きく左右することはよく知られていましたが、これまでの予測研究の多くは、降水量のみに着目するなど、水文過程の扱いが単純化されていました。
これに対し本研究では、7つもの全球水文モデルと4つの気候モデルを組み合わせ、河川流量や土壌水分量、蒸発散量といった水文変数を陽に考慮することで、より現実的なマラリア伝播リスクの将来予測を行いました。過去のマラリア分布と比較することでモデルの精度を確認した上で、温室効果ガス排出量の異なる複数シナリオ下で、21世紀末までのマラリア適地の変化を予測しています。
興味深いことに、水文過程を考慮することで、降水量のみに基づく予測とは大きく異なる変化パターンが浮かび上がってきました。降水ベースの予測では、広範囲で一様にリスクが変化するのに対し、水文ベースの予測では変化がより局所的で不均一になります。特に、ナイル川流域など人口が集中する大河川周辺や、エチオピア高地などの特定の地域で、21世紀末に向けてマラリアリスクが高まる可能性が示されました。一方、西アフリカを中心に、マラリアの適地が全体的に縮小していく傾向も見られました。
これらの結果は、気候変動への適応策を考える上で重要な示唆を与えてくれます。これまでの研究で見落とされがちだった水文要因を考慮することで、マラリアリスクの変化をより正確に予測し、的を射た対策を立てることができるでしょう。加えて本研究で用いられた予測手法は、他の水系感染症にも応用できる可能性を秘めています。
一方で、不確実性が完全に払拭されたわけではありません。使用するモデルや排出シナリオによって予測結果が異なることは、本研究でも示されている通りです。さらに、人口分布や社会経済条件など、マラリア伝播を左右する他の要因との相互作用については、十分に検討されていません。今後は、これらの課題に取り組むことで、より確度の高い影響評価とリスク管理が可能になると期待されます。
いずれにしろ、気候変動がマラリア流行にもたらすインパクトの大きさを改めて突き付けられる研究であり、水文過程を組み込んだ感染症予測の新たな道を切り拓く重要な一歩だと言えるでしょう。著者らの慧眼と野心的なアプローチに敬意を表するとともに、本研究が感染症対策の発展につながることを心から願ってやみません。
表面上での合成と高分解能顕微鏡により、奇数の炭素環cyclo[13]carbonとその二量体cyclo[26]carbonの構造と性質を初めて明らかにした。
https://doi.org/10.1126/science.ado1399
本研究では、13個の炭素原子からなる奇数の環状分子cyclo[13]carbonを、表面上で合成することに初めて成功した。走査型プローブ顕微鏡を用いて、decachlorofluoreneという前駆体分子から塩素原子を除去することでcyclo[13]carbonを作製した。この分子は開殻系で三重項基底状態を持ち、吸着サイトによって歪んだ形状や炭素原子上の不対電子の局在化の程度が異なることがわかった。さらに、cyclo[13]carbonの二量体であるcyclo[26]carbonも合成・同定された。これらの結果は、cyclocarbonやその前駆体が新しい炭素同素体の構成要素として有望であることを示している。
事前情報
炭素原子のみからなる環状分子cyclo[N]carbon (CN) は量子化学計算の検証に有用で、新しい炭素材料の前駆体として重要
奇数のcyclocarbonはこれまで合成例がなく、偶数のものよりさらに不安定と予測されていた
行ったこと
走査型プローブ顕微鏡を用いて、decachlorofluoreneから塩素原子を除去しcyclo[13]carbonを表面上で合成した
cyclo[13]carbonの構造や電子状態を実験と理論計算で解明した
cyclo[13]carbonの二量体cyclo[26]carbonも合成・同定した
検証方法
走査型トンネル顕微鏡(STM)と非接触原子間力顕微鏡(nc-AFM)による分子の可視化
密度汎関数理論(DFT)計算、coupled-cluster理論、多参照摂動論などによる理論解析
分かったこと
cyclo[13]carbonは開殻系の三重項基底状態を持ち、吸着サイトに応じて分子の歪みや不対電子の局在化の程度が変化する
cyclo[13]carbonは環の2箇所でVγ5ドメインを介して背中合わせに相互作用し、cyclo[26]carbonの二量体を形成できる
cyclo[13]carbonの二量体形成は、その三重項状態の安定化に重要である
この研究の面白く独創的なところ
これまで合成が困難とされてきた奇数のcyclocarbonを、表面上での原子操作により初めて実現した
高分解能AFMにより、奇数環特有の分子構造の歪みや電子状態の局在を実空間で可視化できた
2つのcyclo[13]carbonが結合した巨大な環状分子の合成にも成功し、cyclocarbonの二量化過程を実証した
この研究のアプリケーション
新しい炭素同素体やナノ炭素材料の合理的設計への知見を提供
表面上での化学反応の制御による新物質創製の可能性を示唆
不安定分子種の物性解明に有用な表面分析・理論計算の手法基盤の確立
著者と所属
Florian Albrecht, Igor Rončević, Yueze Gao, Fabian Paschke, Alberto Baiardi, Ivano Tavernelli, Shantanu Mishra, Harry L. Anderson & Leo Gross
(IBM Research Europe, University of Oxford, IBM Quantum)
詳しい解説
炭素原子だけで構成される環状分子 "cyclocarbon" は、量子化学計算手法の検証に有用なベンチマーク系であるとともに、様々な炭素材料の前駆体としても注目を集めています。しかし、炭素原子数が奇数のcyclocarbonは合成が非常に難しく、これまで実験的な観測例はありませんでした。それは偶数のcyclocarbonと比べても、エネルギー的により不安定になると予測されていたためです。
本研究では、この難題に挑戦し、13個の炭素からなる奇数環状分子 "cyclo[13]carbon" を、独自の表面合成手法により初めて生成することに成功しました。具体的には、塩素原子を多数持つ平面状の前駆体分子 "decachlorofluorene" を絶縁体表面上に吸着させ、走査型プローブ顕微鏡の探針から電圧パルスを印加することで塩素原子を一つずつ除去し、目的のcyclo[13]carbonを合成したのです。
この分子を非接触原子間力顕微鏡で観察したところ、環構造が大きく歪んだ形状をとっていることがわかりました。さらに詳細な分光分析と理論計算から、cyclo[13]carbonは開殻系の分子で三重項基底状態をもち、13個の炭素原子上に不対電子が非局在化していることが明らかになりました。また、表面上の吸着サイトによって分子の歪みの程度や不対電子の局在性が変化することも見出されました。
驚くべきことに、2つのcyclo[13]carbonが環の一部で結合した巨大な二量体、cyclo[26]carbonの合成にも成功しています。2つの13員環が背中合わせにVγ5ドメインを介して相互作用することで、三重項状態を安定化させながら二量化が進行したと考えられます。
本研究の成果は、これまで仮説の域を出なかった奇数のcyclocarbon類を実在する分子として初めて合成・同定した点で画期的です。さらに、高分解能AFMにより歪んだ環構造や開殻電子状態を実空間で可視化できた点も特筆に値します。
これらの知見は、cyclocarbonやその前駆体分子が、新しい炭素同素体やナノ炭素材料の構成要素として有望であることを示唆しています。加えて、表面上での原子・分子の精密な操作と反応制御が、不安定な化学種の合成や特性評価に威力を発揮することを如実に示した点でも、物質科学の新たな扉を開いたと言えるでしょう。表面分析と理論計算を高度に組み合わせた本研究の手法基盤は、合成化学と物性科学の融合を加速すると期待されます。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
