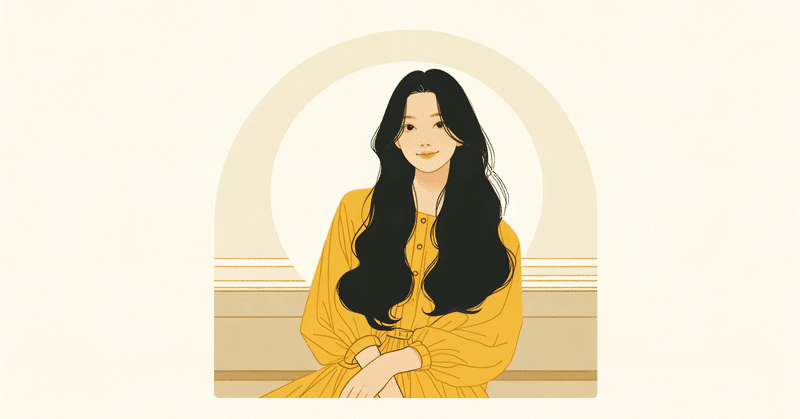
論文まとめ327回目 Nature LiTaO3の特性を活かした低コスト・大量生産可能なフォトニック集積回路の実現!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなNatureです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
Quantum control of a cat qubit with bit-flip times exceeding ten seconds
10秒を超える量子ビットのビットフリップ時間を持つキャット状態の量子制御
「量子コンピュータを実現するには、環境ノイズから量子ビットを守る必要があります。この研究では、猫状態と呼ばれる特殊な量子状態を使った量子ビットを開発。キャット状態は環境ノイズによるエラー(ビットフリップ)に対して自然に保護されますが、一方で量子制御が難しいという課題がありました。今回、ビットフリップ時間が10秒を超える猫状態量子ビットを実現し、さらにその量子状態を自在に制御することに成功。量子制御と高い安定性を兼ね備えた画期的な成果です。」
Lithium tantalate photonic integrated circuits for volume manufacturing
LiTaO3を用いた量産向けフォトニック集積回路
「無線通信用フィルターの材料として大量生産されているLiTaO3基板を用いて、光通信に必要な光導波路や変調器などの部品を集積化したフォトニック集積回路の製造に成功。LiTaO3は同様の性質を持つLiNbO3と比べ複屈折が10分の1以下と小さいため、広帯域での動作が可能。また低損失な光導波路や高効率な変調器の作製、さらにはマイクロ共振器中でのソリトンコム生成にも成功。大量生産性と優れた特性を兼ね備えた次世代フォトニクス基盤技術として期待。」
Targetable leukaemia dependency on noncanonical PI3Kγ signalling
非典型的なPI3Kγシグナルへのターゲットとなりうる白血病の依存性
「白血病細胞の一部は、PI3Kγという分子の非典型的な働きに依存していることが明らかになりました。PI3Kγは炎症シグナルや特定の受容体の活性化によって活性化され、PAK1というタンパク質のリン酸化を促進します。このPI3Kγ-PAK1経路は、がん抑制遺伝子の発現を抑えることで白血病の生存に重要な役割を果たしていました。PI3Kγ阻害剤であるeganelisibは、この経路を遮断し、白血病細胞の死滅を誘導しました。さらに、eganelisibと抗がん剤シタラビンの併用は、より強力な抗腫瘍効果を示しました。PI3Kγ-PAK1経路を標的とした新たな白血病治療法の開発が期待されます。」
Computationally restoring the potency of a clinical antibody against Omicron
オミクロン亜種に対する臨床用抗体の効力を計算機で回復させる
「オミクロン変異株の出現により、多くの治療用抗体が効果を失った。そこで計算機を駆使し、変異を持つオミクロン株にも強く結合するよう既存の抗体の構造を最適化。わずか4つのアミノ酸を置換しただけで、オミクロン株に対する中和活性が大幅に改善。従来株に対する効果も維持した。変異株に対応した改良抗体を迅速に創出できる可能性を示した。今後の変異株対策に新たな選択肢を提供する成果だ。」
Genome organization around nuclear speckles drives mRNA splicing efficiency
核スペックルの周りのゲノム構造がmRNAスプライシング効率を駆動する
「細胞核内には核スペックルと呼ばれる構造体があり、そこにはスプライシングに関わるタンパク質や非コードRNAが高濃度で存在します。本研究では、核スペックルの近くに位置する遺伝子ほど、スプライソソームの結合量が増加し、RNA前駆体のスプライシングが効率的に起こることを明らかにしました。さらに、遺伝子の核スペックルからの距離は細胞の種類によって異なり、それに応じてスプライシング効率も変化することを示しました。また、人為的に遺伝子を核スペックルに近づけると、スプライシング効率が上昇することも証明しました。これらの結果は、ゲノムDNAの立体的な配置がスプライシングの調節に重要な役割を果たしていることを示しています。」
Decoupling excitons from high-frequency vibrations in organic molecules
有機分子におけるエキシトンと高周波振動の分離
「有機分子の発光を制限する高周波振動とエキシトンのカップリングを抑制する方法を発見。電子供与体と受容体を繋ぐ非平面構造分子で、電子と正孔が空間的に分離したエキシトンを形成すると高周波振動と切り離せる。また、電子や正孔準位が非結合性軌道の場合も高周波振動との結合が弱まる。この設計指針により、680-800nmの高効率近赤外発光材料の開発に成功。有機ELや蛍光イメージング、有機太陽電池の性能向上に期待。」
Measurement of the superfluid fraction of a supersolid by Josephson effect
ジョセフソン効果による超固体の超流動成分の測定
「超固体は、結晶と超流動の性質を併せ持つ不思議な物質です。今回、超固体中の隣り合う2つの密度のピークの間で、交互にトンネルを繰り返すジョセフソン振動が起きることを発見しました。このジョセフソン振動の周波数から、超固体の超流動成分を直接測定することに世界で初めて成功。超流動成分は密度のピークが大きくなるほど減少し、超固体独特のダイナミクスを生み出すことがわかりました。」
要約
環境ノイズに対する自然な保護機能を持つ量子ビットで、量子制御と高い安定性を両立
この研究では、環境ノイズに対して自然な保護機能を持つ「猫状態量子ビット」を開発し、ビットフリップ時間が10秒を超える高い安定性を実現した。さらに、この猫状態の量子重ね合わせを制御する技術を確立。従来の猫状態量子ビットに比べて4桁もの安定性の向上を達成しつつ、量子制御も可能にした。この成果は、ノイズに強く、スケーラブルな量子コンピュータ実現に向けた重要な一歩となる。
事前情報
量子ビットは環境ノイズの影響を受けやすく、エラー訂正が必要
猫状態量子ビットはビットフリップエラーに対する自然な保護機能を持つ
しかし従来の猫状態量子ビットは量子制御が難しく、安定性も不十分だった
行ったこと
超伝導回路で猫状態量子ビットを実装
ビットフリップ時間が10秒を超える高い安定性を達成
量子重ね合わせ状態を準備し、トモグラフィーで観測
位相フリップ時間490ナノ秒以上を確認
ホロノミックゲートを用いて、ビットフリップ保護を破らずに量子制御
検証方法
猫状態量子ビットの状態をWigner関数で可視化
ビットフリップ、位相フリップの寿命をラビ振動の減衰から測定
ホロノミックゲートによる量子制御をプロセストモグラフィーで評価
分かったこと
猫状態量子ビットでビットフリップ時間10秒超、位相フリップ時間490ナノ秒超を実現
従来の猫状態量子ビットに比べ、ビットフリップ時間を4桁向上
ホロノミックゲートにより、ビットフリップ保護を破らずに量子制御可能
量子重ね合わせ状態の生成と観測に成功
この研究の面白く独創的なところ
従来の4桁以上に及ぶビットフリップ時間の飛躍的な向上
ビットフリップ保護と量子制御の両立を初めて実証
環境ノイズに強く、スケーラブルな量子ビット実現への道筋を示した点
この研究のアプリケーション
ノイズに強い量子メモリや量子エラー訂正への応用
スケーラブルな量子コンピュータ実現の基盤技術
量子センシングや量子通信への展開も期待
著者と所属
U. Réglade, A. Bocquet, Z. Leghtas
(Alice & Bob, Paris, France; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS-PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Cité, Centre Automatique et Systèmes, Mines Paris, Université PSL, Inria, Paris, France)
詳しい解説
この研究は、環境ノイズに強い量子ビットの実現に向けて大きな前進をもたらすものです。量子コンピュータを実用化するには、量子ビットをノイズから守り、エラーを抑えることが不可欠ですが、これは容易ではありません。そこで注目されているのが、「猫状態量子ビット」です。
猫状態とは、シュレーディンガーの猫のように、2つの状態が重ね合わさった特殊な量子状態のことを指します。この状態は、環境ノイズによるビットフリップエラー(0と1が反転するエラー)に対して自然な保護機能を持っています。つまり、猫状態を使えば、ビットフリップが起こりにくい、ノイズに強い量子ビットが実現できると期待されているのです。
しかし、従来の猫状態量子ビットには大きな課題がありました。それは量子制御が難しいこと、そして安定性が十分でないことです。量子コンピュータでは、量子ビットの状態を自在に制御する必要がありますが、猫状態はその制御が困難でした。また、ビットフリップ耐性はあるものの、絶対的な安定性は不十分で、実用化にはより長いエラー時間が求められていました。
この研究では、これらの課題を見事に克服しています。超伝導回路を用いて猫状態量子ビットを実装し、ビットフリップ時間が10秒を超える驚異的な安定性を実現しました。これは従来の猫状態量子ビットに比べて、4桁もの飛躍的な向上です。さらに重要なのは、量子制御との両立を実証したことです。ホロノミックゲートという手法を用いることで、ビットフリップ保護を破ることなく、量子重ね合わせ状態を自在に制御できることを示しました。
また、490ナノ秒を超える位相フリップ時間も観測しており、総合的に高い性能を達成しています。量子重ね合わせ状態の生成と観測にも成功しており、猫状態量子ビットが量子情報処理に有用であることを示しました。
この研究は、ノイズに強く、スケーラブルな量子コンピュータ実現に向けた大きな一歩と言えます。猫状態量子ビットの飛躍的な性能向上と、量子制御との両立は、量子エラー訂正や量子メモリなどへの応用が期待されます。また、量子センシングや量子通信など、他の量子技術への展開も見込めるでしょう。
量子コンピュータの実現には多くの困難がありますが、この研究はその障壁を大きく下げるものです。今後のさらなる進展に大いに期待が持てる画期的な成果と言えるでしょう。
LiTaO3の特性を活かした低コスト・大量生産可能なフォトニック集積回路の実現
本研究では、無線通信用フィルターの材料として大量生産されているLiTaO3基板上に、低損失な光導波路や高効率な電気光学変調器などの光部品を集積化したフォトニック集積回路の製造プロセスを開発した。LiTaO3は同様の性質を持つLiNbO3と比べ、複屈折が10分の1以下と小さいため、広帯域での動作や複雑な回路設計が可能となる。作製したLiTaO3導波路は5.6 dB/mという低損失を達成し、変調器はC帯で1.9 V・cmという高効率動作を示した。さらに、LiTaO3マイクロ共振器中でソリトンマイクロコムの生成にも成功した。LiTaO3フォトニック集積回路は、大量生産性と優れた特性を兼ね備えた次世代技術として期待される。
事前情報
LiTaO3は無線通信用フィルターの材料として大量生産されている
LiTaO3はLiNbO3と同様に優れた電気光学特性を持つ
LiTaO3の複屈折はLiNbO3の10分の1以下と小さい
行ったこと
イオンスライス法によるLiTaO3薄膜の作製と基板への接合
DUVリソグラフィを用いたLiTaO3光導波路と電極の作製プロセスの開発
LiTaO3導波路の伝搬損失と変調器の性能評価
LiTaO3マイクロ共振器でのソリトンマイクロコム生成の実証
検証方法
周波数コム補正された掃引レーザー分光法による光共振器の損失評価
ネットワークアナライザを用いた変調器の電気光学帯域の測定
光スペクトルアナライザによるソリトンマイクロコムスペクトルの観測
分かったこと
LiTaO3光導波路の伝搬損失は5.6 dB/mと低損失
LiTaO3マッハツェンダー変調器はC帯で1.9 V・cmの高効率動作を達成
LiTaO3の複屈折の小ささにより、広帯域動作と柔軟な回路設計が可能
x-cut LiTaO3マイクロ共振器中でソリトンマイクロコム生成に成功
ラマン散乱を抑制する結晶方位の最適化により安定なソリトン生成が可能
この研究の面白く独創的なところ
大量生産性に優れたLiTaO3基板を用いてフォトニック集積回路を実現した点
LiTaO3の複屈折の小ささを活かし、広帯域動作と柔軟な設計を可能にした点
低損失導波路と高効率変調器という優れた性能を達成した点
x-cut LiTaO3マイクロ共振器中で初めてソリトンマイクロコムを生成した点
この研究のアプリケーション
データセンター間光通信や5G/6G無線通信用の高速光変調器
光周波数コムを用いた分光計測や光周波数シンセサイザ
超伝導量子コンピュータとの量子インターフェース
次世代の高性能かつ低コストな光集積回路の基盤技術
著者と所属
Chengli Wang, Zihan Li, Johann Riemensberger, Tobias J. Kippenberg
(Institute of Physics, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, EPFL; Center of Quantum Science and Engineering, EPFL; National Key Laboratory of Materials for Integrated Circuits, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences)
詳しい解説
本研究は、5G無線通信用フィルターの材料として大量生産されているLiTaO3基板上に、光導波路や変調器などの光部品を集積化したフォトニック集積回路を製造する技術を開発した画期的な成果です。
LiTaO3は、同じ強誘電体結晶であるLiNbO3と同様に優れた電気光学特性を有しており、光変調器などへの応用が期待されてきました。しかし、LiNbO3と比べると研究開発の歴史は浅く、高性能なフォトニック集積回路の実現には至っていませんでした。
研究チームは、LiTaO3がLiNbO3と比べて複屈折が10分の1以下と非常に小さいという特長に着目しました。複屈折が小さいと、広い波長範囲で基本モード間の混合が起きにくくなるため、広帯域動作や柔軟な回路設計が可能となります。また機械的・化学的強度も高く、エッチングによる微細加工に適しています。
まず、イオンスライス法によってLiTaO3基板から薄膜を切り出し、酸化膜付きシリコン基板に接合するプロセスを確立しました。次に、DUVリソグラフィと反応性イオンエッチングを駆使して、幅2μm、深さ500nmの高アスペクト比な光導波路の作製に成功。伝搬損失は5.6 dB/mと低損失でした。さらに、同じプロセスで変調器の光導波路と電極を形成し、VπL = 1.9 V・cm(@C帯)という高い変調効率を達成しました。
また、LiTaO3がLiNbO3同様に大きな光非線形性を有することに着目し、x-cutのLiTaO3マイクロ共振器を用いてソリトンマイクロコムの生成実験を行いました。LiTaO3はラマン散乱が強いため、共振器の結晶方位を工夫してラマン散乱を抑制することで、安定なソリトンモード同期状態を実現。これはx-cut強誘電体結晶での初のソリトンコム生成であり、変調や周波数シフトなど非線形と電気光学効果の組み合わせへの道を拓くものです。
本研究は、大量生産性と優れた特性を兼ね備えたLiTaO3という新しい材料体系を用いて、高性能フォトニック集積回路を実現した点で高く評価できます。広帯域動作や柔軟な回路設計を可能にするLiTaO3の特長を存分に活かしており、データセンター間通信や次世代無線通信、量子情報処理などの分野への応用が大いに期待されます。シリコンフォトニクスに続く、次世代の光集積回路技術の有力な候補として注目すべき成果だと言えるでしょう。
非典型的なPI3Kγシグナル経路への依存性を標的とした、新たな白血病治療法の開発
本研究は、ゲノムワイドCRISPRスクリーニングと機能解析を通じて、一部の急性白血病がPI3Kγ複合体に選択的に依存していることを明らかにしました。この依存性は、自然免疫炎症シグナルの活性化とPI3Kγの制御サブユニットであるPIK3R5の発現上昇によって特徴付けられていました。さらに、PI3Kγの新規基質としてPAK1を同定し、PI3Kγ阻害によるPAK1の脱リン酸化がミトコンドリア酸化的リン酸化を損なうことを見出しました。PI3Kγ選択的阻害剤であるeganelisibは、PIK3R5が活性化された白血病に対して有効であり、シタラビンとの併用によって相乗的な抗腫瘍効果を示しました。本研究は、PI3Kγ-PAK1シグナル経路を標的とした新たな白血病治療法の開発に貢献すると期待されます。
事前情報
PI3Kγは固形がんにおいて腫瘍関連マクロファージの再分極化と抗腫瘍免疫応答の促進に関与することが示唆されていた。
一方、がん細胞自身におけるPI3Kγの役割は不明だった。
行ったこと
ゲノムワイドCRISPRiスクリーニングと急性白血病における機能解析を統合し、PI3Kγ複合体への選択的依存性を定義した。
PI3Kγ阻害剤eganelisibの白血病に対する効果を in vitro および in vivo で評価した。
PI3Kγの新規基質としてPAK1を同定し、その役割を解明した。
シタラビン残存白血病細胞におけるPI3Kγ-PAK1経路の活性化メカニズムを解析した。
検証方法
ゲノムワイドCRISPRiスクリーニング
白血病細胞株および患者由来異種移植モデルを用いた薬剤感受性試験
RNA-seqおよびATAC-seqによる遺伝子発現および染色体アクセシビリティの解析
定量的プロテオミクスおよびリン酸化プロテオミクス解析
分かったこと
一部の急性白血病はPI3Kγ複合体に選択的に依存しており、自然免疫炎症シグナルの活性化とPIK3R5の発現上昇が特徴である。
PI3Kγ阻害剤eganelisibは、PIK3R5が活性化された白血病に対して有効である。
PI3KγはPAK1を脱リン酸化することでミトコンドリア機能を制御している。
シタラビン残存白血病細胞ではGタンパク質共役型プリン受容体シグナルの亢進とPAK1のリン酸化亢進が見られる。
EganelisibとシタラビンはPI3Kγ-PAK1経路の阻害を介して相乗的な抗腫瘍効果を示す。
この研究の面白く独創的なところ
ゲノムワイドCRISPRiスクリーニングにより、PI3Kγ複合体への選択的依存性を見出した点。
PI3Kγの新規基質としてPAK1を同定し、その役割を明らかにした点。
一部の白血病におけるPI3Kγ依存性のメカニズムとして、自然免疫炎症シグナルの関与を明らかにした点。
シタラビン残存白血病細胞におけるPI3Kγ-PAK1経路の活性化メカニズムを解明した点。
この研究のアプリケーション
PI3Kγ阻害剤を用いた新たな白血病治療法の開発
PI3Kγ-PAK1経路の活性化を標的とした、シタラビン併用療法の最適化
自然免疫炎症シグナルやGタンパク質共役型受容体シグナルを利用した、PI3Kγ依存性白血病の同定と層別化治療
著者と所属
Qingyu Luo, Evangeline G. Raulston, Xiaowei Wu, Andrew A. Lane
(Department of Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA)
詳しい解説
本研究は、一部の急性白血病がPI3Kγ複合体に選択的に依存していることを明らかにし、その依存性メカニズムと治療標的としての可能性を示した画期的な成果です。
PI3Kγはこれまで主に固形がんにおいて腫瘍関連マクロファージの再分極化と抗腫瘍免疫応答の促進に関与することが示唆されていましたが、がん細胞自身における役割は不明でした。本研究では、ゲノムワイドCRISPRiスクリーニングと機能解析を統合することで、骨髄性、リンパ性、樹状細胞性の各系統を含む高リスク急性白血病のサブセットがPI3Kγ複合体に選択的に依存していることを見出しました。
この依存性の特徴は、自然免疫炎症シグナルの活性化とPI3KγのP型制御サブユニットをコードするPIK3R5の発現上昇でした。PIK3R5は活性型PI3Kγ複合体を安定化することが示唆されました。興味深いことに、PI3Kγの新規基質としてPAK1を同定し、PI3Kγ阻害によるPAK1の脱リン酸化がミトコンドリアの酸化的リン酸化を損なうことを明らかにしました。PI3Kγ選択的阻害剤であるeganelisibは、PIK3R5が活性化された白血病に対して有効であり、マウスモデルにおいても抗腫瘍活性と忍容性の高さが確認されました。
さらに、eganelisibと標準治療薬シタラビンの併用は、いずれか単独よりも生存期間を延長させました。ベースラインのPIK3R5発現が低い患者由来異種移植モデルにおいても、シタラビン残存白血病細胞ではGタンパク質共役型プリン受容体の活性化とPAK1のリン酸化亢進が見られ、PI3Kγ-PAK1経路の阻害による併用効果が示されました。
本研究は、PI3Kγ-PAK1経路がNFκB依存的ながん抑制遺伝子ネットワークを抑制することで白血病の生存を促進するという新たなメカニズムを提示しました。この知見は、PI3Kγ阻害剤を用いた白血病の新規治療法の開発につながることが期待されます。加えて、自然免疫炎症シグナルやプリン作動性受容体シグナルの活性化を指標とすることで、PI3Kγ-PAK1経路の阻害が奏功する患者集団を同定し、層別化治療を実現できる可能性があります。
急性白血病は予後不良な難治性疾患ですが、本研究で明らかになったPI3Kγへの選択的依存性とその分子メカニズムは、新たな治療標的の同定と創薬に貢献すると期待されます。PI3Kファミリーの中でも特異的な機能を有するPI3Kγに焦点を当てた本研究は、基礎と臨床をつなぐトランスレーショナルリサーチの好例と言えるでしょう。今後のさらなる展開が大いに期待されます。
計算機を活用し既存の治療用抗体を改変することで、オミクロン変異株に対する中和活性を素早く回復することに成功した。
本研究では、オミクロン変異株の出現により効果が低下した既存の治療用抗体COV2-2130について、計算機を用いて改変し、オミクロン株に対する中和活性を回復させることに成功した。複数のオミクロン亜種に結合するよう抗体の構造を最適化し、4つのアミノ酸置換を導入した改良抗体は、オミクロンBA.1やBA.1.1に対して強力な中和活性を示した。また、従来株に対する効果も維持されていた。マウスを用いた実験でも、BA.1.1に対する予防効果が確認された。計算機による抗体設計は変異株に迅速に対応するための有望なアプローチであり、今後のパンデミック対策に新たな選択肢を提供すると期待される。
事前情報
オミクロン変異株の出現で多くの治療用抗体が効果を失った
COV2-2130は他の抗体と組み合わせて使用できる貴重な抗体
効果が低下した高価値な抗体を改変し活性を回復させる方法が求められている
行ったこと
計算機を用いてCOV2-2130を改変し、オミクロンBA.1、BA.1.1に結合力を最適化
4つのアミノ酸置換を導入した改良抗体2130-1-0114-112を設計
設計された376種類の抗体について結合実験や中和実験で評価
2130-1-0114-112の構造をクライオ電子顕微鏡で解析
検証方法
免疫測定による抗原結合評価
偽ウイルスおよび生ウイルスを用いた中和活性評価
マウスを用いた予防効果の検証
変異ウイルスライブラリを用いたエスケープ変異の網羅的評価
クライオ電子顕微鏡による抗体-抗原複合体の構造解析
分かったこと
2130-1-0114-112は BA.1、BA.1.1に対し強力な中和活性を示した
デルタ株など従来株に対する中和活性も維持されていた
2130-1-0114-112はBA.1.1感染マウスでの予防効果を示した
変異ライブラリ解析から、COV2-2130の弱点を克服していることが示唆された
構造解析から、4つの変異が抗原との結合を強化していることが明らかに
この研究の面白く独創的なところ
計算機を駆使し短期間で効果的な抗体改変を実現した点
複数の変異株を同時に標的としてトレードオフなく最適化した点
ごく少数の変異で大幅な中和活性の改善を達成した点
構造解析から改変の効果を分子レベルで理解した点
この研究のアプリケーション
変異株の出現に対し迅速に対応できる抗体開発アプローチ
既存の有望な抗体を活かした改良による開発期間の短縮
免疫ブリッジングによる効率的な承認取得の可能性
他のウイルスへの応用による将来のパンデミック対策
著者と所属
Thomas A. Desautels、Kathryn T. Arrildt、Adam T. Zemla 他37名
(ローレンス・リバモア国立研究所、ロスアラモス国立研究所、ヴァンダービルト大学 他)
詳しい解説
本研究は、オミクロン変異株の台頭により効果が低下した既存の治療用抗体を、計算機を用いて迅速に改変し、オミクロン株に対する中和活性を回復させることに成功した注目すべき成果です。
オミクロン株の出現は多くの抗体医薬の効果を大きく減弱させ、パンデミック対策に大きな課題を突きつけました。中でもCOV2-2130抗体は、他の抗体と組み合わせて使える貴重な抗体でありながら、オミクロン株に対する効果を失ってしまったのです。そこで本研究では、計算機を活用してCOV2-2130をBA.1やBA.1.1など複数のオミクロン亜種に最適化し、わずか4つのアミノ酸置換を導入するだけで、オミクロン株に対する中和活性を大幅に改善することに成功しました。
改良抗体のデザインは、抗原への結合力、熱安定性、ヒト抗体配列との類似性など複数の指標を計算機上で同時に最適化することで行われました。200万を超える候補配列の中から376種類の有望な設計を選び、実験的に評価したのです。最終的に選ばれたわずか4つの変異を持つ改良抗体2130-1-0114-112は、BA.1やBA.1.1に対し強力な中和活性を発揮しただけでなく、従来株であるデルタ株などに対する効果も損なわれていませんでした。また、マウス感染実験でも、BA.1.1に対する予防効果が確認されました。
変異ウイルスのライブラリを用いた網羅的な解析からは、2130-1-0114-112がCOV2-2130の弱点の多くを克服し、エスケープ変異に対してもロバストであることが示唆されました。さらにクライオ電子顕微鏡を用いた構造解析により、導入された4つの変異が抗原との結合を強化するメカニズムが明らかになりました。親和性を高める新たな相互作用の獲得と、不利な相互作用の回避によって、オミクロン株における複数の変異をカバーしているのです。
本研究のアプローチは、変異株の出現に対して迅速に対応できる抗体開発の新たな選択肢を提供するものです。計算機を活用することで、実験のフィードバックを必要とせず、標的とする複数の変異株に対して効率的に最適化が行えます。また、既存の有望な抗体を土台とすることで、開発期間の短縮や、免疫ブリッジングによる承認取得の可能性も期待されます。さらに、今回開発された計算機プラットフォームは、SARS-CoV-2以外のウイルスへの応用も可能であり、将来のパンデミックに備えるための強力なツールとなるでしょう。
今後変異株の脅威とともに生きていくためには、ワクチンに加えて抗体医薬などの治療オプションを迅速に更新していく必要があります。本研究は、計算科学の力を活用することでそれを可能にする道筋を示した画期的な成果だと言えます。変異株に対応した改良抗体を迅速に創出するための新たなアプローチとして、大いに注目されるべき研究だと言えるでしょう。
核スペックルの近傍に位置する遺伝子ほど、スプライソソームの結合が増加し、スプライシング効率が高まることを発見
本研究は、細胞核内の核スペックルと呼ばれる構造体の周辺に位置する遺伝子ほど、スプライソソームの結合量が増加し、RNA前駆体のスプライシング効率が高くなることを明らかにしました。また、遺伝子の核スペックルからの距離は細胞の種類によって異なり、それに応じてスプライシング効率も変化することを示しました。さらに、人為的に遺伝子を核スペックルに近づけると、スプライシング効率が上昇することも証明しました。これらの結果から、ゲノムDNAの立体的な配置が、スプライソソーム濃度の調節を介して、mRNAスプライシングの効率を制御する重要な役割を果たしていることが明らかになりました。
事前情報
核スペックルは、スプライシング関連因子が濃縮した核内構造体である
スプライシングは、RNA前駆体から不要な部分(イントロン)を除去し、エクソンをつなぎ合わせてmRNAを生成する過程
核スペックルの機能的役割については不明な点が多かった
行ったこと
SPRITEによるゲノムワイドな核スペックルとの近接性の測定
snRNAとRNA前駆体の結合量の解析
共転写的スプライシングレベルの測定
細胞種間での核スペックル近傍の遺伝子配置の比較
人為的な遺伝子のスペックルへのリクルートとスプライシングへの影響の検証
検証方法
SPRITE (split-pool recognition of interactions by tag extension)法
snRNAとRNA前駆体の結合量の定量 (RAP-RNA法)
スプライシング効率の測定 (クロマチンRNA-seq、5EU RNA-seq)
異なる細胞種でのSPRITE解析
MS2-MCPシステムを用いた人為的なスペックルへの遺伝子リクルート
分かったこと
核スペックル近傍の遺伝子は、スプライソソームの結合量が多く、スプライシング効率が高い
核スペックル近傍の遺伝子配置は細胞種間で異なり、スプライシング効率の違いと相関する
遺伝子を人為的に核スペックルにリクルートすると、スプライシング効率が上昇する
ゲノムDNAの立体配置がスプライソソーム濃度を調節し、スプライシング効率を制御する
この研究の面白く独創的なところ
ゲノムの立体構造と機能の関連を初めて高解像度で示した点
遺伝子の位置と核内構造体との関係が、mRNAプロセシングに影響することを明らかにした点
細胞種間での核内配置の違いが、スプライシング効率の差異につながることを示した点
人為的な遺伝子の再配置により、因果関係を直接的に証明した点
この研究のアプリケーション
疾患に関連するスプライシング異常の理解と治療法開発への応用
核内の立体的な遺伝子配置を考慮した、遺伝子発現制御機構の理解
合成生物学による遺伝子発現の人為的制御技術の開発
核内構造体を標的とした新たな創薬アプローチの可能性
著者と所属
Prashant Bhat, Amy Chow, Benjamin Emert, Olivia Ettlin, Sofia A. Quinodoz, Mackenzie Strehle, Yodai Takei, Alex Burr, Isabel N. Goronzy, Allen W. Chen, Wesley Huang, Jose Lorenzo M. Ferrer, Elizabeth Soehalim, Say-Tar Goh, Tara Chari, Delaney K. Sullivan, Mario R. Blanco & Mitchell Guttman
(Division of Biology and Biological Engineering, California Institute of Technology; David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles)
詳しい解説
本研究は、細胞核内の立体的なゲノム構造が遺伝子発現の調節、特にmRNAスプライシングの効率に重要な役割を果たすことを明らかにした画期的な成果です。
細胞核内には核スペックルと呼ばれる構造体が存在し、そこにはスプライシング関連因子が高濃度で局在しています。スプライシングとは、RNA前駆体からイントロンを除去し、エクソンをつなぎ合わせてmRNAを生成する過程です。しかし、核スペックルがスプライシングにどのような機能的役割を果たすのかは不明な点が多く残されていました。
研究チームは、ゲノムワイドな核スペックルとの近接性をSPRITE法で測定し、snRNAとRNA前駆体の結合量やスプライシング効率との関連を解析しました。その結果、核スペックルの近傍に位置する遺伝子ほど、スプライソソームの結合量が増加し、共転写的スプライシングのレベルが高くなることが明らかになりました。
興味深いことに、核スペックル近傍の遺伝子配置は細胞の種類によって異なっており、それに応じてスプライシング効率も変化することが示されました。さらに、MS2-MCPシステムを用いて遺伝子を人為的に核スペックルにリクルートすると、スプライシング効率が上昇することも証明されました。
これらの結果は、ゲノムDNAの立体的な配置が、スプライソソーム濃度の調節を介して、mRNAスプライシングの効率を制御する重要な役割を果たしていることを示しています。遺伝子の核内での位置が、その発現や機能に大きな影響を与えるという新たな視点を提供するものです。
本研究の成果は、スプライシング異常に関連する疾患の理解や治療法開発に役立つと期待されます。また、核内の立体的な遺伝子配置を考慮した、遺伝子発現制御機構の理解につながるでしょう。さらに、合成生物学による遺伝子発現の人為的制御技術の開発や、核内構造体を標的とした新たな創薬アプローチにも発展する可能性があります。
細胞核内の3次元的な構造と機能の関連性は、これまであまり注目されてきませんでした。しかし、本研究は、ゲノムの立体構造がmRNAプロセシングという重要な過程に直接関与することを高解像度で示した点で画期的であり、今後のさらなる研究の進展が大いに期待されます。核内の構造的な秩序が生み出す機能の多様性と精緻さを解き明かすことで、生命現象の理解が大きく深まるものと思われます。
有機分子のエキシトンと高周波振動を切り離すことで、無輻射遷移を抑制し高い発光効率を達成
本研究では、有機分子の発光効率を制限する高周波振動モードとエキシトンのカップリングを抑制する分子設計指針を提案した。電子供与性と受容性の部位を持つ非平面構造分子で、電荷移動性エキシトンを形成すると、高周波振動と切り離せることを見出した。さらに電子や正孔準位が非結合性軌道の場合も、高周波振動との結合が弱まることを示した。この設計戦略に基づき、680-800nmで高い発光効率を示す近赤外発光材料の開発に成功した。本成果は、有機ELや蛍光イメージング、有機太陽電池の性能向上に役立つと期待される。
事前情報
有機分子の発光効率は高周波振動モードとのカップリングにより制限される
低周波モードは無輻射失活を引き起こしにくいが、高周波モードは失活を加速
有機分子で近赤外発光材料を開発するには、高周波振動との結合抑制が鍵
行ったこと
様々な有機半導体の励起状態の振動スペクトルを過渡吸収分光で測定
第一原理計算により、エキシトンと分子振動のカップリングを解析
電荷移動性と局在性のエキシトンで高周波振動との結合の違いを比較
電子・正孔準位の非結合性軌道の寄与がカップリングに及ぼす影響を検討
設計指針に基づき近赤外発光材料を合成し、量子収率と寿命を評価
検証方法
超高速過渡吸収分光による励起状態のコヒーレント振動の測定
時間依存密度汎関数法によるHuang-Rhys因子の計算
発光量子収率と励起状態寿命の測定
分かったこと
電荷移動性エキシトンでは高周波振動モードとのカップリングが抑制される
電子と正孔が空間的に分離すると振動による励起エネルギーの変調が小さい
電子・正孔準位の非結合性軌道は高周波振動との結合が弱い
上記の指針により、680-800nmで80-90%の発光量子収率を達成
この研究の面白く独創的なところ
有機分子のエキシトンと振動の結合を精密に測定・計算した点
電荷移動性と電子・正孔の空間的分離がカップリング抑制に重要と見出した点
非結合性軌道の寄与によりさらに高周波振動との結合が弱まることを示した点
従来の常識を覆し、有機分子で高効率な近赤外発光を実現した点
この研究のアプリケーション
有機ELにおける近赤外発光材料の発光効率の向上
蛍光イメージングに用いる近赤外蛍光色素の高輝度化
有機薄膜太陽電池の開放電圧の向上と高効率化
三重項-三重項消滅を利用した近赤外増感太陽電池の高性能化
著者と所属
Pratyush Ghosh, Antonios M. Alvertis, Rituparno Chowdhury, Akshay Rao
(Cavendish Laboratory, University of Cambridge; KBR, Inc., NASA Ames Research Center; Materials Sciences Division, Lawrence Berkeley National Laboratory; Yusuf Hamied Department of Chemistry, University of Cambridge)
詳しい解説
本研究は、有機分子の発光効率を制限する重要な要因である、高周波振動モードとエキシトンのカップリングを抑制する分子設計指針を提案した画期的な成果です。
有機分子の発光では、励起状態から基底状態へのエネルギー緩和の際、高周波の分子振動を介した無輻射遷移が起こり、量子収率が低下します。特に近赤外領域では、エネルギーギャップが小さいため、振動準位を介した失活が支配的になり、発光材料の開発が困難でした。
研究チームは、様々な有機半導体について、超高速過渡吸収分光法を用いて励起状態の振動スペクトルを測定し、第一原理計算と組み合わせて詳細に解析しました。その結果、電子供与性と受容性の部位を持つ非平面構造の分子で、励起により電荷移動状態が生成する場合、エキシトンが高周波振動から切り離されることを見出しました。電子と正孔が分子内で空間的に分離することで、局所的な高周波振動がエキシトンのエネルギーや分布をあまり変調しないためです。
さらに、電子や正孔準位が非結合性の分子軌道に由来する場合、π共役系の結合次数を変調するような高周波振動とのカップリングがさらに弱まることを示しました。電子供与性のトリフェニルアミンやカルバゾール、電子受容性のTTM(トリス(2,4,6-トリメチルフェニル)メチル)ラジカルのHOMOやSOMOは非結合性軌道に相当し、高周波振動から切り離されやすいことが分かったのです。
これらの設計指針に基づいて、一連のTTMラジカル分子を合成したところ、680-800nmの近赤外域で80-90%もの高い発光量子収率を達成しました。過渡吸収スペクトルでは250cm-1以下の低周波モードとの結合しか見られず、高周波振動を介した無輻射失活が大幅に抑制されていました。その結果、同程度のバンドギャップを持つ典型的な有機分子と比べ、非輻射遷移速度が2桁近く低減したのです。
本研究は、有機エレクトロニクスの分野に大きなブレークスルーをもたらす成果だと言えます。従来、有機ELでは電荷移動性の励起状態は発光に不向きと考えられてきました。発光の振動子強度が小さく、輻射遷移確率が低いためです。しかし本研究により、電荷移動性エキシトンは無輻射遷移を大幅に抑制できるため、近赤外域でも十分に高い発光効率が得られることが実証されました。ドナー・アクセプター構造による電荷移動性と非結合性軌道の利用が、有機近赤外発光材料の新たな設計指針になると期待されます。
また本研究の知見は、有機ELだけでなく、蛍光イメージングや有機薄膜太陽電池の高性能化にも応用できると考えられます。近赤外蛍光色素の輝度向上により、生体深部のイメージングが高感度化されるでしょう。有機薄膜太陽電池では、電荷移動性エキシトンからの発光再結合を促進することで開放電圧の向上が期待でき、変換効率の大幅な改善が期待できます。金属ハライドペロブスカイトやGaAs並みの高い発光再結合を有機材料で実現できれば、20%を大きく上回る変換効率も夢ではありません。
本研究は、有機分子の電子状態と振動状態の相互作用を精密に測定・計算し、それが光電変換機能に及ぼす影響を解明した点で、基礎科学的にも大変意義深いものです。励起状態ダイナミクスの理解に基づいて、有機エレクトロニクス材料の革新的な設計指針を導いた点は高く評価されます。有機デバイスの新しい可能性を切り拓く重要な一歩になったと言えるでしょう。
ジョセフソン振動を用いて、超固体の超流動成分を初めて直接測定することに成功
本研究は、超固体における超流動成分をジョセフソン振動から直接測定することに初めて成功した画期的な成果である。超固体は、結晶と超流動の性質を併せ持つ特殊な物質で、その空間的に周期的な密度変調が超流動性にどのような影響を与えるのかは長年の謎であった。
研究チームは、磁性原子のボース・アインシュタイン凝縮体を用いて、双極子相互作用により自発的に形成される1次元超固体を実験的に生成した。そして、超固体中の隣り合う密度ピーク間でジョセフソン振動が起こることを見出した。このジョセフソン振動の周波数から、超流動成分の大きさを直接算出することに成功したのである。
実験の結果、超流動成分は密度変調の深さとともに単調に減少することが明らかになった。これは、A. J. レゲットが1970年に理論的に予言した振る舞いと合致する。本研究により、超固体の超流動成分が1未満になることが実験的に初めて実証されたといえる。
また、この結果は、超固体中の密度のピークとその間の谷で異なる速度で運動するという、通常の超流動や結晶にはない複雑なダイナミクスが生じることを示唆している。超固体の超流動成分の大きさは、渦や超流動電流など、超流動・超伝導の基本現象に直結するため、その解明は多様な超固体的物質の理解に欠かせない。
本研究で開発されたジョセフソン振動を用いた超流動成分の測定手法は、他の超固体候補物質にも応用可能である。これにより、様々な物質における超固体性の理解が飛躍的に進むことが期待される。超固体の不思議な性質の解明は、基礎物理学のみならず、量子技術などの応用にもつながる重要な一歩となるだろう。
事前情報
超固体は、結晶と超流動の性質を併せ持つ特殊な物質である。
超固体の空間的な密度変調が超流動性にどう影響するかは長年の謎であった。
レゲットは1970年に、超固体の超流動成分が1未満になると理論的に予言した。
行ったこと
磁性原子のボース・アインシュタイン凝縮体を用いて1次元超固体を実験的に生成した。
超固体中の隣り合う密度ピーク間でジョセフソン振動が起こることを見出した。
ジョセフソン振動の周波数から超流動成分の大きさを直接算出した。
検証方法
超固体の生成と制御には磁性原子の双極子相互作用を利用した。
密度ピーク間の位相差と粒子数差の時間発展からジョセフソン振動を検出した。
ジョセフソン振動数から超流動成分を算出し、密度変調の深さ依存性を調べた。
分かったこと
超固体中の隣り合う密度ピークの間でジョセフソン振動が起こる。
ジョセフソン振動数から超固体の超流動成分を直接測定できる。
超流動成分は密度変調の深さとともに単調に減少し、レゲットの予言と一致する。
超固体中では密度ピークと谷で異なる速度の運動が生じる複雑なダイナミクスがある。
この研究の面白く独創的なところ
超固体の超流動成分を初めて実験的に測定することに成功した点。
超固体中のジョセフソン振動の存在を発見し、それを超流動成分の測定に利用した点。
レゲットの50年前の理論予言を見事に実証した点。
超固体特有の複雑なダイナミクスの存在を示唆した点。
この研究のアプリケーション
本手法は他の超固体候補物質の超流動成分測定にも応用可能。
超固体の超流動成分は渦や超流動電流など超流動・超伝導の基本現象の理解に重要。
超固体の不思議な性質の理解は新たな量子技術などにもつながる可能性がある。
超固体の自己誘起ジョセフソン接合の性質解明は新物性や応用にもつながるかもしれない。
著者と所属
G. Biagioni, N. Antolini, B. Donelli, L. Pezzè, A. Smerzi, M. Fattori, A. Fioretti, C. Gabbanini, M. Inguscio, L. Tanzi & G. Modugno
(Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli studi di Firenze, Sesto Fiorentino, Italy; CNR-INO, Sede di Pisa, Pisa, Italy; European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy, Università degli studi di Firenze, Sesto Fiorentino, Italy; ほか)
詳しい解説
本研究は、超固体という結晶と超流動が共存する特殊な物質の性質を解明する上で、画期的な成果といえる。超固体は、原子や分子が規則正しく配列した結晶構造を持ちながら、同時に摩擦なしで流れる超流動の性質も示す。この一見相反する2つの性質が同居する謎の物質である。
特に本研究で着目したのは、超固体の持つ空間的な密度変調が超流動にどのような影響を及ぼすのかという点だ。通常の超流動体や超伝導体では、粒子の密度は一様だが、超固体では密度が周期的に濃淡を繰り返す。1970年、物理学者のA. J. レゲットは理論的考察から、この密度変調によって超固体の持つ超流動成分(全粒子に占める超流動を担う粒子の割合)が1未満に減少すると予言した。しかし、それを実験的に確かめることは容易ではなかった。
研究チームは、磁性原子のボース・アインシュタイン凝縮体を用いることで、この難題に挑んだ。磁性原子は双極子相互作用により自発的に密度変調を形成し、1次元超固体となる。研究チームは、この超固体の隣り合う密度のピーク間で、交互に粒子のトンネルを繰り返すジョセフソン振動が起きることを見出した。そして、このジョセフソン振動の周波数が、超固体の超流動成分の大きさと直接関係することを明らかにしたのだ。
実際に測定された超流動成分は、密度変調が大きくなるほど単調に減少し、レゲットの理論予言をみごとに裏付ける結果となった。超固体の超流動成分が1未満になることを実験で初めて示したのは、本研究の大きな功績だろう。さらに興味深いのは、この結果が示唆する超固体特有の複雑な動的振る舞いだ。超流動成分が1未満であることは、超流動体とは異なり、超固体中では密度のピークとその間の谷で粒子の運動速度が異なることを意味する。これは、通常の超流動体や結晶には見られないユニークな性質と言える。
また、超流動成分の大きさは、量子渦や超流動電流など、超流動・超伝導の根幹を成す現象の性質を左右する。したがって、本研究で開発されたジョセフソン振動による測定手法は、超固体に限らず、超流動や超伝導を示す物質一般の理解を大きく進める可能性を秘めている。実際、同様の空間変調構造は、ヘリウム薄膜や特殊な超伝導体など、様々な物質で研究されている。本手法はそれらにも応用できるはずだ。
さらに本研究では、超固体中に自発的に形成されるジョセフソン接合の性質も明らかになった。通常のジョセフソン接合とは異なり、その結合の強さが密度変調とともに自在に変化するのだ。これは、超固体ならではの現象で、新奇な物性や機能の開拓にもつながるかもしれない。
超固体は、物質の示す異なる性質が一つに融合した究極の量子物質とも言える。本研究は、その超固体の神秘に迫る重要な一歩となった。複雑な超固体の物性解明は、基礎物理学の発展のみならず、将来の量子技術などの応用にもつながる可能性を秘めている。今後のさらなる進展が大いに期待される。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
