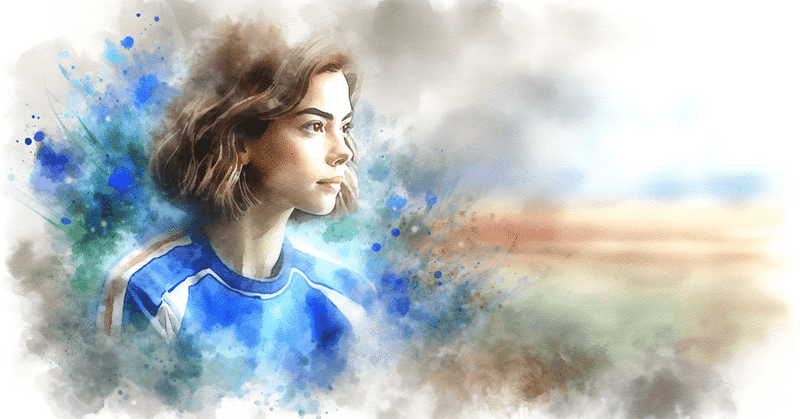
論文まとめ331回目 SCIENCE 深層学習を活用し、低コスト・低電力の0.05テスラMRIで全身を高画質に撮像することに成功!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなSCIENCEです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
Atomically dispersed hexavalent iridium oxide from MnO2 reduction for oxygen evolution catalysis
MnO2還元で調製した原子分散6価イリジウム酸化物の酸素発生触媒特性
「プロトン交換膜水電解の酸素発生触媒には高価なイリジウム酸化物が用いられるが、活性と耐久性のさらなる向上が求められている。本研究では、原子分散した6価のイリジウム酸化物をMnO2で酸化することで合成。従来の触媒の105倍の質量活性と108回転以上の寿命を達成し、高電流密度でも安定に動作することを確認した。6価イリジウムの特異な配位構造が高性能の鍵であり、資源制約のあるイリジウムの大幅な低減につながることが期待される。」
Whole-body magnetic resonance imaging at 0.05 Tesla
0.05テスラでの全身磁気共鳴画像法
「MRIは高価で大型なため普及が限られている。本研究では、0.05テスラという超低磁場の小型MRI装置を開発。電磁干渉を深層学習で除去し、大規模な高磁場MRIデータを活用した超解像技術により画質を大幅に向上。低コストかつ低電力で、体の様々な部位を鮮明に撮像可能に。より手軽で幅広い医療現場へのMRI導入が期待される。」
Isotopic evidence of long-lived volcanism on Io
イオにおける長期間の火山活動の同位体的証拠
「イオは木星の衛星で、活発な火山活動で知られています。この研究では、電波望遠鏡ALMAを使ってイオの大気を観測し、硫黄と塩素の同位体比を調べました。その結果、重い同位体が濃縮していることがわかりました。シミュレーションによると、イオは太陽系の年齢と同じくらいの間、現在と同程度の火山活動を続けてきたことになります。表面を溶岩が何度も覆い尽くしてしまうイオですが、大気の同位体比を調べることで、長い歴史の一端が明らかになりました。」
Scalable decarboxylative trifluoromethylation by ion-shielding heterogeneous photoelectrocatalysis
イオンシールドを活用した不均一光電極触媒による脱炭酸的トリフルオロメチル化反応のスケールアップ
「トリフルオロメチル基は医薬品などに重要だが、その導入は高価な試薬を要する。本研究では、安価なトリフルオロ酢酸から電気化学的にトリフルオロメチル基を発生させ、半導体光触媒を用いて芳香族化合物に効率的に付加することに成功。電極に吸着した酢酸イオンが基質の酸化を防ぐ「イオンシールド」効果で、選択的かつスケーラブルな反応が可能に。新たなトリフルオロメチル化法の開発に道を拓く成果だ。」
Spike timing–based coding in neuromimetic tactile system enables dynamic object classification
スパイクタイミングに基づくコーディングを用いた神経模倣触覚システムにより、動的な物体分類が可能に
「人の指先の触覚は、物体に触れた瞬間のわずか数ミリ秒の情報から物体の特徴を素早く読み取ることができます。本研究では、この仕組みを模倣した人工触覚システムを開発。触れた瞬間の信号のタイミングを活用することで、従来のシステムよりも高速かつ精密に物体を識別できました。生物の神経系に匹敵するミリ秒単位の時間分解能を実現し、触覚情報を動的に処理できる画期的なシステムです。ニューロロボティクスや義手への応用が期待されます。」
要約
MnO2還元で調製した原子分散6価イリジウム酸化物が示す高活性かつ高耐久な酸素発生触媒特性
https://doi.org/10.1126/science.adg5193
本研究では、プロトン交換膜水電解の酸素発生触媒として、原子分散した6価のイリジウム酸化物(IrVI-ado)をMnO2で酸化することで合成した。IrVI-adoは従来の酸化イリジウム触媒に比べて105倍の質量活性と108回転以上の寿命を示し、高電流密度条件下でも安定に動作することがわかった。IrVI-adoの高い活性と耐久性は、6価イリジウムの特異な配位構造に起因すると考えられる。本成果は、希少なイリジウムを大幅に低減した高性能な酸素発生触媒の開発につながることが期待される。
事前情報
プロトン交換膜水電解は水素製造の有望な手法だが、高価な酸化イリジウム触媒の使用量低減が課題
イリジウム酸化物の活性と耐久性のさらなる向上が求められている
高酸化数のイリジウム種は高活性な触媒になり得ると理論的に予測されている
行ったこと
K2IrCl6の配位子をMnO2で酸化的に置換し、原子分散6価イリジウム酸化物(IrVI-ado)を合成
IrVI-adoの構造を各種分光法で解析
IrVI-adoの酸素発生触媒特性をプロトン交換膜水電解セルで評価
検証方法
X線吸収分光法、X線光電子分光法による原子分散構造の解析
プロトン交換膜水電解セルによる電気化学的酸素発生活性・耐久性の評価
In-situ X線吸収分光法による高電流密度動作時の構造安定性の検証
分かったこと
IrVI-adoは6配位の孤立イリジウムサイトが酸化マンガンに分散した構造を有する
IrVI-adoは従来の酸化イリジウム触媒の105倍の質量活性と108回転以上の寿命を示す
6価イリジウムは高電流密度条件下でも安定に存在し続ける
イリジウム-酸素結合の共有結合性が高いことが高活性と高耐久性に寄与すると考えられる
研究の面白く独創的なところ
6価イリジウムの合成に酸化マンガンを利用した点
原子分散触媒で6価イリジウムの特異な配位構造を実現した点
理論予測されていた高酸化数イリジウムの高活性を実験的に証明した点
資源制約のあるイリジウムを大幅に低減できる可能性を示した点
この研究のアプリケーション
高性能かつ低コストな水電解用酸素発生触媒の開発
イリジウム使用量を大幅に削減した水電解システムの実現
再生可能エネルギー由来の高純度水素製造プロセスへの適用
他の遷移金属への展開による新規高活性触媒の開発
著者と所属
Ailong Li, Shuang Kong, Ryuhei Nakamura
(RIKEN Center for Sustainable Resource Science (CSRS); Tokyo Institute of Technology, Earth-Life Science Institute (ELSI))
詳しい解説
本研究は、プロトン交換膜水電解の酸素発生触媒として高性能かつ低コストなイリジウム触媒の開発に挑んだ意欲的な成果である。プロトン交換膜水電解は水素社会の実現に向けた有望な水素製造技術だが、アノード側で使用される高価な酸化イリジウム触媒の使用量低減が大きな課題となっている。また、触媒の活性と耐久性のさらなる向上も求められている。
理論計算からは、高酸化数のイリジウム種、特に6価のイリジウムが高活性な酸素発生触媒になり得ることが示唆されていたが、これまでその実験的な実証は困難であった。本研究では、4価のイリジウム錯体K2IrCl6を出発物質とし、その配位子をマンガン酸化物MnO2で酸化的に置換することで、6価イリジウム酸化物(IrVI-ado)の合成に成功した。XAFS、HERFD-XANES、XPSなどの各種分光法による構造解析から、IrVI-adoは6配位の孤立イリジウムサイトが酸化マンガンマトリクスに原子分散した構造を有することが明らかになった。
プロトン交換膜水電解セルを用いた電気化学測定の結果、IrVI-adoは従来の酸化イリジウム触媒と比較して飛躍的に高い酸素発生活性を示すことが分かった。質量活性は105倍、ターンオーバー数は108回転以上に達し、貴金属使用量を大幅に低減できる可能性が示された。また、2.3 A cm-2の高電流密度条件下でも安定に動作し、優れた耐久性を有することも確認された。その高い活性と耐久性は、6価イリジウムの特異な配位構造に起因すると考えられる。XAFSの解析から、IrVI-adoではイリジウム-酸素結合の共有結合性が非常に高いことが示唆された。その結果、酸素発生反応の律速段階である酸素-酸素結合生成が促進され、同時に過酷な電解環境下でのイリジウム溶出が抑制されたと推測される。
本研究の最大の特徴は、酸化マンガンを利用して原子分散6価イリジウム触媒を合成した点にある。バルクの6価イリジウム酸化物は熱力学的に不安定で合成が困難だが、原子分散化によって初めてその合成と安定化に成功した。さらに孤立サイト構造により、6価イリジウムの特異な配位環境を実現している。この合成手法は他の遷移金属にも適用可能であり、新たな高活性触媒の開発につながることが期待される。
また、本研究は理論予測されていた高酸化数イリジウムの高活性を実験的に証明した点でも意義深い。計算化学と実験化学の協奏により、触媒設計の新たな指針を提示したと言える。実用的な観点からは、IrVI-adoが示した高い質量活性と耐久性は、著しいイリジウム使用量の低減を可能にし、低コスト水素製造の実現に寄与すると期待される。
本触媒をプロトン交換膜水電解システムに適用することで、再生可能エネルギー由来の安価かつ高純度な水素製造が加速されるだろう。水素社会の実現に向けて、イリジウムなどの希少金属の使用量を如何に減らせるかは共通の課題である。原子分散という触媒設計指針は、そのブレイクスルーになり得る。本研究はまだ基礎的段階だが、更なる発展により水電解触媒の革新につながることを大いに期待したい。
深層学習を活用し、低コスト・低電力の0.05テスラMRIで全身を高画質に撮像することに成功
https://doi.org/10.1126/science.adm7168
MRIは医療に革命をもたらしたが、高コストと特殊な設置環境のため普及が限られている。本研究では、0.05テスラという超低磁場の小型MRI装置を開発した。電磁干渉を能動的に検知・除去する深層学習技術と、高磁場MRIの大規模データを活用した超解像技術を導入。これにより、低コスト・低電力で体の様々な部位を鮮明に撮像することに成功した。本手法は幅広い医療現場へのMRI導入への道を拓くものと期待される。
事前情報
MRIは非侵襲で多彩なコントラストが得られる優れた医用画像技術だが、高価で特殊な設置環境を要するため普及が限られている
これまでの開発は高磁場化が主流で、低磁場MRIの発展は1.5テスラ超伝導装置の登場後に停滞していた
近年、低磁場MRIの低コスト性が再注目され、頭部を中心に開発が進んでいる
行ったこと
0.05テスラ永久磁石を用いた小型・省電力のMRI装置を開発
能動的な電磁干渉検知と深層学習を用いた干渉除去技術を導入し、電波・磁気シールド不要を実現
高磁場MRIの大規模データを活用した3次元深層学習超解像技術を開発
健常者ボランティアを対象に、脳、脊椎、腹部、肺、筋骨格、心臓など体の様々な部位を撮像
検証方法
開発した0.05テスラMRI装置による健常者ボランティアの全身撮像実験
従来の画像再構成法と深層学習超解像法による画質の比較
大規模な高磁場MRIデータセットを用いた深層学習モデルの学習と評価
分かったこと
0.05テスラの超低磁場でも、体の様々な部位を8分以内に約2×2×8mm³の分解能で撮像可能
能動的電磁干渉検知と深層学習除去により、シールドなしでも明瞭な画像が得られる
高磁場MRIデータを活用した深層学習超解像により、ノイズやアーチファクトが大幅に低減され空間分解能が向上
脳、脊椎、腹部、肺、膝関節など、様々な解剖学的構造を鮮明に可視化できる
この研究の面白く独創的なところ
超低磁場でありながら電波・磁気シールド不要という、シンプルかつ低コストなMRI装置を実現した点
大規模な高磁場MRIデータを活用する深層学習により、0.05テスラの画質を飛躍的に高めた点
従来の高磁場MRIでは難しかった全身レベルでの撮像を、低コストかつ短時間で可能にした点
この研究のアプリケーション
多様な医療現場への低コストなMRI導入による、診断イメージングのアクセシビリティ向上
深層学習を活用した画質改善により、低磁場MRIの新たな応用可能性が拡がる
患者に優しく移動可能な装置による、ベッドサイドや在宅でのMRI撮像の実現
著者と所属
Yujiao Zhao, Ye Ding, Vick Lau, Christopher Man, Shi Su, Linfang Xiao, Alex T. L. Leong, Ed X. Wu*
(Laboratory of Biomedical Imaging and Signal Processing, Department of Electrical and Electronic Engineering, The University of Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong SAR, China)
詳しい解説
MRIは医療に革命をもたらした画像診断技術ですが、高価な装置と特殊な設置環境を必要とするため、世界的にみるとその普及は限られています。特に中低所得国では、人口当たりのMRI台数が著しく少ない現状があります。MRI開発は長らく高磁場化が主流でしたが、コストや設置の障壁を下げるには、むしろ低磁場化が鍵を握ると考えられるようになってきました。
本研究は、この低磁場MRIの可能性に挑んだ画期的な成果です。0.05テスラという超低磁場でありながら、体の様々な部位を高画質に撮像できる小型のMRI装置を開発しました。永久磁石を使うことで電力消費を最小限に抑え、電磁干渉を深層学習で除去する新手法により、電波シールドや磁気シールド室が不要になったのです。さらに、大規模な高磁場MRIデータを活用した3次元深層学習超解像により、低磁場ゆえのノイズやボケを大幅に低減し、空間分解能と組織コントラストを飛躍的に高めることに成功しました。
健常者ボランティアを対象とした撮像実験では、脳、脊椎、腹部、肺、膝関節など全身の様々な部位の画像を、8分以内で約2×2×8mm³の分解能で取得できました。提案手法による超解像画像は、従来の高磁場MRI画像に肉薄する品質です。本研究が目指すのは、MRI装置のシンプル化・低コスト化・小型化により、これまで手の届かなかった多様な医療現場に高品質のMRIを導入することです。
重要なのは、この超解像の成功は深層学習という新たな技術の賜物だという点です。つまり、低磁場MRIのハードウェアに磨きをかけつつ、蓄積された高磁場の画像データという「資産」をフル活用して画質改善を図る発想が功を奏したのです。この戦略は、CTやPETなど他のモダリティの低コスト化・高性能化にも応用できるかもしれません。
本研究のインパクトは計り知れません。小型で移動可能な装置による病室やホームでのMRI撮像が現実味を帯びてきます。世界の隅々までMRIを届けることで、医療格差の是正に貢献できるでしょう。また、超解像技術は従来の高磁場MRIの高度化にも役立ちます。シンプルな装置で昨日まで不可能だったことを可能にする。それが、深層学習時代の新しいMRIの姿なのです。この革新的な一歩が、世界中の診断イメージングを変えていくに違いありません。
木星の衛星イオの長期にわたる火山活動を、イオ大気中の同位体比から明らかにした。
https://doi.org/10.1126/science.adj0625
木星の衛星イオは、潮汐加熱によって活発な火山活動を示している。しかし、表面が火山流によって覆われているため、その活動がどれほど昔から続いているのかは不明だった。本研究では、ALMAを用いてイオの大気中の硫黄と塩素の同位体比を観測した。その結果、軽い同位体が優先的に失われることで、両元素とも重い同位体に富むことがわかった。モデル計算の結果、イオは利用可能な硫黄の94~99%を失っており、太陽系の年齢と同程度の期間、現在と同レベルの火山活動が続いてきたことが示唆された。この成果は、イオの長期の進化における火山活動の重要性を明らかにするものである。
事前情報
イオは木星の衛星で、太陽系で最も活発な火山活動を示す天体である。
イオの火山活動は、木星の潮汐力による内部の加熱に起因する。
イオの表面は火山噴出物に覆われているため、活動の歴史を知るのは難しい。
行ったこと
ALMAを用いて、イオの大気中の二酸化硫黄、一酸化硫黄、塩化ナトリウム、塩化カリウムの回転遷移を観測した。
観測データから、硫黄と塩素の同位体比(34S/32S、37Cl/35Cl)を導出した。
質量分別を考慮したモデル計算を行い、イオの火山活動の歴史を推定した。
検証方法
ALMAによる電波分光観測
回転スペクトル線の同定と解析による同位体比の導出
レイリー分別モデルを用いた質量損失率と活動期間の見積もり
分かったこと
イオ大気中の硫黄と塩素は、太陽系の平均値に比べて重い同位体に富む。
34S/32S = 0.0595 ± 0.0038(δ34S = +347 ± 86‰)
37Cl/35Cl = 0.403 ± 0.028(δ37Cl = +263 ± 88‰)
イオは利用可能な硫黄の94~99%を失っている。
イオは太陽系の年齢と同程度の期間、現在と同レベルの火山活動を続けてきた可能性がある。
この研究の面白く独創的なところ
イオの大気組成から、火山活動の長期史を探る新しいアプローチを提示した点
電波分光という手法を用いて、イオの同位体比を高精度で測定した点
質量分別モデルを適用することで、活動の継続期間を定量的に推定した点
これまで謎に包まれていたイオの進化における火山活動の重要性を明らかにした点
この研究のアプリケーション
イオの進化や内部構造を理解する上での重要な制約となる
潮汐加熱を受ける他の衛星の火山活動を探る上でのモデルケースとなる
質量分別を利用した大気進化の研究手法として、他の天体にも応用可能
将来のイオ探査における観測ターゲットの選定などに活用できる
著者と所属
Katherine de Kleer, Ery C. Hughes, Francis Nimmo, John Eiler 他
(カリフォルニア工科大学地質惑星科学部、カリフォルニア大学サンタクルーズ校地球惑星科学部、ニューヨーク大学リベラルスタディーズ学部、コロンビア大学天体物理学研究所、アメリカ自然史博物館天文学部、NASAゴダード宇宙飛行センター)
詳しい解説
本研究は、木星の衛星イオの長期にわたる火山活動の歴史を、大気中の同位体比から探った画期的な成果です。イオは太陽系で最も活発な火山活動を示す天体として知られていますが、その表面は絶えず新しい火山噴出物に覆い尽くされるため、活動がいつから続いているのかを知るのは困難でした。
研究チームは、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA)を用いて、イオの希薄な大気中の二酸化硫黄(SO2)、一酸化硫黄(SO)、塩化ナトリウム(NaCl)、塩化カリウム(KCl)の回転スペクトル線を高感度で観測しました。そして、スペクトル線の形状から、硫黄と塩素の同位体比(34S/32S、37Cl/35Cl)を高い精度で導出することに成功しました。
驚くべきことに、硫黄と塩素はどちらも、太陽系の平均的な値に比べて重い同位体に大きく富んでいることが明らかになりました。34S/32Sは+347 ± 86‰、37Cl/35Clは+263 ± 88‰と、極端に高い値を示したのです。これは、イオの大気から軽い同位体が優先的に宇宙空間に失われてきたことを示唆しています。
研究チームは、この同位体の分別が火山ガスの放出と大気の散逸によって起こると考え、レイリー分別モデルを用いて定量的な解析を行いました。その結果、イオは利用可能な硫黄の実に94~99%を失っていると見積もられました。現在と同程度の火山活動が続くとすれば、それは太陽系の年齢に匹敵する期間、つまり数十億年にわたることになります。
この研究は、イオという一つの衛星の大気組成から、太古からの火山活動の歴史を読み解くという、独創的なアプローチを取っている点で特筆に値します。表面地形からはわからないイオの長期進化の姿を、大気の情報から浮き彫りにしたのです。また、同位体の分別を手がかりにして、活動の継続期間を定量的に推定したことも画期的だと言えるでしょう。
本研究の成果は、イオの内部構造や進化を理解する上で重要な制約となります。また、潮汐加熱を受ける他の衛星の火山活動を探る上でのモデルケースとしても役立つはずです。さらに、質量分別を利用した大気進化の研究手法は、他の惑星・衛星にも応用可能性を秘めています。
今後、この研究で明らかになった知見を手がかりに、イオ探査計画における観測ターゲットの選定などが進められていくことでしょう。また、イオと同様の環境にある他の天体でも、同位体組成の研究が活発化するかもしれません。太陽系の衛星の中で特異な存在と思われてきたイオですが、その進化の歴史は、私たちに惑星科学の新たな扉を開く鍵を与えてくれそうです。
トリフルオロ酢酸を利用した新たな芳香族化合物のトリフルオロメチル化反応
https://doi.org/10.1126/science.adm8902
本研究は、安価なトリフルオロ酢酸を用いた芳香族化合物のトリフルオロメチル化反応の新手法を開発した。モリブデンドープ酸化タングステン半導体光電極上に吸着したトリフルオロ酢酸イオンが「イオンシールド」として働き、基質の酸化を防ぐことで選択的かつスケーラブルな反応を実現。380時間以上の電極安定性と、100グラムスケールの合成を光電気化学フロー反応器で達成した。本手法は、医薬品などに有用なトリフルオロメチル基の導入を、環境調和性に優れた電気化学的手法で行う道を拓く重要な成果である。
事前情報
トリフルオロメチル基は医薬品や農薬などに重要な官能基だが、その導入には高価な試薬が必要
芳香族化合物のC-Hトリフルオロメチル化は基質の酸化電位が低いため、選択的な反応が困難
トリフルオロ酢酸は安価だが、脱炭酸的トリフルオロメチル化には高い酸化電位を要する
行ったこと
モリブデンドープ酸化タングステン半導体光電極を用いた不均一光電気化学反応の開発
トリフルオロ酢酸イオンの電極吸着による「イオンシールド」効果の発見と機構解明
基質適用範囲の検討と、グラムスケール合成への展開
検証方法
サイクリックボルタンメトリーによる酸化還元電位の測定
水晶振動子マイクロバランス(EQCM)による電極表面吸着種の解析
13Cラベル実験や速度論解析による反応機構の考察
光電気化学フロー反応器を用いた長時間安定性試験と大スケール合成
分かったこと
半導体電極に吸着したトリフルオロ酢酸イオンが「イオンシールド」となり、基質の酸化を防ぐ
イオンシールドにより、熱力学的電子移動の順序が逆転し、選択的トリフルオロメチル化が進行
電極のモリブデンドープにより価電子帯の位置が最適化され、高い反応性と安定性を実現
広範な芳香族・複素環式化合物に適用可能で、100グラムスケールの合成にも成功
この研究の面白く独創的なところ
電極に吸着した反応剤が「イオンシールド」となる新概念を提唱した点
イオンシールドにより、基質の酸化を防ぎ選択的なトリフルオロメチル化を実現した点
安価なトリフルオロ酢酸を用いて、環境調和型の電気化学的手法を開発した点
半導体材料の価電子帯制御により、高活性かつ安定な光電極触媒を設計した点
この研究のアプリケーション
医薬品、農薬、機能材料などへのトリフルオロメチル基導入法への応用
イオンシールドの概念を活用した新たな選択的電気化学反応の開発
半導体光電極触媒を用いた他の化学変換への展開
環境調和型で大スケール合成も可能な電気化学プロセスへの発展
著者と所属
Yixin Chen, Yuchen He, Yong Gao, Jiakun Xue, Wei Qu, Jun Xuan & Yiming Mo
(College of Chemical and Biological Engineering, Zhejiang University, China; Engineering Research Center of Functional Materials Intelligent Manufacturing of Zhejiang Province, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, Zhejiang University, China; Department of Chemistry, Zhejiang University, China)
詳しい解説
本研究は、トリフルオロメチル基の導入に安価なトリフルオロ酢酸を用いる新しい電気化学的手法を開発した画期的な成果です。トリフルオロメチル基は医薬品や農薬、機能材料などに幅広く用いられる重要な官能基ですが、その導入には従来、高価で取り扱いに注意を要する試薬が必要でした。一方、トリフルオロ酢酸は安価で入手容易な化合物ですが、脱炭酸的にトリフルオロメチル基を発生させるには非常に高い酸化電位が必要で、芳香族化合物へ選択的に導入することは困難でした。
研究チームは、トリフルオロ酢酸イオンを酸化してトリフルオロメチルラジカルを発生させる新たな不均一光電極触媒反応を開発しました。モリブデンをドープした酸化タングステン半導体の光電極を用い、その表面にトリフルオロ酢酸イオンを静電的に吸着させることで、「イオンシールド」と名付けた保護層を形成させたのです。サイクリックボルタンメトリーや水晶振動子マイクロバランスを用いた解析から、この吸着層が芳香族基質の電極表面への接近を防ぎ、酸化的な電子移動を抑制することが明らかになりました。つまり、本来なら基質が先に酸化されてしまうところを、イオンシールドにより酢酸イオンが優先的に酸化を受けてトリフルオロメチルラジカルを発生し、効率的なカップリングが進行するわけです。
この巧みな反応設計により、熱力学的に不利な電子移動の順序が逆転し、芳香族化合物の位置選択的なトリフルオロメチル化が実現しました。本反応は様々な置換基を持つ芳香族化合物や複素環化合物に適用可能で、反応点は最も電子密度の高い位置に導入されることがわかりました。また、モリブデンを添加して価電子帯の位置を最適化することで、効率的な電荷分離と高い光電流が得られ、長時間の連続反応にも優れた安定性を示しました。
さらに研究チームは、本反応が大スケールでの合成にも適用できることを実証しました。光電気化学フロー反応器を使うことで、100グラムスケールの基質を用いた合成に成功。380時間以上に渡る電極の安定性も確認されました。こうしたスケーラビリティの高さは、従来の均一系触媒では困難だった点で、不均一電極触媒の大きなアドバンテージと言えます。
本研究は、トリフルオロメチル基の導入を安価な試薬と環境調和型の電気化学的手法で行う新たな道筋を示した点で非常に意義深いと言えます。開発した光電極触媒反応は、効率性、選択性、スケーラビリティに優れ、実用的なトリフルオロメチル化法としての応用が大いに期待できます。さらに、イオンシールドの概念は、他の電極触媒反応の設計にも活かせる可能性を秘めています。高い酸化力を必要とする反応剤を吸着層として保護し、より酸化されやすい基質の反応を制御する。そうした新たな反応設計指針は、有機電気化学の発展に大きく貢献すると期待されます。
本研究は、有機合成化学と電気化学、材料科学の知見を見事に融合した成果であり、サステナブルな有機合成を目指す上で重要な一歩を画したものと言えるでしょう。この革新的な電極触媒反応が、医薬品や機能材料の開発にどのようなインパクトを与えていくのか。今後の展開から目が離せません。
スパイクタイミングに基づくコーディングを用いた神経模倣触覚システムにより、動的な物体分類が可能に
https://doi.org/10.1126/science.adf3708
本研究では、人間の指先の触覚情報処理を模倣した神経型触覚システムを開発した。このシステムは、物体に触れた瞬間の信号のタイミング、特に最初のスパイクのタイミングを利用して、触覚と把持に関する動的な情報をコード化する。この戦略により、生物の神経系に匹敵するミリ秒単位の時間分解能で高度に動的な情報をシームレスにコード化し、触覚特徴の動的な抽出を可能にする。物体に触れると、システムは接触と把持の初期段階で物体を迅速に分類し、ニューロロボティクスやニューロプロステティクスに求められる高速な触覚フィードバックへの道を開く。
事前情報
触覚情報の迅速な処理は、人間の触覚探索と巧みな物体操作に不可欠
従来の電子皮膚は物体との相互作用時に触覚信号のフレームを生成するが、時間情報のコーディングや特徴抽出には適さない
行ったこと
人間の指先の触覚情報処理を模倣した神経型触覚システムを開発
スパイクタイミング、特に最初のスパイクのタイミングを使って、触覚と把持に関する動的情報をコード化
ミリ秒単位の時間分解能で高度に動的な情報をシームレスにコード化し、触覚特徴の動的抽出を実現
物体との相互作用時に、接触と把持の初期段階で物体を迅速に分類
検証方法
開発したシステムを用いて、様々な物体との相互作用実験を実施
スパイクタイミングに基づく情報処理による物体分類性能を評価
従来の電子皮膚との性能比較を行い、提案手法の有効性を検証
分かったこと
スパイクタイミングに基づくコーディングにより、ミリ秒単位の高い時間分解能で触覚情報を処理可能
最初のスパイクのタイミングが、物体の特徴を素早く読み取るのに特に重要
従来の電子皮膚と比べ、物体分類の性能が大幅に向上
触覚と把持の初期段階で、迅速かつ精密に物体を識別できることを実証
この研究の面白く独創的なところ
人間の指先の触覚情報処理を忠実に模倣した点
スパイクタイミングという新しい情報コーディング戦略を採用した点
ミリ秒単位の高い時間分解能を実現し、生物の神経系に匹敵する性能を達成した点
触覚情報を動的に処理し、素早く物体の特徴を抽出できる点
この研究のアプリケーション
ニューロロボティクスにおける高速で精密な触覚フィードバックの実現
義手などのニューロプロステティクスにおける自然な触覚の再現
触覚を利用した物体認識や操作の高度化
生物の触覚情報処理メカニズムの理解に役立つ知見の提供
著者と所属
Libo Chen, Sanja Karilanova, Soumi Chaki, Chenyu Wen (Uppsala University, Sweden)
Lisha Wang, Bengt Winblad (Karolinska Institutet, Sweden)
Shi-Li Zhang (Uppsala University, Sweden)
Ayça Özçelikkale, Zhi-Bin Zhang (Uppsala University, Sweden)
詳しい解説
本研究は、人間の指先の触覚情報処理を忠実に模倣した神経型触覚システムを開発し、触覚情報のコーディングと処理に新たな道を開いた画期的な成果です。
人間の触覚は、物体に触れた瞬間のわずか数ミリ秒の情報から、その特徴を素早く読み取ることができます。この驚異的な能力は、触覚受容器から中枢神経系へのスパイク信号のタイミングに基づく情報コーディングによって実現されていると考えられています。
研究チームは、この生物学的な仕組みに着目し、スパイクタイミングに基づくコーディング戦略を採用した人工触覚システムを開発しました。このシステムは、物体に触れた瞬間の信号、特に最初のスパイクのタイミングを利用して、触覚と把持に関する動的な情報をコード化します。
従来の電子皮膚は、物体との相互作用時に触覚信号のフレームを生成しますが、時間情報のコーディングや特徴抽出には適していませんでした。一方、本研究のシステムは、ミリ秒単位の高い時間分解能で高度に動的な情報をシームレスにコード化し、触覚特徴の動的な抽出を可能にします。
様々な物体との相互作用実験の結果、このシステムは接触と把持の初期段階で物体を迅速かつ精密に分類できることが実証されました。従来の電子皮膚と比べ、物体分類の性能が大幅に向上したのです。
本研究は、生物の神経系に匹敵する時間分解能と情報処理能力を持つ触覚システムを実現した点で非常に独創的です。また、スパイクタイミングという新しい情報コーディング戦略を採用し、触覚情報を動的に処理できる点も画期的だと言えるでしょう。
今後、このシステムはニューロロボティクスや義手などのニューロプロステティクスにおける高速で精密な触覚フィードバックの実現に貢献すると期待されます。また、生物の触覚情報処理メカニズムの理解にも役立つ貴重な知見を提供するでしょう。
触覚は私たちの日常生活に欠かせない感覚ですが、その情報処理メカニズムには未だ謎が多く残されています。本研究は、触覚の神経科学と工学の架け橋となり、両分野の発展を大きく促進する成果だと言えます。今後のさらなる進展に大いに期待が持てる研究だと思います。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
