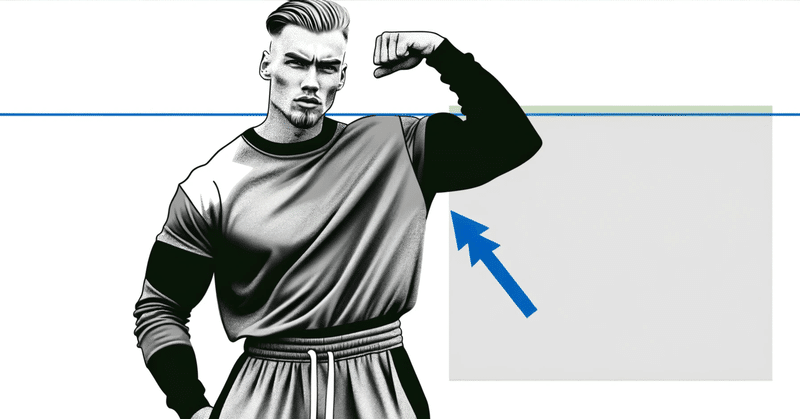
論文まとめ336回目 Nature 育児行動を促進する新規の副腎細胞型の進化!?など
科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなNatureです。
さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。
世界の先端はこんな研究してるのかと認識するだけでも、
ついつい狭くなる視野を広げてくれます。
一口コメント
One-third of Southern Ocean productivity is supported by dust deposition
南大洋の生産性の3分の1はダストの堆積によって支えられている
「南大洋は地球上で最も生物生産性が高い海域の一つですが、鉄が不足しがちです。風に運ばれるダストには鉄が含まれており、それが海の生物を育んでいることは知られていました。今回、11年分の海洋観測データと大気モデルを組み合わせ、南大洋の生物生産量の実に33%がダストによってもたらされた鉄に支えられていることが初めて定量的に示されました。さらに、最終氷期にはダストの供給量が5~40倍も多く、その影響がより大きかったことも明らかになりました。ダストが海の生態系や炭素循環に果たす役割の理解が大きく進展しました。」
Evolution of a novel adrenal cell type that promotes parental care
育児行動を促進する新規の副腎細胞型の進化
「ネズミの仲間には一夫一婦で子育てをするものもいれば、オスが子育てをしないものもいます。研究グループは、一夫一婦のオールドフィールドマウスの副腎に、近縁種のシカマウスにはない新しい細胞型があることを発見。この細胞は20α-OHPというホルモンを産生し、それが脳内で代謝されて育児行動を促進することがわかりました。脳以外の組織で育児行動を制御するホルモンが作られるのは初めての発見で、ホルモンと行動の進化の関係を考える上で重要な成果といえそうです。」
Physiological temperature drives TRPM4 ligand recognition and gating
生理的温度がTRPM4のリガンド認識とゲーティングを制御する
「体温がタンパク質の構造や機能に影響することは知られていたが、その詳細は不明だった。TRPM4は体温で活性化するイオンチャネル。クライオ電子顕微鏡を使って生理的な37℃でTRPM4の構造を調べたところ、低温とは異なる「温かい構造」が見つかった。この構造変化により、Ca2+やATP、薬物の結合部位が変化し、チャネル活性を巧妙に制御していた。タンパク質を生理的温度で研究することの重要性を示した画期的な研究だ。」
Photocatalytic doping of organic semiconductors
有機半導体の光触媒ドーピング
「有機半導体のドーピングは、デバイス性能の向上に不可欠だが、強力なドーパントを必要とするなどの課題があった。本研究では、光触媒を電子のシャトルとして利用することで、空気中の酸素など弱いドーパントでも、有機半導体を簡便かつ効率的にp型およびn型ドーピングできる画期的な手法を開発。また、p型とn型の同時ドーピングにも成功。有機エレクトロニクスの発展に大きく貢献する成果だ。」
Superconducting diode effect and interference patterns in kagome CsV3Sb5
カゴメ格子CsV3Sb5の超伝導ダイオード効果と干渉パターン
「カゴメ格子物質CsV3Sb5では、フラストレーション、トポロジカルな電子状態、電子相関の絡み合いにより、様々な対称性の破れが起こる。本研究では、試料の熱履歴により制御される自発的な超伝導ダイオード効果と、磁場中で現れる超伝導干渉パターンを発見。これらは、超伝導状態で時間反転対称性が自発的に破れ、超伝導ドメイン境界に超伝導電流が流れることに起因すると考えられる。」
The temperature sensor TWA1 is required for thermotolerance in Arabidopsis
シロイヌナズナの熱耐性に必須な温度センサー TWA1
「植物は気温の上昇に適応するため、温度を感知して熱ショック応答を活性化する必要があります。この研究では、シロイヌナズナのTWA1というタンパク質が20〜30℃の温度変化を感知する新しいタイプの温度センサーであることを発見しました。TWA1は温度上昇に応じて立体構造を変化させ、転写抑制複合体を形成して熱ショック応答を制御します。TWA1を欠損させると植物の熱耐性が失われ、TWA1を過剰発現させると熱耐性が向上することから、TWA1は植物の熱適応に必須であることが明らかになりました。TWA1の発見は、地球温暖化に適応した作物の開発にもつながると期待されます。」
要約
風で運ばれるダストが、南大洋の生物生産性の33%を支えていることが初めて定量的に示された。
本研究では、11年分の海洋生物地球化学観測データと南半球のダストシミュレーションを組み合わせることで、風で運ばれるダストに含まれる鉄が南大洋の年間純群集生産量(ANCP)に与える影響を初めて定量的に評価した。その結果、現在の鉄に乏しい南大洋のANCPの33% ± 15%がダストによる鉄によって支えられていることが明らかになった。さらに最終氷期には、ダストの堆積量が現在の5~40倍も多く、南大洋のANCPの64% ± 13%がダストの影響を受けていたと推定された。本研究は、南大洋全域におけるダストによる鉄の供給と、氷期・間氷期サイクルにおけるその影響の大きさを定量的に示した初めての研究であり、ダストが地球の炭素循環や気候に果たす重要な役割を裏付けるものである。
事前情報
南大洋は鉄が不足しがちな海域で、風で運ばれるダストが重要な鉄供給源と考えられてきた。
ダストによる鉄供給が南大洋の生物生産性を高め、気候を調節している可能性が示唆されてきた。
しかし、南大洋全域で、ダストによる鉄供給が生物生産性に与える影響は定量化されていなかった。
行ったこと
11年分の自律型生物地球化学観測フロートによる硝酸塩データと南半球ダストシミュレーションを組み合わせた。
鉄が不足する南大洋において、ダストによる鉄供給量と年間純群集生産量(ANCP)の関係を経験的に導出した。
現在と最終氷期における、ダストによる鉄供給が南大洋のANCPに与える影響を定量的に評価した。
検証方法
自律型生物地球化学観測フロートによる硝酸塩濃度の観測データを使用。
南半球のダストシミュレーションモデルを適用。
ダストによる鉄供給量と硝酸塩の減少量(ANCP)の関係を回帰分析によって導出。
最終氷期のダスト堆積量を見積もり、ANCPへの影響を評価。
分かったこと
現在の南大洋のANCPの33% ± 15%がダストによる鉄によって支えられている。
最終氷期にはダストの堆積量が5~40倍も多く、南大洋のANCPの64% ± 13%がダストの影響を受けていた。
ダストによる鉄供給は、南大洋の生物生産性を大きく左右する重要な要因である。
氷期・間氷期サイクルにおいて、ダストが炭素循環や気候に果たす役割は非常に大きい。
この研究の面白く独創的なところ
自律型観測フロートのビッグデータと大気モデルを組み合わせた革新的なアプローチ。
南大洋全域を対象に、ダストによる鉄供給の影響を初めて定量化した点。
現在だけでなく最終氷期も評価し、ダストの役割の大きさを明らかにした点。
ダストと海洋生態系・炭素循環・気候のつながりを具体的に示した点。
この研究のアプリケーション
地球規模の炭素循環や気候変動のメカニズム解明に貢献。
過去の気候変動の理解に役立つ知見を提供。
南大洋の生態系や物質循環のモデル研究の高度化に寄与。
将来の気候変動予測の精緻化にもつながる可能性。
著者と所属
Jakob Weis, Zanna Chase, Christina Schallenberg, Peter G. Strutton, Andrew R. Bowie & Sonya L. Fiddes
(Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS), University of Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia; Australian Research Council Centre of Excellence for Climate Extremes (CLEX), University of Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia; Australian Research Council Centre for Excellence in Antarctic Science (ACEAS), University of Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia)
詳しい解説
南大洋は、地球上で最も生物生産性の高い海域の一つであり、大気中の二酸化炭素を吸収する重要な役割を果たしています。しかし、南大洋は鉄が不足しがちな海域でもあります。海洋の植物プランクトンは光合成を行うために鉄を必要としますが、南大洋では陸地から離れているために河川からの鉄供給が乏しいのです。
そこで注目されてきたのが、風によって運ばれてくるダスト(鉱物粒子)に含まれる鉄です。ダストは砂漠など陸上から巻き上げられ、大気を通じて遠く離れた海域にまで運ばれます。ダストに含まれる鉄が海に供給されることで、植物プランクトンの生育が促され、南大洋の生物生産性が高められると考えられてきました。
しかし、南大洋の広大な海域全体で、ダストによる鉄供給が生物生産性にどの程度寄与しているのかは定量的に示されていませんでした。また、過去の氷期と間氷期では、ダストの供給量が大きく変動したと考えられていますが、その影響の大きさも不明でした。
本研究は、こうした課題に挑戦した画期的な研究です。南大洋全域で自律的に観測を行う生物地球化学フロートから得られた11年分という膨大な硝酸塩データと、南半球のダストの大気輸送モデルを組み合わせるという独創的なアプローチにより、ダストによる鉄供給と南大洋の生物生産性の関係を初めて定量的に明らかにしました。
硝酸塩は植物プランクトンの生育に必要な栄養塩の一つで、その消費量から生物生産量を見積もることができます。一方、ダストに含まれる鉄の量は、大気モデルから推定することができます。本研究では、ダストによる鉄の供給量と硝酸塩の消費量の関係を50の海域で解析し、ダストが南大洋の年間純群集生産量(ANCP)に与える影響を定量化したのです。
その結果、現在の鉄が不足しがちな南大洋では、ANCPの33% ± 15%がダストによる鉄に支えられていることが明らかになりました。さらに驚くべきことに、ダストの供給量が現在の5~40倍も多かったと推定される最終氷期には、南大洋のANCPの64% ± 13%がダストの影響を受けていたというのです。
本研究は、ダストが南大洋の生態系に果たす役割の大きさを初めて定量的に示しただけでなく、氷期・間氷期サイクルにおけるダストの影響の大きさも明らかにしました。ダストは単に海の生態系を支えるだけでなく、地球規模の炭素循環や気候変動に大きな影響を与える可能性があるのです。
南大洋は地球の気候を調節する上で非常に重要な海域ですが、その生態系は微妙なバランスの上に成り立っています。本研究は、そのバランスを支える要因の一つがダストであることを明確に示しました。
ダストは砂漠化など人間活動の影響も受けるため、将来的にはダストの供給量が変化する可能性もあります。本研究の知見は、そうした変化が南大洋や地球全体に与える影響を予測する上でも重要な手がかりになるでしょう。
地球規模の物質循環と気候のつながりを解き明かす上で、ダストという一見小さな存在が、実は重要な鍵を握っていたのです。本研究は、そうした地球システムの複雑さと精妙さを浮き彫りにした、画期的な成果だと言えます。
一夫一婦のオールドフィールドマウスでは、副腎に20α-OHPを産生する新しい細胞型が進化し、それが育児行動を促進していることが明らかになった。
本研究では、一夫一婦で育児を行うオールドフィールドマウスの副腎に、近縁の雑婚性シカマウスにはない新しい細胞型「ゾナ・イナウディタ」が存在することを発見した。この細胞型は20α-OHPというプロゲスチン代謝物を産生し、それが脳内でアロプレグナンジオール(allo-diol)に変換されて育児行動を促進することを明らかにした。さらに、この細胞型の出現にはGadd45aとTnnという遺伝子の発現上昇が重要であることを遺伝学的に示した。本研究は、脳以外の組織が行動を制御するメカニズムの一例を示すとともに、ホルモンと行動の進化の関係を考える上で重要な知見を提供するものである。
事前情報
哺乳類の育児行動は主に脳の神経回路によって制御されていると考えられてきた。
プロゲステロンなどのステロイドホルモンも育児行動に関与することが示唆されているが、その詳細なメカニズムは不明。
オールドフィールドマウスは一夫一婦で、オスメスともに積極的に育児を行う。一方、近縁のシカマウスは雑婚性でオスは育児をしない。
行ったこと
オールドフィールドマウスとシカマウスの副腎のトランスクリプトーム解析と1細胞RNA-seq解析。
両種の副腎と血中のステロイドホルモン量の測定。
20α-OHPとその代謝物allo-diolを両種に投与し、育児行動への影響を調べた。
両種の交配F2個体を用いたQTLマッピングにより、ゾナ・イナウディタの出現に関わる遺伝子座を同定。
検証方法
RT-qPCRとin situハイブリダイゼーションによる遺伝子発現解析。
LC-MS/MSによるステロイドホルモン量の測定。
育児行動の定量的評価(巣作り、仔の保温、毛づくろいなど)。
F2個体のゲノムワイドSNP解析とQTLマッピング。
分かったこと
オールドフィールドマウスの副腎に、20α-OHPを産生するゾナ・イナウディタという新規の細胞型が存在する。
オールドフィールドマウスの副腎と血中の20α-OHP量は、シカマウスよりも有意に高い。
両種に20α-OHPまたはallo-diolを投与すると、育児行動が促進される。
ゾナ・イナウディタの出現には、転写因子Gadd45aと細胞外マトリックス成分Tnnの発現上昇が重要である。
Gadd45aとTnn遺伝子座のcis-regulatory variantsが、両遺伝子の発現差に関与している。
この研究の面白く独創的なところ
両種のマウスの育児行動の違いに注目し、その分子基盤を詳細に解明した点。
脳だけでなく副腎にも着目し、新規の細胞型と育児行動を結びつけた点。
1細胞RNA-seqにより新規細胞型を同定し、その出現機構まで遺伝学的に解明した点。
進化的に近縁な2種の比較から、行動の種差を生み出す分子メカニズムに迫った点。
この研究のアプリケーション
ホルモンと行動の関係、特に末梢組織から脳への作用を理解する上で重要な知見。
育児行動の制御機構の解明と、その破綻による育児放棄などの問題の理解に貢献。
副腎の細胞型と機能の多様性、ホルモン産生の進化メカニズムの理解に貢献。
行動の種差を生み出す遺伝メカニズムの解明に向けた比較ゲノム研究のモデルケース。
著者と所属
Natalie Niepoth, Jennifer R. Merritt, Michelle Uminski
(Zuckerman Mind Brain Behavior Institute, Columbia University; Department of Ecology, Evolution and Environmental Biology, Columbia University)
詳しい解説
本研究は、一夫一婦のオールドフィールドマウスと近縁の雑婚性シカマウスの育児行動の違いに注目し、その分子基盤を副腎に見出した画期的な成果である。 哺乳類の育児行動は主に脳の神経回路によって制御されていると考えられてきたが、本研究はそれ以外の組織、特に内分泌器官である副腎にも着目した。トランスクリプトーム解析と1細胞RNA-seq解析により、オールドフィールドマウスの副腎には20α-OHPを特異的に産生する細胞群「ゾナ・イナウディタ」が存在することを突き止めた。
20α-OHPはプロゲステロンの代謝物で、脳内でさらにallo-diolに変換される。行動実験から、20α-OHPとallo-diolはどちらも育児行動を促進することが示された。つまり、ゾナ・イナウディタで産生された20α-OHPが脳に作用して育児行動を引き起こしていたのである。
ゾナ・イナウディタはシカマウスの副腎には存在せず、オールドフィールドマウスで進化的に新しく獲得された形質と考えられる。その出現メカニズムを探るため、両種の交配F2個体を用いたQTLマッピングを行ったところ、Gadd45aとTnnという2つの遺伝子座が浮上した。両遺伝子ともゾナ・イナウディタで特異的に発現しており、その発現量はcis-regulatory variantsによって制御されていた。
Gadd45aは転写制御に関わる因子で、Tnnは細胞外マトリックスの成分である。これらの発現上昇がゾナ・イナウディタの分化・成熟を促し、20α-OHP産生能の獲得につながったと考えられる。オールドフィールドマウスでは、Gadd45aとTnn遺伝子座のcis-regulatory variantsによってこれらの遺伝子発現が上昇し、ゾナ・イナウディタが出現したのだろう。
本研究は、脳だけでなく末梢の内分泌器官も個体の行動制御に重要な役割を果たすことを示した点で意義が大きい。また、ゲノム情報と1細胞解像度の発現情報を組み合わせ、種間の行動差を生み出す遺伝メカニズムに迫った点も特筆に値する。ゾナ・イナウディタの発見は、ホルモン産生の多様性と進化可塑性を示す好例でもあり、内分泌学の新しい研究の方向性を示唆するものだ。
今後の研究により、育児行動以外にもゾナ・イナウディタが影響を及ぼす形質が明らかになるかもしれない。また、ヒトを含む他の哺乳類でも、種特異的な副腎細胞型が同定される可能性が期待される。ホルモンと行動の関係について、脳から内分泌器官、さらには全身へと視野を広げた研究が求められる。
生理的な体温がTRPM4チャネルの構造と機能を大きく変化させ、リガンド認識とゲーティングを制御する。
本研究は、温度感受性のあるTRPM4チャネルを生理的な37℃で構造解析し、低温とは異なる「温かい構造」を発見した。この構造変化により、Ca2+、ATP、薬物デカバナジン酸の結合部位が変化し、チャネル活性の調節機構が明らかになった。また、変異体解析や電気生理学的実験から、この温度依存的な構造変化とリガンド認識がTRPM4の生理機能に不可欠であることを突き止めた。本研究は、タンパク質を生理的温度で研究することの重要性を示すとともに、温度感受性のあるTRPチャネルの分子機構の理解に大きく貢献するものである。
事前情報
温度はタンパク質の構造と機能に大きな影響を与えるが、その詳細は不明な点が多い。
TRPM4は温度感受性のあるCa2+活性化陽イオンチャネル。
TRPM4の変異は不整脈などの重篤な心疾患と関連する。
TRPM4の既存の構造は非生理的な低温で解析されたもの。
行ったこと
生理的な37℃でTRPM4をCa2+、ATP、デカバナジン酸存在下でクライオ電子顕微鏡解析。
TRPM4の変異体を作製し、リガンド結合部位の同定と機能解析を実施。
37℃と低温でのTRPM4の構造変化とリガンド認識機構を比較解析。
検証方法
クライオ電子顕微鏡による高分解能の構造解析。
変異導入によるリガンド結合部位の同定。
パッチクランプ法による電気生理学的解析。
分かったこと
37℃ではTRPM4は低温とは異なる「温かい構造」をとる。
「温かい構造」ではCa2+の結合部位が新たに形成され、チャネル活性化に重要。
「温かい構造」ではATPとデカバナジン酸の結合部位が変化し、阻害と活性化を制御。
「温かい構造」への変化はチャネルの開口につながる。
変異体解析から、これらの構造変化とリガンド認識はTRPM4の生理機能に必須。
研究の面白く独創的なところ
TRPM4を生理的な37℃で初めて構造解析した点。
温度による劇的な構造変化とリガンド認識の変化を発見した点。
リガンド結合部位が温度で変化する新奇な制御機構を解明した点。
タンパク質の生理的温度での研究の重要性を示した点。
この研究のアプリケーション
TRPM4の生理機能と病態生理学的役割の理解に貢献。
TRPM4を標的とした心疾患などの新規治療法開発に役立つ。
他の温度感受性タンパク質の分子機構解明に応用できる。
生理的条件下でのタンパク質研究の重要性を示し、創薬などに影響。
著者と所属
Jinhong Hu, Sung Jin Park, Juan Du & Wei Lü
(Van Andel Institute, Grand Rapids, MI, USA)
詳しい解説
本研究は、温度感受性のあるイオンチャネルTRPM4について、生理的な体温に近い37℃で構造と機能を詳細に解析した画期的な成果です。TRPM4は体温付近で活性化する特殊なチャネルで、心臓のリズムなどに関わる重要なタンパク質ですが、その分子メカニズムには謎が多く残されていました。
研究チームは、クライオ電子顕微鏡を用いて、37℃でTRPM4の構造を約3Åという高い分解能で決定することに成功しました。驚くべきことに、TRPM4は37℃では今まで低温で見られていたのとは大きく異なる「温かい構造」をとることが明らかになりました。特に細胞内ドメインの構造が大きく変化し、新たなCa2+結合部位が形成されていました。変異体を用いた解析から、このCa2+結合が温度依存的な構造変化とチャネル活性化に必須であることが証明されました。
さらに、ATP(生体内の代表的な阻害剤)とデカバナジン酸(活性化剤)についても37℃で解析したところ、これらのリガンドの結合部位も「温かい構造」では大きく変化していました。ATPは「温かい構造」の新たな部位に結合することで、チャネルを閉じた不活性状態に固定する一方、デカバナジン酸は「温かい構造」特有の部位に結合し、チャネルを開口させることがわかりました。変異体の電気生理学的解析からも、これらの結合部位が生理的な温度でのTRPM4の機能制御に重要であることが裏付けられました。
本研究は、温度がタンパク質の構造と機能に極めて大きな影響を与えることを如実に示した点で非常に意義深いものです。これまでタンパク質の構造解析は主に低温で行われてきましたが、本研究は生理的温度で解析することの重要性を物語っています。温度に応じてリガンドの結合部位や作用が劇的に変化するという新たな制御機構の発見は、他の温度感受性タンパク質の理解にも大きなインパクトを与えるでしょう。
また、TRPM4の異常は不整脈などの重篤な心疾患と関連することから、本研究で得られた構造機能連関の知見は、TRPM4を標的とした新たな治療法の開発にも役立つと期待されます。
本研究は、温度生物学とタンパク質科学、構造生物学の観点から見てもきわめて挑戦的かつ重要な研究であり、今後のさらなる展開が大いに期待されます。温度の変化は単なるタンパク質の”ゆらぎ”ではなく、その構造と機能を巧妙に制御する自然の妙技なのかもしれません。
光触媒を用いて有機半導体を効率的にp型およびn型ドーピングする新手法を開発
有機半導体の化学ドーピングは、電荷キャリア濃度や輸送特性を制御し、デバイス性能を向上させる重要な手法である。しかし、従来のドーピング法は、反応性の高い強力なドーパントを必要とし、ドーピング過程でドーパントが消費されるなどの課題があった。本研究では、光触媒を用いて、空気中の酸素など弱いドーパントでも有機半導体を効率的にp型ドーピングできる新しい手法を開発した。この手法は、さまざまな有機半導体と光触媒に適用でき、3,000 S/cm以上の高い電気伝導度が得られる。さらに、有機塩を用いることで、n型ドーピングやp型/n型の同時ドーピングにも成功した。本光触媒ドーピング法は、有機半導体のドーピングを大きく進歩させ、次世代有機エレクトロニクスデバイスの開発に大きく貢献すると期待される。
事前情報
有機半導体のドーピングは、デバイス性能の最適化に不可欠
従来のドーピング法は、反応性の高いドーパントを必要とし、ドーパントが消費される
弱いドーパントを用いる効率的なドーピング法の開発が望まれていた
行ったこと
空気中の酸素を弱いp型ドーパントとして利用する光触媒ドーピング法を開発
さまざまな有機半導体と光触媒でp型ドーピングを実証
有機塩を用いてn型ドーピングとp型/n型同時ドーピングを実現
検証方法
吸収スペクトル測定によるドーピングの確認
X線光電子分光によるアニオンの浸透の解析
電気伝導度測定によるドーピング効果の評価
過渡吸収分光法による電荷移動メカニズムの解明
分かったこと
光触媒の励起状態が有機半導体を酸化・還元し、弱いドーパントで再生される
酸素、ジフェニルジスルフィドなどの弱い酸化剤でp型ドーピングが可能
トリエチルアミンなどの弱い還元剤でn型ドーピングが可能
p型とn型の有機半導体を同じ溶液中で同時にドーピングできる
有機塩のみが消費され、光触媒は再利用できる
この研究の面白く独創的なところ
光触媒を電子シャトルとして利用し、弱いドーパントでドーピングを実現した点
p型だけでなくn型、さらにp型/n型同時ドーピングにも成功した点
有機塩のみを消費する、環境に優しく低コストなドーピング法を開発した点
高い電気伝導度と結晶性を両立できる点
この研究のアプリケーション
有機EL、有機太陽電池、有機トランジスタなどの性能向上
有機熱電変換デバイスの高性能化
印刷プロセスによる有機デバイスの製造
p型/n型の階層構造を持つ有機デバイスの開発
著者と所属
Wenlong Jin, Chi-Yuan Yang, Simone Fabiano (Laboratory of Organic Electronics, Department of Science and Technology, Linköping University)
有機半導体のドーピングは、有機ELディスプレイ、有機太陽電池、有機トランジスタ、有機熱電変換素子など、さまざまな有機デバイスの性能を最適化する上で不可欠のプロセスです。しかし従来のドーピング法は、強い電子受容性や供与性を持つ分子をドーパントとして用いる必要があり、ドーピング過程でドーパントが消費されてしまうという課題がありました。弱いドーパントを用いて、効率的にドーピングを行う新しい手法の開発が求められていたのです。
本研究で開発された光触媒ドーピング法は、この課題を見事に解決しました。光触媒を電子の受け渡しを媒介するシャトルとして利用することで、空気中の酸素やアミンなどの弱いドーパントを用いて、有機半導体を効率的にp型およびn型ドーピングすることに成功したのです。p型ドーピングでは、光励起された光触媒が有機半導体から電子を奪い、還元状態となります。還元状態の光触媒は酸素などの弱い酸化剤によって容易に再生されます。一方、n型ドーピングでは、光励起された光触媒がアミンなどの弱い還元剤を酸化し、還元状態となった光触媒が有機半導体に電子を与えます。どちらのドーピングでも、有機塩のアニオンがドープされた有機半導体のカチオンを安定化する役割を果たします。
この光触媒ドーピング法の最大の特長は、その汎用性の高さです。ポリチオフェン、DPP、BTBTなど、さまざまな有機半導体に適用でき、アクリジニウム系色素などの一般的な光触媒が利用できます。驚くべきことに、p型とn型の有機半導体を1つの溶液中に共存させ、同時にドーピングすることもできます。しかも、その過程で消費されるのは安価な有機塩のみで、光触媒は繰り返し使えるのです。弱いドーパントを活用した環境に優しく低コストなドーピング法の実現は、有機エレクトロニクスの実用化に向けた大きな一歩だと言えるでしょう。
また本手法によるドーピングでは、有機半導体の高い結晶性を維持したまま、バルク全体を効果的にドーピングできることも大きな利点です。実際、ドーピングされたポリマーは3,000 S/cmを超える非常に高い電気伝導度を示しました。高い電気伝導度と高い結晶性・配向性を両立できる本手法は、高性能な有機デバイスの開発に大きく貢献するものと期待されます。例えば本論文では、p型とn型のポリマーを同時ドーピングして作製した熱電変換デバイスが、従来の個別ドーピングによるデバイスに匹敵する発電性能を示すことが実証されています。
本研究は、光触媒の新しい応用先を開拓しただけでなく、有機半導体のドーピング技術に革新をもたらす成果だと言えます。この光触媒ドーピング法によって、高性能な有機デバイスの低コスト製造や、複雑な階層構造を持つ高次有機デバイスの開発が大きく前進するでしょう。高分子半導体の実用化に新たな道を拓く画期的な研究として、大いに注目されます。
カゴメ格子CsV3Sb5で時間反転対称性の破れた超伝導を示唆する自発的な超伝導ダイオード効果と超伝導干渉パターンを発見
本研究では、カゴメ格子物質CsV3Sb5の薄膜試料において、磁場のない状態で自発的な超伝導ダイオード効果が観測された。このダイオード効果の極性は熱履歴によって制御され、時間反転対称性の破れた背景の中で、動的な超伝導ドメインが存在することを示唆している。さらに、外部磁場を印加すると、臨界電流に二重スリット超伝導干渉パターンが現れることを発見した。このパターンの特徴は熱サイクルによって変調される。これらの現象は、磁束量子化によって制約されたドメイン境界に沿って、周期的に変調された超伝導電流が流れることの帰結だと提案される。本結果は、このカゴメ系で時間反転対称性の破れた超伝導状態が実現していることを示唆しており、マヨラナゼロモードなどのエキゾチックな物理の探索への可能性を開くものである。
事前情報
カゴメ格子系では、フラストレーション、トポロジカルバンド、相関効果の相互作用により豊かな量子状態が生まれる。
カゴメ格子物質AV3Sb5 (A=K,Rb,Cs)では、カイラル電荷秩序、電子ネマティック秩序、ローテーションペアー密度波、超伝導などの対称性の破れが見られる。
超伝導の性質については未解明の部分が多い。
行ったこと
本質的なCsV3Sb5薄膜において、磁場フリーの超伝導ダイオード効果を観測した。
外部磁場下での臨界電流の振る舞いを詳細に調べた。
熱サイクルによる超伝導ダイオード効果と臨界電流振動パターンの変化を調べた。
検証方法
微細加工したCsV3Sb5薄膜試料の電気抵抗・電流-電圧特性の精密測定
磁場印加時の臨界電流の振る舞いの詳細な解析
熱サイクルを加えた際の超伝導特性の変化の解析
分かったこと
磁場のない状態で自発的な超伝導ダイオード効果が生じ、その極性は熱履歴で制御される。
外部磁場下で臨界電流に明瞭な二重スリット干渉パターンが現れる。
干渉パターンの特徴(周期、位相)は熱サイクルによって変調される。
これらの現象は、時間反転対称性が破れた超伝導状態で、ドメイン境界に沿った超伝導電流によって説明できる。
この研究の面白く独創的なところ
自発的な超伝導ダイオード効果を発見し、その極性が熱履歴で制御できることを示した点
外部磁場下で明瞭な二重スリット干渉パターンを観測した点
干渉パターンの特徴が熱サイクルで変調されることを発見した点
ドメイン境界での超伝導電流の存在を示唆した点
この研究のアプリケーション
時間反転対称性の破れた超伝導体の基礎物性解明
マヨラナゼロモードなどのエキゾチックな粒子の探索
方向性を持つ超伝導素子の開発
超伝導量子ビットへの応用
著者と所属
Tian Le, Zhiming Pan, Xiao Lin (Key Laboratory for Quantum Materials of Zhejiang Province, Department of Physics, School of Science and Research Center for Industries of the Future, Westlake University)
詳しい解説
本研究は、カゴメ格子物質CsV3Sb5において、自発的な超伝導ダイオード効果と超伝導干渉パターンを発見し、その起源を動的な超伝導ドメインと時間反転対称性の破れで説明した画期的な成果です。カゴメ格子系は、幾何学的フラストレーション、トポロジカルなバンド構造、電子間相互作用の絡み合いにより、多彩な量子状態が生まれる舞台として注目を集めています。特にAV3Sb5 (A=K, Rb, Cs)では、カイラル電荷秩序、電子ネマティック秩序、ローテーションペアー密度波、超伝導など、多段階の対称性の破れが報告されており、超伝導の性質解明が大きな課題となっています。
研究チームは、高品質のCsV3Sb5単結晶から機械的に剥離した薄膜試料を用いて、精密な電気抵抗・電流電圧特性の測定を行いました。まず驚くべきことに、磁場のない状態で自発的な超伝導ダイオード効果、すなわち電流の方向に依存した臨界電流の非相反性が観測されたのです。しかもそのダイオード極性は、試料を超伝導転移温度直上まで昇温して冷却するという熱履歴によって制御できることが分かりました。これは、時間反転対称性の破れた背景の中に、動的な超伝導ドメインが存在することを強く示唆する結果です。
さらに研究チームは、外部磁場下での臨界電流の振る舞いを詳細に調べ、驚くべき発見をしました。臨界電流が磁場に対して明瞭な二重スリット干渉パターンを示したのです。量子力学の教科書に出てくる二重スリット干渉実験のように、一定周期の振動に加えて、より長周期の振動が重なっている様子が捉えられました。さらにこの干渉パターンの周期や位相が、熱サイクルによって変調されることも明らかになりました。
これらの現象を統一的に説明するために、研究チームは次のようなシナリオを提案しています。CsV3Sb5では、超伝導状態で時間反転対称性が自発的に破れており、安定化エネルギーがほぼ等しい2種類の超伝導ドメインが形成されます。ドメイン境界に沿って、磁束量子化によって制約された超伝導電流(エッジ電流)が流れており、それが自発的なダイオード効果の起源になっていると考えられます。外部磁場はドメイン構造のエネルギーバランスを変化させ、ドメイン境界の再配置を促します。この再配置過程が、臨界電流の干渉パターンとして現れているのです。熱サイクルは超伝導ドメイン構造をランダムに変化させるため、干渉パターンの周期や位相のシフトが生じると説明できます。
本研究は、カゴメ格子物質における時間反転対称性の破れた超伝導状態の存在を強く示唆する結果であり、超伝導の舞台としてのカゴメ物質の重要性を印象づけるものです。トポロジカル超伝導体の有力候補と目されるCsV3Sb5において、マヨラナゼロモードなどのエキゾチックな粒子が生まれている可能性も十分にあります。本研究で開発された、自発的ダイオード効果と干渉パターンを用いたドメイン構造の特性評価手法は、今後の研究に大きく貢献するでしょう。基礎物性の理解に加えて、方向性を持つ超伝導素子の開発や、超伝導量子ビットへの応用なども期待されます。フラストレートしたカゴメ格子という特殊な舞台で繰り広げられる、超伝導の新しい姿を明らかにした本研究は、大いに注目に値する成果だと言えます。
植物の新規温度センサーTWA1が熱ストレス応答と耐性に必須であることを発見した。
植物は気温の上昇に適応するために、温度を感知して熱ショック応答を活性化することが知られている。しかし、その温度センシング機構の詳細は不明だった。本研究では、シロイヌナズナを用いて、新規の温度センサータンパク質TWA1を同定した。
事前情報
植物は熱ストレスに適応するため、熱ショック応答を活性化する。
熱ショック応答では、HSF1転写因子がシャペロンなどの熱ショックタンパク質の発現を誘導する。
これまでに、いくつかの温度センサーが知られていたが、TWA1のような20〜30℃の比較的低温域で機能するセンサーは報告されていなかった。
行ったこと
ABA応答変異体のスクリーニングから、twa1変異体を単離した。
TWA1が熱ストレス耐性に必須であることを示した。
TWA1が20〜30℃の温度変化に応答して立体構造を変化させることを明らかにした。
TWA1の温度依存的な相互作用因子としてJAM2転写因子とTPL転写抑制因子を同定した。
TWA1が熱ストレス応答の初期に重要な役割を果たすことを示した。
検証方法
twa1変異体とTWA1過剰発現体の熱ストレス試験
酵母two-hybridシステムを用いたTWA1の温度依存的な相互作用解析
FRET-FLIM法を用いたTWA1の立体構造変化の解析
植物細胞とタバコ細胞でのTWA1とJAM2、TPLの相互作用解析
定量的RT-PCRによる熱ショック応答遺伝子の発現解析
分かったこと
TWA1は20〜30℃の比較的低温域の温度変化を感知する新規の温度センサーである。
TWA1は熱ストレスで立体構造を変化させ、JAM2-TWA1-TPL転写抑制複合体を形成する。
TWA1は主要な熱ショック転写因子HSFA2の発現誘導に必要である。
TWA1は熱ストレス耐性の獲得に必須であり、TWA1を過剰発現させると耐性が向上する。
近縁種のTWA1オーソログは感知温度域が異なり、生育環境に適応している。
研究の面白く独創的なところ
20〜30℃の比較的低温域で機能する新規の温度センサーTWA1を発見した点。
TWA1の温度依存的な立体構造変化と相互作用様式を複数の手法で実証した点。
近縁種のTWA1オーソログの感知温度域が生育環境に適応進化している点。
TWA1の発見が地球温暖化に適応した作物開発につながる可能性を示した点。
この研究のアプリケーション
TWA1の温度特性を改変することで、熱耐性の高い作物が開発できるかもしれない。
異なる温度感受性を持つTWA1オーソログを利用して、地域や気候に適した作物の育種が可能かもしれない。
TWA1は温度制御スイッチとして、温度依存的な遺伝子発現システムに応用できる可能性がある。
著者と所属
Lisa Bohn, Jin Huang, Susan Weidig, Zhenyu Yang, Christoph Heidersberger, Alexander Christmann, Erwin Grill - ミュンヘン工科大学 植物学教室
Bernard Genty - エクス・マルセイユ大学
Pascal Falter-Braun - ヘルムホルツ環境健康研究所、ミュンヘン大学
この研究は、地球温暖化に適応するための植物の新しい能力を明らかにしました。温度センサー TWA1は、20〜30℃の比較的低い温度変化を感知して、植物が熱ストレスに耐えるための防御応答を引き起こすことがわかりました。TWA1を欠損させると植物は熱に弱くなり、逆にTWA1を多く発現させると熱耐性が向上します。
TWA1は温度に応じて立体構造を変化させ、JAM2転写因子やTPLタンパク質と結合して転写抑制複合体を形成することで、熱ストレス応答遺伝子の発現を制御していました。また、TWA1の構造変化はわずか10℃の温度差で150倍もの感度で起こり、これは知られている中で最も温度感受性の高いタンパク質の一つであることがわかりました。
さらに、TWA1の近縁種のオーソログを調べたところ、それぞれの植物の生育環境に合わせて最適な感知温度域に適応進化していることも明らかになりました。
この発見は、地球温暖化に適応するための作物開発に新たな道を開くかもしれません。TWA1の温度特性を改変したり、異なる温度感受性のオーソログを利用したりすることで、気候変動に強い品種の育種が期待できます。また、温度制御スイッチとしての応用にも期待が持てるでしょう。
最後に
本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。
