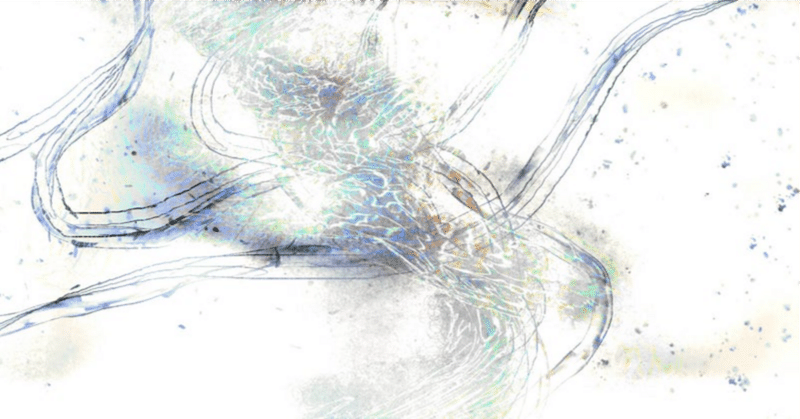
濁点(1)
1
二十歳になるまでには死ぬんだろうなと思っていた。小学五年生の頃だ。別にビョーキしていたわけでも、自殺願望があったわけでもない。単純に自分があと数年も生きられるという実感がなかっただけ。生きていることが不思議でならなかった。でも、結局、死ななかった。なぜだろう。成人する前に死んでしまう人より、生きてる人の方が多いから、ということならまあそうなのかもね。だって生きてるんだもの。仕方がないよ。
これは二十歳の女の子の、悩める物語? 全然違う。地球は尚もくるくる回って回って回って回って、あっという間に私を三十六歳にした。はい残念、おばさんでした。ああ残酷だ。あんまりだ。
そんなことよりそろそろ時間だ。電話をしなくちゃいけない。
「熱があるので今日も休みます。すみません」
「そうですか、わかりました」
電話の向こうで呆れているのが分かる。十日間も連続で休み続ければ当然かもね。
「明日はたぶん行けると思います」そう告げて受話器を置いた。
でも、行かない。行くわけがない。
私は銅線製造工場の事務として派遣されることが決まった。でも、どうにもやる気になれず休み続けている。そのうち派遣先からは契約を切られるかもしれないけれど、所属している派遣会社は私に親切だ。いつだって次を探してくれるし、担当者も一緒に頑張りましょうと言ってくれる。
頑張るのはあんただろ、って逆に言ってやりたい。
私はべつに、生活費に困っているわけではなかった。実家だし、母はなにも言わないし、父の遺産もまだあるし、寡婦年金も足しになっている。だから人よりはある程度自由に暮らせている。
問題は家の中にあった。私ももうおばさんだしさ。でも、孫のことは最初から求められてすらいなかったと思う。そもそも、両親は子供嫌いで私も同じ。孫や我が子は別だから、なんてふざけたことを一度も口にしなかったのが救いかしら。
六十を少し過ぎた母はまだまだ元気で、二週間から月に一回くらいは友人たちと一緒になってツアー会社の企画する旅行へ出かけ、半年に一回は海外を満喫して帰ってくるというありさまだ。私は旅行や観光があまり好きではなかったから、どこにも行かず家に居続けている。でも船は好きかもしれない。家族旅行の中での一番の思い出が、フェリーで寝泊まりしたものだったから。デッキで風を浴びながら見た、太陽を水平線の向こうに飲み込む海の全貌はとても美しかった。はずだ。
記憶の中の美しさなど当てになるもんか。
「お昼、なに食べたい? あと晩御飯と」
昼食にはまだ早かったけれど、買い物を先に済ませたかった私は母に聞く。私は日がな一日、暗闇に沈んでいるような人間じゃない。仕事を休んだ日は、家事のすべてを母に代わってすることにしていた。最近はずっとだ。
「そうねえ、そうめんがいいわねえ。でも夜はなんでもいいわよ」
必要な食材を思い浮かべながら料理の手順を追い、頭の中でそうめんを完成させる。うん、まあ、いいかもね。でも、「なんでもいい」は困る。「なんでもいい」は自分を捨てているのとおんなじだ。
昔、高校生だったころ、マクドナルドでクラスメイトが同じことを言った。だから子供向けのハッピーセットを注文してあげた。別にクラスメイトの幸福を望んだわけじゃない。お前の好みなんて知るか、このハッピー頭、という意味を込めただけ。文句は言ってこなかったけれど、不機嫌そうな顔をしながら食べていたのを思い出す。
母には、きちんとしているところを見せたかったから、夕方になったらもういちど食べたいものを聞いて、それから二度目の買い物に行こう。べつにスーパーをなんど訪れようとも、苦にはならなかった。
洗濯と料理は似ている。放り込むものと放り込む先と、調味料の種類が違うだけだ。洗剤の味は苦い。昔は、気づくか気づかないくらいの微妙な量を食事によく入れられていたけれど、いろいろと調べてみて毒性の低さを知ったから、お茶で薄めながらなにくわぬ顔で食べ続けてやった。やがて母は洗剤を入れることを諦めた。
知らないとでも、思っているのか。
洗濯機を回している間は掃除機をぶんぶんかける。家の掃除機はダイソンだから吸引力も抜群だ。母はテレビの音量を上げて少し迷惑そうにすることもあったけれど、家事を疎かにするわけにはいかないのだから仕方がない。お互い我慢しなくちゃね。
ハンディタイプの掃除機のほかには、地べたを這いずるロボット掃除機も持っている。
このロボは、ときどきコードを絡めてしまったり、設定しているはずの進入禁止区域に入ったりしてしまう。だから、ずいぶん昔に飼っていた犬と同じ名前で、ごんたくれの「ごん太」と名付けた。犬のように吠えることも噛みつくこともないけれど、動いている間はずっとうるさい。母はごん太を思い出すからと掃除機につけた名を嫌っていた。そうは言っても、ごんたくれはごんたくれなんだから、やっぱり「ごん太」で問題ない。悲しみを思い出せばいいんだ、と思った。
家事は労働だ。それ以上でもそれ以下でもない。でも、人は人を消費するし、人によって消費されるし、人として形作られる。だったら人を育む家事は、アーレントの言う「制作」でもあるかもしれない。だからきっと、私は今もこうして母と過ごしているんだろう。結局、人間の出来損ないとして。
結婚もしておらず、子も持っていないことを幸せの形と呼ぶにはまだ遠い。どうやら自由の旗印だけでは抗しきれないようだ。自由とはこれほど軽いものだったんだろうか。なんにせよ、洗濯物をバッグに入れてコインランドリーへ行こう。
自転車は電動だから少しも疲れない。髪を風に乱しながら私はこぎ続ける。見知った顔に頭を下げることもない。人間の関係なんて、どうでもよかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
