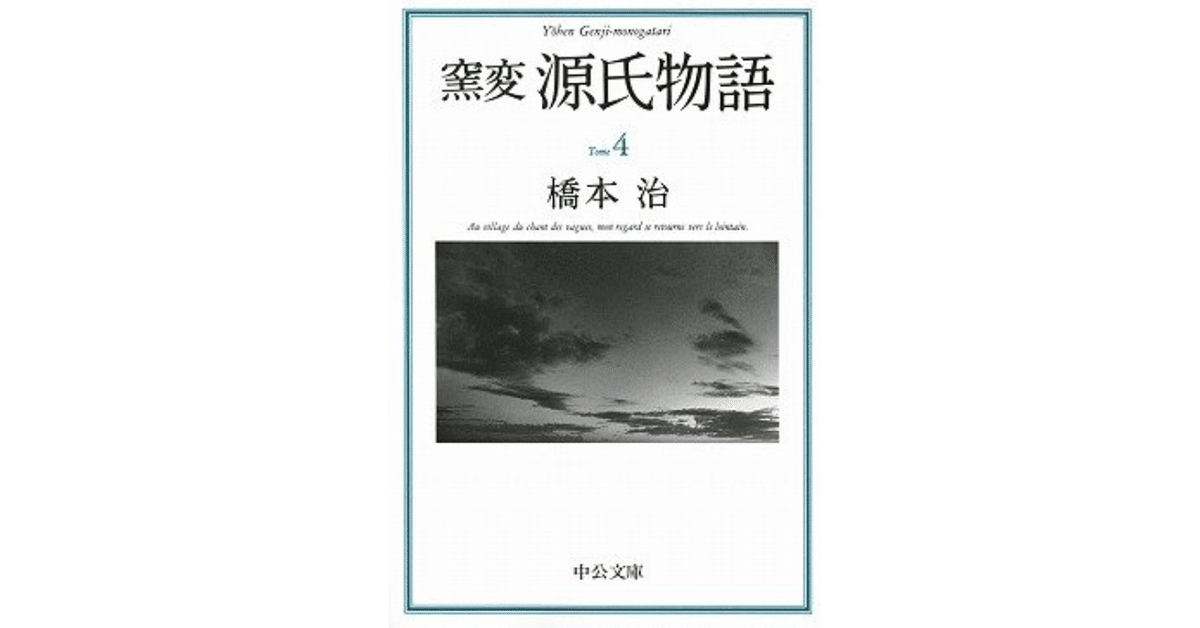
窯変は男たちの「源氏物語」
『窯変 源氏物語〈4〉 花散里 須磨 明石 澪標 』橋本治(中公文庫)
源氏はJ・フィリップ、葵の上はR・シュナイダー…フランスの心理小説と似通った部分があるから、配役はフランス人で構想。(花散里/須磨/明石/澪標)
須磨
葵の母の大宮と弘徽殿女房とを今まで同一人物として読んでいていたようだ。このへんは系譜が錯綜するから、混線するのだと思う。右大臣家が弘徽殿女房で、左大臣家が大宮なのだが、頭の中将が右大臣家の婿となったりするもんだから、混乱したのだと思う。
光源氏が雁の歌を読むと男の従者たちが連なって雁の歌を詠むのが連歌という形式と共に雁が故郷(京)を離れて飛び去る姿をそれぞれ詠んでいて雁のように連なっているのだった(それぞれ恋人、友、京を捨て、須磨に至る)。このへんは紫式部の上手さだな。
(光源氏)初雁は恋しき人のつらなれや旅の空飛ぶ声の悲しき
(良清)かきつらね昔のことぞ思ほゆる雁はその世の友ならねども
(惟光)心から常世を捨てて鳴く雁を雲のよそにも思ひけるかな
(前右近将監)常世出でて旅の空なる雁がねもつらに遅れぬほどぞ慰む
前に読んだ時は女性への手紙(和歌)ばかりに目を奪われたが、「須磨」ではそれ以上に男の友情(政治的)?というものが語られるのである。
明石
明石の入道は喜劇的だが光源氏の復活を語る上では重要な人物でトリックスター的。
明石の君は父の決めた光源氏の嫁入りになかなか了解せず、その冷たさから六条御息所に似ているとされるのだが、年齢が二十七歳ということもあるのか、自分の意見を持った女性として描かれていた。それは明石という閉鎖空間でプライド高く育てられたからだろうか?光源氏の和歌(言葉)には靡かないのだ。明石の君が光源氏に惹かれるのは、琴の合奏を通してで、明石の君は宮中にもいない唯一の名演奏家だと光源氏に認めさせる。それで田舎娘が光源氏と同等だと認めさせるのだ。ここは先行する『うつほ物語』の影響を感じさせた。
そして光源氏の都での評価も百八十度変わり、都へ復帰となる。そのとき明石の君はすでに懐妊していた。
澪標
光源氏が都へ戻ることは、明石の君の母親にしてみればもう明石の君は見捨てられたのだと明石の入道と口論になるのだが、ここも夫婦漫才のようで面白かった。明石の入道としてみれば自分の思惑通りで、権力の中心にいる男に娘を嫁がせる。そして娘が子(女)を産んで、それを帝の妻にしようとしたのだから、入道の妻にしてみれば田舎の受領の絵空事のように思えたのだ。
ここで受領階級の宮廷内の偏見について、光源氏も考えるのだが、明石の君が宮廷内の誰よりも琴の出来る演奏家だった。そこに紫式部は自身の境遇を重ねたのかもしれない。音楽(芸術)の力は世界を変える力を持っているのだ。何より光源氏が明石の君に授けた琴は、桂木の笛と共に『源氏物語』の三種の神器になっているのだと思う(あと一つはなんだろう?)
明石の君は、地方の世界の受領の娘にしか過ぎなかった。光源氏のお礼参りとしての住吉詣の行列によって、その身分の差をまざまざと見せつけられるのだが、そこで娘の乳母としてやってきたのが桐壺帝にも愛された都の地位のある女だったのだ。
それまで光源氏は明石の君の妊娠に無関心であった。それは過去の妊娠、藤壺や葵の上の妊娠が不幸しかもたらさなかった男児だったからである。それが姫だと知ると摂関政治の力をまざまざと知ることになるのだ。つまり娘を天皇の皇后として嫁入りさせることで力を得るという摂関政治のシステムを理解するのである。それは明石の入道の受領階級の見果てぬ夢だと思っていたのだ。
弘徽殿女御の力もその時に本当に知るのだった。むしろ弘徽殿女御は敵でさえなく、先例に過ぎないのだから。むしろ悪帝としての桐壺帝のもののけをどう払うか問題だった。桐壺帝が悪帝なのは正しい妻というものがありながら、桐壺の更衣、藤壺という女との欲望を統率することが出来なかったこと。帝は何でも自由に出来る立場にいながら、執権政治というシステムの中で従属させられられる。その反抗として恋(欲望)を無理に押し通す桐壺帝の悪性があったのだ。正しいのは弘徽殿女御らの后側の論理なのである。
その嫡子として正統ではない光源氏が降格させられるのだが、それは正しいシステムの論理としては当然のことであった。愛なんて、そこでは問題にならない世界なのである。だが光源氏はそのシステムを理解してなかった。須磨・明石で中央政権から離れてみたときに、中央の力をまざまざと考えたのである。それが橋本治が『源氏物語』から読み解いていく権力の物語だ。
窯変が特異なのは男たちの世界が輝いているところだった。腹心としての惟光の重要性。それは光源氏の手足となって尽くす道化師のような存在でもあるが、主人を批評できるのも道化師でもあるのだった。なぜ一人称なのに光源氏に反する批評の声が出てくるのか、そこにモノローグでも惟光という自己内対話という世界が築かれていくのだった。紫の上の心情なんて須磨にいる光源氏には分かるはずはないと思うのだが、手紙でそうした日記を細やかに綴っていたとされるのだった。
紫の上の嫉妬心さえ光源氏は可愛いと思ってしまうのだ。それは光源氏が立場上紫の上と同等にいないからだった。明石の君に娘を産ませたことで、紫の上の重要な役割が与えられるのだが、それまでの期間は乳母を明石に派遣するのだ。それも天皇の后としての教育のために、すぐにでも明石の地方性が身についてしまったら外戚として執権政治が出来なくなるからだった。
いつの間にか権力の中心に返り咲く手立てを持っていたのだった。最初はそれから逃れようとして女に現を抜かしていたのかもしれない。今までも女のことでは失敗を重ねてきたのだが、今回はその女の娘を得ることによって父権制の中心に自分がいることに気がついたのだ。しかし、まあ明石の姫は幼すぎるというので、もう一人娘が光源氏の前に現れてきたのだった。それ伊勢の斎院、六条御息所の娘だった。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
