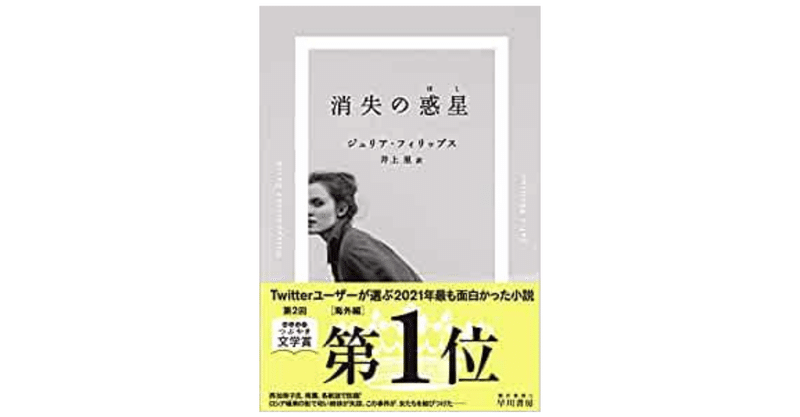
純文学ミステリーSFで消失した文学なのか?
『消失の惑星【ほし】』ジュリア フィリップス, 井上 里 (翻訳)
第2回みんなのつぶやき文学賞[海外編]第1位
「喪失の悲しみは計り知れない。だが、喪失から再生しようともがく人間は美しい」――西 加奈子
◆◆◆書評・メディア露出◆◆◆
クロワッサン(2021年5月25日)書評(瀧井朝世氏・ライター)
婦人公論(2021年5月11日)書評(豊崎由美氏・書評家)
WEB本の雑誌(2021年3月31日)書評(松井ゆかり氏・書評ライター)
日本経済新聞(2021年3月20日)書評(蜂飼耳氏・詩人)
共同通信(2021年3月)書評(江南亜美子氏・書評家)
QJWeb(2021年3月6日)書評(豊崎由美氏・書評家)
この痛みから、目を背けることはできない
ロシア極東の街で幼い姉妹が失踪。この事件がばらばらに生きる女たちを結びつけた――。
新鋭米国作家による文芸作品。全米図書賞最終候補作
【あらすじ】
遠い街、見知らぬ人が受けた傷。
その痛みは、あまりにも身近――
8月のある午後、ロシア東部のカムチャツカ半島の街で、
幼い姉妹が行方不明になった。警察の捜査は難航し、
事故か誘拐かもわからぬまま時ばかりが過ぎる。
失踪事件は、半島中の女性たちに影を落としてゆく。
姉妹の母親、2人を最後に目撃した研究者、
心配性の恋人に監視される大学生、自身も失踪した娘をもつ先住民族の母親……
ばらばらに生きてきた12人の女性の言葉がつながるとき、
事件はふたたび動き出す。
カムチャツカの美しい情景、そこに生きる女性たちの痛みと希望を克明に描き、
世界から注目される米国作家による文芸作品。
2019年全米図書賞最終候補作、23の言語で翻訳決定。
ソ連時代からプーチンのロシアに変わるカムチャッカ半島の話で、世代間ギャップのディスコミュニケーションを描いている。チェーホフのスタイルを汲んでいると思うが、働く女性は自立していく女性である。それはロシアの男性中心主義とは反するものだ。ただ希望は、女性同士の繋がり、シスターフッドと呼べるものなのか?繋がっているようで、離れ離れに。それはカムチャッカ半島から伸びるクルリ諸島のようで、北方四島もその先に見えそうで見えない(実は日本も影響を与えている→日本車や密漁の闇市場)。また北海道の別の先にはサハリン(囚人の)島もあった。
三世代の物語が連作短編のスタイルで語られていく。その過酷な生活の中にロシアの少数民族の暮らしがある。ソ連解体後の自由主義経済社会のカムチャッカは、日本の影響もありそうだ。日本車や密漁での闇の繋がり。最初誘拐犯は日本人(中国人でもいいけど)関係者ではないか疑った。臓器提供とかのヤバい話。そういう映画があった。
豊かさを求めて自立していく女性は、反体制にならざる得ないのだ。両親、夫、子供が、その反対勢力なわけだった。その孤立がディスコミュニケーションの小説として、胸を撃つ。
カムチャッカ半島。モスクワよりも日本の方が近いロシアの僻地。ディコミュニケーションの小説。ふとチェーホフの短編を想い出す。カムチャッカ半島がサハリン島と似ているかもしれない。そしてカムチャッカ半島に連なるのがクルリ諸島(北方四島)である。
八月に幼い姉妹の行方不明事件があり、その後に一ヶ月づつ暦に沿った連作短編集。事件の関係者もいれば、ただ事件を知ってその変化に気づく人もいる。カムチャッカという半島の閉ざされた地のコミュニケーションの話なのかなとも思う。
この小説に出てくるエウェン人はツングース人とも言われ、ロシア人よりは我々に近い。アイヌとはかなり近いように思える。
そうした島の繋がりは空から見れば見えない連鎖があるように思うが半島の内部はディスコミュニケーションの世界。この小説が日本でも読まれたのはそんなところかもしれないと思った。季節(12ヶ月)の連作短編でもあり、それぞれが分離した話とも読める。五月のUFOの陰謀論めいた弟の話がいい。次に二月かな。七月はずるいよな。あそこは泣くにきまっているじゃん。
八月幼い姉妹(アリョーナとソフィア)が男の車に連れられ行方不明になった。
九月親友だと思っていたディアナの母ワレンチチ・ニコラエヴナ(学校関係者で保守的)が事件があってから付き合いを止めてくれと言い出す。オーリャの母は日本語通訳者でシングルマザー。
十月若いカップル、事件の目撃者であるオクサナの同僚カーチャとマックスのキャンプ。テントを積み忘れた(彼に愛想を尽かすが)車中泊する夜、熊に襲われた。クラクションを鳴らして熊を追い払った彼の株が急上昇!
十一月九月に登場した嫌なオバサン、ワレンチチ・ニコラエヴナ再登場。水疱が出来て総合病院へ。すぐに癌かもしれないと、すぐ除去するように言われるまま手術室へ。それも裸で手術室に行かなければならなかった。
十二月クシューシャはアリーサに誘われて民族舞踏クラブに入る。クシューシャは少数民族の出身で、白人である彼氏、ルースランに守られているが、次第に同じ舞踏の相方チャンダーに惹かれていく。少数民族の娘リリヤの失踪事件からクシューシャの保護者となったルースランとチャンダーの葛藤。
十二月三十一日大晦日のパーティ。クリスティーナとラダの親友マーシャが帰ってくると(レズビアン的な関係?)もう、かつてのように馬鹿騒ぎできる年頃ではなかった。大人びたマーシャ。ラダは地元に染まっていくがマーシャはより自分自身を出すようになっていた。ここでそれは危険なこと。
一月ナターシャはUFO陰謀論に取り憑かれる弟がいる。失踪した妹リリヤはUFOに連れされたと言う弟。弟の方を連れ去ってくれればいいのにと思うナターシャだ。母はすでにリリヤを亡き者としている(事件の姉妹もとっくに殺されているのだから彼女も死んでいる)。それはリリアがあまりにも活発な娘であったので男関係の噂が絶えなかったからだろう。リリヤの自由奔放さに憧れるナターシャだったが、妊娠が発覚すると隣町の少数民族の男と結婚した。警察署に務める親友のアンフィーサに事件の膠着状態の状況を聞く。アンフィーサはナターシャの弟を病だと思っていた。それを聞くとナターシャは腹を立てた。そんな弟も妹も母も家族なんだと。この話が一番いい。ナターシャの複雑な感情の綾が孤立していく家族のディスコミュニケーションを良く語っている。チェーホフを想い出す文章。
二月レヴミーラの夫は救急隊員で事件の捜索をしていたが、氷山の山崩れによって事故死してしまう。レヴミーラの親戚アーラがリリヤの母だった。すぐ街の警察に頼めば解決すると言ったがリリヤの失踪事件ではろくな捜査も行われずに警察の不信感が増していく。レヴミーラは前の夫もソ連が崩壊する年に亡くしている。死に彩られたレヴミーラの人生だが、生きていく決心をする。
ブーツ、ベルト、書類、マフラー。グレブ(先の夫)が事故に遭ったあと、自分もじきに死ぬのだと思った。あるいは、自分も死んだのだと思った。あの日、グレブはいなくなり、レヴミーラは、悲しみという名の重力に引きずられるようにして、彼の記憶をいつまでも追った。だが、レヴミーラは生きる。生きなくてはならない。彼女がしてきたのはそういうことった。他の者たちがいきられなかったときに、彼女は生きていた。そこに喜びがないのだとしても。
三月先住民の男と結婚したナージャ。その前に妊娠していたので、娘を生むためには彼が必要だと思った。その当時付き合っていた別の男は彼女を拒否した。先住民の男の生活との意見の対立。彼女は実家へ戻って、過去の男と出会う。危ない男だった。酔っ払って深夜に尋ねてくるような男だ。娘はパパに会いたがっている。娘の為に家に帰ることにする。
四月ゾーヤは娘の面倒をみてくれるタチアナ・ユリエヴナ。ゾーヤの夫コーリャも警察の捜索隊で今日大人の遺体を発見したという。操作隊連中は酔っ払いゾーヤは地元連中に嫌気がさす。そして移民の男とのランデブーを想像する。地元の男たちのナショナリズム的な話題。
五月オクサナは少女誘拐事件の目撃者だが、事件は解決に向かわずに、彼女の証言は宙吊りになって彼女が悪いように噂を立てられる。事件から十ヶ月後に愛犬が部下の不注意から逃げ出す。愛犬はオクサナにとってかけがえのない犬だった。ある日夫が崖に枝を投げて愛犬が追っかけていくが、戻ってきた。夫の悪い冗談を許せなくて離婚する。愛犬はあのときに死んでいたら、今回のこともないのだし、誘拐事件の目撃もなかった(愛犬の散歩中の出来事だった)。
自分の身は自分で守れるのだろうと思ってきた。警察官であれ、親であれ、友人であれ、勝手に自分の領分へ踏み込んでくることのないように、心に壁を作り、むやみに感情をおもてに出さないように気を付ける。大学院で学位を取り、いい仕事に就く。外貨で貯金し、期日どおりに請求書の支払いをする。神経をナイフのようにとがらせていれば、周囲の者たちはそれを慎重に扱うようになる。これで安全だと思い、だがそう思った瞬間、自分はどれだけ無防備に、会う人すべてをしんらいしてしまったかに気づくのだ。
オクサナはようやく、母親が自分に会いにきたかを理解した。愚かさから自分を絶望に追いやることは耐え難くつらい。愚かな者たちは、鍵の壊れたドアをそのままにしたせいで、あるいは我が子をひとりにしたせいで、戻ってきたときに、自分が何よりも大切にしていたものが消えているのを知る。それに耐えられないなら、その手で破壊してしまいなさい、目撃者になりなさい。自分の人生が崩壊しいく、その瞬間の。
六月姉妹失踪事件の母親マリーナは「統一ロシア党の機関誌」の記者で、エウェン人の夏至祭を取材して、そこで大学の舞踏クラブの指導者、アーラ・イノケンチエヴナと出会う。マリーナは、娘たちが生きていることを信じられない夫とも別れていた。夏至祭というのは、生と死の境界ということだ。植物の再生祭。アーラ・イノケンチエヴナは行方不明になったリリヤの母親だった。エウェン人の夏至祭の踊りを学生たちに教えることで、この困難な苦悩に耐えてきたのだ。先住民族の自然とのコミュニティ。その絆が大切だという。ソ連時代にそういったコミュニティは破壊された。その夏至祭に来ていた他の記者たちが失踪事件をまた取材する。早川はミステリーだとするとこの月で事件解決なのだが。誘拐事件は解決されなければならないというセオリー通りだった。
七月ここは早川はもう一つSFの部門もあるのだった。この二通りの解釈のできるところが小説としては上手いのか、ここは泣けるじゃん。ほとんど五月の弟の説が正しかった。それでも、もう一つ別のヒロインたちのおとぎ話にも出来るのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
