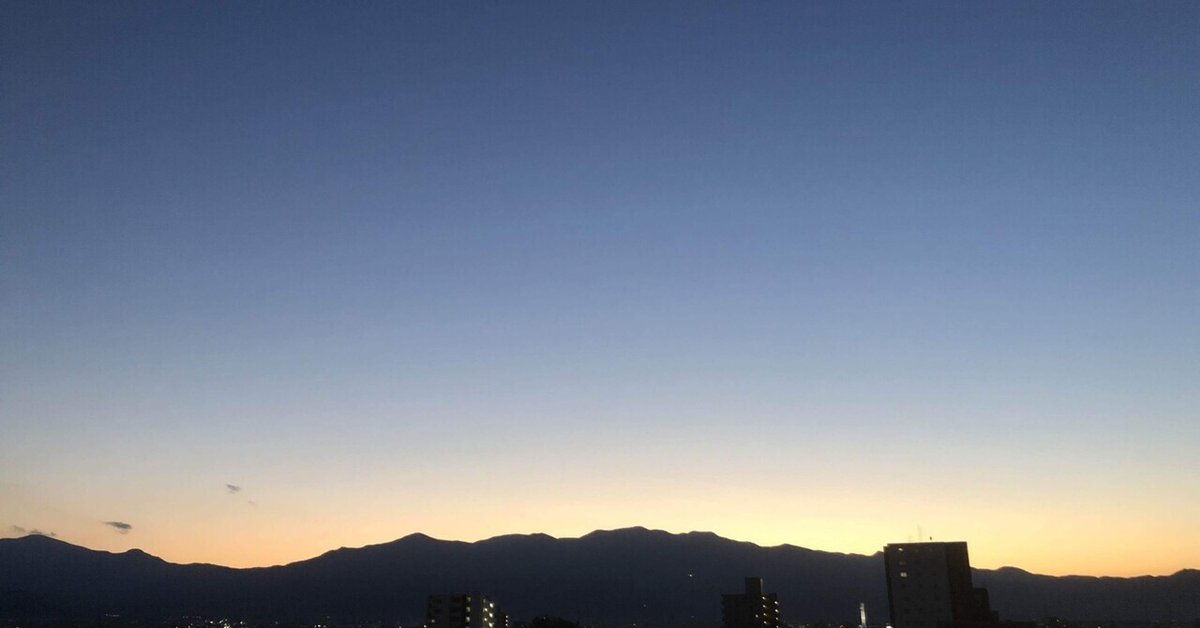
【研究者日記】行動活性化とあおき①
先日、行動活性化についてのマガジンをあげましたので、今日はこれができあがるまでのお話をします。①と書いてますが、②は気が向いたら書きます。
といってもずーっとさかのぼって、もう8年も前の話です。
わたしは博士課程に進学した時に、認知行動療法って認知に働きかけるテクニックと行動に働きかけるテクニックがあるけど、実際どっちがどう効果があるんだろう?ということを調べたいと思っていました。
というのも、うつ病の人の症状パターンって1000通り以上あるのに、どの人にも同じ方法が効果があるなんてことはありえないだろうと考えたからです。その当時、認知行動療法はパッケージになっていましたから、研究の土台に乗せた場合、そのパッケージを行うのがいろいろな技法の詰め合わせの認知行動療法だったわけです(臨床では違うよ)。
けどパッケージ→うつ症状全体ってざっくりしすぎじゃん、実際効果がある個所とない箇所ってあるでしょ。そういうところが疑問に思って、認知行動療法を各技法に分けた時にどの技法がうつ症状のどこに効くんだろうか?ということに興味を持ち始めました。
とはいっても、仮説が立たないと研究は進まないから、まだ介入研究をする前に、その前提になるデータを取ろうと考えました。そこでは大学生を対象にして、認知的要素と行動的要素って、うつ病の中核症状であるうつ気分と興味・喜びの喪失にどう影響するんだろう?という研究をしました。
結果としては、認知的要素はうつ気分にだけ影響し、行動的要素はうつ気分と興味・喜びの喪失のどちらにも影響しました(成果はこちら)。
「まじか。」
と私は思いました。というのも、卒論から修論にかけてずーっと認知的要素について研究してきて、わりかし認知的要素がうつ症状を悪化させているという信念のもと研究をしてきて、ここに来て、「え?行動っすか?」と思ったわけです。
まあ、わりかし気持ちを切り替えるのは早いほうで、結果が出てしまったものはしかたがない、そこから、行動活性化の研究にしぼって研究をしよう!と思い始めたわけでございます。
続きはまたどこかで!!!
以下は、宣伝です。
行動活性化の仲間たちが、行動活性化治療マニュアルの日本語版を作成してくれました。わたしもちょっとだけお手伝いいたしましたので、ご興味ある方はご覧くださいませ。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
筆者 あおきしゅんたろうは福島県立医科大学で大学教員をしています。大学では医療コミュニケーションについての医学教育を担当しており、臨床心理士・公認心理師として認知行動療法を専門に活動しています。この記事は、所属機関を代表する意見ではなく、あくまで僕自身の考えや研究エビデンスを基に書いています。
フォローやチャンネル登録してもらえたら泣いて喜びます!
Twitter @airibugfri note以外のあおき発信情報について更新してます。
Instagram @aokishuntaro あおきのメンタルヘルスの保ち方を紹介します(福島暮らしをたまーに紹介してます)。
YouTube ばっちこい心理学 心理学おたくの岩野とあおきがみなさんにわかりやすく心理学とメンタルヘルスについてのお話を伝えてます!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
