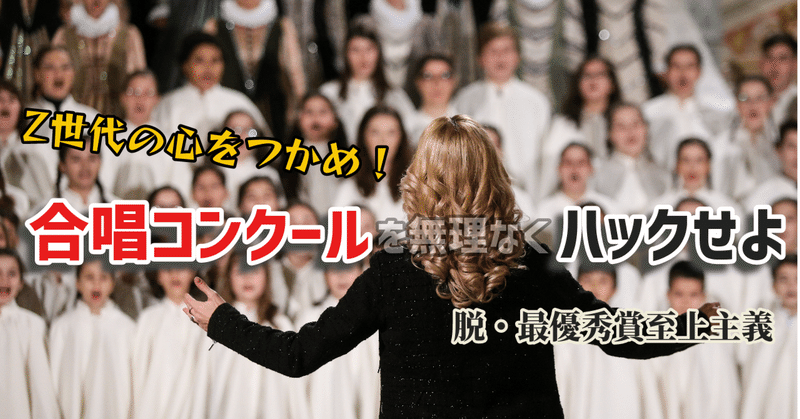
【脱最優秀賞至上主義】『合唱コンクール』をハックする【持続可能な行事】
皆さん、こんにちは。
記事に興味をもっていただき、ありがとうございます。
今回のテーマ

10月に入りました。
この時期の大きな学校行事はなんでしょうか?
そう、「合唱コンクール」です。
今回は生徒と教員の立場からこの合唱コンクールについて考えます。
自分自身の苦い経験やこれまでの教員経験をもとに、合唱コンクールを考えたいと思います。
あらかじめ申し上げておくと、「合唱コンクールで最優秀賞を獲る方法」や「合唱が上手くなる方法」には触れません。
今回お伝えするのは、「令和時代の合唱コンクール」です。
私にとっての合唱コンクール

学校行事で一番好きなのが合唱コンクール。
スポーツが苦手で運動会で活躍できなかった私にとっては、唯一自分を活かせる行事だったといえるかもしれません。笑
手前味噌になりますが、最優秀賞を学生時代と教員時代の両方で獲得したことは良い思い出になっています。
地元の福島県郡山市は合唱が盛んな地区でした。
市内の中学校で最優秀賞を獲得したクラスは文化センターで合唱する機会が与えられるというくらいの熱の入りようです。
高校球児にとっての甲子園のように、喉から手が出るほど欲しい「文化センターへのチケット」
このチケットを獲得するために、最優秀賞へ向けてかなり合唱の練習をしたのを覚えています。
また、教員になってからも、勤務した学校のそれぞれで最優秀賞を獲ったクラスを担任させてもらっています。
私の指導力のおかげではありません。(生徒もそう言っていました。笑)
合唱へのモチベーションを高めてくれた生徒のおかげで良い結果を手にすることができました。
学生時代の友人、衝撃の告白

成人してから学生時代の友人とご飯を食べにいきました。
過去の話が弾み、合唱コンクールの話になりました。
先ほどお伝えしたとおり、友人と私が所属したクラスは最優秀賞をとることができました。
学生時代、合唱コンクール本番までは朝・昼休み・放課後と毎日練習を重ねました。
集合して川原で歌った記憶もあります。
10月からは文字通り、毎日を合唱に捧げるような日々だったと思います。
そんな合唱への日々を楽しかったエピソードとして話そうと思っていた私。
しかし、友人の言葉に耳を疑うことになりました。
彼が言った言葉が、私の合唱コンクールへの向き合い方を変えました。
彼はこう言ったのです。
「朝練、正直しんどかった」
「練習自体は嫌いではなかった。だけど、練習に出なければいけない雰囲気が嫌いだった。」
ハッとしました。
『キツかったけど、楽しかった』という記憶で終わっていた合唱コンクールが、全く別物になった人もいるのだと知り、頭を金槌で叩かれたような衝撃を受けました。
合唱コンクール≠競争

合唱コンクールはきちんと戦略を立てて臨まなければ、最優秀賞しか眼中にない、ただの『競争』で終わってしまいます。
競争の先にあるのは、一部の人間の充実感。
おそらく中学時代の私は、最優秀賞を最上目標に掲げて練習していたと思います。
そうすると、クラス内で同じ目標を目指せない人が絶対にいるはず。
30人が全く同じゴール目掛けて走るなんてありえないわけです。
それは一種のカルト宗教みたいなもので、私個人の感想としては、そんな集団に嫌悪感すら抱いてしまいます。
私も経験したことがある、この虚しい現実を味わってほしくないですよね。
教員として臨んだ、初めての合唱コンクールは、今思えば「最優秀賞」しか眼中にないような状態であったと思います。
技術論を話し、スポーツのトレーニングのように練習を重ねる日々。
私の姿勢に合わせてくれた生徒たちのおかげで最優秀賞を獲得しました。
その時は嬉しくてしょうがなかったですが、果たして合唱コンクールの名を借りた「競争」の先に何を残せたのか、今となっては猛省しています。
「クラスの雰囲気に違和感を感じた生徒はいなかったか」「毎日の練習に嫌気を感じた生徒はいなかったか」こんなことを考えるのです。
最重要の目的を最優先にする

合唱への向き合い方を180度変えた私。
そんな私が合唱コンクールの練習のはじめにクラスで話すことがあります。
それは合唱コンクールの目的です。
学校の行事である以上、目的がなければいけません。
当然ですが、目的は「最優秀賞」であるはずがありません。
最優秀賞が目的であれば、学年で1クラスしか目的が達成できない行事に成価値などないはず。
私は「合唱コンクールの目的はなんだろうね?」とクラスの生徒に問います。
そうすると、このような回答が返ってきました。

私はこれらの答えが「大正解」であると思います。
途中の「先生のクラス最優賞記録の保持」は気を遣ってくれただけでしょう。笑
競い合うことで勝つのは1クラスです。
でも、クラスとして独立した目的を意識することで、個々の向上が目的になるのです。
持続可能な合唱練習

合唱練習あるあるをご存知でしょうか?
「男子ちゃんと歌ってよ!」
「女子も歌ってないだろ!」
これは持続可能性が低い合唱練習をしていると起きます。
なぜなら、目的が意識できていないからです。
目的がクラスの質の向上であれば、「どうすれば全員が歌いやすくなるか」を議論する方向に進むはずです。
持続可能な合唱練習にするコツがあります。
それは「教員が無理しないこと」です。
先生が苦しい練習が生徒にとっても苦しい確率は1000パーセントです。(当社調べ)
「朝練毎日はしんどいなー」と思っている先生がいたら、それは頑張りすぎです。
生徒の中でも、同じように感じている生徒が絶対にいます。
じゃあ、どうすれば無理のない、持続可能な練習ができるのでしょうか?
ここで、私が具体的にどうしているかを紹介します。
渡部オリジナル合唱ルール
①週明けの月曜日は朝練習しない
②朝練習は週に3回まで
③朝練習は喉を労って60%の音量でOK
④昼休みはパート練習のみ
このくらいゆるーくやるのが大切です。
やる気のない練習3回より、やる気のある練習1回に価値があります。
「しんどい」と感じる生徒が多い状況で練習するのはNGです。
全員が楽しい合唱練習は現実には難しいかもしれません。
しかし、大多数が楽しくて、残りの人たちも「まぁこのくらいなら」と思えるくらいの練習を目指しています。
※ここまで話しても、どうしても最優秀賞が欲しいと考える人がいるかもしれません。私の実体験なので、サンプル数1ですが、これでも最優秀賞は獲得できました。
5年後に笑って話せる合唱コンクールに

合唱コンクールの理想は、同窓会で全員が笑って話せることだと私は思います。
同級生の飲み会の話のネタの1つにでもなれば、それでOKなんです。
人生100年時代に、合唱コンクールは何千分の1の思い出にすぎません。
もし、5年後「あれは正直面倒だったよな」と1人でも言われたらアウトな気がします。
わざわざ練習して、嫌な思い出が残っているなんて最悪ですよ、本当に。
偉そうに語っていますが、生徒の本音を100%理解なんてできない以上、
今私が行なっている実践が理想通りかは分かりません。
でも、少しでも理想に近づけるように頑張っていこうと思います。
先生方の合唱コンクール指導の参考になれば、嬉しいです。
また、私の合唱コンクールに対する考えと違う考え方をお持ちの方も、ぜひ教えてください!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
