
越の白山(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 8)
※画像では、「ルビつき・縦書き」をお読み頂けます。
越の白山
岐阜城の廊下を歩いていた熊千代は、津田坊に呼び止められた。
熊千代は立ち止まり、一緒に歩いていた小姓に先をうながした。
「ではうまく持っていけな、古新」
「助かる。ではまたな、熊千代」
熊千代は岐阜城づとめの中で周囲に少しずつ、うちとけていた。
次々に下る戦の号令、戻れば茶会に軍議にと常に騒がしく忙しい。池田古新は信長の小姓でひとつ年下、いかにも尾張の田舎武士の息子でしかも次男坊だが、気取りがなく地に足がついている。調度品の整理を命じられ困っているときに手伝ったことから仲良くなった。
熊千代とそばの一室に入り、襖を閉めると津田坊は囁いた。
「これはまだ内密の話だがな、おまえとおれは親戚になるらしいぞ」
「お坊様と、おれがか?」
熊千代は目を丸くした。
「おれは、明智のむすめを妻にもらうことになった」
津田坊は腕を組み、人の気配がないか伺いながら話していたが、ふと見ると熊千代があまりにも驚いた顔をしているので怪訝な顔をした。
「おい、聞いているのか」
片手で肩をつかんで揺するが、ガクガクと首が動くだけで、熊千代は完全に固まっている。心なしか白目になっているような気がして、津田坊は不安が増して軽く相手の頬を叩いた。
「おまえももらうのだぞ。おい!」
「おれ、も……?」
「おれは二女で、おまえは三女だ。おれたちは義兄弟になる。あの高名な明智の姉妹をわれらがひとりじめだ」
真っ白になっていた頭にやっと血の気が戻って来た。思考を懸命に動かして言葉の意味を読み取ろうとする。二女と三女、おれは三女、三女…。
では上様は、本当に約束を守って下すったのだ!
「しかしお前の父上は断ったそうな。知っているか?叔父上が再三お話になり、最後はきつくご命令になってやっと承知したとさ」
父はやはり、断ったのか…。
「やたらと固辞してくるので始末に負えぬと、間に挟まれた佐渡守がぼやいておった」
上様からの命ならば父も、また明智どのも反故には出来まい。ひとまずは安泰だ。あの子は、上様がおれに下されたのだ!
にわかに胸がどきどきしてきて、熊千代は立っていられないような、宙に浮くような感覚に襲われた。
気分が高揚しているのは熊千代だけではないとみえ、津田坊はうっすら紅潮した頬でつぶやいた。
「明智の三姉妹が美人だというのは、皆は噂しておるだけだが、おれは知っている。本当に美しい」
熊千代は手をぎゅっと握りしめ、見た目は笑顔のままだったが、内面は突然、真顔になった。
疑念が浮かぶ。
お坊殿は、珠子どのを見たことがあるのだろうか?あの子を見てそれでも二女どの(熊千代は名前を知らなかった)でよかったと、心から言われるのだろうか?
「使いをして村重どのを訪ねた時に見たことがある。荒木には明智のお岸どのが嫁いでおり、妹御が訪れていた。お岸どのは荒木の側室のだしどのと比べられ、今楊貴妃にはかなわぬなどと言う者もいるが、おれはそうは思わん。さしうつむいて、こぼれる花のごとき風情であった。妹御は……」
そこから先を言わなかった。熊千代は、津田坊の目が霞んで夢にさ迷うのを見た。
「おれも思わぬ果報を得たわ!こやつめ!」
耳をつまんで引っ張られた。
津田坊がうれしそうな顔をしているのを見て、熊千代も心底嬉しくなる。ただ、念を押すのを忘れなかった。
「お坊殿は、三姉妹をみな見られたのですか?」
「いや、おれが見たはお岸どのと、おれの嫁になる二女の聡子どのの二人だけだ」
熊千代はほっとした。
◇
「師匠!師匠!瓢庵師匠!」
熊千代は岐阜城の内部にある茶庭の露字に飛び込んだ。
中では一目見て、堺の町衆だとわかる大男が、うなるような声で同じ商人らしい誰かと話をしていた。
「なんだあいつは。けつのあなのちいせえぐずがよう。だめだだめだ!そんなはした金で手放せるか!」
相手が去ってから熊千代はきいた。
「ぐずとは誰のことだ?」
「悪態は真似すんな。どうだうまくいったんか。どうか。この野郎、きかぬ坊主めが、どうせ失敗したのだろう」
「うまくいったのだ、師匠のおかげだ!」
「ふん、まあ茶の一つでも飲んでけ」
熊千代が猛烈に茶の湯を習いたいと催促してきたので、松井康之は岐阜城をたずね、信長の祐筆(秘書)をしている実の伯父をたずねてみていた。
伯父の松井友閑は祐筆のみならず相談役も兼ね、高名な茶人でもある。
熊千代の様子を見、また藤孝に向けて織田家内部の状況を書き送っているのもこの友閑だった。松井も、この伯父からの指南を受け、茶の湯を修めた経験がある。
熊千代の茶の湯の指南をお願いしたいと問うと、友閑は手を止めずにさらさらと書状を書き進めながら答えた。
「おまえや藤孝どのがいるではないか」
松井康之は言いよどんだ。
「不仲の噂は聞いておる」
友閑は書状を書いては広げ、また次々に書き綴る手を止めないので、彼の周囲には扇のように紙が広がっていた。見惚れるほどの達筆だった。
「どんな覚えの悪い者にも、弟子に対しては声一つ荒げたことのない殿が、熊千代君にだけは感情を止められないご様子なのです」
「藤孝どのは恥をかきたくないのだろう。それも親の情というもの」
やっと伯父は筆をおき、松井に向き直った。
「良い者がいる。変わった奴で、口が悪く豪快だ。熊千代君とは合うだろう。紹鷗の孫弟子で腕は確かだぞ。堺衆に顔が繋げるのもよいだろう」
というわけで紹介されたのが、この堺の町人の大男、山上宗二だった。ゆっくり露地を歩きながら宗二は教えた。
「いいか一期に一度だぞ。一期に一度の会とて亭主を畏敬すべし。もう二度とないということだ」
「明日死ぬかもしれんということか?」
熊千代が岐阜城に勤めている短い間にも、小姓たち、居並ぶ荒武者や大名たちも一人、二人とよくいなくなった。
彼をよくからかっていた少年が、一族の失態の連座になって切腹したという。またある者は貴重な器を壊して、部屋で一人で自害しているのを見つけたという話もあった。常に誰かが、いつの間にかいなくなっていて、後でこれこれこうなったと聞かされる。
死はごく身近だった。
小姓だけではなく、城中を自在に歩き回っている商人たちや中間たち、下人はさらに入れ替わりが激しかったし、斬られるのを見ることも多ければ、死んで倒れているのを見るのも多かった。
「それだけではない。日月は落ちればまた昇り、季節はまた巡り来るように見えてもこの一日、一時、一瞬はすべて違う。そこを流れておる風も空気も、虫の声、鳥の囀り、木の葉の落ちた痕、そしてここよ。内側だ、おまえの考え、おまえの気持ち、我らの関係、すべてが二度同じことはないということだ」
ふといゆびが天から動いて、熊千代の胸にさした。
「天をかける雲から、おまえの内部に到るまで、何一つ同じではない。この茶の一杯、この記憶がおまえのなかに凝縮され、刻み付けられるのだ」
宗二はにやりと笑う。
「因みにな、これはおれの師匠の師匠の言葉だそうだ」
「なんだ受け売りか」
ぎゅうっと口をひねられた。
「うるせえがきめ。ちったあ静かにしておれんのか」
荒々しく言って、無言になり、躙り口から茶室に入ると道具に向かった。この山上宗二の師とは利休、またその師とは武野紹鴎にあたる。
そうか、亭主を畏敬すべきなのだな。
熊千代は背筋を伸ばして座る。不思議なことに、この入り口を入ると、まるで茅の輪をくぐったように、荒れている心も苛立たしさも、背後に落としてきたようになくなった。
集中も学んだ。寺で禅をやっていたから、飲み込みは早い。再度熊千代にひととおり教え、場所を変わって茶を点てる熊千代を鋭い目で宗二は観察した。
我流ながらもかなり練習したとみえ、子供のくせに手慣れた手前だ。一息ついて茶碗をもち、宗二を真似ていちど置いてから少し考え、わずかに持ち上げて置きなおした。
「なぜそこに置いた」
「いかんのか」
「いかんとは言うとらん。理由を聞いておる」
「ここがちょうどよい。手も届くし、見た目もよい」
「少し回したろう」
「ここのちょっと変わった模様がいちばんよい。そいつがよく見えるからだ。茶の湯とは何人もでするのだろ。今は師匠が客なんだから、こいつを見たかろう。この向きがいちばんきれいだ」
宗二は舌を巻いた。
天性のものだこれは。教えてもおらぬのに。
腕組みをすると、大声で言う。
「小僧は筋がよいが、下手に褒めぬがよいか。天狗になっては元も子もない。厳しゅうするから、へこむなよ」
怒鳴るような言い方だが、熊千代はほめられたのがわかった。嬉しさを胸の奥に隠して熊千代はうなった。
「おれはへこんだりせぬ!いくらでも厳しゅうしろ」
帰り道に宗二は熊千代に言った。
「いつかわしの師匠に紹介しちゃる。すごいお人だぞ」
「師匠がすごいと言うのだからそれはすごいだろうな?」
「こやつ」
可愛くてしかたないという顔で宗二は笑った。
◇
信長が厳しく口止めをしていたため、嫡子信忠からも万見仙千代からも、熊千代の意向はもれなかった。
この件についてはあれこれ奇妙なこと続きだったが、信長がまたひとつ不思議に思ったのは、蒲生忠三郎がこの話を聞いて満面の笑顔になったことだ。
「これはまた、幼き身でよき果報を得られたものですな!」
自分のことを棚に上げてそんな風に言ってすましているが、義兄である信忠と何事かささやきあっては、面白そうに一人笑いしている。
蒲生が部屋を辞して廊下に下がると、そこには当の熊千代が真面目くさった顔で背筋を伸ばして控えていた。
あっ!
信長も信忠も見ている前、熊千代が自分の顔を見て大きく口を開けたのを、蒲生はさっと体で隠して扇を広げた。
「これはこれは細川の熊千代どの、縁組がまとまったとか、まことにおめでとうございまする」
氏郷はにこやかに扇を閉じると、嫌味なほどあざやかにまた一礼して、熊千代にささやくように言い残した。
「蒲生忠三郎氏郷でござる。今後ともよしなに」
信長が外から声をかけた。
「なんだ、もう仲良くなっておったのか。こいつはなかなか抜け目ない」
熊千代は顔を真っ赤にして下をむき、蒲生氏郷の名前を反芻していた。
父がいつも、蒲生蒲生蒲生と、こうるさい小言を言ってくるあいつか!
熊千代は確信した。
ますますだいきらいだ!
おれがきらいなのは、松井康之とこざかしい頓五郎、それに蒲生氏郷だと、熊千代は勝手にひとりで心に決めた。
◇
良家の子息としては妙に狡猾な所もある熊千代は、どきどきしながらも家では何食わぬ顔をしていつもどおり放埓に振舞っていた。誰も何も疑っていない様子だったが、ただ、父が何とも不審げな目でこちらを伺うようにじろじろ見てくるのを感じていた。
「熊千代、おまえ上様に何やら失礼なことを申し上げたりはせなんだろうな」
「知らん」
「親に向かって何という口のききかたぞ!」
これは藤孝ではない。彼が口を開くよりも早く、麝香が雷を落としたのだ。藤孝は耳を押さえたくなったが、麝香が恐ろしくて口も出せない。
これでは話もできぬ。
「こちらへ参れ!」
耳を引っ張るようにして、小部屋へ入った。
正座をして姿勢を正すと、熊千代もさすがに神妙に座っている。鼻水のあとが残っているのを見ないふりをして、藤孝は重々しく言った。
「おまえに縁談が来ておる。というよりも上様からの命ゆえ、断ることはできぬ。相手はな、明智殿の三女だ」
熊千代の表情はまるで動かなかったが、目玉が少しだけ揺れたのを藤孝は見逃さなかった。この小僧が何か策を練ったらしきことを藤孝はいよいよ確信した。
再三辞退したのだが、思わぬ藤孝の抵抗に逆に意地になった信長から矢の催促が入り、とても断るという雰囲気ではなくなった。
明智十兵衛は素直に受けたという話も届き、不承不承に藤孝はこの縁談を承諾することにした。
「何を申し上げたか知らぬが、何やらおまえの思うとおりに進んでおるようだな」
何か言わねば不自然だと思った熊千代は、
「明智の娘ならば、もろうてもよい!」
と、でかい声で怒鳴った。
藤孝は、一発ぶん殴りたいと思いながら苦々し気に息子の強情な顔つき(と鼻水の痕)を眺める。
確かに、熊千代は岐阜城にいる間は、親の自分が驚くほど我慢しているように見える。そういう時は、こやつもそれなりに頑張っておるのだなと感心するのだが、一旦、勝竜寺城に戻って来ると鬱憤を解消するがごとく暴れまわり、また些細なことで刀を抜くので始末に困っていた。
奧では刀こそ抜かないものの、弟、妹たちに対する態度はひどいもので、弟には拳骨が飛ぶし妹には手こそ出さないがわめきちらし、結果として号泣と吠え声の嵐を巻き起こす。
多分、外で我慢している分、うさを晴らしているのでありましょうと、これは松井の言なのだが、それにしても……と藤孝は思う。結婚となれば、この家中の大騒ぎを相手の娘は見ることになるのだ!
明智十兵衛の娘がだ。
恥ずかしくて身の置きどころがない。
と共に、こんなとんでもない糞餓鬼に目をつけられた、あの見目麗しい利発そうな娘が心底、気の毒でならなかった。
「よいか、今のままではおまえはな、間違いなく嫌われるぞ」
藤孝は重々しく説教を始めた。
「女子はな、それぞれの性や好みは違うておるとはいえ、主に奥向きでは穏やかなる男を好むもの。十兵衛を見ろ!明智の娘らは常日頃から父親を見て、男というものはこういうものかと見おぼえておるはず。また、明智の左馬之助を見ろ!物静かで折り目正しく、思いやり深く信心深く、教養にすぐれ故実を諳んじ、連歌も見事な出来栄えでこなす。連歌というのはな、いにしえの故実を知らねば恥をかくのだ。武勇は無論、第一ぞ!だがよいか?明智の息女はかような者たちに囲まれて育っておる」
自分で言いだしておいてだが、やはりこんな熊千代を我慢できよう娘がいるとは思われない。
特に、松井康之と仲の良い左馬之助はどこからどう見ても文句の付けようがない。婚約の約定を違えたのを十兵衛自身も残念がっていることから、代わりに姉妹を嫁がせようと思っているのではないかと薄々想像していた。
だがこれで、二女も三女もその希望は潰えたわけだ。
藤孝が、想像するだけのみならず、そのことを口にして語ってきかせると、目に見えて熊千代の顔が曇ってきた。
どんどん暗雲が垂れ込めてくる。
そのわかりやすさもまた不快だ。
「おまえのように、あれはいやでこれはいや、喧嘩ばかりで腹あしく、口は悪ければ手も出る、足も出る、すきあらば刀を振り回す、という、かような、奴が……」
藤孝の説教の声は沈みはじめる。どんどん不安が増して来た。
やはり断りたい。
だが林佐渡守の口調では、これ以上は逆鱗に触れてしまいかねないような気配があった。
娘御に逃げ出されてしまいでもしたら?
こやつがこんなにひどいと、十兵衛に訴えでもされたら。
それを上様に知られでもしたら。
嫁御が嫌うからといって、熊千代が奥向きで機嫌が悪くなりでもされたら、一体どんな大騒ぎになるやら想像もつかない。
耐えがたいのは、十兵衛にここまでとはという(十兵衛はそんな腹を外に見せるような奴ではないが)思いを抱かれたら!
まだ輿入れも終わっていないがすでに恥ずかしい。
明智が熊千代の勇猛さを見初め、この御子ならばと信長に頼んだのだとか、絆をいっそう強固にして、共に丹波攻略にあたるようにとの上意であろうなどなど、様々な噂、思惑がとびかう中で、十兵衛を除いてはおそらく、藤孝だけが、珠子の人としての気持ちを思いやっている人間であっただろう。
「お前がどこぞで娘御を垣間見たか、噂に踊らされたか知らんが、見た目で好んだおなごを無理に嫁にもろうたとて、お前は良いかも知れぬが、娘御にとってはとんだ不幸かもしれぬのだぞ。これを期に、おまえも明智殿に恥じぬように、よおおおおく、よくよく精進せねばなるまいぞ!」
◇
信忠と津田坊(信澄)はいとこ同士で小さい頃から見知っている。年も近く、部屋に入れば儀礼的な態度をすっかり崩し、熊千代の前でも二人して寝転んだり雑談をしたりして遊んでいた。
「降伏した浅井の家臣、磯野の養子に入るという話が出ていたから、おれとて、織田家のためのお役目ならばと覚悟していた。どんなおなごをもらうことになり、どこへ養子にやられてもかまわぬとな。だが本当は、美濃のむすめが欲しかった」
「義母上のようなか?」
津田坊は照れくさそうに笑う。
義母上とは、帰蝶さまのことか?
後ろに控えたまま、熊千代は二人を観察していた。
「三介は取りたくもない嫁を取って、名家の北畠氏を制圧せねばならぬ」
信忠は静かに言う。
「父上は、お気に入りには見境がないところがある。坊はまた妬まれるぞ」
「そう思うなら、いずれおまえが平等に遇せばよいではないか」
四年も前に、信忠の実弟三介(信雄)は北畠氏、三七(信孝)は神戸氏の養子に入り、それぞれの娘と縁組をさせられている。養嗣子になり、家の名と土地、家臣を掌握していわば乗っ取りを行うためだ。
「三介も三七も上様の実子。おれは連枝として皆を下から支えねばならぬ身だ。張り合うつもりなぞないのだがな」
「わたしは父上の言われるがままに為すしか術はない。それは皆と同じことだ。反論を許さぬお方ゆえ」
信忠の言葉には、父である信長に対するかすかな批判が混じっていた。
「とりあえずおれは、国衆をまとめる治世の技も城づくりも、明智どのから習うつもりだ。だが左様なあらゆる知識を総集して天下一の大家なるはそなたの父ぞ、おい、熊千代!」
突然、津田坊は熊千代の方を向いて呼びかけた。
「はっ?」
「さて尋問するか」
「うむ」
あっという間に熊千代は、二人に両側を挟まれ、囲まれてしまった。
「さあ白状せよ」
「明智の三女とはどういう仲なのだ?絶対にもともとの知り合いだろう?おかしいと思ったわ」
「忠三郎も賛同していた。おそらく懇意なのでありましょうとな」
「あ……会ったことが一度もないとは言っておりませぬ!坂本城で会ったり、文などしていないのはほんとうです」
熊千代は抗弁したが、両側からやいのやいの言われて、ついに白状した。白蛇を見たので、追って行ったらその子に変わったのだということを、つかえながらしどろもどろに話した。
「笑うなよ。お坊?」
信忠はこんな時も姿勢を正し面を改めて静かに言ったが、津田坊も笑うことなく真面目な顔をしていた。
「ふうん、それは白山の蛇神かもしれぬな。幸若舞にあるだろう。越の大徳」
斜めに寝転んで肘をついた体勢で、津田坊はかいつまんで教えてくれる。
「偉い上人さまが白山に登られて、伊邪那美神の化身である妙理大菩薩の顕現をみて、白山修験場を開かれた」
「うん。おじいさまが深く帰依しておられたのだよな」
おじいさまとは、信長の父、亡き織田信秀のことだ。
「一説には菊理媛ともいわれるが、こいつは巫女だ。男と女、またあの世とこの世の狭間を取り持つ女神だ。幽玄の存在よ」
熊千代の真剣な顔が可愛く、また面白く、津田坊は起き上がってあぐらをかきなおすと説明をした。
「おれも小さい頃に聞いただけなのだがな。白山には、三千匹の蛇が住んでいてわるさをする。越の大徳さまに諭されて千匹ずつ分けられ、池や剣や山の下に封じられた。だが、追われ逃れて各地へ散ったものもおるそうだ。きっとそなたの見た白蛇は、美濃から来たのであろう。明智殿が親蛇で娘は小へびよ」
「思ひやる越の白山しらねども、ひとよも夢にこえぬ夜ぞなき」
信忠が吟じた。
津田坊が熊千代にささやく。
「おなごに送るやつでな、顔を見たことはないけれどそなたが恋しいという歌だ」
さらに信忠にはずいぶん無遠慮な口調でずけずけと言った。
「松姫であろうが。いつまで待っておる。もうほかに正室を取ったらどうだ。相手はいくらでもいる」
信忠は黙っているので、熊千代ははらはらしながら二人を見守った。
「あの信玄の娘だ。ものすごい、いかつい髭面の大女かもしれぬぞ。使いの者なぞ、姫というだけで美しいと付けるからな」
「……」
「まあいい。これ以上いじめるのはやめる。おまえが好きな女なのだ。戦って手に入れるしかなかろう」
「戦か」
信忠の穏やかな顔がひときわ曇る。
「そうだ!父親はもうおらぬ。勝頼なんぞ異母兄にすぎぬ。勝って勝頼ずれの首を晒し、松姫を奪うのだ。それでこそ男であろう」
俄かに目を光らせ、白い細面の顔を歪めて猛々しい顔つきになった津田坊の方がずっと、信長に似ていると熊千代は思った。
「姫は自害するやもしれぬ」
「文と贈り物で心を繋いでおくことだ。おれは一足先に美女と祝言よ」
◇
うちしおれて何度もため息をついている藤孝に、妻の麝香は眉根を寄せてたずねた。
「何をそんなに反対しておられる。あなたは実は十兵衛殿が嫌いだったのか?向こうが偉くなっておるのが気に入らぬのか?」
「そんなの気にしてるようだったらこんなに親しく付き合っているものか。そもそも十兵衛の並々ならぬ才は他ならぬこのわしが一番よく知っておる。何なら上様より知っておるわ。それより麝香よ、おまえはそれでよいのか?」
「熙子どのの於子ならば、大丈夫」
簡潔に答える。妻のこのきっぱりした所が藤孝は好きだった。浪人時代に手を取り合い、家を行き来して苦境を乗り越えた仲、奥向きには奥向き同士の絆があるのであろう。
「娘というのはな、いわば人質のようなもの。関係強化と言うが、別に関係を強化しないといけないようなそんな軽い仲と思って欲しくないのだ。わしは十兵衛を裏切らぬし、十兵衛はわしを裏切らぬ」
だが上様とてそこまで熊千代に肩入れされるならば、いっそ織田家の娘として養女にしてもらえれば、だがそんな箔をつける意味もないほど今はあちらの方が立場は上だし……。
最後の方は、ついうっかり声に出ていたらしい。耳を捻りあげられた。
「あなたは一体、何も取りもせぬ狸の言うような、いつからそんなになられたか!?城を追われて野を彷徨うても、蟄居になろうと、牢人暮らしをしようと、わたしはあなたを見捨てようなどと思ったことは一度もございませぬ!」
「苦労をかけたゆえ、少しは良い目をと思っておるのではないか!」
「あなたがぐずぐず言うておるわけの一つがわからぬとでも思うか?」
麝香は一段と声を低くした。
「婚礼の!費用を!どう、するのじゃっ!」
さらに藤孝のへこみ方が激しくなった。うなだれた首がもとに戻らない。
「どうなさる!」
「こ、今度、大名たちから、指南の礼金が入るゆえ……」
「焼け石に水じゃ!」
「……」
「うちの金蔵は、からっぽ!帳簿は真っ赤!婚礼となれば、ただならぬ額が必要となりまする。元服に初陣が先であろう、その費用もいりまする、こればかりはもう堺の町衆にも吉田殿にも、まして明智殿にも借金できませぬぞ!」
「金も借りておきながら、むすめももらうとはいやはや、わしもどうしたらよいやらわからぬわ」
「だから切り詰めて早う返しなされっ!あなたのお宝を十か二十か売ればよろしいことであろう!」
「ううう……」
◇
正式な婚約の前に、藤孝は熊千代を伴って明智の坂本城へ内々の挨拶に赴くこととなった。岳父(舅)となるならば、会わせないわけにもいかない。
藤孝の顔が曇る理由はほかにもある。
伏見城に蟄居している、兄にも会いに行かねばならぬ。
兄の三淵藤英は今、頑として臣従を拒んだまま、いまだ伏見城内に閉じ込められている。信長も今は黙っているが、兄がこの先説得に応じるとも思えない。駒として使えぬならば行きつく先はただ一つ、名誉の死を賜るだけだ。
こんな時に、十兵衛の娘と息子の縁談が信長の肝煎りで成り立ったなどと、どの面さげて報告出来ようか。
後悔はしていなくとも、兄を目前にすればやはり苦しいだろう。
義昭を見捨て、信長を迎えた藤孝に、上野の讒言は讒言ではなかった、弟と思って見誤ったと兄の三淵藤英は罵倒し、藤孝を討つため自らの伏見城から勝竜寺城を攻めようとすらした。
柴田勝家の説得にやっと応じて二条城を明け渡した時に、捨て台詞のように言われた言葉がまだ藤孝の中に残っている。
「おまえは明智に会ってから、おかしくなっていった」
織田家中で、似たようなことを誰かが信長に言っているのを聞いたような気がする。
いつも将軍の御傍におり、一門を率いて陣頭に立っていた兄だ。父の家督を継いだとはいえ、庶子である藤孝とは立場も誇りも違う。
──いくさはいくさ。冷酷にならねば、勝ち残れませぬからなあ。
いかにも秀吉の言いそうな台詞が、今は藤孝の中で大きくなっている。
仕方がないことだ。時は遡れなず、覆らないならば、あらゆる業を懐に納め先に進まねばならない。
岩成の死を飲み込んだとき、藤孝の中で何かが変わった。
もはや後ろをふりかえるのはやめよう。
◇
「どこにも出せぬ、まことに恥ずかしき倅なれば……」
坂本城で明智十兵衛と応対する藤孝に謙遜の意図など微塵もなく、手を焼いていることは十兵衛もよく知っている。
「どうか明智殿からも、行儀作法を躾てもらいたい」
丁重にお願いする。
情けなきお顔をなされまするなと、出かける前にも、麝香にもう一度一喝された。かような烈女である姑とうまくやれる娘というものが、この世に存在するであろうか?
「こちらへ」
明智十兵衛は熊千代を手まねいた。
立って開いた襖《ふすま》の向こうには三女、十《とお》になる明智珠子が膝に手をそろえて座っていた。深々と頭を下げる。
「熊千代どの。こちらが珠子じゃ。どうか仲良うして下されよ。あちらで茶でも飲んで、少し話でもして行かれればよろしかろう」
嫁入り前にあっさりと対面をさせる気さくさに、藤孝は絶句した。
十兵衛はほほ笑む。
「我等の仲で今更、遠慮もありますまい」
第八話 終わり
画像(縦書き・ルビつき)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。


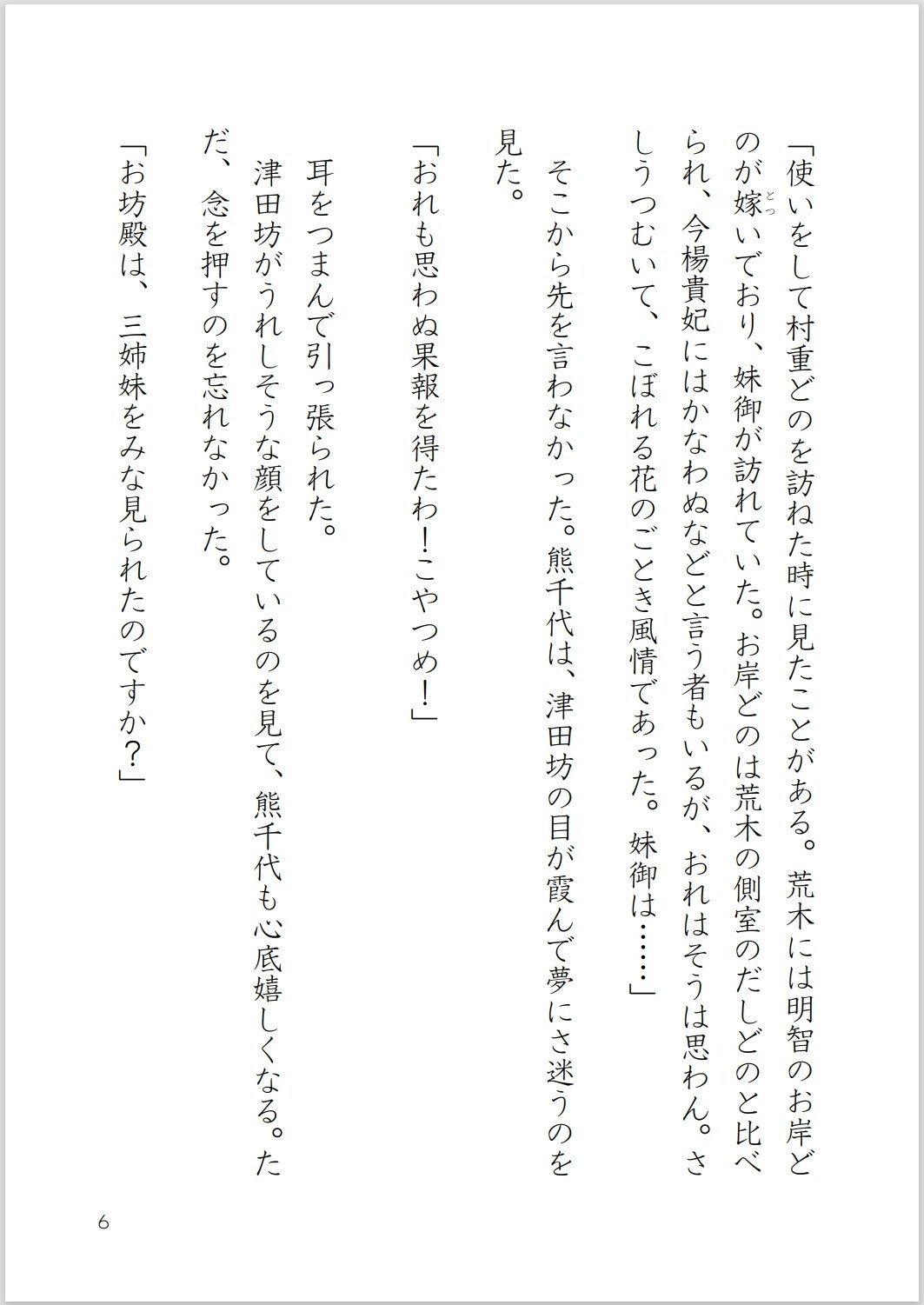






















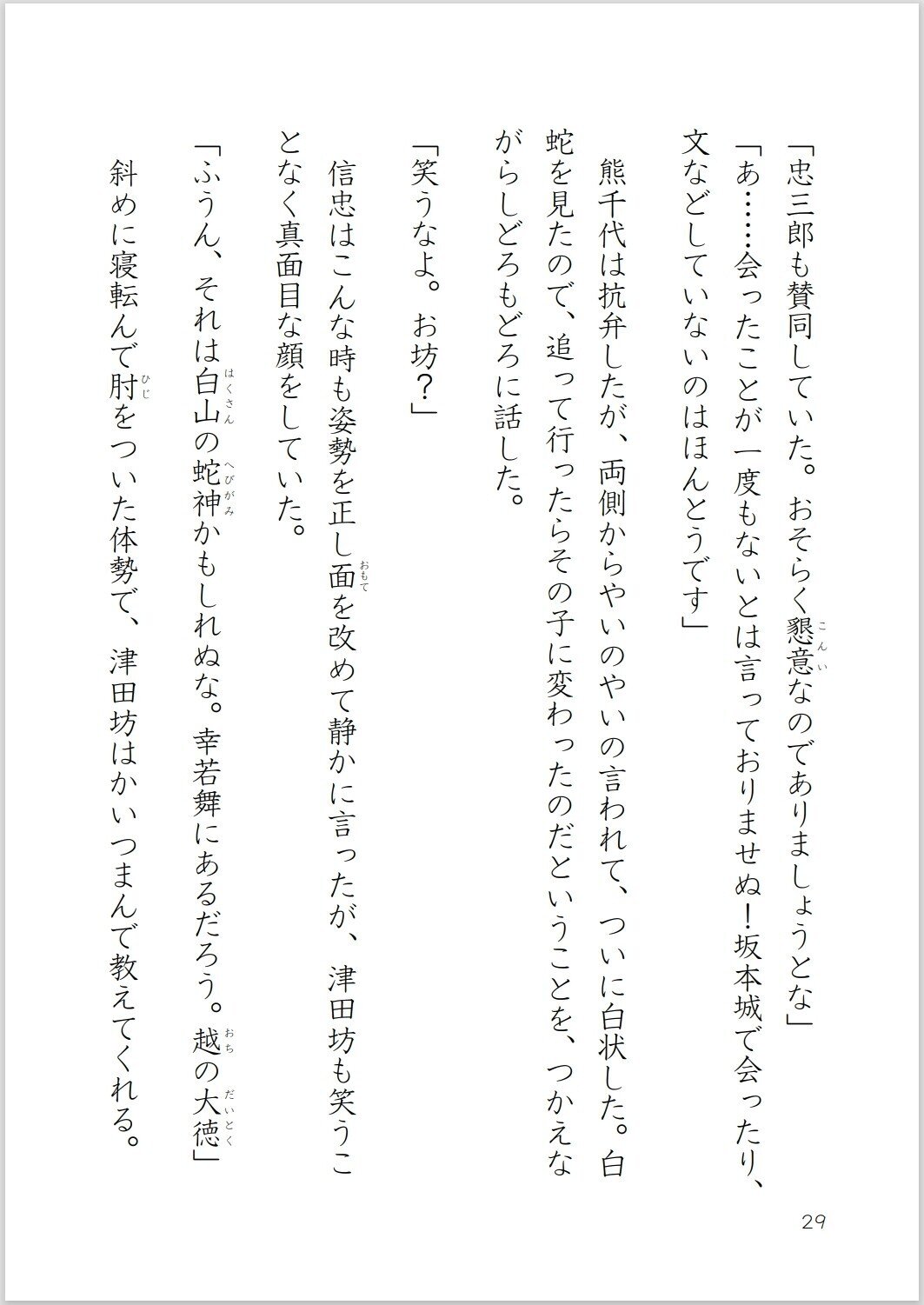





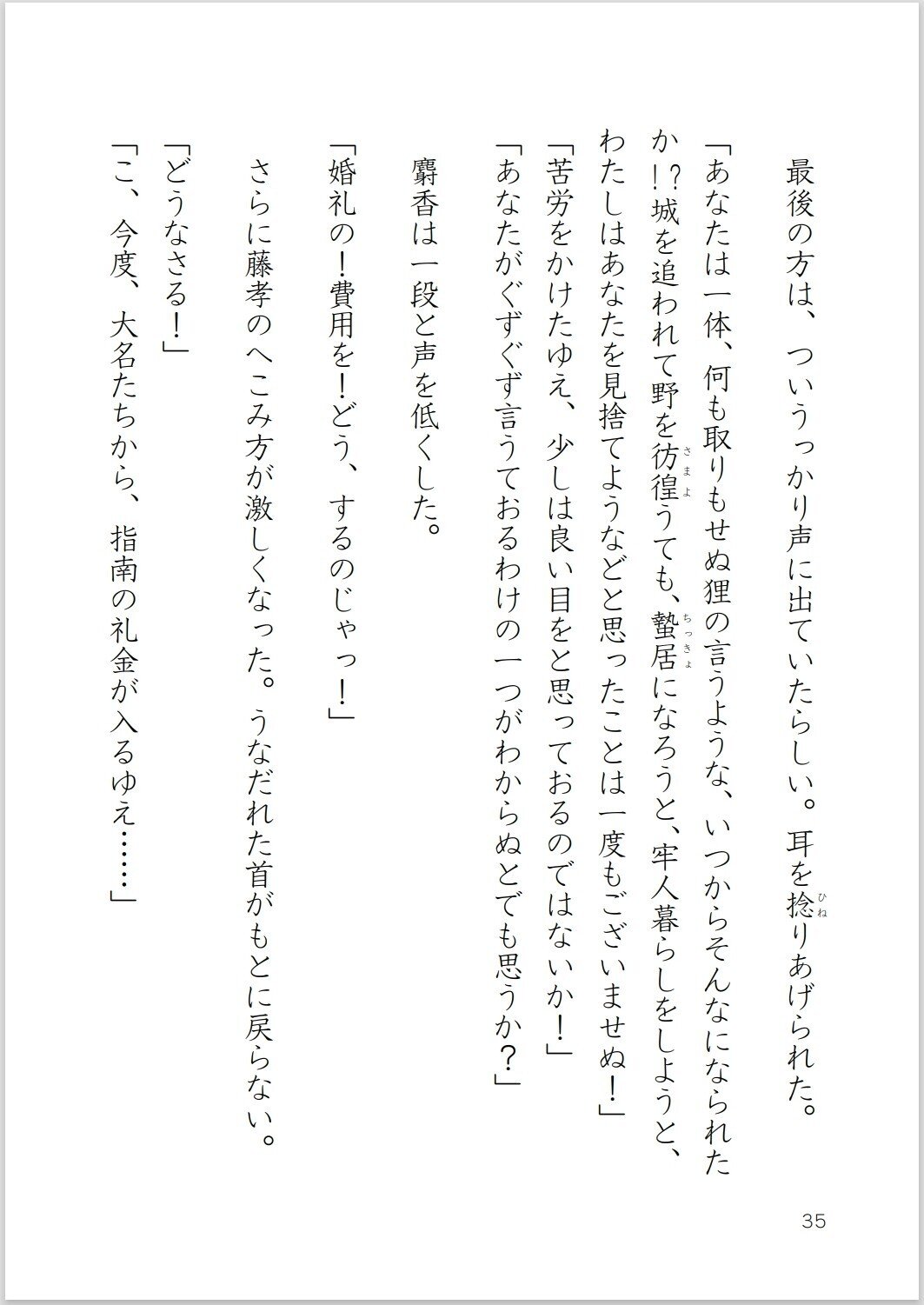

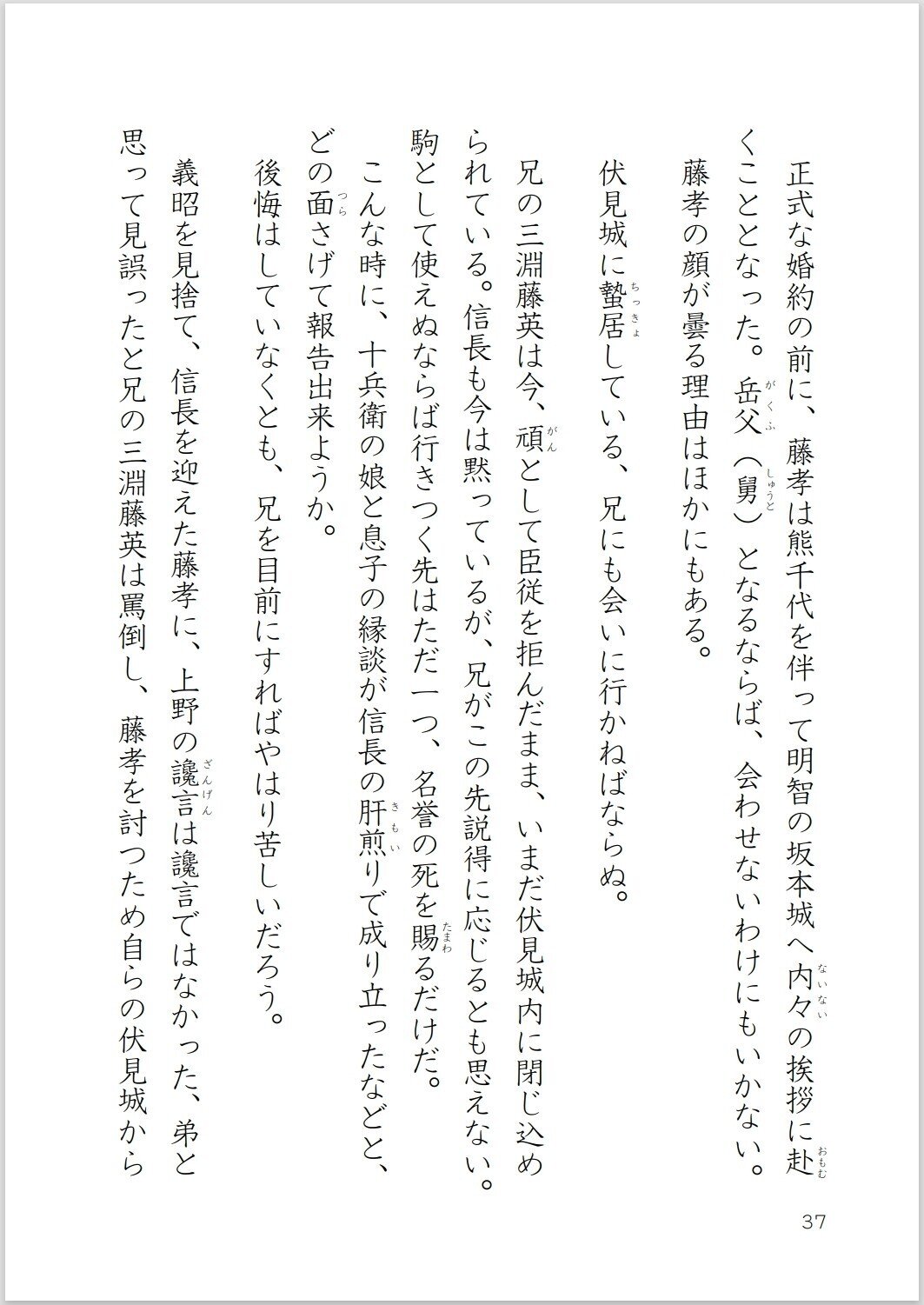




画像。本型。見開き版。
ちょっとテストで、見開き版を載せてみました。





















いいなと思ったら応援しよう!

