
貝と蝶と(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 9)
※画像で「縦書き文」をお読み頂けます。
貝と蝶と
小さな許婚一組を残し、遠慮した松井康之と明智左馬之助は、御簾を下ろしてから主人二人に付き添って控えの間に入った。左馬之助がしきりと首をひねっているので、松井はどうかしたのかとそっと尋ねる。
「先ほど、わたしは熊千代君にものすごい顔で睨まれたのだが、何かお気に召さぬことでもしたかな?」
ああ、と松井はうなずいた。
「気にすることはない。わたしもいつもにらまれておる」
◇
熊千代と珠子はしばらく黙って向き合った。
傍には珠子の乳母らしき老女と侍女が二人、傅いている。
坂本城は勇壮な岐阜城とは違う繊細で壮麗な美しさがあった。山水を描いた見事な屏風絵に、女たちの華やかな打掛の色が加わって、熊千代はまるで別の国にいるような心地がした。
縁談がほぼ確定となり喜びがひと段落したあと、熊千代の中では、さまざまな情報がぐるぐると渦巻いていた。
信忠と津田坊が何気なく口にした話は、熊千代の心を打った。
男とは、好きなおなごが欲しければ力を持ってしても奪うものなのだ。自分とて、知略(と勝手に自負していた)によって得たこの話。
──娘御にとってはとんだ不幸かもしれぬぞ。
不幸なのか、どうなのか、確かめねばならぬ。熊千代は決心していた。
うじうじ悩むのはみっともない。立派な男子の所業ではない!
父が言っていた明智左馬之助とはどのような男であろうか。明智家の娘たちは皆、左馬之助の妻になるのを心待ちにしていたりしたのだろうか。そんなのは我慢ならない。時と場合によっては!
物騒な意図を秘めた目で、熊千代は挨拶がてらに左馬之助をじっと観察したが、思っていたのとはまるで違っていた。顔立ちは凛々しいが、細身で背の高い主人よりもがっしりとしている。容易に動かせない風格があり、松井が好きそうな奴だと熊千代は思った。
◇
少女は目の前に座った熊千代を眺めている。少年の顔は緊張のためか白くなっており、ひどく思いつめた顔色だ。
お珠さま、決して好奇心に負けて、じろじろと上から下まで見たりしてはなりませぬよ、と乳母にかたく言い含められていたが、姉のお聡は笑った。お珠の好奇心は底無しだもの。何から何まで観察するに決まっておる。
「最初に問いたい」
口を先に開いたのは熊千代の方だった。
「おまえはほかに思うておる男でもおありか!この熊千代の妻になって不服はないか!」
熊千代の顔があまりにも真剣なので、珠子はうっすら頬を歪めた。その様は大人の男でも凍りつきそうな艶があったが、熊千代は緊張のあまり気付く余裕がなかった。嘲笑されたかとのみ受け取って激昂する。
「何がおかしい!」
「あればどうするの」
「彼奴を殺す!」
白かった顔にさっと朱が走り、半立ちになって刀を抜きそうな気配に、付き添いの乳母と侍女が顔色を変えたが、珠子は眉一つ動かさない。
そばに置いた螺鈿細工の箱の中から、百人一首やすごろくや貝を取り出して二人の間に並べ始めた。
「不思議よなあ」
ひとつの真っ赤な貝を取り上げて透かした向こうに気色ばんだ熊千代の目を見る。切れ長の目が貝に隠れて片方だけこちらをまともに見る、そのまぶしさに熊千代は心臓が高鳴った。
「りんきの実をあげたではないか。だから悋気(嫉妬)いたすのか?」
とすれば、この子はあの時のことを覚えているのだ。そして相手が細川の子息であったことも知っている。熊千代はいっそう頬が赤くなった。
「寺の坊主は、あれは利宇古というのじゃと言っていた」
「あれはね、おまえが泥だらけで泣いてたからあげたのです」
「泣いてなどおらぬ!」
わめいて足を踏み鳴らすのをほったらかしに、珠子は勝手に話を続ける。
「父上はね、お珠に見られると皆、蛇に遭うた蛙のようだと言うの。ぴたりと止まって動かなくなってしまう。たれもあまりあそんでくれぬ」
熊千代はもじもじしてから、腰から手を離し、またどすんとあぐらをかいて座った。
「さ、何かしてあそびましょう。めおとになるのだからよいのでしょ。あのときみたいにおいかけっこがよいか。おはなしでもするか」
熊千代は少しやわらいでいた。
これはまだ、まるでこどもだ。おなごではない。戦のことも知らぬし、泥と血だらけの世間もあまり知らぬのであろう。
かえって気安くなり、にじりよって再度たずねる。
「のう、おれの妻になってよいのか?」
「しつこい」
「この耳で聞かねば帰れぬ!すきか、きらいか、聞きたいのだ」
少女はきっとなった。
「そもそも、思うた男とは何?どういうのが思うておるということになるの?すきか、きらいかということ?それと、めおとは関係あるの?みな、お互い顔も知らぬのに『とつぐ』のでしょう。そう母上から聞きました」
思わぬ鋭い切り替えしに、熊千代は返事が出来ない。
「わたしは父上のことははだいすきです。でも父上の小姓たちも、同じ年の者も小さい者もおるが、みな遠巻きでじろじろ穴があくほど見てくるだけで、話しかけても返事もせぬし、みんなだいきらいじゃ。おとこはきらい!」
思わぬ激しさに吃驚している熊千代に、珠子は打って変わって嫣然とほほ笑んだ。
「でも、熊千代は違いますね。おいかけっこしたではないか。だからあそんでくれますか?」
◇
明智十兵衛は苦笑した。
「何をはらはらなされているのです」
「いや、うちのはまことに、まことにたわけの乱暴者で見境がないゆえ、おとなの侍女を泣かすこともしばしばなのじゃ。些細なことで火がついたようにかっとなると手がつけられぬ。ご息女が恐ろしいと思われても不思議はない。泣かしでもしたら、いやじゃと思われたら、どうしたらよかろうか。上様に顔向けができぬ」
「では様子を見に行くといたそう」
十兵衛は腰を上げ、藤孝は後ろに続いた。
扇子で顔を隠し、部屋の外から、外に控えている侍女にそっと声をかける。
「如何か」
「仲良う遊んでおられます」
細く開いた御簾の間を大の男が二人、首を伸ばして中をのぞいた。
藤孝は信じられずに目をむいた。
「か、貝合わせ……」
絶句した。眩暈がして思わず柱にすがりついた。あ、あの熊千代が……。
きっぱりした、鈴の音のような声音が聞こえてくる。
「和歌は上の句と下の句を離してもそのままで美しゅう見えるのと、合わせねばまるで意味がわからぬのとあるでしょう」
「ふむ」
熊千代は、歌の合わせ方はわからないまでも、珠子がすでに揃えた貝の形を蝶のように置いて並べた。簾越しに射す、早くも斜めになりかけた冬の日射しを見て、いくつか蝶の片羽を裏返して置いた。
すると、光の加減で蝶が舞っているように見える。
「こうしたが面白い」
少女は手を叩いて喜んだ。
「熊千代は上手いのう。ずっとこのままにしておきたい」
「お珠はこれがすきか」
「すき!すきじゃ」
ぱあっと熊千代の顔が輝いて、とろけそうな笑顔になる。
今日は念には念を入れてきちんと鼻も拭かせ、衣装は熊千代が自分で選んでいた。こうして見ていると、黒の色調に袴から覗く太刀の下緒だけが真っ赤な組紐を用いていて、憎らしいほど洒脱に見え、いかにも良家の嫡男の若殿に相応しい。
しかし、それよりも藤孝が胸をはっと突かれたのは、こんなにも幸せでうちとけた顔をしている熊千代は、たとえ上様の前でも見たことがないという事実だった。
御簾を上げ、十兵衛が中に足を踏み入れると、娘ははじけるように立って、父親の腰にまとわりついた。
立ち上がると、顔の小ささと細さにだまされていたことに気がつく。わりに背が高く、華奢なりの丸みのある体つきに、既に女性が宿っているのを感じてはっとした。改めて眺めた今、十兵衛に顔立ちがよく似ている。
「細川殿がお帰りだ」
「父上、父上。まだ熊千代どのとあそびたい」
いやいやと固辞して力ずくで熊千代を引きずり出そうと思いながら藤孝が口を開いたとき、衣擦れの音とともに、明智の妻である煕子が現れた。
「いかがですか?」
「大事ない」
「本当に?熊千代君は無事でしょうか?参っておられませんか。あの子が何ぞやらかしはいたしませなんだか?」
藤孝は疑問に思う。
うちは熊千代が娘御を取って食うのではないかと心配していたが、明智家の方は、なぜだか熊千代がとって食われてはいまいかというような心配をしているようだ。
「これは、煕子殿」
「細川さま、お久しゅうございます」
内室は手をついて、深く丁寧なお辞儀をした。十兵衛もそうだが、奥方もこちらが目上であった時の事を今でも忘れない。
そんな穏やかな内室が、よほど不安とみえまだ言っている。
「本当に大丈夫なのでしょうか」
「思うたよりも平気そうであった。幼い頃から交われば、熊千代君も珠子はかようなものとわかってくれるであろう」
大人たちの会話は続くとみて、珠子はちょろりと姿を消していた。熊千代がまだ座っている部屋に戻り、二人で顔を寄せて何ごとか語らってはくすくす笑っている。初対面とは思われない睦まじさだ。藤孝はそっちが気になって、会話が頭に入ってこなかった。
煕子は不安気に藤孝の方を向いた。
ここの所、あまり具合がよくないと聞いていたが、病をおして出てきたようだ。
「あの子の執念深さと言ったら、本当に参ってしまいます。侍女たちも泣かされ困らされ、やりこめられまする。あの調子でデモデモダッテを繰り返されては、御子息も参ってしまうのではなかろうか。嫌われはしますまいか」
年嵩の乳母が、堪えきれぬ顔で口を出した。
「質問責めとなるとこれはもう矢の催促、この度のめでたき仕儀も、夫婦とは何か、なぜ自分なのか、上様はなぜ自分のことを知っているのか、どうやって決めたのか。なぜ、なぜ、なぜ!それは大変でござりました」
しまいに珠子はふと、それは断ることも出来るのか、と尋ねてきて家中すべてが血の気が引いたことまでは、女衆たちはさすがに口を噤んで言わなかった。
「わたしもあれをひどく甘やかしてしまったゆえ、いつまでも子供で困りまする。これから武家の妻になる心得を十二分にといて聞かせねばならぬ。嫁入り修行はこれからです」
「いや、そのような……」
「こんな世の中ゆえ、どうなるかもわからぬが、末頼もしい立派な御子息。まことに良縁を頂いたと思っております。どうか細川殿にお珠をお頼み申したい」
本当はあまりしばしば会わせぬがよいのだ、と藤孝はひそかに考えた。
そうだ十兵衛の言うとおり、明日もわからぬ世の中、ましてあの麗質だ。何事かあって、ぬか喜びになっては熊千代が哀れというもの。熊千代だとて、どこかで病を得るか、戦で功を焦って何ごとかあるなりすれば、嫡男は次男に挿げ替えねばならないのだから。
◇
帰り道に、来た時と同じく、明智左馬之助が城外まで付き添った。松井康之は明智家とは一定の距離を保っている。十兵衛もそれと察して何事も言わないが、そんな松井も左馬之助だけは別格であるようだ。親しく囁き交わす姿があった。
この右腕の甥がいる限り、明智家は安泰であろう。しかし、もう二十をとうに越えた壮年となっているのに、十七であったお岸をもらいそこねてから艶聞のひとつさえ聞こえてこないのはどういうわけだろうか。挨拶をする姿に、今回の婚約に対して何ら蟠りを持っている様子はなく、十兵衛の寵童であったとか、衆道の方を好むというのはこれは単なる噂に過ぎないらしい。
その左馬之助の背後に、もう一回り若い侍が控えているのを見て、藤孝は首を捻る。確かにどこかで見た顔だった。それも、敵側として見たのではなかったか。
あれはつい数ヶ月まえ、一乗谷で滅んだばかりの朝倉の家老、山崎吉家の眷属ではあるまいか。
心を読んだように、十兵衛は言う。
「山崎どのの甥御でござる」
「吉家どのの一族は、一乗谷で討死なされたと聞いたが」
「甥御は柴田殿にお願いして一命を助け、こちらに引き取り申した。昔、山崎家で子息の武術指南をしたことがあってな、その縁です」
明智はその場で彼を呼んで、藤孝に挨拶をさせた。
十兵衛にはこういう所があった。家中の将はいついかなる事が起きようと、いずこへも士官できるよう、主に遠慮せずどこにでも顔を売れとの配慮なのだ。市政では敗残の兵は皆殺しになり、妻子は売り飛ばされると思われがちだが、嫡男は連座しても次男以下および三男から下の子供は、降伏し恭順の意を示せば許され、国衆や家臣を束ねて仕えるのが一般的だった。
明智の家中はそういった、雑多な人材であふれていた。
「配下が多くなり、家中をまとめるのが大変です」
「そなたならば問題はなかろう」
明智家中は美濃の兵よりも、すでに近江周辺の者の方が多いように見える。また、幕臣として仕えていた下士たちの顔もそこかしこにあった。麝香の弟、沼田光友がおり、米田の息子是政がもらったばかりの妻は煕子の姪だ。複雑にからみあう縁戚関係を形成するのは大名だけではない。配下の家臣たちもまた同じだった。この中で熊千代とあの娘の縁組は不思議な縁につながれた最後のくさび、明智光秀と細川藤孝が切っても切れぬ仲になったことの証であるような気がした。
あまりにも強い結びつきが不安でもあり、だがどこかでこの不思議な男の運命に絡め捕られていくような愉悦もある。
◇
麝香が無駄を許さず、家計を締めるだけ締め上げたので、熊千代はやっと岐阜城の麓に借家を持つことができた。小姓部屋のすし詰め状態から解放されてほっとする。
これほど困窮しているのは、藤孝が勝竜寺を気合を入れた二重堀に改修したからでもあった。この土地は摂津と山城の堺近くに位置した要所でもあり、軍用の費用も並大抵ではない。十兵衛の援助がなければ完成も難しかっただろう。
家人は二、三人しか置く事は出来ないが、熊千代のそばには有吉がずっとついていた。
お付きがあのようなばかで大丈夫か?と半笑いで聞いてくる朋輩に対して、熊千代はむきになって言い返す。
「四郎右衛門はばかではない!詫びて訂正せよ!」
「ばかではないか。何を聞いても返事もせぬし、ぬぼーっとただ突っ立っているだけ!この前は川で溺れかけたそうではないか。家臣の質が知れたものよ」
当然、取っ組み合いの大喧嘩となった。
有吉は幼名、万助を元服して四郎右衛門立行と変えていた。
父、藤孝は岐阜と勝竜寺を行き来するのに有吉だけではさすがに不安だったとみえ、隣接する高槻城の高山家に頼んで、ここの嫡男と往来時に機会が合えば同行するよう頼んでくれた。
「高山彦五郎と申す。熊千代君にはどうぞ宜しゅうに」
礼儀正しく挨拶をした二十の若武者をはじめて見たとき、熊千代はぎょっとした。
彼は今人気の南蛮渡来の天鵞絨を用いた外套を羽織っていたが、それよ驚いたのは、彼は若いのに顔も手も傷だらけだった。袖口からも見えるほどで、特に首にはまだ癒えきっていない赤黒い生傷が口を開いており、その傷は後頭部から始まってほとんど首半分を回っている。その傷の上に、真っ白な数珠が取り巻いているのが、よりいっそう奇怪な印象を与えた。胸に下がっている数珠の先には十字型の鋳物がついて揺れていた。
熊千代が遠慮も何もなく、まじまじと彼を見ていると、高山彦五郎右近はほほ笑んだ。
「わたくしは南蛮教。熊千代君には、お珍しいか」
「いやそうではない。その……」
「ああ、この傷の方でござるか」
「痛まぬのか?」
「もう、大方よくなった。もはや痛みませぬ」
こともなげに言う彼を、熊千代は尊敬する気分になった。熊千代は岐阜城で見慣れている南蛮服などより、はるかに傷の方に興味があった。しげしげと見ては触れたがりさえする始末なので、高山右近は快く傷にまつわる逸話を話してくれた。傷跡はまだ生々しく、縫い合わせた痕に血が黒くこびりついている。
高山父子の主君だった和田是政の戦死後、仕えていた息子の和田惟長が高山父子の殺害を計画しているという。父子は荒木村重に相談、後援を得て惟長と右近(彦五郎)が話し合いに入った。
「心苦しいとはいえ、趨勢は最早変えられぬ。義昭さまをお見捨てする覚悟で信長さまにお仕え頂けるよう、最後の説得に上がりましたが、聞き入れてもらえなんだ。刀を抜き、お互いに切り結ぶうちに灯火が倒れて、あかりが消え申した」
右近の言葉は静かで淡々としている。
暗闇の中で、声と気配だけを頼りの闇雲な立ち回りの中で、右近は首にぬるぬるしたものが流れるのを感じて手をやった。痛みすら感じなかった。灯火が付けられ、血だと気付くより前に、右近は昏倒した。運び出された時には大量の血を失っており、傷も深く、もう駄目だと思われたが右近は奇跡的に回復した。
和田惟長も重症を負い、熊千代の叔父、藤英の伏見城まで逃げ落ちたが死亡したと言う。
荒木村重と細川藤孝が、揃って信長を逢坂の関で出迎えるのは、この事件のわずか十八日後のことだった。
「去年の話でな」
「それで、そこまで癒えたのか。すごいな」
「如来のお導きでござる」
右近は目を閉じ、額から胸、左肩から右肩へとわたる、不思議な印を切った。熊千代は妙な顔をする。
「それは何だ?」
「祈りの作法でござる」
「おれも九字護法ならば切れるぞ。出陣するときにうまく出来るよう、練習したのだ。臨・兵・闘・者・皆・陣・烈・在・前!」
あまりにも右近が笑うので、熊千代は気を悪くした。彼が南蛮教について、最初に触れたのは、このとき彦五郎右近が語った十字についてがはじめてだった。
だが右近は南蛮教についてはそれ以上突っ込んで触れようとせず、話は首の傷に戻っていった。十も違うのに右近は決して若年扱いをせず、大人に話すような調子で話した。
「荒木にけしかけられたのではないかと、藤孝殿は気にされるが、わたしは自ら選択してやったのです。公方さまと惟長どの……二重の主君への裏切りです。この罪は傷とともに私が負うていかねばならぬ」
だしぬけに熊千代は激しい口調で怒鳴った。
「それは彼奴が悪い!成敗されて当然だ!だから伏見の叔父上(藤英)も、ずっと蟄居になって出ては来れぬ」
「熊千代君はそう思われるか」
「主君を見捨てたというならば、父上とて同じこと。だがそれの何が悪い?誰がもっともお仕えするにふさわしいかは見ればわかる。信長さまにお味方するは当然のことだ。彦五郎、そなたは何一つ気にすることはないぞ!」
十の少年に慰められて、高山右近はまた笑ったが、かすかに表情に暗い影が射した。
別れ際に、右近は一言言い残した。
「熊千代君は、明智様のご息女と御婚約が整ったとのこと、明智様には南蛮教のことは話されぬがよろしかろう」
「そうか?」
「あまりお好きではないようなので」
熊千代はこのやり取りのことをあまり深くは考えず、素直にただうなずいた。
第九話 終わり
画像(縦書き・ルビつき)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。
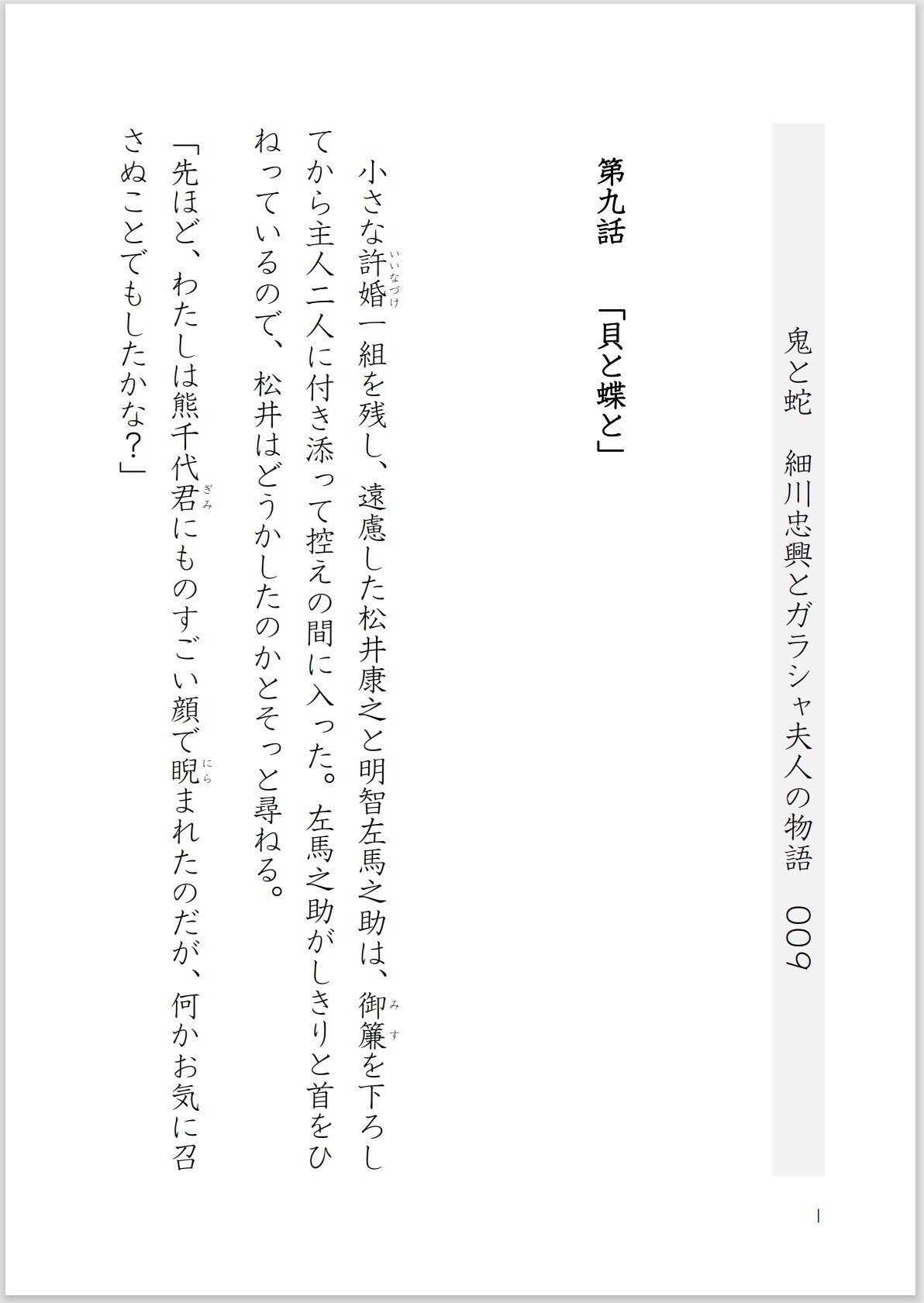
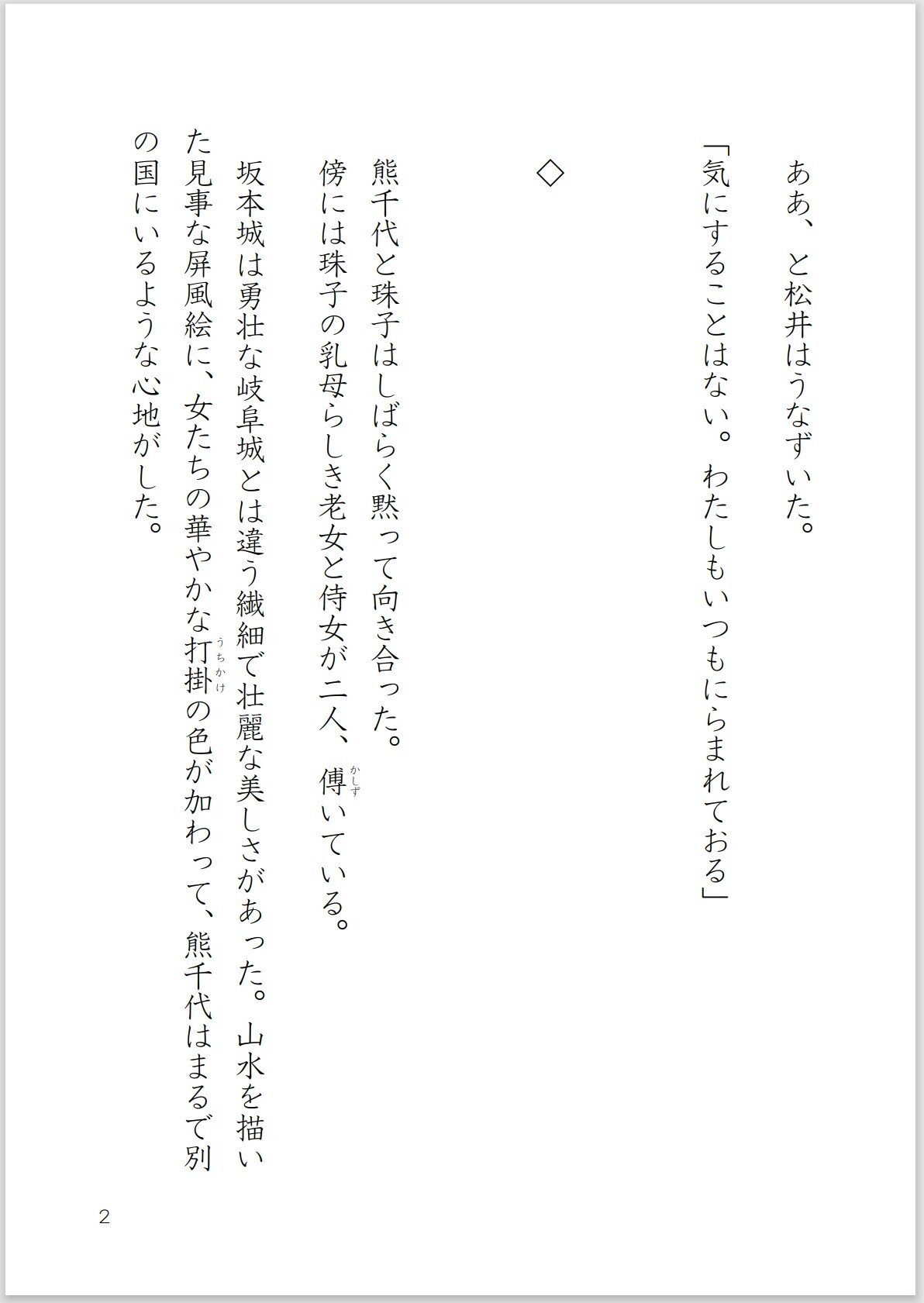






















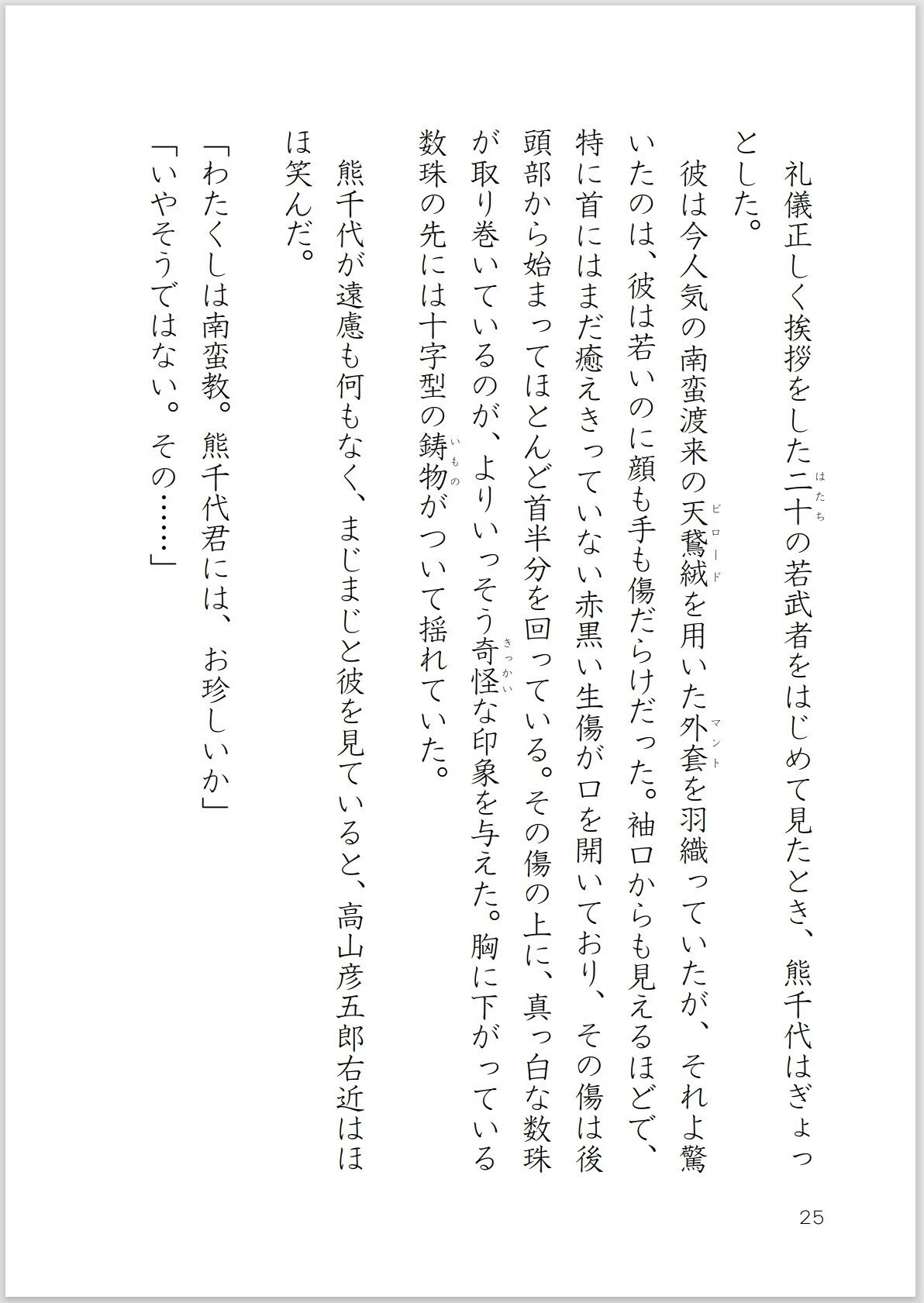






画像。本型。見開き版。
ちょっとテストで、見開き版を載せてみました。







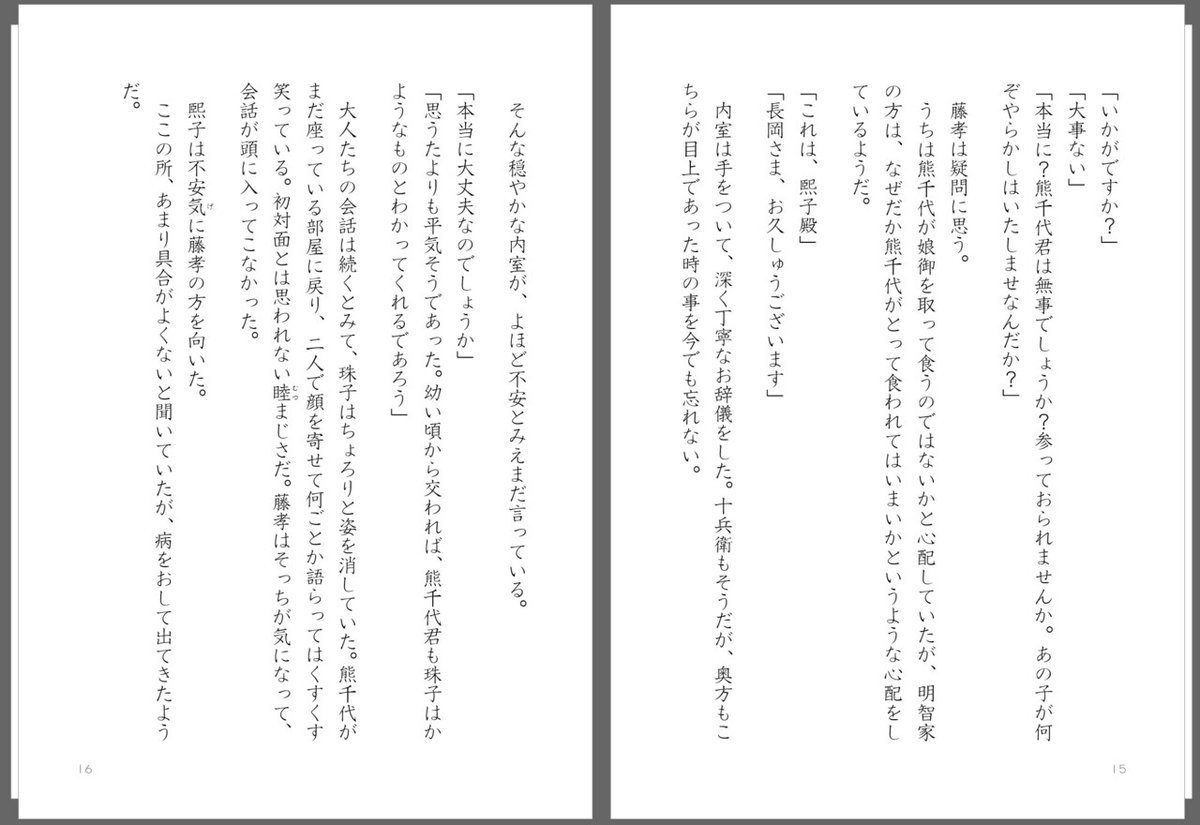








いいなと思ったら応援しよう!

