
上つ方への御挨拶(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 6)
※画像で、「ルビつき・縦書き」をお読み頂けます。
上つ方への御挨拶
鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 006
第六話 「上つ方への御挨拶」
熊千代は岐阜城の前に立っていた。
見上げるように聳え立つ山の中に、複雑に絡み合いながらとぐろを巻いた龍のように、鮮やかで壮麗な館が天守へと繋がっていた。
ついに訪れた「上つ方への挨拶」だ。
あの高名な信長公に会える。どんな言葉をかけられるのだろう。
さすがの熊千代の胸も、朝からどきどき高鳴りっぱなしだった。
珍しく母が世話を焼いて、服装を模様から折り目まで、細部まで厳しく点検している。もともと身だしなみにうるさくはあったが、今日はとみに入念だ。
熊千代はこっそり米田是政に聞いてみていた。
「上様とはどんなおひとだ?」
「それは恐ろしいお方と聞き及びます」
松井に聞くといらんことまで長々とおしゃべりがはじまって、情報過多でいやになってくる。有吉はなにも話さない。松井、有吉に次いで米田氏もいつの間にか勝龍寺城に屋敷を構えていた。それが今の激動の京都の政情に関わっているからだと、熊千代も薄々はわかっている。
母の荒っぽい手つきがあちこちしわを伸ばし、帯をぎりぎり締めあげるので熊千代はうっと喉がつまる。
ふと、母にたずねてみた。
「お目見えのとき、言うてはならんこととは何だ」
「ない」
麝香は短く言うと、熊千代の背をバンと叩いた。
力が籠っているその言い方と背の痛みが、熊千代にはどうやら母が臆するな、と言いたいように聞こえた。蝉の声がやかましい。
七月ももう、終わろうとしていた。
◇
正月に明智十兵衛光秀と重ねた密談で、能では熊千代に痛い目に合わされた時期から、藤孝には目まぐるしくも胃の痛い日々が続いていた。
不気味に存在を示し黒雲のように迫る信玄を、義昭、浅井朝倉勢のみならず、信長に敵対するすべての人々が待ちわびている。信長派と見なされている藤孝は、一挙手一投足に細心の注意を払わねばならなかった。
そんな時勢の中で明智十兵衛は、二月にはもう公然と義昭を離れた。信長の一軍として、義昭が動かした今堅田の一揆に水軍で参戦したのだ。
十兵衛は信長を選んだ。武田を物ともせず真っ向から手向かう態度を表明したこの行動は、他に比べればごく小さな戦闘ではあったが、影響は大きかった。流れが変わる。
激した義昭は信長に対してついに追討の教書を出し、信長も応じた。京に軍勢を率いて向かう。
その時だった。
信玄が死んだ!
死をかたく秘するよう言い残したという信玄の遺言だが、隙間をぬって知らせは野火のようにあっという間に広がった。
京は鎮圧、義昭は追放され、間髪を入れずに行動を移すつもりの信長の前にはこれから浅井、朝倉攻めが控えている。
まるでこうなることを知っていたかのような十兵衛の覚悟の離反、義昭は、『何か』に見放されたのだ。
あの頃の騒然とした明日の形勢もわからない日々からまだ数か月しか経っていない。こうして信忠の元服挨拶に訪れることが出来るとは、藤孝にも信じられない思いだった。
◇
活気ある生き生きとした岐阜の城下町を抜け、広大な庭園と煌びやかな武家屋敷の一隅を抜けていく。熊千代は楽しくて仕方がない。
藤孝の目からしても、岐阜は京よりもずっと治安よく統制が取れている。誰もが笑顔で目に輝きがあった。
謁見のための広間に入ると、藤孝は、熊千代を下座に置いてまずは挨拶をした。
柴田勝家が信長の側に控えている。
じろりと藤孝及び熊千代を流し目で見て、すぐに視線を前に向けた。そっぽを向いたようにも見えた。
義昭が信長を迎え撃つため槙島城へ退去した後、藤孝の兄である三淵藤英は二条城の明け渡しを断固として拒み、どうあっても出て来ようとはしなかった。どうしてもと言うならば火を放ち、踏み込んでこの首を取ってからにすべしと言い放つ。
藤英は三日間、粘りに粘ったが、ついに柴田勝家の説得に応じた。
柴田が、幕臣の中でも見上げた覚悟の武将、と兄を誉めていたことを藤孝は知っている。
兄は、藤孝が義昭を離れ、信長についたことを烈火のごとく怒り、自らの手で討ち果たすと一時は青竜寺城に向かおうとしたと聞く。
この場で藤孝は山城国長岡一円の知行を許され、一万石の加増を賜った。
「望外の幸せ、有難く承りまする」
有難く受けつつも、これほど旧い幕臣の身でありながら、掌を返した裏切者。兄の覚悟とは大違いだと、柴田の、周囲の逸らした視線が語っている。
年を経た後世ならばいざ知らず、この頃の藤孝はまだ、それが何だ!と突き放せるほど吹っ切ることが出来てはいなかった。胸は苦さでいっぱいだ。
ただ、蛙の面に水を流したような何事もない気配の涼しい顔は、内裏や公家衆近くで過ごした彼にとってはお手のものでもある。
不安を抱えながらも素知らぬ体で、熊千代を振り返り、前に出てこさせた。
「わが嫡男、熊千代にございます」
熊千代は両の拳を床にあて、前にいざり出てて礼をする。
「熊千代にござりまする!」
◇
いざとなれば熊千代は度胸が据わった。しっかりと礼をする。腰を低くした丁重な父親とは違い、不敵にまっすぐ、睨みすえていると見えるほど信長の顔に真正面から、目と目を合わせて向かいあった。
「うむ、よいつらがまえだ」
顔見せだけのつもりが、信長は一目でたいそう熊千代が気に入ったようだった。笑顔で扇を開け閉めしながら、軽口で熊千代に直接語り掛ける。
「お前はまだ寝小便も抜けぬうちに、早くも合戦の真似ごとをしたらしいな」
石合戦のことを言っているらしい。
藤孝は、あんな小競り合いが信長の耳にまで届いている、また覚えているのかと肝が冷える思いをした。
さては十兵衛だなと、ひそかに疑うが、信長はあっさりと言う。
「藤吉郎が言うておった」
どうやら先手を打たれたようだ。
「まだ小さい故まさかそんなわけはない、嘘であろうと言う者たちもおるが、この話は本当だとな。あの時は佐久間と浅井長政ずれも喧嘩しておったわ。荒くれどもには困ったものだが、かような童の身で喧嘩を仕掛ける奴がいるとは思わなんだぞ」
そういうことに、なっているのか。
思わず藤孝は梅干を思いっきり噛んでしまったような顔になったが、近習の小姓たちも柴田権六も、みな笑顔でこちらを見ている。
熊千代は、よくわからないが褒められていることと、上様が上機嫌だということだけはわかった。目を輝かせて鋭い目で眼前を見つめている。
信長は、上座を離れると熊千代の前まで来る。顔を覗き込んで問いかけた。
「お前は父母と離れても平気か?」
「はい!」
「母が恋しゅうはないか?」
「おれ、わたくしは、騒乱の中で野放図に育ちましたゆえ、父母などあってなきがごとしでございました!」
「これ!」
「ははははは」
信長は気持ちよく笑う。
「はっきりした坊主だ。では、城づとめもできるか?」
「はい!」
「よし、では信忠の小姓として仕えよ」
よくわからないが、熊千代はとても幸せな気持ちだった。
「ありがたき幸せに存じまする」
大声で答え、完璧に作法にかなった礼をした。手の付き方、頭の下げ方、文句ない。
肝心の藤孝が驚いた。子息を小姓に上げるのは、人質でもあるが信頼のあかし、いわば、幹部候補生と認められた証拠でもある。
最後まで歯向かった兄、藤英のこともあり、よくて放免、悪くすれば人質として置いていけと言われるのではないかと思っていた。
中でも信長と信忠の小姓は数も限られていれば、特に目に叶った者だけを置くため、若手にとっては熾烈な争奪戦の末に手に入る役職だ。
信長ではなく、信忠の小姓であったのも藤孝にとってはありがたい。次期織田家の当主の周囲につなぎを作り顔が売れる、最高の位置であるとひそかに算段する。
信長が振り向いて命じた。
「仙千代、あとで奇妙のところに連れて行き、城内を案内してやれ」
えっ?
藤孝は思わず変な声を喉から出してしまった。
今日から!
準備が……心得が……教育が……。暴れ者が……。
眩暈がしてきた。ぐるぐる天井が回る。
いつもどこ吹く風と平静でにこやかな顔を崩さない藤孝の不可解な動きに、柴田勝家まで妙な顔をしている。
ついつい、いつもの苦い顔で熊千代を横目で眺めてしまった。
こやつ本当に、大丈夫なのか?
わしもただ単純に喜んでいたが、これが実は我が家の命取りとなるようなことにならぬだろうな?
「心配するな、親父どの」
柴田がうなるように言う。
「性根の座った子息とお見受けするわ。子供はすぐ慣れる」
「権六は子供の世話は慣れておるからな」
家老の林が嫌味とも軽口ともわからぬような口を出すが、本人は返事もせずに知らん顔をしている。
肝心の熊千代は、緊張もなく大胆で、しかも嬉しそうだった。
これは面白いことになったぞ。おれはしばらく、ここにおれるのか。
そんな熊千代の表情を見守っていた信長の機嫌もさらに良くなる。
信長はおよそ藤孝が見たことのないような笑顔で、熊千代を近くに呼び寄せ、さまざまなことを聞く。
「ふむ、和歌は嫌いか」
「きらいでござりまする!あのようなぐじぐじとした色恋などしたくありませぬ!」
「これはしたり、苦労するな、これは」
「親父殿が困った顔をしてござる」
いつもは京のよそ者めという顔でななめに見てくる織田家中の古強者まで、笑いながら顔を見合わせている。
「古今伝授の和歌の達人が、息子殿にはしてやられるな」
熊千代の目は輝いた。
よくわからぬが、ここのひとたちはみんなすきだ!
上様はとくにすばらしい。
立派で、堂々として、煌びやかで、神のごときお方だ!
信長はさらに親しげに言う。
「おれはな、おまえを見たことがあるのだぞ」
「まことでござりまするか?」
「おうさ、二条城の落成式でな、お前は『猩々』を舞ったのだ。おれは小鼓を打っていた。記憶にないか、小さかったからな」
「覚えておらぬとは、おれ、わたくしは自分をけしからん奴だと思いまする!」
「ははははは」
信長は額に眉を寄せて大真面目で言う熊千代の顔がおかしかったと見えて、大笑いしている。
「普請場では合戦にて一働きした上で、落成すれば何食わぬ顔でひとさし舞っていたというわけだ。大器よのう、親父殿」
藤孝は顔が赤くなるのを感じた。
弟の玉甫が寺で四苦八苦してなんとか仕込み、やっと舞わせた舞だった。それなりに何となく形になっていたので、うまく誤魔化せたかとほっとしていたのに、そのような噂の中、そんな目で見られていたのだ。
ここが殿中でなければ、頭を抱えたい。
「お前の舞は筋がよい。また披露して見せよ」
「はい!精進いたしまする!」
◇
「どけ、邪魔者めが」
誰かにきつい声をかけられた。
小姓部屋へ向かう途中、万見仙千代が誰かに呼び止められたので、熊千代は少し離れた渡り廊下で外を眺めていた。庭園の樹木の間からは城下の賑わいが覗き見える。ここは標高が高く景色は実に見事で、熊千代は見惚れていた。
そこに不愉快な声を上げられたのでむっとする。さらに押しのけるよう乱暴に突きのけられて、熊千代はかっとなった
睨み据えると、今度は後ろに付いている少年が咎めてくる。
「何だその面は。こちらをどなたと心得ての顔か」
「おい、よせ」
誰かが間に入ってきた。仙千代ではない、別人だ。
突き退けたのも咎めたのも、かばったのも皆、十五、六の少年だった。
「こやつ、今日入ったばかりだろう。新入りには親切にせねばならぬ」
「偉っそうに」
相手が吐き捨てるのをよそに、間に入った少年は、体で熊千代を隠し、
「こら!」
こつんと扇で頭を叩いて見せたが、ちっとも痛くはなかった。寸前で扇の音をたて、前髪には柔らかく触れただけだ。
咎めた方は荒々しいすさんだ顔つきだったが、こちらは気持ちのいいすっきりした顔をしている。熊千代を引っ張って横に連れて行き、たずねた。
「おれは津田の坊丸。おまえは細川の熊千代か」
そうだと答えると、声を低くして諄々と諭す。
「廊下を渡る時は注意せよ。前から来る先輩は避けて礼をし、いちど戻って通り過ぎるまで待たねばならぬ。目をつけられては、今のようなことになるゆえな」
熊千代は素直に頷いた。
「津田の坊丸どの、ありがとうござりまする!」
「存外に素直な奴」
相手は笑った。顔も立ち居振舞いも、どことなく上様に似ている。息子の一人だろうか。あの乱暴な方は、実に嫌な奴だった。
万見仙千代が後ろから小走りで近づき、軽く礼をする。津田の坊丸は鷹揚にうなずいた所を見るに、どうやら彼は仙千代よりも偉いのだ。
「こやつが新入りだな。仙千代、あとは良い。おれが案内する。お前も忙しいだろう」
「お坊どの、ではお頼み申しまする」
「立派になられまして。爺は嬉しゅうごぞいますぞ」
振り向くと、背後には柴田権六勝家が立っている。
「柴田の爺!」
津田坊は笑顔をみせ、勝家も強い髭面がほころんでいる。先ほどまでの硬い表情が嘘のようだ。歴戦の武者と聞いている柴田勝家がこんな顔もするのだなと熊千代は思う。
津田坊は、ああ、と伸びをして放言した。
「おれも早う元服したいわ。かような城うちづとめの采配だけでなく、戦に出たいぞ」
柴田はふっと真面目になった。
「まずまず、よう信忠君と三介さま(信雄)、三七さま(信孝)を我慢してお待ちなさった。次はすぐに来ましょう。殿がことのほか若を手放しがたく、信頼されておりますからな」
「じれったいことよのう」
◇
津田坊に連れられて熊千代はさらに奧へ向かう。すれ違う人々の中に、きらびやかな上臈たちが多くなった。下働きの下男、下女たちも入り乱れて働いている雑然とした様子でありながら、風紀が乱れている気配は露ほどもなく、ぴりっとして、統制が取れている。何よりも活気がある。
信忠と名を変えたばかりの信長嫡男、奇妙丸はなよやかな貴公子然とした若者で、優しい口をきいた。
「父上にいきなり言われて驚いたであろうが、ゆっくりと慣れていけばよい」
ひっきりなしにあちこちへ頭を下げ続け、最初の方は気を付けていたがそろそろ、記憶の中での顔と名前が一致しているかあやふやだ。
「横におられるは、奥向きの長であられる御方さまだ」
顔を上げた熊千代は、その奥向きの長であるという婦人よりも、下座にひっそりと控えている影にあっと声をあげた。
「明智殿!」
岐阜城の中でも奧深くの屋敷内で、こんなにも親しく見知った顔を見るとは思わなかった。相変わらずの穏やかな優しい笑顔をしている。ほっとして、思わず飛びつきたいような衝動に襲われたが、熊千代は堪えた。
「さてもお疲れになったことでござろう」
婦人が説明してくれた。
「十兵衛はわらわのいとこじゃ。幼なじみでもあってのう。先ほどまで、そなたの話を聞いておりました」
「父上への謁見は、どうであった」
信忠が笑いながら問う。皆、信忠よりも信長の方の挨拶の方が緊張もするし、恐ろしいとわかっているのだ。
「素晴らしいかたでございました」
「だから申したでありましょう」
「ほんに、この御子はまさに殿のお好みじゃ」
熊千代の鋭い眼は、さっと右、左へと動き、皆の表情から力関係を読みとろうとする。それは、石合戦で周囲をうなりをあげる石つぶてを見ていた時も、坂の上から動きを眺めていた時も同じだった。
ひとみを動かすことなく、表情を変えることなく意識を広げて全体を見る。目を動かし、顔色を変えてしまうと、相手に次の動きを悟られるからだ。
十兵衛は、津田の坊丸に丁寧に頭を下げた。
「お坊どの、熊千代君のこと、まことにありがとうござりまする」
津田坊はうなずき、少しぞんざいな態度であるなと熊千代は思った。
それなりに年配ではあるが美しい奥方は、半ばうっとりと従兄弟を見ている。織田家の中枢にここまで入り込める明智十兵衛の特別さは、我が父にはないだろう。熊千代はそこまで素早く見て取っていた。
明智十兵衛は立ち上がる。
「さて、わたしは藤孝どのの所に参って、安心させてさしあげるとしよう」
十兵衛が床についた手は男には似ない白さで指は細長く、ふと熊千代の脳裏に、あの少女の真っ白な手がちらついた。新しい世界と思うここでも明智は彼を気遣い、見守っている。何故だかそのいたわりに対して、気分がよくなかった。
十兵衛どのが心配するは、おれが一人前ではないからだ。
いつまでも守られる小僧っ子と見られていたくない。
「大丈夫です。一人でやってみせまする!」
生意気そうな、きつい口調が出た。
いつも慣れている十兵衛だからこそではあった。十兵衛にはそれとわかるが、柴田勝家や津田坊が驚いたような顔をした。
一人前になるのだ。
早く、一刻も早く一人前になって、上さまにも十兵衛殿にも、認めてもらうのだ。顔が真っ赤になって、力んでいる熊千代を見た十兵衛は笑顔を浮かべ、こちらも短く答えた。
「その意気でござる。では」
◇
「おまえはまったく呆れたやつだな。明智殿は今日のためにわざわざ、奧にいてくれたのだろうに」
言葉通りあきれた顔をしながら、津田坊は城内を歩きながら説明をしてくれた。
「この城は複雑だ。早くに覚えて道に迷うなよ。上から殿、室たちと赤子、さらに子息たちの住む場所となっておる。信忠さまは元服をされたので、新たに部屋を賜った」
裏屋敷のさらに裏をぬけて坂道を降りながら、岐阜城内の屋敷構成を順を追って教える。
「お前は小姓部屋で寝起きすることになる。麓にあるゆえ、毎朝駆け上がることになる。足腰が鍛えられるぞ。守役は小姓どものしつけもやる。柴田の爺も見回ってくるが厳しいぞ」
朝早く起き城の雑巾がけ、庭の掃除、衣装の世話、上つ方の身繕いの準備、勉強、武術の稽古。
「遊ぶ暇などない。そして小姓部屋は雑魚寝ゆえ、慣れろよ。自分の城のようにちやほやはされぬ。きつくて根を上げるやつも多い」
どうやら、小姓の生活とは交代で上のお世話をしながらの、寄宿制の学校のようなものらしい。
「おれは野育ち、寺育ちゆえ、山がけも雑魚寝も慣れておりまする」
また呆れたような顔をして、ついに津田坊は噴き出した。
「京から歌詠みの子が来ると聞いたのだ。ひょろひょろとして懐に筆など持ち歩き和歌を吟ず、公家のような奴であろうとみなが噂しておった。だが、まるでそんな感じはしないな。明智殿の言う通りだ」
公家ではない!父上だって立派な武人だ。
むっとするが、人はそんな風に見るのかと察するところもあった。
「まあ、いらぬ喧嘩をせぬように気を付けろ。いじめる奴がおればおれの名を言え。津田のお坊が目をかけているとな」
「そんなこと、言いませぬ!」
「好きにしろ」
熊千代はいきなり立ち止まると、津田坊の袖の裾を握って、先輩の顔を下から見上げると問いただした。
「津田坊どの!こうまでようして下さるのは、明智どののお指図か?」
余計な気遣いはいらぬ、一人でやってみせようとの気概が、心底にまだ色濃く残っていた。
津田坊は冷たく答えた。
「明智殿から一言はあったが、おれは気に入らん奴にまで心をかけてやる暇はない」
ということは、熊千代のことは気に入ったと言ってくれているのだ。
そこは熊千代は素直に嬉しくなった。ぱっと顔を輝かせるのを、津田坊は苦笑の体で見降ろしている。
「ならば、ありがたくお受けする。ありがとうござりまする!」
「お前はまず言葉の使い方から学べ。めちゃくちゃだぞ」
一回り大きな手が伸びてきて、熊千代の前髪をくしゃくしゃ撫でた。あたたかくて、頼もしかった。
「最初からそう気張るな、また見に来てやる」
第六話 終わり
画像(縦書き・ルビつき)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。






























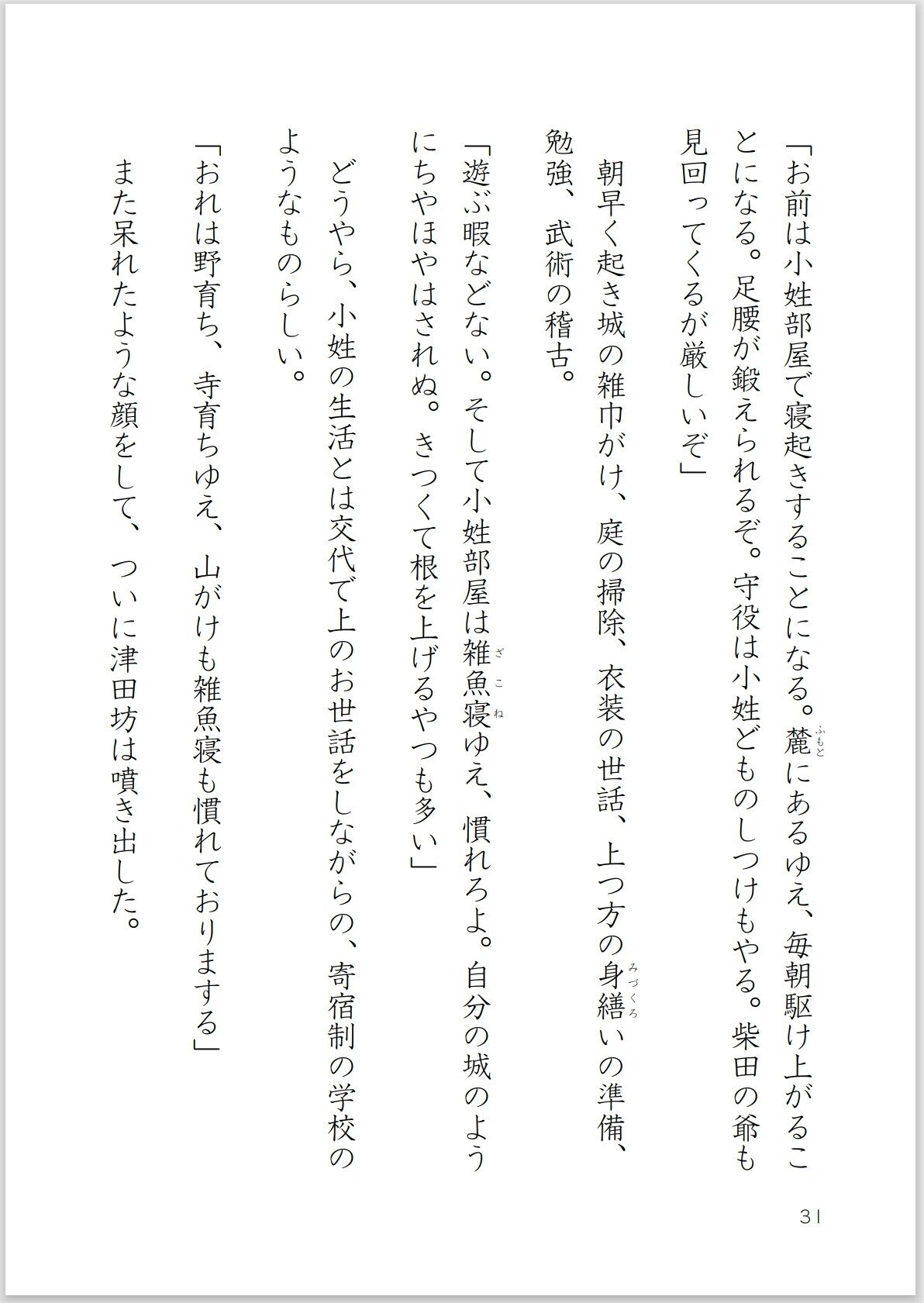



いいなと思ったら応援しよう!

