
櫃の中(鬼と蛇 細川忠興とガラシャ夫人の物語 14)
※画像では、「ルビつき縦書き文」をお読み頂けます。
櫃の中
お聡が津田信澄に嫁入りした翌年の天正四年の正月、信長は熊千代の衣服の紋を見とがめた。
「その紋はどうした?なかなか洒落ておるではないか」
熊千代は赤くなった。裏腹に得意そうな、芯から嬉しそうな顔をする。
「上様のお腰物を持ちました時、束にこの紋を拝見して、見事と存じました。心だけでも常におそばにおりたく、こうして使わせて頂きました!」
信長はいたく上機嫌になった。以後、そなたの家紋とすべしと言い、熊千代はありがたく受けた。これは細川の九曜紋の始まりとなる。
浮き立つような軽やかな足取りで去って行く熊千代を見て、信長は言う。
「あやつを見ると気分がよくなる」
周囲は同意しながらも、どことなくひきつった顔をしている。
北畠を制圧しに行った信雄の首尾が不調である知らせが入っており、つい先刻には正月の挨拶に訪れた北畠の使者に対して信長は凄まじい殺気を放った。その場で切られるのではないかと、周囲がヒヤヒヤした直後のことだったので、秀吉などは黒田(小寺)官兵衛に向けて苦笑混じりの軽口を叩いた。
「全くあの小僧の天然ぶりには参る。本気で言っておるのだから恐ろしい。取り入ろうとする奴らの方がまだマシだ」
◇
勝竜寺城では、藤孝が懲りもせずに、熊千代を座らせて説教を始めていた。
「よいか、なべて物事に過剰に期待してはならぬ。たとえば病を得るということもある。お前も六道図ぐらいは見たであろう?人の生は病気と切っても切れぬ関係ぞ。労咳、疱瘡、瘧、瘡……」
「珠子はきわめて丈夫で、風邪ひとつひいたことがないと言うておりましたぞ。顔色もつやつやしておったが」
「いかにも死にそうにないように見えても死ぬることだってあるのだっ!!!」
この長男には本当に苛々させられる。眉を逆立てたまま部屋に戻ってから、藤孝は膝を叩いた。
「仲良うても子が出来ぬこともあるということを教えておかねばならぬ。うむ、こればかりはわからぬからな」
妻の麝香が呆れて叱りつけた。
「左様なことは早すぎじゃ!まだ具足を付けるか付けないか、嘴が黄色いどころか、羽も生えておらぬというのにいらぬ心配というものです」
あやつは男女のことをどこまで知っておるのかな?
藤孝は首をひねりかけたが、まあ、どうせ小姓部屋でいくらでも吹き込まれておるであろうと思い直した。城勤めをしておれば耳にも目にもしておろう。津田殿といい蒲生の嫡男といい、仲の良い兄貴分はいくらでもいるようだし……。
ふと、書き散らした熊千代の手習い紙が目につき、拾い上げた。
感心なことに、最近は熱心に勉学にも励むようになっておるようだ。
「また、らくがきか」
藤孝はガックリと頭を垂れた。
熊千代はついに具足始め(甲冑着用の儀式)の準備に入った。
一般的には初陣と元服、結婚は同時期に行われるが、元服は信長が許さない。
「まだまだ、早い!そなたはここに居てもらわねば困る」
しかし初陣は熊千代がせがむので時期が早まった。
──一刻も早く!早く戦へ!
駆り立てる気持ちが、目を血走らせる。
前年は五月の長篠の大勝利の夢も冷めやらぬうちに、 明智十兵衛は八木城攻めに取り掛かり、 七月には越前平定に津田信澄が養父となった磯野と向かう。やっと鎮まった越前は柴田勝家に託され、北の庄に城を構える。織田家中は落ち着くどころかいよいよ苛烈な争いに入っていった。
石山合戦の始まりだった。
◇
「伺いたいことが御座います」
お聡は、夫信澄の前にきちんと坐った。
「何だ改まって」
信澄はこの若い妻が可愛くてならないらしく、笑顔で受けながら姿勢を崩した。真面目に取り合う雰囲気ではない。お聡は真剣だった。
「これまで、お傍についてご面倒をみておられた女人がおられたとのこと。どこにも姿が見えませぬ」
「暇を取らせた」
信澄は短く、簡単に言う。お聡は膝をすすめた。
「わたくしに遠慮しておられるのなら、余計なことでございます」
「ならば奥はおれが何人おなごを抱えようと平気だと申すのか?こうして添うたばかりだと言うのに、いきなり側室の世話とは出来すぎだな」
「それが勤めと覚悟をして参っておりまする」
「覚悟なあ」
信澄はごろりとひっくり返って、お聡の膝に頭を載せて笑顔で見上げた。
「お前のような美女がいるのだから……」
「わたくしは、美女などではございませぬ!」
お聡は伸ばしてくる信澄の手を払い、頭を膝からはたきおとした。信澄は驚いた顔をしたが、もっとびっくりしたのはお聡自身だった。
「左様な扱いは、居心地が悪うございます」
一度振り上げた拳を、どうしたらいいのかわからないお聡は、裾を払って部屋を出てしまった。
部屋を一旦出てからつくづくと考えた。
ここのところ毎日共にいて、話も楽しくはずみ、殿と過ごす時間がとても幸せであった。殿がわたしにお優しいのにつけこんでばかなことを言ってしまった。どうしたのだろう。あの人の前では冷静になれない。
涙が浮かんできた。
すべて私が私に自信がないゆえだ。
お聡はいつも、三姉妹の中で器量は劣ると言われ続けてきた。ここに来てからいきなりちやほやされたとして、いい気になって、ならば夫がたまを見れば、いったいどう思うであろう。いつもそうであった。あの細川の生意気坊主も、そして父上も。
たった一つ、わたしがたまにも負けぬのは、盤上の勝負だけであったのだ。
所在なくぐるぐると部屋を廻った挙句、部屋に戻ると、信澄は何事もなかったように平気な顔をしている。
侍女たちに顔を向けて、からかうようにこんな風に言った。
「そなたらも奥には従うがよい。我が奥は怖いぞ?早々に叱られたわ。いつまでも鼻の下を伸ばしておってはならぬとな」
気を使って、侍女たちは笑顔を浮かべながらそっとお互いに促しあって静かに下がった。二人とも若い。十九歳の夫に十六の妻の、他愛ない諍いだ。
くつろいでいる信澄のかたわらに、お聡は腰を落とした。
「怒って出ていかれて……戻られぬかと思いました」
「気丈なようでも、やはりおなごは嬉しいとみゆる」
思わずお聡の頬に、ぽろりと涙がこぼれる。
「あなたはなぜ左様によいかたなのですか?聞いていたのとまるで違います。恐ろしくもなければ激しやすくもなく、ひとの気持ちがようわかって優しいかたです」
「そうあるのは、奥のそばだけでよい」
真面目な顔で信澄は言った。
「外に出ればおれはおれの役割を演じねばならぬ。連枝のひとり、上様のお気に入り、家中の引き締めだ。三介と三七を争わせぬように目を光らせておらねばならぬ。皆がおれの顔色を伺い、恐れている。それでいいのだ。父上の御無念を晴らし、再びわが家を盛り立てるため。弟たちが後ろ指を指されぬよう、母上がのどかに暮らせるように」
お聡ははじめて、夫の本心からのことばを聞いたような気がした。
どんな睦言よりも、甘い褒め言葉よりも、こんな風に心を打ち明けてくれる夫が好ましいと思った。
◇
「大変でございます!」
坂本城へ緊急の知らせが入って、城内の空気は一気に緊迫した。その知らせの声はただならない。
「殿が……殿が!十兵衛さまが!」
「まさか討ち死にされたのか」
「まだではございますが、一万五千の軍勢に取り囲まれており、もう望みはないかと思われます。三日も持ちこたえられるかどうかという所にて」
「救援は!」
「京におられた上様が取る物もとりあえず向かわれましたが、火急のことにて兵が集まらず、上様の軍もわずか三千……」
大阪の天王寺砦を目の前にした城で、信長は歯噛みをしていた。髪が逆立つ気配に、近習も誰一人声もかけられない。
わずかな手勢しかいないため、信長自身も危険だった。三千の兵と、一万五千。目算が甘かった。坊主ずれどもに負けるものかとあるが、相手は数を頼んでいるうえ、雑賀衆の鉄砲隊を味方につけている。
ここで明智を失って、後を任られせる相手がいるであろうかと、冷たい算段が胸を走る。
歯を食いしばった信長の唇の間から、声が漏れた。
「いない」
誰もいない!光秀しかおらぬ。
鬼武者だが頭の回らぬ連中か、欲深な国人どもか。秀吉は強いが駒だ。徳川はいま傍にいない。あれは東の抑え、手駒だ、手駒がいない!
公私を捨て、我が身のすべてを賭けて仕えてくれる者だ。結果を出してなお、私に走らぬ者。朝廷との交渉も出来、あの手強い延暦寺のある坂本をあれほど安定して納めている。鬼の棲む丹波を平定し得る者だ。
彼の落ち着いた優しい顔が浮かんだ。
助ける理由を探す心の奥底に潜む、それとはっきり意識しないまでも、ここ十年の間常に、明智は信長の精神の支えであった。
誰一人信用できない。
慈悲の心を持ちながら修羅に陥らず、天魔の仕業を成す託宣を下す者、あれを失うぐらいならもはやこの先は何もない。
「このまま突撃する。陣は三段構えで突破するぞ」
「よく言って下さった、上様!」
松永久秀が低く太い声で言う。横で目を血走らせた細川藤孝もうなずいている。
先鋒は佐久間信盛、そして松永と藤孝がつとめることとなった。どちらも明智とは親しい間柄だ。
だが荒木は断った。明智とは親戚であるのにと信長は以外に思ったが、その時は構っている暇はなかった。
逆に、断りそうだと思った藤孝は、蒼白な顔をしているがじっと腰を据えて瞳を燃やしている。何としても親友の命を救おうという気迫に満ちていた。
きっぱりと宣言することばは、さすがの説得力がある。
「こちらの三千はただの兵ではありませぬ。鍛え上げた練度を誇る歴戦の強者ども、一万五千と言えども寄せ集め、有象無象の衆にすぎぬ。鉄砲は弓と兵をあわせ、将の巧みな采配があってはじめて生きるもの。雑賀の兵と云えども、何するものぞ!」
光秀とともに息子が天王寺砦に閉じ込められている佐久間が雷のような声で呼応した。
「武田を倒した我らが誰に負けるものか!たとえ誰が来ようと蹴散らしてくれようぞ」
これは敗軍の士気ではない。十兵衛の運はまだ尽きていない。ということは、織田の運も生きているということだ。二番手には秀吉が付いている。滝川一益も稲葉一鉄もおり、精鋭中の精鋭が揃っている。
信長は前線の兵の間を巡り、士気を鼓舞する。
全軍に凄まじい気迫が漲って、心がみな一つとなった。
「一点突破ぞ、行け!」
「突っ込め!」
数を頼んでいた本願寺の兵は、思わぬ優勢と目の前にぶらさがった勝ち戦に油断した。凄まじい勢いの信長軍に追い散らされて天王寺砦への合流を許してしまった。
◇
砦に入った信長と藤孝は、光秀のもとに駆け付けた。
「ひどい怪我だ、十兵衛。だが安心せよ、もう大丈夫だ」
「藤孝殿!上様!」
信じられないという表情で切れ長の目を見張り、赤黒い血がこびりつく死人のような肌の明智の顔が紅潮した。
「御みずから、かような場所まで……お怪我まで」
「惟任、ここをよう持たせた。そなたの最後まであきらめぬ粘りがあってこそだ」
信長は脚に銃弾を浴びていたが、至極元気で笑顔を見せながら明智の手をしっかりと握った。後ろから秀吉が剽軽な顔をのぞかせて笑わせ、同じ美濃一族の稲葉一鉄が忙しく持参した薬を処方しはじめた。
「まだこれからぞ、この勢いのまま、奴らを追い落とし、撃破する!」
様々な国人衆の集合体である織田家が、手負いの光秀と劣勢をおして自ら助けた信長を中心にして、ここに居合わせた誰もが、強い連携と絆に、感動と幸福を感じていた。
藤孝は、明智の顔色を見て、彼が織田家における役割も重要性も、信長の気性もよくわかって賭けに出ていたことを悟った。
しかし、これで、十兵衛はしばらく動けぬ。
そう心うちに呟いたのは、藤孝だけではなかったはずだ。
地盤を固める余裕もなく、ひたすら戦に明け暮れる。薄氷を踏むような危うさは新興勢力である織田家の定めでもあった。
◇
天王寺砦から戻ってしばらく光秀は病の床に伏した。
煕子が自分の病状をおして献身的に介護をした。珠子も七歳と五歳の弟たちの世話に明け暮れ、今までとはうってかわって忙しい生活となった。
そんな中で信澄とお聡がうまくいっている知らせが、帰蝶づてに届いていた。荒木の家でのお岸のことに心を悩ませていた十兵衛と煕子にとっても、心が明るくなる便りだった。
「思ったより大変です」
しかしお聡は、そんな風にお珠に書いてよこした。
岐阜城の奧屋敷は広くて大きくて、たくさんの方がおられる。帰蝶さまがまとめておられるけれど、側室がたいそう多いので、お子たち、姫たちと入り乱れており、女の派閥があって厄介です。
帰蝶さまのおそばに仕えていますが、織田家に明智家の女たちを引き連れて入ったら気取っていると陰口をたたかれておりまする。尾張の者は近江の者に敵意を持ち、近江の者は美濃の者を馬鹿にする。
殿は大変ではありません。たいそうお優しい。
でも信長さまと似ておられる所があり、とにかくご贔屓が甚しくて気に入らなければまるで駄目、明智の父上のお力を借りるのもいやなご様子。だから刺激しないように注意だけはしておりまする。
「姉上、大変そうだわ」
手紙を置いて珠子は嘆息した。
「それは大変ですよ。帰蝶さまなど、信忠さまの生みの親である側室、吉乃殿が生きていたときは、もっとひどかったと聞いております」
乳母が横から口を出した。
母は珠子の髪を手ですいた。
「おたまはよい。身内に嫁ぐようなものだもの。あの癇癪もちのいたずら坊主どのは、あなたしか目に入らないようだし。さあ、あなたは輿入れのための勉強がありまする」
「またあれを習うのか?」
おたまはうんざりした顔をした。
「大事なことです。生きていくために欠かせぬ知識でありますからね」
夫婦生活の錦絵を並べて見せている煕子も珠子も夢にも思わない悩みを、岐阜城で暮らすお聡が抱えていることを、この母娘は知らなかった。
◇
お聡の人に言えぬ悩みとは、三七こと信長の三男、信孝にしきりと話しかけられることだった。
鈴与がなつくので可愛く思って相手をしていると、色々と理由をつけて入ってきてはどっかりと座り込み、こうして仲良くして頂いて……から始まって、小一時間も話をする。その間、鈴与はほったらかしのまま、お聡とにばかり水を向けるので、居心地が悪く、また気味が悪かった。
「あやつは悪い奴ではない。才もある。落ち着けぬ理由があるだけだ」
夫の信澄はいい、確かにこうして話をしていれば、いつも何かに駆り立てられるように苛々しているものの、愚かではないことはわかる。
織田の奧屋敷では今、二人、三人と子を上げてまだ寵愛の離れない、お鍋の方という信長の側室が幅をきかせはじめている。
閨で相手をすることが多くなれば、自然とお役を離れた側室など挨拶以上に話をすることもなくなっていく。信孝の母、坂氏が気が気でないのが見て取れた。
そう聞けばお聡としても、三七どのも大変なことだ、と思うものの、こうして訪問が度重なると鬱陶しい以上に心が重くなってきた。夫に相談するのも自惚れのようで言いにくい。
最初は気のせいかと思っていたが、気を付けて誰にも漏れぬようにしていた参拝の寺に姿を見せて、偶然でござるなとやって来られた時には、さすがのお聡もすっと背中が冷えるような心地に襲われた。
「七兵衛はこんな奥方をもらって、心底、幸せ者だ」と繰り返すのも嫌だった。
ある日、鈴与の目の前なのに、つっと手を握ろうとする仕草を見せて、思わずお聡は立ち上がった。今まで丁重にしていた配慮を振り捨てて、語気荒く叫ぶ。
「三七どの!お戯れもいい加減になさいませ」
「そなたは、そなたは、今まで見たどの女子よりも好ましいと思う」
熱心に言い、なおもとりすがろうとするのをすり抜けて、お聡はさっと部屋の外へ出た。鈴与も侍女もみな置き去りだが構いはしない。
足音が追いかけてくる。
まさか、これでも諦めぬとは。
お聡は震える足を前に出し、真っ白になりそうな頭を懸命に動かした。ここで気をしっかり持たねば、あらぬ噂にもなり、噂ではすまぬことになるやもしれぬ。
お珠を追いかけてあちらこちら走り回っていたのが役に立った。
迷路のような岐阜城の奧屋敷をすり抜け、侍女や下女たちが不思議そうに見る中を、音もなく走った。
これ以上行けば、表屋敷の裏手に出てしまうという場所に、お聡は思い切って飛び出した。一本道の庭つきの中部屋が重なる場所で、お聡は立ちすくんだ。これ以上逃げる場所がない。
庭の敷石に、足軽より少しましな恰好をした男がひとり腰かけている。お聡は一瞬、ぎょっとした。見たこともないほど大きい、巨人のような大男だ。背中を向け、一心不乱に饅頭にかぶりつきながら書を広げている。こちらには気付いていない様子だった。
身を隠す場所を探して手近な部屋に入ると、蓋が空いている櫃がひとつあった。こういった場所によく身を潜めて隠れていた珠子のことが頭をかすめ、ばかばかしいとは思ったが櫃の中に身を鎮める。どたどたと、もう慣れっ子になった足音が聞こえて、お聡の隠れている部屋に入ったり出たりする音がする。
「おい、そこの木偶の坊!」
「はいっ、は、はい」
ふがふがと口を動かしながら、大男が慌てて立ち上がって書を落としたり拾ったりしている音が聞こえた。
「これは、気が付きませず申し訳ございませぬ!」
「ここに女子が一人、来なんだか」
「は、はぁ……?」
険しい顔つきで詰問する信孝の前で、大男は土に膝をついたまま、直角になるほど首をかしげた。頬の髭には饅頭の欠片がくっついたままでいる。
「まことに不調法にて、恥ずかしながら饅頭を食べるのに夢中で何も気が付きませなんだ」
「饅頭を食べるのに夢中とは何だ!」
信孝は額に青筋を立てて怒鳴った。
お聡ははっと身動きした。自分のせいであの者が斬られるようなことがあれば、出て行かねばならない。
「お許し下さいませ!」
いかにも情けない声で、大男は平身低頭で平服している。
「成りは大きいくせに、ものの役に立たぬ奴!そんなことでは戦場で見張りも勤まらぬ!」
いらいらした声と共に、どたどたと足音は去って行った。
◇
「御前様、もう大丈夫でございます」
低い声がかかって、お聡ははっとした。御前様と呼んだ。わたくしの顔を見知っていたということだ。
そっと身づくろいを整えてから出て行き、相変わらず庭におとなしく膝をついている大男の顔を見て、お聡はこの男、見た目よりずっと敏い奴であると思った。背中を向け、書を開いてものをほおばりながら、一部始終を観察していたのだ。よく見てみれば、その顔と体格にはかすかに見おぼえがある。
「そなた、殿のお近くで見たことがありますな」
「藤堂与右衛門と申します。磯野の殿にお仕えしておりまして、今日はお供を仕っておりました」
そうか今、殿(信澄)は義父となられた磯野殿にご面会しているのであった。
「この恩は忘れませぬ。与右衛門どの、まことに助かりました」
なぜ追いかけられていたのか、どういうわけなのかなど、余計なことを言わず聞かず、あとは黙っておとなしく控えている。いかにも実直そうな顔と大きな図体の横に、皿に乗った饅頭と本が置かれていた。お聡はおかしくなった。この体格ならば、さぞかし腹も減るであろう。
皿の横に置かれている書は、どうやら囲碁の指南書であるようだ。
「碁が好きなのですか?そなた」
少女のような若い奥方の前で、小さくなって大男は頭を掻いた。
「三度の飯と同じくらい打ち込んどります」
彼女を探す侍女たちの声がして、お聡は重ねて礼を言いおいて立ち上がった。
信澄が戻ってきて、岐阜城から義父となった磯野の所領、高島郡の城にうつると聞いたとき、帰蝶はひどく残念がったが、お聡の安堵はそれは大きかった。
◇
同年の十一月、熊千代は十四で甲冑を初めてつけた。
「こう、冑の緒はきっとしめまする。」
鎧着初、とも具足始ともいう。鎧親は千秋太郎介掌之という熱田大宮司の流れを汲む明智の一門がつとめることとなった。藤孝も機嫌よく「名前が縁起がよい」と言う。
椀箱のような具足櫃に腰掛けて、兜をかぶる。
後世に有名な山鳥の尾を頭に生やした形のかぶとだが、この時は孔雀の羽がついていた。
「関東の大大名、北条家。その二代目である北条氏綱殿が遺し申した言葉にございまするが」
ぎゅっ、と千秋が忍緒を縮める。
「三十年も前のことでござるが!」
ぎゅっ。
「今もまだあたらしき言葉にて」
みしっという音が聞こえたような気がした。
熊千代は振り返ろうとしたが、頭を動かすことも出来ない。仕方なくされるがままになっていた。
「今こそ!」
ぎゅっ。
「勝って兜の緒を締めよと……」
みしみしという音は、尻の下から聞こえてくる。
それが次第に大きくなってバリバリバリ、というすごい音とともに、腰かけていた櫃の底が抜ける。熊千代は兜と鎧の重みに耐え兼ね、後ろへ向かって仰向けにひっくり返ってしまった。
「あーーー!」
もちろん兜はおち、孔雀の尾も曲がってしまった。
脚がさかさまに具足櫃から天井へ向かって突っ立っている。
「ああっ!若!若ー!」
「大丈夫でござりまするか」
皆、儀式の道具を放り出し、総出で助け起こそうとする。
「いかん、抜けん!」
「まず起こせ!それから抜け!」
「いや壊せ!櫃を壊せ」
「けがをするぞ」
「鑿と金槌をもて!」
てんやわんやの大騒ぎになった。
今度は総出で熊千代を壊れた櫃から抜こうとするが、あちらからもこちらからも手が出ているので、四方から引っ張られてどうにもならない。
「やはりちょっと早すぎたのでは……それでなくとも小柄だし……」
「シーッ!」
はぁ……。
藤孝は、肩を落として盛大にため息をついた。
最近、こやつのことでは万事うまくいきすぎるような気がしていたのだ。
櫃にはまりこんだ状態でひっくり返っている熊千代のぽかんとした顔と突き出た脚を見て、
「ぷ、ぷ、ぷ……」
「う……」
「笑うな!笑ってはならぬ!若がお気の毒……」
笑いをこらえててんでに下を向き、背中を向ける郎党たちの中、完全にあっけにとられて棒立ちになっていた鎧親役の千秋は、何を思ったかそこでさっと扇子を開いて上にかざした。
大声を張り上げる。
「こ、これは目出度い。縁起のよい!」
米田宗堅が白髪頭を真っ赤にして湯気を出しながら怒鳴った。
「頭でもおかしゅうなったか?これの何が縁起が良い!悪いの間違いであろう!」
「櫃を割って、兜が取れた。すなわち、丹波八都は割り取りになさるべし、との神託にござる!」
おお~!
ぱちぱちぱち。
「千秋どの、うまいことよう言うた!」
「なるほどこれは吉兆じゃ!」
皆が囃し立て、場はどっと沸いて和やかな気配に変わる。
藤孝も多少機嫌を直して、笑顔になった。しかしひそかに、しまった!なぜわしはそれを千秋よりも先に気付かなんだか!と歯噛みをした。(藤孝はそういう性格だった)
「何が吉兆だ!」
熊千代ははまりこんだまま、足をばたばたさせて怒鳴った。
「早く起こしてくれー!」
第十四話 終わり
画像(ルビつき・縦書き)
画像は、最初のひとつをクリックすると、スライド式に読むことができます。











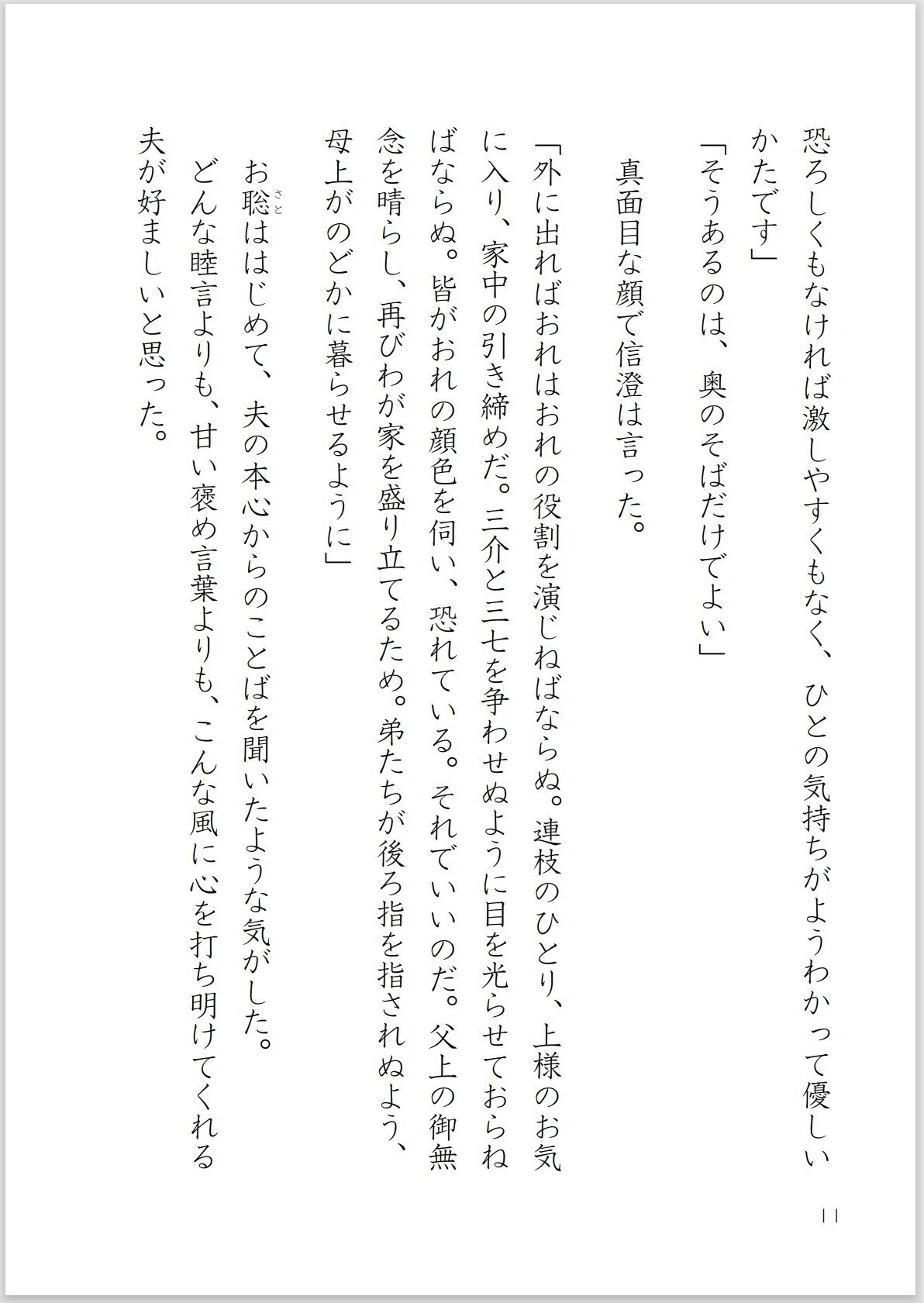
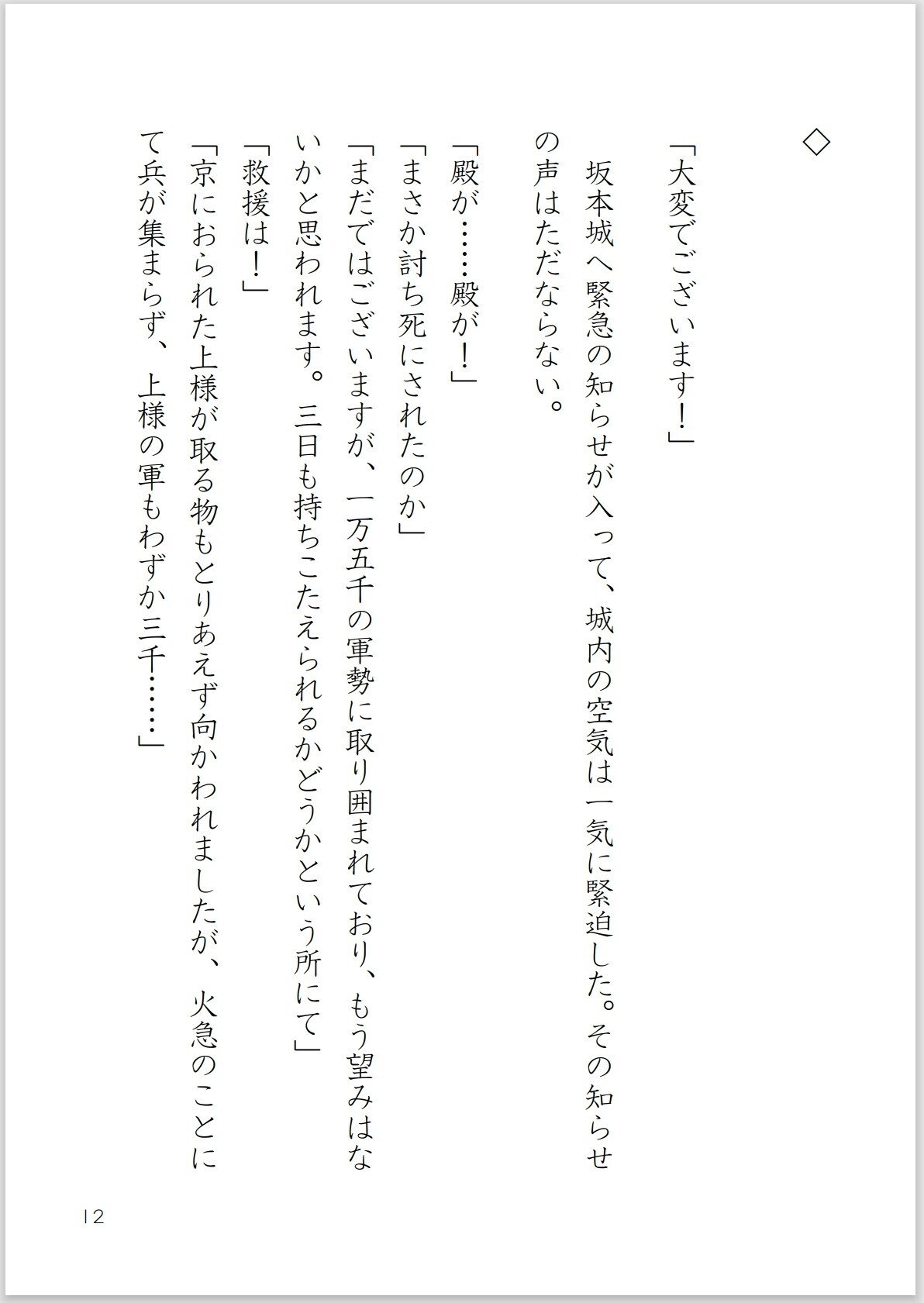

























画像。本型。見開き版。













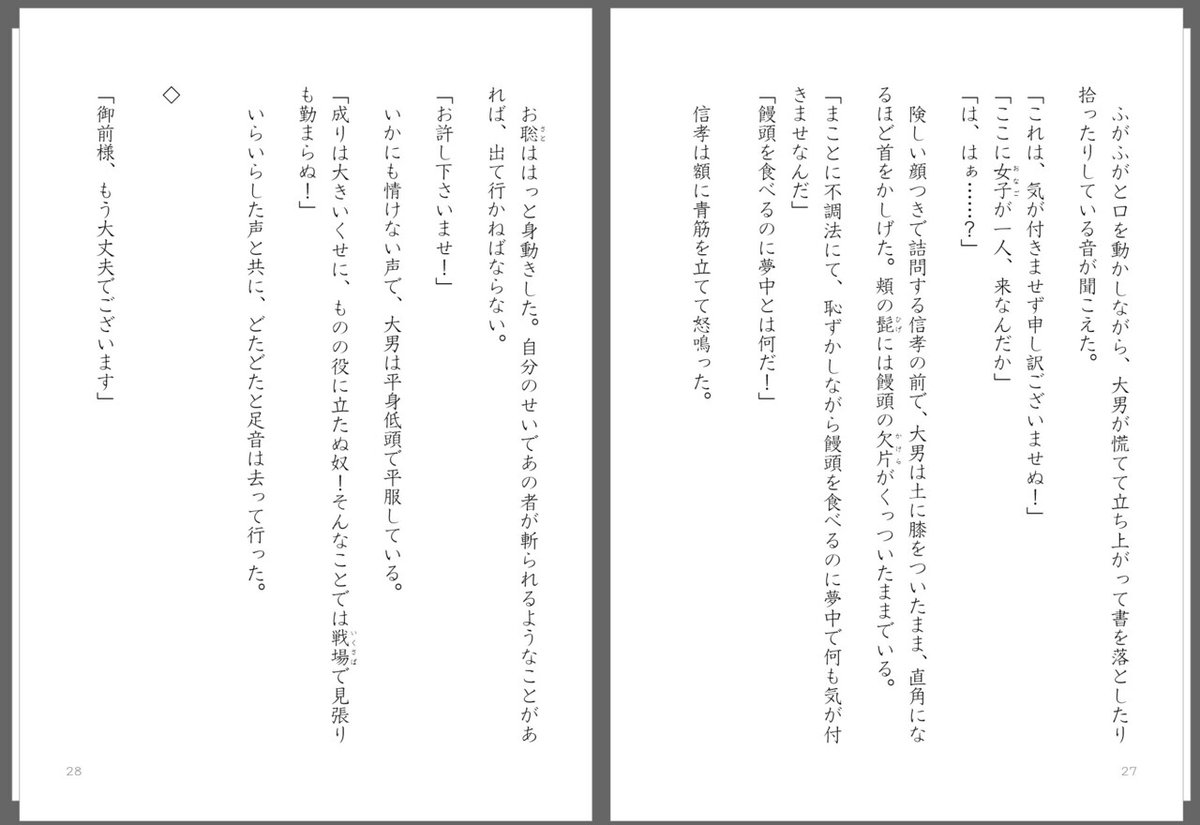





いいなと思ったら応援しよう!

