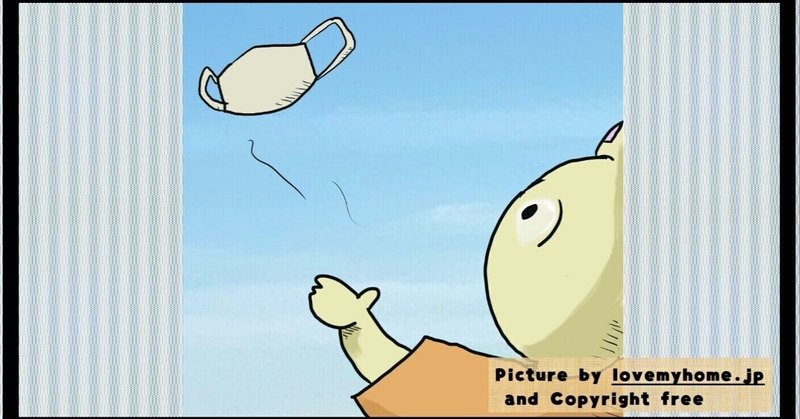
こうして施設ケアマネは存在意義を失う【施設ケアマネの役割や動きの改善案】
こんにちは、アルゴです。
いきなりですが、この記事にたどり着いた方へ宣伝です(笑
今、長期にわたって漫画を描いてまして、note、Twitter、ブログ、マンガボックス、LINE漫画などにアップしています。
↓↓↓
ボクのnote記事を見てくださる方は、介護・医療関係の方かと思いますので、漫画にはあまり興味ない・・・と思われるかもしれませんが、ちょっとまってください。
『社畜』とか痛烈な言葉をタイトルに使っている漫画ですが、描いている内容は介護施設の現状と、そこで働く人達の悩みをピックアップした真面目なものです。
全17話構成で、今、第4話まで描き終わっています。
介護施設で働く人であれば共感、楽しめる内容だと思うので、上のリンクから第1話を見てみてくださいね。
施設ケアマネの存在価値が薄い理由
さて、本題です
施設ケアマネという存在にコミットしてお話します。
昨日の記事からの続きになっていますので、まだ見ていない方はそちらをお目通ししていただくと幸いです。
↓↓↓
皆さんの働いている介護施設での『施設ケアマネ』ってどのような感じですか?
現場ではたらく皆さんのイメージは??
・とにかくケアプランをつくる人
・パソコンの前に座って何をやっているのかイマイチわからない人
・現場が大変になると手伝いにきてくれる人
様々かと思います。
しかし、介護施設の現場ではたらく人が誰もが一度は疑問に思ったことありませんか?
「施設ケアマネって必要なの?」・・・と。
私達が施設サービスを提供するには、ケアプラン(個別の計画書なども)を作り、ご本人もしくはご家族の承諾を得なければなりません。
これは法律で決められています。
なので、ケアプランはケアマネの資格を保持した職員がゼッタイに作らなければなりません。
ゼッタイに必要な職種なのにも関わらず、施設ケアマネの存在意義がうすいのは理由があります。
それは・・・
ケアプラン自体の価値が、現場の職員に浸透していないからです
昨日の記事でも書きましたが、介護の仕事というのは、ケアプランの内容をまったく知らなくても、『何となく』でケアできてしまうのです。
・そのご利用者の飲んでいる内服薬のひと粒ひと粒の内容と効能
・そのご利用者のもっている病気と、その病気の症状のすべて
・そのご利用者の家族構成、生活歴
上記のような内容について、自分がケアをするご利用者の情報全てを知っている人など、リーダークラスでもなかなかいないんじゃないでしょうか?
「この起床時薬はこの曜日にぜったいに服用しなければならない」
といったようなめちゃくちゃ大切な情報はもちろんアタマにいれるでしょうけど、そうではない情報はそんなに関係なく、その場その場の状況で、ケアができてしまうのです。
だからケアプランにこう書かれているから・・・とか、理屈っぽいことでその場その場のケアを変更するなど、よほどのことがない限りありません。
この
『ケアプランの存在価値が現場に浸透していないこと』
こそが、施設ケアマネの存在意義が薄れている最大の理由ともいえます。
ですが、昨日の記事でお話したとおり、
本来、ケアプランというのはそのご利用者にとってケアの目指すべき方向を表すものなので、非常に重要なものなのです。
ケアプランを理解していないからこそ、
「٩(๑`^´๑)۶私は私の慣れたやり方でケアしているんだから、文句言わないでよ!」
・・・といった横暴な職員がやりたい放題してしまいます。
そして、ご利用者にとっても
「(;_;)職員のAさんはこういうケアをしてくれるのに、職員のBさんはぜったいにやってくれないのよねぇ…」
・・・と、職員によって受けるケアが変わってしまうということが出来てしまいます。
だから、共通の認識を得るために、ケアマネの作るケアプランは、本来めちゃくちゃ大切なものなのです。
ケアプランを現場に浸透させるためにどうするか?
ケアプランの重要性は先に述べました。しかし問題は、ただの紙きれになってしまいがちなケアプランを、どう現場に浸透していくかです。
私も施設ケアマネ業務をはじめたばかりのころ、作りながら
「うーん…こんなことやって、現場にどれだけ意味があるんだろ…」
と悩みながら作ってました。
しかしその後、施設内で先頭にたって様々な改革を行うことにより、いろいろなものを劇的に改善できました。結果、職員全員がケアプランに目を通し、プランに意見をし、評価をするまでにいたったのです。
以下でその改革内容をお話します。
①施設内でケアプランの勉強会を行う
1つ目は、施設内でケアプランの勉強会を、現場の職員あてに行ったことです。
1回やれば良いというわけでなく、最低でも現場職員全員が最低1回受けられるくらいの回数をこなしましょう。そして、それを毎年継続して行っていきます。
そもそも現場職員がケアプランについて学ぶ機会というのはそうそうありません。ケアマネの試験を受けようとしている方や資格をもっている方は別ですが、そうでなければ、技術以外の勉強ってなかなかしないもんです。
研修を行う際の注意点ですが、パワーポイントで作ったものをただ説明して終わり・・・などだと効果が薄く、次の日には7割以上忘れてます。それだと意味があまりないです。
グループワークや、次の日から実践できる内容を盛り込む工夫が必要です。
効果的な研修の仕方ということについて、この記事では書ききれません。ご興味がある方は、以前出版した書籍にも書きましたので、ご覧ください。
↓↓↓
②カンファレンスはきっちりやること
ケアプランを作るうえでカンファレンスをすることは当たり前です。
当たり前すぎてここに書くことじゃないかもしれないですが、本当にこれがきっちりできていないケースもあります。
最悪、職員2人くらいですませてしまう場合もあり、ただの形式的なものになってしまっている場合があります。
昨日の記事で書いたとおり、多職種連携と情報共有ってものすごい大切です。
ケアマネ、相談員、介護職員、看護職員、機能訓練員、管理栄養士など、様々な職種をあつめていろいろな観点から意見を出しあいましょう。
コロナ渦の現状、ご本人、ご家族を呼べるケースはなかなかないかもしれませんが、意思を反映させることはとても重要です。
③ケアプランの評価を居室担当に行わせること
従来型、ユニット型関係なく、どのご利用者にも居室担当はいますよね?
居室担当の役割といえば、衣類を整えたり、バースデーカードをプレゼントしたり、そういったことはどこの施設でも行っていると思います。
でもきっちりカンファに参加したりしている施設ってなかなかないですよね。
そもそも施設ケアマネの存在意義を上げる前に、ご利用者と直に接している居室担当の意義すら薄れることもあります。
私はその居室担当に、ケアマネの作ったケアプランを毎月評価してもらい、意見をさせることにしました。
ここで、居室担当の力量が関わってきますが、きっちり行う職員はこまかくケアプランをチェックしてくれて、修正をしたほうが良いとアドバイスをくれるようになりました。
ケアマネはケアプランを作る上で、モニタリング、アセスメント、カンファレンスなどを実施するわけですが、やはりどんなことでもケアマネ一人が誰の意見も聴かずに作ると、独りよがりのプランになってしまいます。
そしてだからこそ、ケアプランは紙クズ、ケアマネは存在意義を失っていくのです。
そうならないために、ケアプランの作成に、居室担当をはじめとした現場の職員を巻き込みましょう。ウザいって思われるくらい、巻き込んでしまったほうがいいです。
そして大切なこと。
できたケアプランは、意見をくれた居室担当に必ずフィードバックします。「あなたの意見はここにこういうふうに反映しました」と成果を示すのです。
④現場の職員がケアプランを目通しする機会を設ける
私が最初に勤めた特養では、カンファレンスはきっちりやるのに、できたケアプランは棚の奥にしまわれ、現場の職員が目にすることはありませんでした。
これでは、何のためのケアプランかわかりません。現状のケアを文字にして、ご家族に承認をもらうための紙クズになりさがっていたのです。
記事の最初にお話したとおり、ケアプランに存在価値がないのに、施設ケアマネに存在意義があるわけがありません。
作成したケアプランは、全員が目を通せる機会を作りましょう。
私が最後に勤めた施設では、ケアプランは書類として出力もしますが、基本的には電子ベースで各自が閲覧できるようになっていました。
そして先にお話したとおり、ケアプランの評価を居室担当が行うシステムを確立したため、嫌が上にも閲覧することになります。
⑤施設ケアマネは現場の手伝いはするな
どこの施設でもよく聴く話なのですが、施設ケアマネは現場のいち業務を手伝いにいくという話があるのですが、基本的にはやめたほうがいい・・・というかやめるべきです。
理由は、手伝っても現場の業務量がラクになることはないからです。50人の介護職が51人になっても、さほど違いはありません。このことに関しても、先程紹介した著書には詳しく書いています。
もちろん、急な病欠でどうしても人出が足りない・・・そして、救急搬送でさらに人手がとられた・・・などの理由であれば仕方ありません。
ですが、日常的に介護職の業務を手伝いにいくことは、良かれと思ってやっているのでしょうが、施設にはマイナスになってしまいます。
それをするのなら、自分にしかできない仕事にコミットしましょう。
施設ケアマネなんて、一施設に、一人か二人しかいないでしょう。
なので、施設ケアマネの存在意義を施設で作るには、その人自身の努力と工夫が大きなカギを握っています。
サポートですか・・・。人にお願いするまえに、自分が常に努力しなくては。
