
十数年でたった一人だけ、サービスの利用をお断りしたご利用者
こんにちはアルゴです。
昨日の記事では自作マンガとして、介護の仕事に関わったことのない人でも伝わるように描いたつもりです。
今日は昨日のマンガとは真逆のような話をします。
私は今まで特養や在宅系サービスなどで現場介護職、管理職、相談員、CMなど様々な福祉職を経験しましたが、その中には当然、困難事例と言われるケースは多々ありました。
それはおそらく皆さんの経験の中でも、同様だと思います。皆さんのnote記事を拝見する中では、私が経験したよりも大変な経験をされているなぁと感じることもあります。
ただ、私は十数年間の福祉職人生の中で、自分の施設・・・自分の部署がいちご利用者・ご家族に対し、サービスの提供をお断りするということは、どれだけ大変でもしませんでした。
皆さんの事業所のスタンスはどうでしょうか?
私が今までに勤めた事業所は基本的にどこも、『どんな事例でも受ける』というスローガン的なものを掲げ、実際にそのとおりにしていました。
しかしながら、たった一人だけお断りしたケースがありました。
今日はそのケースについてお話します。
障害者サービスから介護保険サービスに移ってきたご利用者

その方は40代にして障害を患い、長い間、障害者のサービスをご利用されていた男性の方でした。
(以後、Aさんと呼びます)
Aさんが私の施設のショートステイに初めて来られた時は60代と若めでしたが、認知症もなく、身体が自由に動かないという事以外では、特に問題はないということでした。
Aさんがショートステイをご利用されたその日の夜、夜勤にあたったのが私でした。
日中の記録を見ると、とくに変わったことは何もありませんでした。認知症もないことから、必要時はナースコールを押してくれるということで、むしろ安心していました。
ところが、とんでもなく大変な方だと、その夜勤で思い知ることになるのです。
ナースコール連打 & 説教 & 職員への誹謗・人格否定

その施設は特養でしたがショート夜勤だったので、22時入りでした。
22時に入ると、その方もすでに入眠されていたようでした。
「^_^ よし、夜勤開始!」
といつものルーティンに入ろうとすると、ナースコールが!
どうやらさっそくAさんからです。
呼ばれていってみると、足の位置を直してほしいということでした。
Aさんは手は自由に動きますが、足は自分の意思では動かせません。私はAさんの言われた通り、ベッド上で両足のポジションを整えるようにしました。
しかしAさんは
「(゚Д゚)違う違う!そんなやり方じゃないんだよ!お前は障害者の扱いを勉強したほうがいい」
と初対面の私に強めの口調で告げてきました。
( (-_-)障害から介護のサービスに映られたばかりなのかな… )
そんなことを思いながら私はAさんに謝罪をし、今一度、両足のポジションを整えます。しかし・・・
「(゚Д゚)おい、そんなところを持つと痛いよ!こっちの身になってみろよ!」
決して乱暴なやり方もしてないつもりなのですが、その方にとっては痛みのある動かし方だったのか、なかなか納得いかないようです。
その後もAさんに言われるまま微調整をして10分ほど・・・足を動かすだけで10分です。
「(゚Д゚)うーん、なんかしっくりこないんだよな。これで寝られるんかな。まぁいいや」
としぶしぶ納得されたようでした。
ようやく退室。そして、ようやく夜勤のルーティン、他の方のオムツ交換に行こうと準備をします。
ところがまたAさんからナースコールが!すぐに再度伺います。
「(゚Д゚)やっぱりこれじゃ駄目。寝れない。」
と話され再度調整します。もはや自分でも、数ミリしか動かしていないような気がして、さっきと何が違うのかわからない状態でした。
そして、退室します。他の方も待っていたので、とりあえずは離れなることにしました。
しかしその後1分もしないうちにまたまたナースコール!
「(゚Д゚)ちょっと小便がしたいんだけど」
Aさんはカテーテルを使用し、部屋に設置してあるボトルに自分で排尿はできます。なので、夜間の排泄は自立であると前情報にありましたので、予想外でした。第一、たった今、足のポジション直したばかりなのに…(-_-)
22時に私が夜勤入りしてから、とにかくナースコールが多く、他の方のケアがほとんどできない状態でした。
初めてショートステイを利用されることから、どこまでの対応が必要かもわからず、初日は毎回報室していたのでした。
結局、夜間帯に20〜30回ほどナースコールがあったでしょうか。認知症がある方ならともかく、さすがの私も少し疲れてしまいました。
一晩中、起きていた感じがします。ナースコールがなかった時間は、最高で20分間くらいだけでしたから。
しかし私が夜勤から帰った朝、その日中にあった事がもっと大きな問題が起きていたようです。
Aさんは足を自分で動かせず自分では立位ができませんでした。そのかわり、誰かの手を借りると、立位がとれます。
しかしAさんを立位させるその方法も、生半可なことではありませんでした。Aさんはとても大柄な男性であり、体重は60kg〜70kgあったのです。日中のトイレ介助には、男性職員が3人がかりで行う必要がありました。
ユニット型特養は基本的に1フロア1人の職員しかいないことがほとんどですから、相談員や隣のユニットの職員を借りて対応したそうですが、それでもトイレ介助をするのに30分以上とられたといいます。
さらにその日の日中、職員をより好みするような言動が出始めます。
Aさんの要望にうまく対応できなかった職員がナースコール対応をすると、
「(゚Д゚)違う!お前じゃ駄目だ!別の職員をよこせ!」
と乱暴な対応です。
日中〜夜間、ナースコールを連発して職員を捕まえっぱなしにするばかりか、職員を差別し、人格を傷つけるような発言もあったとのこと。
結局・・・
私が夜勤明けで家でグーグー寝ていたその日のうちに、相談員経由でAさんの利用をお断りしたとのことでした。
実は以前、特養に本入居していたが、退所させられていたAさん
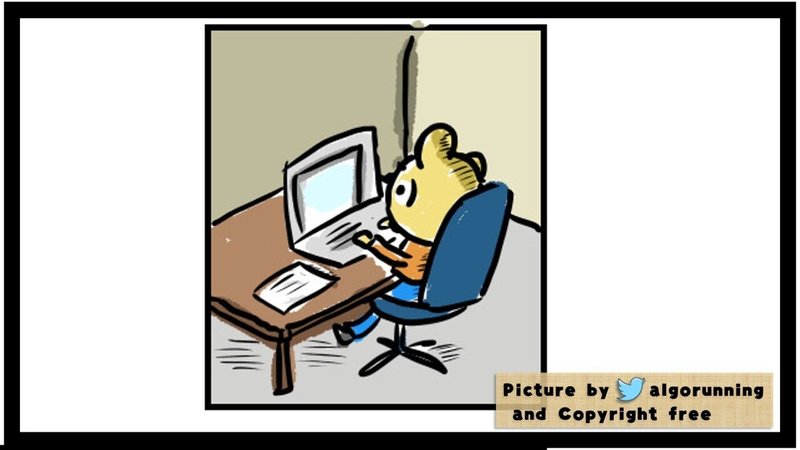
相談員がAさんの担当在宅ケアマネに利用の中止を連絡したところ、事前情報にはなかった事実が判明しました。
Aさんは障害のサービスから介護保険に移った後、市内の別の特養に本入所していたというのです。
そして、そこの施設長に土下座をされて、やむなく退所をしたということでした。
退所後、うちのショートステイを利用し、結局うちも断ったという状態です。
特養を退所する理由として、
●亡くなった時
●入院をし、戻って来れないと判断した時
(療養型などに映る時含む)
●在宅復帰する時
などです。
それ以外の理由で退所するなんてことは、よほどの理由がない限りありません。
Aさんが前の特養を退所した理由は、Aさんの言動やそれに対応する職員の苦労なども加味すると、何となく想像はできますよね。
でも、施設長が土下座って・・・・。私はそんなことあるのか、とちょっと驚きました。
ご利用者の課題を隠す在宅ケアマネ、余計に印象悪くなる

Aさんがいろいろワケありだったのは、在宅ケアマネなら重々承知なはず。当然ですよね、その人のケアマネなんですから!
当然、ショートステイとしてサービスを提供する私たちにも、その情報は必要だったはずです。
ですが、特養に本入所していた事実や、理由があって無理やり退所させられた事実をケアマネは隠していたのでした。
結果的に私たちの施設もご利用をお断りしたから、その事実が発覚したわけですが・・・。
そのケアマネジャーに限らず、困難なご利用者をサービス事業所に受けてもらおうとするあまり必要な情報を隠すことは、決して珍しくはありません。
というか、大体大変なご利用者というのは、来てから大変だ・・・ということがわかるものです。
事前に
「この方、ちょっと大変ですよ。他でも断られたんですけど、よろしくおねがいします」
という感じで教えてくれるケアマネの方が少ないかもしれませんね。
ただ、正直にそのご利用者特性などをお話しないことって、まったくもって誰も得しないと思うんですよね。
迷惑するのは、
●情報を聴いていなかったサービス事業所
●必要な情報がサービス事業所に行かなかったことで、スムーズなケアをウケられないAさん自身
●様々な施設、事業所から利用を断られて、困惑するAさんのご家族
だったりします。
CMの立場からすると、大変な利用者の大変な情報を全部伝えたら、サービスを受けられなくなるかも・・・と思っているのかもしれません。
でも、一度そういうことがあると、またそのCMから来るご利用者は本当に何も隠し事がないのか・・・?と疑ってしまいます。
そして、CMと事業所の信用が崩れるのは、結果的に誰も得しません。
様々なサービスをお断りされてしまう困難なご利用者に対して、私たちはどうやって接していけばいいのか?

しかし行き場を失ったAさんのようなご利用者とご家族は、一体どうすれば良いのでしょうか?
私たちサービス提供者側の中では
「受けてあげたい」
という気持ちがある一方で、
「ε-(´∀`*)もう来ないのか、ホッとした」
という職員もいるでしょう。
人格を否定されるようなショックを受けた職員からすれば当然のことです。
この記事の冒頭でお話しましたが、私自身の十数年の福祉職人生の中で、お断りしたのはその方だけで、大半はうまくいったのでした。
次回の記事ではそのケースについて、いくつか触れてみたいと思います。
つづく・・・
サポートですか・・・。人にお願いするまえに、自分が常に努力しなくては。
