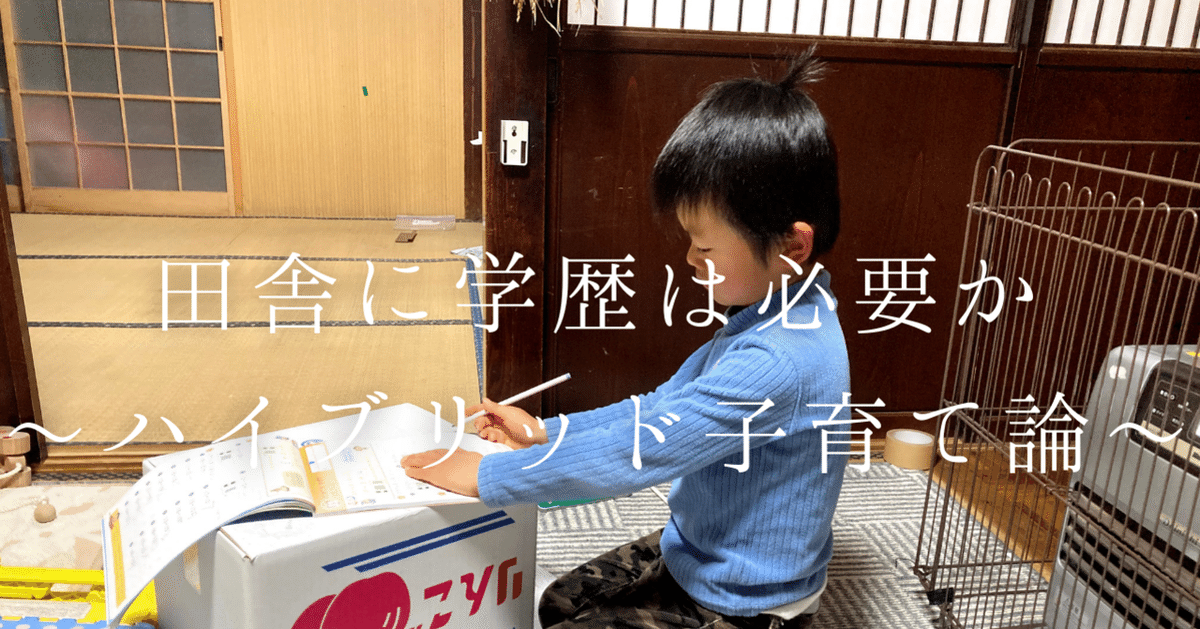
田舎に学歴は必要か ~ハイブリッド子育て論~
「お前、大卒だったな。オレは高卒だ。高卒だけど、知恵はたくさんあるんだ。」
恵那の田舎に住んでもう8年になるが、いまだ近所の年配の方に会うたび、そうすごまれる。
当方としては特に大卒を自慢した覚えはないのだが、都会から来た大卒者、ということが何か気に障るのか(いや全然悪い人ではないのです。むしろよくしていただいている人です)。
近所だと大卒なのは役所に勤めている一部の人、若い世代含めて大概は高卒→就職、という人が多い。田舎の教育レベル云々ではなく、妻の地元の友人たちには、大学に進学している人が割合多いと聞く。それも全国の有名どころだったりする。つまりそれらの大学行った人たちはその先から帰ってきてない、ということらしい。
大学卒業以降、あまり学歴がフィーチャーされる世界にいなかったので、あらためて、お前大卒だろ、と言われることや、この先の子育てで必ず直面する進学のことを考えると、どうも学歴というものはこの先も自分を振り回してきそうだ。
今回は田舎での学歴にまつわるあれこれと、これから子育てする上で田舎であることの可能性について書いていきたい(7000字)。
看板の写真は、自らリンゴの段ボール箱を机代わりにして、勉学にいそしむ長男である。令和であることに間違いはない。
1.受験戦争に揉まれた日々
冒頭に書いたが、オレの最終学歴は大学である。
そこに至るまで熾烈な中学受験を戦い、界隈ではそれなりに名のある私立中高一貫校に通った経験を持つ。
そこまでして合格した中学ではじめた吹奏楽部で出会ったドラムに没頭、すぐに「オレはドラムでプロになる!」と勉強を捨て去った。
当然成績は一切浮上することなかったのだが、それでもオレのドラマーとしての将来を親に納得させるには、大学までは行っておかないとという思いで、受験。
門前の小僧とは恐ろしいもので、学年で最下層、参考書はドラムマガジンという状態にもかかわらず、現役でバンバン東大やら早慶やら当たり前に受かるやつらのなかにいるだけで、都内の中堅私立大学に受かるだけの学力がついているものである。
晴れて自由だ、何かを勘違いして大学に通い出すも、オレにとってはドラムでプロになるための免罪符のようなものだったので、ここでも教室にいく手前でジャズ研の部室に吸い込まれる。単位は音符となって霧散しあえなく留年、5年をもって卒業を果たす。
2.「大卒」の使い道
さて苦労して得た最終学歴「大卒」は、オレが大学卒業後既定路線通り音楽活動に邁進していくことで、大卒者の大特権「新卒採用」の唯一の機会を放棄し、その意味を失った。
スタジオ系ミュージシャンを志していたのだが、ここでは大卒なんてものが何か役に立つことなどはほとんどない。この界隈いろんな人がいるが、基本的には実力勝負の世界。中卒だろうが大学院までいこうが、同じ土俵に上がってグッドサウンドだせりゃOK。
ジャズ系だとまた○○大ジャズ研出身みたいなものが幅を利かせたりすることもあるが、まあ実力がなければ仕事がないのは同じだ。
自分が大卒だと意識する場面は、バイトの履歴書を書くときだけに限られてきた。
大学卒業から10年後に地域おこし協力隊に応募した際には、社会学部社会学科卒業、と書いたことで、何か社会に対してアカデミックなアプローチができそうな見栄えだけはするなと、悦には入ったが、実際問題パラディドルで詰まったオレの大学生活から社会学の見識を呼び起こすことは至難の技だった。
いや、むしろ任期中、役立つかもと思って中途半端に社会学的なことを学びなおしたことで、かえって現場にアカデミックっぽいものを得意げに持ち込み、町の人たちを混乱させ、己も混乱し、地域と自分との距離感を埋めることを妨げていたと感じる。
前の記事でも書いたが、地域の人たちはそんな屁理屈で生きているわけじゃない。
自分たちで暮らしを築いていかなくてはならない以上、頼りになるのは世代を超えて伝えられてきた知恵と、自らの経験と、ある種の勘。
地域に大学の研究室が入って地域活性化の実践研究とかやったりしているが、確かに自分たちには気が付かなかった目線が提供されることで、思考の攪乱を起こし、うまく回れば地域全体が活気づくこともあろう。
しかし、あくまで外からの目線を咀嚼し実行するのは地域の側である。アカデミズムそのものが地域を変えるわけではない。それはそんな研究室をあちこちで見かけ、その顛末を聞いて、確信できたものである。
だからアカデミズムは必要ない、と言っているのではない。田舎の在り方を過剰に美化するつもりもない。
むしろ、学ぶ姿勢のある住民たちが地域活性化の大きなカギになる、言い換えれば住民たちが学びたいと思えるように興味を湧き立てる工夫が必要であることをアカデミックな立場の人たちは知ってらっしゃる、んだよね?
3.学歴より大事なこと
まあそれはいいとして。
協力隊を終えて、さらに農山村部に引っ越したことで、大卒という肩書はもはや風前の灯となろうとしている。
ここではフローチャート作って新しいローカルの青写真を語るよりも、トラクターを動かせる方が価値がある。ロープの結び方を知っている、チェーンソーで木が切れる、マニュアルの軽トラを乗れる。冬場スタッドレスタイヤに交換しようと車屋さんに持っていくと、これくらい自分でできるでしょう、と暗に言われる(いやオレはやってるよ)。
小難しいゴタクよりも、サバイブできる能力が実際に必要なこの地で、オレはとことん無力と感じる。
そんなの学校や大学で習わんかったし。
そんなの得意な人が得意なことやってくれたらいいじゃん。そう言いたくもなるが、そんな問いかけはここでは無意味だ。一人ひとりがたくましく生きていくことが求められ、その美意識をひしひし感じる。
冒頭でおじさんに言われたように、そのサバイバル術に長けた地元の人たちから湧いて出てくる生活の知恵の前に、学歴があることは何の意味もなさない。
ここには学歴を追い求める空気はなく、熾烈な受験戦争を肌で感じることはない一方、逆に言えば、大学まで進学するには相当な理由があるはずだ。
オレが現役大学生時代の周りに多くいたのは、とりあえず入っておこうと思って、とか、親から将来大企業に入れば生活安泰だからと言われているから、というなんとなくという受け身で進学する必然性がない人ばかり。
(まあオレがそういう人ばかり引き寄せていたのもあるだろう)
数少ないサンプルではあるが、こちらで聞いた大学進学者の進路としては、司法書士や経営者、高級官僚、教師など大学進学した必然性を持つ。
妻の通っていた地元の公立進学高校では、なぜその大学に行きたいと思うのか、目標のために最適な進路は何か、を先生たちが積極的にサポートする体制があったと聞く。
いや当たり前の話過ぎるのだが、何か受験戦争真っ只中に揉まれた者として、やりたいことがあって大学に進む、という意志に羨ましささえ覚えてしまうのだ。
4.常識を疑うために必要なこと
とはいえ高等教育なんて田舎には無意味だ、行く必要などない、と言うつもりもない。
前の記事で、ヨソモノが田舎の暮らしも知らずに変革なんて謳っていいのか、とか書いたにもかかわらず、田舎が末永い暮らしをこれからも営んでいくために、暮らしや仕事に必要な知識や経験”だけ”でいいのか、という疑問は常にある。
田舎を守るために必要と思われた経験則だけでは、外の世界の変化についていけなくなり、困窮してきていることは明らかだ。
オレが暮らしながら感じるのは、常識を疑う意識、がここには必要だ、ということ。
では地元の人たちの常識とは何か。
具体例は色々とあるが、ネガティブな方に集約すると以下のような言葉となる。
「ここには(魅力や資源が)何もない」
「ここには仕事がない」
「ここは不便だ」
「ここではやりたいことができない」
田舎に行けば驚くほど多くの人が同様に口にするのに出くわすだろう。
田舎を守るために自分たちの経験則で暮らしてきたがゆえに、著しい変化を嫌い、それがいつしか自分たちの地域をネガティブに捉えることで、変化から身を守るようになった。とオレは仮説を立てる。
ここに魅力があって、仕事もあって、便利で、やりたいことができる場所なら、どんどん身の回りのものが変わっていってしまうという不安に起因しているのではないだろうか。
しかし今まさに田舎が生き残っていくのに、常識からの脱却が必要だ。自分自身や妻のためにも、子どもたちのためにも、この田舎が末永くあってほしい。
そのためには、空き家や耕作放棄地が増えて荒廃してはやはり住みづらい。山林が放置されれば災害の危険も増す。行政の財政が厳しくなれば、インフラ整備もままならない。
人は少なくても、世代が循環していくバランスが必要だ。
だがこれらの問題に相対するには、持ち前の経験や知識、勘だけで太刀打ちできるだろうか。物事を俯瞰して見て外の世界と比較し体系的に整理することで、はじめて見える世界だってある。高等教育はその考える力を身につける場所でもある。
「ここにはいろいろあるじゃない」「仕事作れるじゃない」「やりたいことやれるじゃない」こんな”非常識”を運んでくるのは、やはりヨソモノだったり、Uターン者であったりする。
決して大卒である必要はないが、その多くはなんらかの専門知識の習得や社会活動に関わることで、広い世界とも深くかかわった経歴を持っていたりする。
前記事でも書いたが、普通に暮らしている地元の人たちにとって、ヨソモノが地域の変革を叫ぶことへのアレルギーは非常に強いと感じる。しかし、そういう人たちが地域の人たちと「暮らし」を共にし、自身の「暮らし」を通して、新しい価値観を表現している姿は、最初こそ理解されずとも、少しずつ共感を呼ぶはずである。
そうしてサバイブ能力に長けた人たちと、新しい常識を体現する人たちとが融け合わさった時、田舎ほど可能性のある場所もないだろう。問題はどうやって融け合わさるか、だ。
そのカギはやはり次世代に生きる子どもたち、ということになるだろう。
5.子どもたちの行く先
子どもたちのことを考えたときに、田舎の教育のデメリットとしてよく、選択肢の少なさが挙げられる。確かに進学できる高校の数も限られている。習い事にしてもバリエーションが少ない。
また基本的に大学に行くとなると、通学に時間がかかるので、たいていは一人暮らしとなり経済的な負担が大きい。
オレには2人のまだ幼い子供がいる。
受験戦争や学歴を求められない一方選択肢に限りがある中にあって、彼らがどのような進路を取るのか、ここで育ったわけでないオレには想像がつかない。
やはり大学まで行かせて幅広い見識を持たせるべきなのか。それともたくましく生きていく術さえ身につけば、それでよしとするのか。
もちろん元気でいてくれて、人の役に立つことを最初に考えられる人間になってもらえたら、多くを望むことはないだろう。
そのうえで、やりたいことをとことんやらせてあげたい、というのは一番に考えることでもある。
オレは、受験戦争を潜り抜けた先の進学校でドラムに出会ったという皮肉はあるが、好きなことをずっとやってきた。残念ながら花開くことはなかったが、それでもやってきてよかったと思ってる。ドラムを通して出会えた人や世界がオレを形作ってきた。そんな自分のライフワークに出会えたことは幸運としか言いようがない。
できれば子供たちにも、好きなことをしているときにしか味わえない豊潤な時間を知ってほしい。一つの世界を深く掘り下げていったときに出会える一つの真理のようなものに出会えた時の喜びを味わってほしい。
それが学術的なものであってほしいと心のどこかで思っていることも隠せるものではない。学歴の価値を自ら蹴散らしてきたにもかかわらず、どっぷりとその世界に漬け込まれていた悲しい性かもしれない。
まあそれはオレ自身の課題だ。子どもにはビジネス的なものでも、アートでも音楽でも、自然や農業でもハンドクラフトでも、なんでもいいのだけど、自分はこれがやりたい、というものに出会ってほしい、と切に願っている。
ただでさえ選択肢の少ない田舎の中で、「常識的ではない」自分が幅広い分野のモノゴトを示していくのは役割だとも思う。
6.ハイブリッドな感性を育てたい
さて、もうすぐ小学生になる我が長男は、ロボットコンテストをテレビで目撃して以来、ロボットに夢中である。幸いにも市内にマンツーマンでロボットからプログラミングまでを指導してくれる教室があったので、ちょっと前から通わせている。探せばあるものである。
子ども向けにPythonをアレンジしたプログラムを教えてくれて、息子も楽しいようだ。
何も田舎に来てまでそんな都会の子みたいなことを、なんて言う向きもあるかもしれないが、
同時に彼は普段から家の周りにあふれる自然の中にあるものに触れる日常がある。
虫や花、鳥、季節の星座の移り変わりを自分の目で観察し、土に触れ、池の氷に触れ、川の冷たい水に足を浸す。そんなことも大好きだ。
時々小枝や石や花を集めては、個性的なオブジェを作ったりしている。

彼にとっては、どちらも同じ興味の土台にあるようだ。
彼を見ていると、自然への感性に優れながら最先端のテクノロジーにも精通するハイブリッドな知性を持った人物に育っていくのではないか、とさえ思えてくる。
まあ親バカではあろう。そんな期待通りにいくわけでもなかろう。
ではあるが、オレも持続的な社会を築こうとする人間として、子どもに接するときにはこんなことを心掛けている。
・自分のやっていることがどんな風に人の役に立てるのか考えさせる。
・少子高齢化、人口減少など地域の暮らしや社会の課題を明らかにし、どうしたらいいか一緒に考える。
・誰もが同じ考えとは限らない。正解が一つだとは限らない。
こういう意識が彼の中で根付けば、例えいったんは外の世界へ出るにしても、また地域の役に立とうと帰ってくる、という確証はない。
その答えは少なくともあと2~30年後を待たねばならない。
しかしあながち見当違いな方向性ではなさそうだ。もはやその流れは始まっているかもしれない、ということを次で見てみたい。
7.ハイブリッドな感性の育て方
これからはハイブリッドな感覚を持った子供たちが自分の地域に還元する目的で外の世界とつながりを持つ、ないしはアカデミックな教育を受ける、ということが地域の課題解決に大きな役割をもつことなことになるかもしれない。
そんな取り組みの先駆けになっているのが、海士町の事例だ。
まさに町の子どもたちが地域の課題に触れ、解決のために外の世界とつながり学び、自分たち自身で町のために動き始めている。まあなんと有意義な高校生活であろう。日本海の離れ小島にもかかわらず入学希望者が殺到している、というのもうなずける。
ここまで行政や全地域的な取り組みができれば言うことないが、なかなかハードルが高そうな話である。
そこでもう一つ身近な事例を紹介したい。
恵那のお隣、中津川市の中学生が世界的な発明コンテストで銀賞を受賞したというニュースが2020年秋頃全国でもニュースになっていた。
現場仕事の職人さんであるお父さんを見て育ち、自分で作り上げる力を身につけながら、人の役立つことや世の中への幅広い興味関心が合わさって、課題解決を果たした。オレには彼の中にハイブリッドな感性が育っているように見えて仕方がない。
この中学生が将来どんな道に進むのかはわからない。アカデミックな研究など彼は必要としないかもしれないし、さらに興味を深めてその道を行くかもしれない。
どちらにしろ、彼にとってここはすでに、資源のある場所だろうし、やりたいことのできる場であるだろう。それが将来の仕事に結び付くかもしれないし、自分で仕事を作ることができる可能性だってある。
オレにとってこのニュースは、ものづくりが身近にある地方の教育の可能性を見た気がして、勇気づけられるものだった。
以上の話をまとめると、
結論:
学歴がなければ思い通りの人生を歩めない、なんてことは少なくともこの田舎ではなさそうだが、一人ひとりが地域や社会の課題解決のために自分は何ができるか、何がしたいか、そのために必要な学習機会はどこにあるのか、を次世代とともに考え、支えていくことは末永い暮らしのためには必要。
最後にオレの中高からの友人の言葉を紹介する。彼もまたオレと同じく子育て真っ最中で、子どもの中に育まれる多様性について、こんなメッセージを送ってくれた。
子どもは、(中略)、その交流を通じて関与者全員とその関係性を発展・成長させていく「シルクロードの街」のようなものでなければならない。
この言葉を聞いたとき、瑞々しい感覚が溢れてきて仕方がなかった。
地元の価値観だけでもなく、都会の価値観だけでもない。ましてオレの価値観だけでもない。地元に生まれ育った妻の価値観だってある。同居するお義母さんは「なにもない」を地でいくし、少なくとも中学まで変わらない息子の友人たちの家庭も移住組だったり地元組だったり、それぞれだ。
それらが子どもの中をあたり前にどちらもあるものとして行き来することで、豊かなオアシスの都市のようなものが子どもの中に広がる。
オレが今も移住希望者の相談などに乗っているのは、人口が増えてほしいから、ということだけでなく、そんな子どもたちが育つ場所であってほしいから、という思いがあるから。
進路に悩み自分探ししている人は、ぜひ我が家に立ち寄って、自分のいる場所とは違う価値観に触れてみるのも良い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
