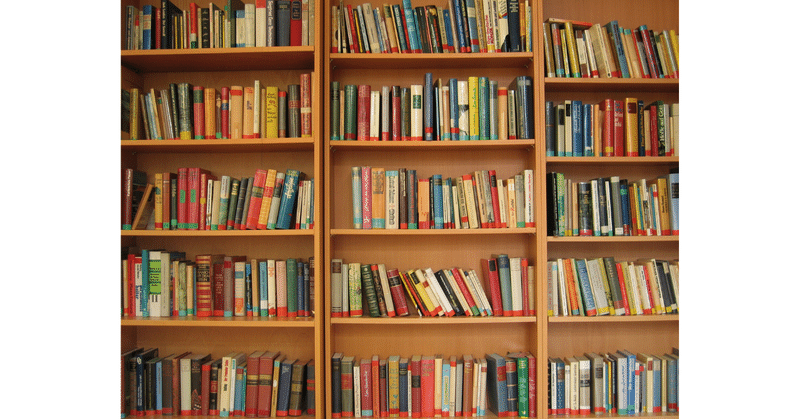
『頭のいい人が話す前に考えていること』 安達 裕哉
アマゾンで評判の本を読んでのメモと思ったことを書いてみます。
社会的知性
本書では頭の良さを社会的知性と学校的知性の2つに分けて、主に社会的知性に関する説明がなされている。
社会的知性の構成要素を➀他者の思考を読み、➁他者の信頼を得て、③他者を動かすと定義。
➀他者の思考を読む
・冷静に傾聴することの重要性。
・他者の思考を読むことで、結論から話しやすくなす。
➁他者の信頼を得る
・相手の立場になるか立ち止まって知識を使い、むやみにアドバイスしたり、知識をひけらかしたりしない。謙虚に。
・話す場合に事実と意見を分ける。
・コミュニケーションの中で整理しながら一緒に考えを深めていく。
・考えを深めるための、質問のクオリティは重要。
③他者を動かす
・言語化する側になることで「頭のいい人」と認識される。
・思考の質→言語化の質→アウトプットの質
・言語化するというコストを払うことで人が動く。
本当に頭のいい人
・大切な人を大切にできる人
所感
言語化するって難しい
思い返すと昔から言語化することが苦手で、「すごい」「やばい」を多用してコミュニケーションをとっていた。
大学に入学した頃から、講義の感想やレポートを提出しなければならず、思ったこと、考えたことをどう表現していくか悩んでいた。
そもそも、大学時代は言語化することが苦手だという認識もなく、「能力ないから仕方ない。」と割り切っていた。
看護師を経て、大学院に進学したあたりから言語化することが苦手な自分に気付いた。きっかけとしては、指導教官との関わりや、書物を読む中で指導教官の言語化のうまさと、自分の言語化の下手さを痛感した。
指導教官にどうしたら言語化がうまくなるか聞いたところ、文章を書いて、他人に読んでもらうしかないと言われた。
この本の中では、言語化の習慣の一つとして、読んだ本をアウトプットできるように「読書ノート」を作ることをあげている。 また、「やばい」「えもい」といった小学生並みの感想を使わないことも心がけるようにと。
言語化の訓練のために、本を読んで感じた、考えたことや身近な人と話して感じた、考えたことをアウトプットする場としても、noteを使っていきたいと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
