
大学=「個性」をのばすことで短所を補う
大学とは、長所をのばすことで短所を補う場でありたいと、そう願っています。あなたの欠点には興味がありません。いかにその光るところを見つけられるか、それをのばせるか、それが私の大学教員としての教育の役目だと思っています。
本田宗一郎とともに世界のHONDAを創った藤沢武夫さんの言葉に、こんな言葉があります。
私には欠点がない。だからナンバーワンにはなれない。
欠点があるかないかよりも、もっと大切な「何か」が問われていますが、さしあたりそれを「個性」と呼ぶことにします。
大切なことほど目に見えない。だからこその哲学。
安心安全デザイン研究室では、西田哲学をベースとして「個性」とは何かを扱っていますが、ここでは複雑な哲学の論理構造をなるべく避けて、「個性」について考えていきたいと思います。
まず、1つ言えるのは、見えたものは「個性」ではないということです。見えたものとは、比較によってとらえたものであり、固定したものです。自分の性格や特徴というのも他人との比較において見られるものである限り、それは「個性」ではないのです。
私たちは見えたことだけを見ているのではなく、また比較によってしかものをとらえていないのでもありません。言語にすると、比較でものをとらえるというあり方になるだけで、すべてが言語で表されるということではありません。そのため、日常言語では表しきれない何かを論理的に扱う際には哲学が必要となるのです。

「個性」は「もの」ではない
「個性」は観念的に考えられるものではないため、「個性」とは何かを考えるためには、それを正しく問うこと=「行動」が求められます。
われわれは、現在形で生き、完了形で認識する。
ものづくりを行う工学部はこのこと=「行動」を大切にします。ここで言う「行動」は、何かと何かとの間合いを取ることであり、計測可能な動作や運動とは異なります。
物理的には動いていなくても、それが間合いを取ることである限り「行動」です。目には見えません。そして、そのこの間合いを善くすることが「個性」の働きです。
「個性」は一人だけのものではない。
間合いを取る「行動」は自分と他者、あるいは自分と組織や社会など、何かと何かとの「あいだ」で行われます。この「あいだ」は自分だけのものでも、相手だけのものでもない、自他の分別をしないような「こと」の場です。
「個性」はこれを善くするため、自分にとっても、相手にとっても、またそれを取り巻く環境にとっても善い作用となります。あなたがその「個性」を発揮しようと思ったら、誰かの「個性」を豊かにすることと同時に成立することになります。
それはチームが勝つためにやるということ
栗山監督の仰るように、二刀流はただ自分がやりたいからやるのではなく、「個性」を発揮するためにやるということなのです。
「個性」が豊かとは?
「個性」が豊かとは?と言われたら、具体例として真っ先にあげるとすれば、それは「季節」です。例えば、秋は秋だけでその「個性」を発揮することはありません。秋は木々や野鳥を秋めかせ、花や小川も秋めかせます。
秋になれば、あなたも秋らしく、一層あなたらしさが際立ちます。そうやって、秋はあらゆるものの「個性」を引き出すことによって、はじめて秋は秋としての「個性」を発揮するのです。

松下幸之助さんの奥様である松下むめのさんも、「個性」について次のように述べています。
あまり目を見張るような格好はおかしいと思います。
『あの人、えらいきれいな格好をしてたけど、どんな格好してはったかな』と、思い出そうとしてもなかなか思い出せないような格好、それが一番。
とっぴな、人の目をわざとひかせるような格好ではなく、わざとらしくなく、しかもその人をひきたてるような服装。やはり自分の個性に合う服装ということになるでしょう。
「個性」は場も引き立て、自己や他者の関係もよくします。組織の中の歯車の一つとなっても、あえて目立つことをしなくても、あなたらしい「個性」は必ず発揮できます。ですから、松下幸之助さんもおっしゃるように、『必要のない社員(人間)など、一人もいない』のです。
いま、日本のものづくりに「見えないものを観る力」が必要とされていて、そのことを多くの方に知っていただきたくて、noteでの記事を展開し始めました。
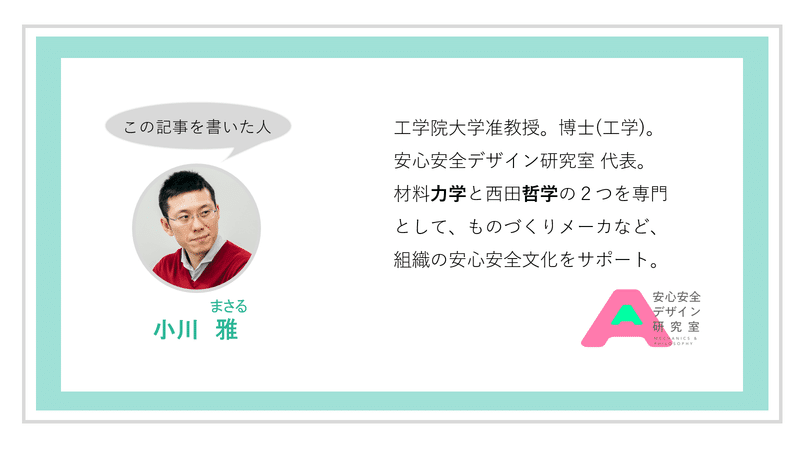
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
