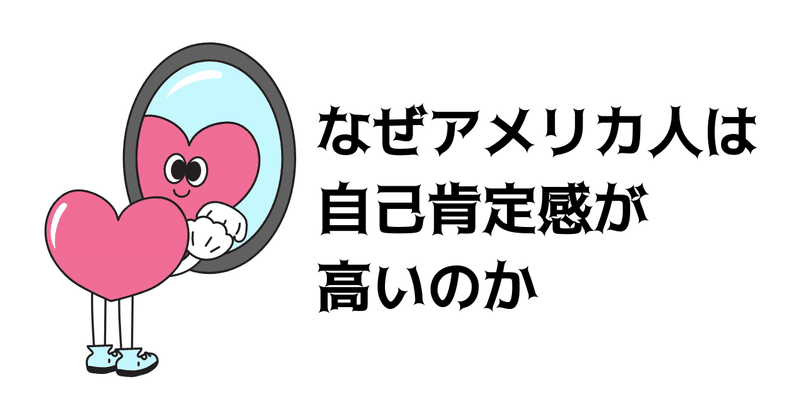
なぜアメリカ人は自己肯定感が高いのか
自己紹介
ご覧頂きありがとうございます。新卒で食品会社に就職し、営業職を経験したのちにアメリカの子会社に赴任。約10年間海外駐在しています。
自分自身への備忘録も兼ねてアメリカでの体験や自身の考えをnoteに残していきたいと思います。同じ境遇やこれから海外に挑戦したいという方にとって少しでも参考になれば幸いです。
はじめに
アメリカで仕事をし始めた時、「知っている」「出来る」というアメリカ人に任せて痛い目を見ることが何度かありました。そういう痛い目を何度か経験した後、まず言っている通りにはならないということを学びましたが、出来ない・知らないなら最初にそう言ってよと彼らの言動が理解できませんでした。
私はそこには彼らの自己肯定感の高さがあると思っています。
日本人の10分の1も怒られていない?
アメリカで子育てをしていると怒られるという経験が日本と比較して相当に少ないなと感じます。感覚的に10分の1程でしょうか。もしかしたらもっと少ないかもしれません。
例えば学校教育において、日本であれば廊下を走っている生徒がいれば、先生は「廊下を走ってはダメ」とか「誰かにぶつかって怪我でもさせたらどうするの?」というような注意の仕方をすると思います。
しかし、アメリカの先生は「歩いてくれると嬉しいな」というような禁止というよりは協力を求めるような言い方をして、素直に聞いてくれた生徒には「ありがとう」とまで言っています。
廊下を走るというルールを破っていた生徒が最後には感謝をされる…、日本で育った私からするとなんとも違和感のある光景でした。
そもそも日本の学校教育には意味わからないようなルールが数多くあります。私が通っていた高校では整髪料の使用は禁止されていました。寝癖だらけて登校している生徒はOKですが、整髪料できっちりセットしてきている生徒はルールを守っていないことになります。社会に出ると整髪料で身だしなみを整えるのは社会人としてのマナーですが…
そのようなよく分からないルールがあり、日本の学生はよく分からないところで怒られて育ちます。むしろどんな理不尽なルールにも従順に従う、理不尽さに対しての耐性をつけるためにそういう仕組みになっているのかと思うくらいです。
そんなことを守らせる為に生徒を指導しなければならない教員の苦労も大変なものがあるのではないでしょうか。
逆にアメリカではドラッグや銃というもっと深刻な問題から子供達を守る必要がありますので、それら以外はどうでも良いというのが実際のところだろうと思います。
また怒る代わりにペナルティという仕組みが存在します。小学生でも謹慎処分があったり、義務教育にもかかわらず学校からキックアウトもあり得ます。そういう意味では日本より厳しい部分もあります。自由の国とはいえど、自由には義務が伴うということですね。
いずれにせよ、怒られるということは自己肯定感に少なくないダメージを与えると思います。ただ怒られるという経験が足りていないが為に、社会に出てから、少し注意を受けただけで激昂してしまうようなアンガーマネジメントが出来ない大人も多々いるようです。
自分の意見を幼少期から求められる
そしてアメリカでは小学生の頃から自分の意見を伝えることを繰り返し訓練します。時代もあるのでしょうが、小学校高学年の娘がGoogle Slideを使ってプレゼンテーション資料を作っている時には驚きました。
そのようなツールを使って何度も自分の意見を伝える訓練を幼少期からつみます。積極的なディスカッションも行われるようです。自分の意見を持たない生徒は評価されませんので、生徒も必死のようです。
正しい・正しくないはそれほど重要ではなく、自分の意見を論理立てて説明すること、異なる意見があることを受容することが求められます。
そういう意見が受け入れられるという経験を幼少期から繰り返すことで自己肯定感が高まっていくのだろうと思います。
日本は世界的に見ても極めて同一性の高い国民性ですので人と異なる意見を持つことに対するハードルはどうしても高くなってしまうと思います。
また同一性が高いとどうしても正しい・正しくないという評価になりやすく自己肯定感の醸成には繋がりにくい部分があるのではないでしょうか。
200%自信がないとYesと言わない日本人
50%でYesと言うアメリカ人
最後にYes(出来る)に対しての基準の違いがあるように感じます。
日本のビジネスの現場では多少の問題が起きても大丈夫という確証があって初めて「出来る」と言うと思います。それは出来ると言ってできなかった場合、信用を失う、責任を取らされる、人に迷惑をかけることを恐れるからだと思います。
逆にアメリカ人は感覚的にではありますがおそらくは50%くらいの確度で出来ると言っているように感じます。どちらかというと、それは約束というよりは意思表明であり、彼らはそこから有言実行になるよう努力しているように思います。
ここには紳士協定の日本と契約社会のアメリカという前提の違いがあると考えています。つまり日本での口約束は実質的に”契約”(破れば信用を失う)であるのに対して、アメリカではさほど大きな意味も持ちません。約束を果たせなかったのは十分なサポートを得られなかった為だと平気で言ってくる人もいます。このあたりは高い自己肯定感の弊害(=自分は悪くない)だなとは感じますが…
しかしながら成長という意味合いにおいては確実に出来るとわかっていることに取り組むのと、実力以上のことに取り組むのとではどちらの方が良いでしょうか。私は後者だと思います。
成功確率は結局半々くらいなのかもしれませんが、困難な課題に挑戦して成功することにより成功体験を積み、それらがさらに自己肯定感の醸成につながっていっているような気がします(もちろんそれが逆に働いたらどんどん自己肯定感は下がっていくだろうと思います)。
日本の場合、出来て当たり前のことに取り組んでいるとしたら、たとえ成功しても成功体験の蓄積にはつながらないのかもしれません。当然自己肯定感の醸成も叶いません。
ここの感覚の違いに気付いてからは、プロジェクトマネジメントの要点を抑えることができるようになり、痛い目に遭うこともなくなりました。
最後に
自己肯定感の醸成にはもっと多くの要素が関わってくると思いますが、怒られる(=自己肯定感が下がる)経験が少ない、意見が受け入れられる、成功体験を積むということがアメリカ人の自己肯定感の高さにつながっているように感じます。
日本では社会・文化的に自己肯定感を醸成するのは難しい部分は確かにあるように感じます。特に相場観がなく他者からの評価がそのまま自己評価につながってしまう幼少期は。重要な人格形成期に必要は自己肯定感を身につけられなかったのだとしたらそれは勿体無いなとは思います。
しかしながら社会に出て、色んな経験を積むことで他者の評価を受け入れつつも自分自身の物差しで自己評価を下していけるのではないでしょうか。それが出来るようになってくると自己評価を高めていく好循環を作っていくことができるかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
