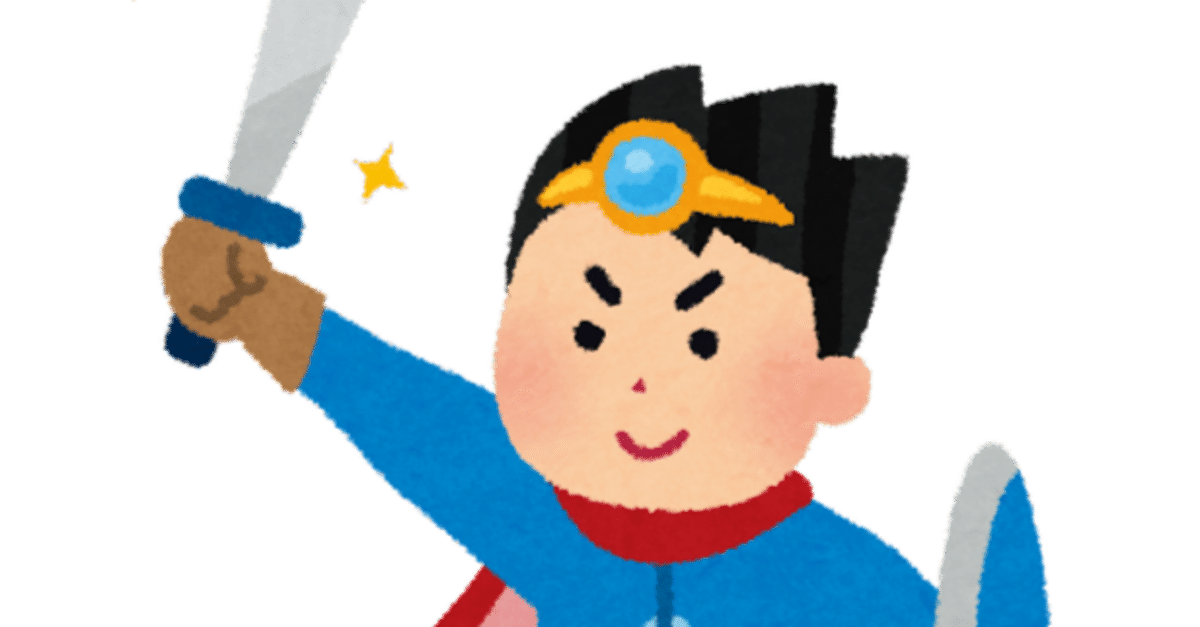
【独自考察】失われた《Love Song 探して》の理由に迫る
~スーファミ版ドラクエ2をプレイして違和感を感じたところ(その2)~
スーファミ版のドラクエ2をプレイしていく中で、特にファミコン版の記憶と比較して、私が違和感を感じたところを、良し悪し含め、とりとめもなく、ダラダラとここに記していくシリーズの「その2」という位置づけで書き始めたのだが……もはや内容は、《Love Song 探して》中心となってしまったので、タイトルも改めた。
いずれにしても、まだ「その1」を読まれていない方は、ついでに読んでいただければ幸いだ。
ということで、以下の内容は、ファミコン版では非常に旋律的だった《Love Song 探して》という楽曲が、スーファミ版では、どうして非常にシンプルなピチカートアレンジとなったのかを個人的に考察したものである。
○《Love Song 探して》とは……?
まず、《Love Song 探して》という楽曲について簡単に説明しておきたい。この曲がゲーム内で最初に使われたのは、ファミコン版ドラクエ2の復活の呪文(又は名前)入力する際の音楽で、いかにも、すぎやまこういち氏の作曲らしい、非常に旋律的でメロディックな音楽だ。復活の呪文の入力というのは、当時の小学生のプレイヤーにとってはゲームが始まる前の数分間の苦行だったのだが、そんな気持ちを和らげてくれるには十分すぎる快活な音楽だった。
FamDQ2Love.mp3
余談だが、やはりこんな苦行は早く終わらせたいという気持ちが強かったのか、我が家では、復活の呪文を競うようになるべく早く入力することが兄弟間でのバトルに発展していた。具体的には、曲の1ループが終わる前に入力が終われば「勝ち」という遊びだったのだが……これ、物語が進むにつれ復活の呪文の文字数が多くなってくると、意外に難しい。
なお、ファミコン版においては、この曲は、ゲームプレイ中にも聴くことができる。それは、とある街のとある街人に話しかけることで、街の音楽がこの《Love Song 探して》に切り替わるのだが……この音楽を聴きながら、街の中を散策しながら買い物したのも楽しかった思い出だ。
この辺に関連した裏話は、実は、次の記事が興味深い。
○スーファミ版ドラクエ2における《Love Song 探して》の違和感
さて、今回スーファミ版のドラクエ2をやってみて、まず、この曲を聴く時間がほとんどないことに気づかされる。それは、当然に「復活の呪文の入力の必要がない」からであり、復活の呪文の入力が、冒険の書を選択するたった数秒間に置き換わったことに他ならない。一応、冒険の書選択以外にもゲーム開始直後の名前入力の場面でも聴くことはできるが、同様に、名前入力もそんなに時間がかかるものでもなく、かつゲーム開始時に1度しか入力しないものであり、短い時間であることに変わりはない。
違和感はそれだけではない。聴く時間が短いどころか、あんなに旋律的でメロディックな音楽だったものが、どうしても表現の幅に制限のある弦楽器のピチカートアレンジとなってしまったのだ……。
SFamDQ2Love.mp3
いや、このアレンジはこのアレンジで、なかなか素晴らしい。ちょっと聴くと、まるでチャイコフスキーの交響曲第4番の第3楽章を彷彿させる(特に、このピチカートアレンジのオーケストラ版を、少し(1.2倍程度)早く再生すると、よりその印象が強くなる。)。
Tchai4-3.mp3
(1966年、カラヤン(指揮)、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団)
ただ、個人的には……私は、もっと違ったアレンジが聴きたかったのだ。当時のファミコン版のサントラは、東京弦楽合奏団による演奏であり、これは、いわゆる管弦楽にドラムセットとベースとサックスを組み合わせたような編成とでも言えるのだろうか。これがまた、80年代ポップス感いっぱいの、すがすがしく気持ちのいいアレンジで、特にサックスのソロが非常にいい味を出してくれている。ドラクエ2も、ファミコンからスーファミに進化して音色も豊かになったことから、私は、スーファミ版の《Love Song 探して》は、このような気持ちよくも心地よいアレンジを想像していたのだ。
FamSntrDQ2Love.mp3
(1987年、東京弦楽合奏団)
しかし、どうしてこのすがすがしい CD アレンジベースをスーファミ版に採用しなかったのだろうか……。
なお、念のために書いておくが、私は、決してすぎやま氏をディスったり否定したりしているわけではない。というのは、彼は、制作側の注文どおり、求められたとおりに作成しただけだろうと考えるのが自然だからである。
では、なぜ、制作側は、このようなピチカートアレンジにしたのだろうか。このことについて、以下、考察してまいりたい……。
○冒険の書の選択画面(復活の呪文入力画面)の音楽の歴史
さて、どうしてこの《Love Song 探して》が、スーファミ版になってピチカートアレンジになったのを知る手がかりとして、まずは、ドラクエシリーズの冒険の書選択画面(復活の呪文入力画面)の音楽から振り返っていきたい。
・ドラクエ1(ファミコン版)
ファミコン版のドラクエ1(以下、特に断りがない限り、全て初出のものとする。)においては、《街の人々》という、いわゆる街の音楽が流れる。もしかしたら、単に呪文入力時の音楽を用意していなかっただけなのかもしれない。ドラクエ1の音楽については、開発の終盤になった段階で、すぎやま氏の音楽に差し替えられたと言われているし、ゲームのロムカセットの容量も制作期間も限られていただろうから、既に用意された楽曲の中から何が一番ふさわしいかを考えたときに、この街の音楽が選ばれたのではないだろうか。
・ドラクエ3
ドラクエ3では、特に音楽は流れない。
「いや、超低音の三角波の音が聞こえてくるだろう!?」
というマニアックな声が聞こえてきそうだが(笑)、ここは一般には「無音」ということで問題ないだろう。
FamDQ3Select.mp3
参考までに、この超低音の三角波の音は、NES BAND(マツケんさんをリーダーとする実機演奏バンド)においても、きちんと採譜されているので、これは単なるノイズではないと言っていいだろう(ドラクエ制作側が意図したものかどうかは別として。)。
これも1同様、既にある楽曲の中から何か選んで流してもよかったのだろうが、実は3は、タイトル画面も非常にシンプルだし、容量の都合で音楽を流す余裕もなかったのではと考える(そもそも、冒険の書を選択するのも一瞬だし。)。
・ドラクエ4
ドラクエ4は、全5章からなる物語だが、その章と章の間に《間奏曲》が流れる。《間奏曲》の意味を調べれば、
劇や歌劇などの幕間に演奏される軽い音楽
とのことであるが、
これは、実際にドラクエ4において、章が変わるタイミングでそれぞれの物語の間の区切りとして流れる音楽だ。
ドラクエ4においても、(ドラクエ1のように)冒険の書選択画面の音楽を考えた際、既にある楽曲の中から何か選んで流すとなれば、やはりこの《間奏曲》がピッタリだったのではないか、と考えている。
FamDQ4Intermez.mp3
・ドラクエ5~7
私が実際に遊んだドラクエシリーズは、実は7までなのだが……少なくとも5以降7までにおける冒険の書選択画面の音楽は、この《間奏曲》で定着している。5も6も7も、特に章区切りの作品というわけでもなく、ゲームプレイ中においては、この《間奏曲》が使われることもないので、この曲は、わざわざこの冒険の書選択の時の音楽として用意されたと言えるし、いずれにしても、ここにこの《間奏曲》が、冒険の書選択画面の音楽として確立されたと言っていいだろう。
SFamDQ5Intermez.mp3
・ドラクエ1(スーファミ版)
そして、いよいよスーファミ版となってドラクエ1も煩わしい復活の呪文の入力がなくなり、冒険の書選択へと切り替わったのだが、その際、音楽をどのようにするかと考えれば、それは、やはりファミコン版と同じ楽曲を選択するのが適当だろう。そして、その際、スーファミになって、音も豊かになったんだからどのようにでもアレンジできたはずだ。
とはいえ、スーファミ版ドラクエ1の発売時期は、既にスーファミ版のドラクエ5も発売済みの頃。前述のとおり、冒険の書選択においては、《間奏曲》が定着し始めた頃だ。よって、《間奏曲》をそのまま使ってもよかったのだろうが、ファミコン版の1の復活の呪文入力のときの音楽《街の人々》を尊重しつつも《間奏曲》のピチカート奏法の雰囲気も取り入れたことで、結果、《街の人々》のピチカートアレンジになったのではないだろうか。
SFamDQ1Name.mp3
とはいえ、さすがに街に入った後に流れる音楽がピチカートアレンジでは違和感がある。よって、街に入ると普通にスーファミの豊かな音色で《街の人々》が流れる。ということで、ここにスーファミ版ドラクエ1において、2つの《街の人々》が生まれることになったのだろう(ちなみに、このオーケストラ版の変奏曲風のアレンジは、大変に素晴らしい!)。
SFamDQ1People.mp3
○なるべくしてなったピチカートアレンジ
そして、いよいよスーファミ版のドラクエ2の話だが……。
この流れによれば、どうして《Love Song 探して》がピチカートアレンジになったのかについては、改めて説明するまでもないだろう。ただ単に、スーファミ版の1同様、ファミコン版のドラクエ2の復活の呪文入力の音楽《Love Song 探して》を尊重しつつも、《間奏曲》のピチカート奏法の雰囲気も継続した結果と考えるのが自然だ。
ただ、残念なのは……前述のとおり、スーファミ版ドラクエ1は、街の音楽と冒険の書選択画面の音楽ということで、それぞれ別々の――つまりは2つの《街の人々》があるのだが、スーファミ版の2の《Love Song 探して》は、ピチカートアレンジの1つしかない。結局、復活の呪文専用の音楽に成り下がってしまったのだ。
その後、ドラクエの音楽というのは、いわゆるゲームのサントラレベルから1つの音楽としての地位を確立し、今や、様々な楽器や編成で演奏されているが、少なくとも、私が確認できた次の編成における編曲にあっても、この《Love Song 探して》は、ピチカートアレンジがベースとなっていると感じる。
弦楽四重奏版(マティアス・ムジクム・カルテット)
金管五重奏版(東京メトロポリタン・ブラス・クインテット)
ギター曲集(南澤大介)
トロンボーン四重奏版(東京メトロポリタン・トロンボーン・カルテット)
ここまでくると、もはやこのピチカート編曲が原曲だったのではないか? くらい思えてしまう……。歴史の改竄とまでは言わないが、とにかく悲しくて仕方がない! どうしてこうなってしまったのか……。
ちなみに、ファミコン版ドラクエには、バイエル併用のピアノ楽譜が販売されていて、ほとんどの楽曲がファミコンのピコピコ音(原曲)に忠実な楽譜となっているところ、なぜかこの《Love Song 探して》は、前述のサントラ(東京弦楽合奏団による演奏)を元とした楽譜となっているのだ。これは、冒頭からファミコン版にはないシンコペーションから始まるので一目瞭然だ。
そして、実は、このピアノ演奏は音源として残っていて、具体的には「ドラゴンクエスト オン・ピアノ VOL.2」に収録されている。バイエル併用というと、どうしてもピアノ初心者向けのアレンジであり、やや薄っぺらく物足りなく感じるのでは? と思う方もいるかもしれないが、それでもこの《Love Song 探して》は、比較的しっかりと聴ける音楽に仕上がっているのでオススメだ(難易度も、バイエル終了程度となっている。)。
OnPDQ2Love.mp3
また、スーファミ版のドラクエ2における《Love Song 探して》以外の音楽は、この東京弦楽合奏団による演奏の影響を色濃く受けている気がしている。この辺の関係を図説すると、次のようなイメージになるだろうか。

もしかしたら、元々すぎやま氏の原曲があって、それを元にそれぞれファミコン版、同サントラ、スーファミ版に落とし込んでいるのかもしれないが、いずれにしても、この《Love Song 探して》については、東京弦楽合奏団による演奏のアレンジでスーファミ版にも組み込ませることができなかったのか――そして、やはり、そのとある街で歌わせることができなかったのか――と残念で仕方がない。
だいたい、スーファミ版のドラクエ2のラダトームの城の音楽を1の城の音楽を当てたり、2の竜王の城の音楽も1と同じにするようなこだわりを見せるのであれば、やはりここにもこだわってほしかったものだ……。
○(余談)すぎやまこういち氏のゲーム音楽に対するこだわりを垣間見る
余談だが、こだわりといえば、すぎやま氏のゲーム音楽のこだわりについて、ここに私が知っている範囲で記しておく。まずは、4の気球の音楽だ。
FamDQ4Balloon.mp3
気球に乗ると敵と遭遇することもなくなり、それこそこの曲のタイトルにもあるとおり「のどかな」空の旅が始まる。通常、戦闘シーンに切り替われば、曲も戦闘の音楽に切り替わり、戦闘終了後は、戦闘に入る前の音楽の曲の頭に戻ることになるが、気球に乗っている間は戦闘がないため、同じ曲を長く聴くことになる。そのため、この曲は1ループが比較的長い曲としてつくられている、というのだ。
また、スーファミ版のドラクエ2では、冒頭にムーンブルク城が魔物におそわれる、ファミコン版にはないシーンが挿入されるようになったが、この際の音楽も、まるで劇音楽のように、そのシーンと音楽のタイミングをピッタリと合わせている。これは、7における挿入ムービーでの音楽も同じような配慮をしていたらしい。
以上をふまえると、この《Love Song 探して》も、やはり復活の呪文の入力にそれなりの時間がかかることを想定して、その作業が苦とならないようにあえて長めで心地のよい旋律的な音楽を用意してくれたのではないか、と思えてくる。
ただまあ……スーファミでは、冒険の書を選択するだけで済むので、そんな苦行から開放されてしまったので、この曲の役目も終わった、という考えもなくはないか……。いや、しかしそれにしてももったいない!
○機種の違いによる音色などの違い
・ファミコン版とスーファミ版との比較
編曲の違いについては上に記してきたので、ここから先は、音色の違いなどに触れてみたい。
今回、改めてファミコン版とスーファミ版の音楽を聴き比べたのだが、やはり個人的にはファミコン版のピコピコ音が耳に馴染む。音の輪郭がはっきりしているし、頭の中で3つの音を区別して追いかけることができる。
輪郭がはっきりといえば、やはり呪いの音楽は特に強烈だ。これは、今聴いてもドキッとするし、3以降については、冒険の書が消えたときの音楽にこの呪いの音楽を当てるとか、センスが良すぎるというかインパクトが強すぎというか……ただでさえデータが消えてショックが大きいところにトラウマレベルが降りかかる。
FamDQ3Curse.mp3
ちなみに、この音楽を比較的簡単に聴く方法だが……ファミコン版の4であれば、「冒険の書を作る」を選択して、名前入力の最中にリセットすればよい。ちょっとやり直すつもりでリセットしただけだったのだが、タイトル画面の後に、間髪入れずに勢いよくこの音楽が流れたときには、本当にドキっとして心臓が痛くなる……。
それに対し、スーファミ版の呪いの音楽は、なんだかぼやけているというか、やはり音の輪郭がはっきりしていないイメージがある。
SFamDQ1Curse.mp3
あとは、以前の投稿でも記したが、スーファミ版は、ファミコンと比較して場面が変わった際の音の始まりと画面の表示のズレも気になった。
・ファミコン版と MSX版の違い
ちなみに、MSX版の《Love Song 探して》もまた、ファミコン版と違って、非常に興味深い音をしている。同じピコピコ音であり、一般の人が何気なく聞いたら違いに気づかないかもしれないが、少なくとも次の違いがある。
①三角波の有無
上にも書いたが、ファミコン音源には、アクの強い三角波と言われる音色のパートがある。これは、低音域においては、ベースのような力強い音を出しつつも、高音域では木管楽器のような柔らかい音色も出してくれ、非常に万能選手な音源である(なので「迷宮組曲」の楽器箱においては、それこそ本当にベースとピッコロの役割を引き受けている。)。
MeiKyuGakki.mp3
そして、MSX の内蔵のPSG音源には、この三角波に相当する音源が……ない。よって、ファミコンと比較して全体的に「しまり」がないような印象を受ける。
②ポルタメントの有無
逆に、MSX版にある要素としては、この曲中に数カ所ポルタメント(グリッサンド)がある。これは、ファミコン版ドラクエ2をリアルタイムでやった方ならすぐに聴き分けられるだろう。どうしてポルタメントを入れたのか……? については、前述したとおり、やはりこの曲が「歌」を意識していて、そのような歌い方に合わせて楽曲を作ったからではないだろうか。
③アーティキュレーション(各音の処理)の違い
これも、②と同様に、歌を意識した結果だと思うのだが、MSX版は、冒頭の単純な8分音符♪の羅列の場面において、テヌートとスタッカートか交互に現れるような、ややリズム感のある旋律となっている。
④調(調号)の違い
もうひとつの違いは、そもそも曲の調が異なっている。調というのは、ハ長調とか、まあそういうやつで、身近なところではカラオケでも歌いやすいように全体の音を上げ下げすることがあると思うが、まあそういうものだ。
より具体的には、ファミコン版はト長調で始まるのだが、MSX版では、ヘ長調で始まる。言い換えると、MSX版は、ファミコン版と比べて1音低めの音楽となっているのである。
ちなみに、《Love Song 探して》以外の曲も、他の曲も同様に、音が低くしているようだ。なので、全体的に少し暗い雰囲気も感じるのだが、逆に、どことなく落ち着いた曲調というか、より重々しいというか……ファミコン版よりもMSX版は、少し歴史ある風格すら感じられるのは、私だけだろうか。
FamDQ2Castle.mp3
MSXDQ2Castle.mp3
しかし、どうして MSX版では、ファミコン版と「調」を異ならせたのだろうか? これは、意図的な理由があったのだろうか。あったとすれば、それはどんな理由なのだろうか? これは、すぎやま氏から要望があったのだろうか、それとも制作側の都合があったのだろうか。又は、ハード的な制約などがあったのだろうか?
参考までに、だいぶ話はそれるが、ゲームボーイの「ロックマンワールド2」においては、「プログラムのミス」により、制作側の期待どおりに音楽が再生されていないのでは? とも言われている。
https://www.romhacking.net/hacks/4695/
確かに当時を思い出すと、「ロックマンワールド2」の音楽は、ややクセがあったというかキンキンとした違和感はあった。
MSX版のドラクエについても、このようなプログラムミスではないと思いたいのだが、「調」が違う理由についてご存じの方がいたら教えていただければ幸いだ。
ちなみに、スーファミ版の「調」は、ファミコン版と同じようだ。
⑤音の響かせ方の違い
音の響きというのは、やや曖昧な表現ではあるが、音の加工とも言えるかもしれない。実は、ファミコンの音源の矩形波というのは、何も音を加工しなければ、なかなかシンプルで単純な機械音だ。音量や音程を一切いじらなければ、ストレートで勢いがあり、むしろ耳に痛くも感じる。
例えば、ファミコン初の RPG と自称するゲームとして有名な(実のところシューティングゲームとして広く知れ渡っている)「頭脳戦艦ガル」というゲームがあるが、このゲームは、タイトル画面の音楽を始め基本的にシンプルな音色で、勢いよく耳に届くのが感じられるだろう(個人的には、このゲームの雰囲気に合っているので、嫌いではないのだが。)。
ZSGalgTitle.mp3
話をドラクエ音楽に戻すが、この辺の音の加工が、実はファミコン版と MSX版で異なっているように聞こえる。具体的には、ファミコン版は「振幅の短い音量の変化」でやさしい響きを表しているのに対し、MSX版は「振幅が長めの音程(?)の変化」で響きを表しているように聞こえるのである。言い換えれば、ファミコン版は、(ホールなどの)空間による音の広がり(残響)を意識した音作りをしているのに対し、MSX版は、それこそ歌を意識したような、もはやビブラートと言っていいような音の響かせ方なのだ。これは、ファミコン版と MSX版で異なったアプローチをもっていると言っていいだろう。
ちなみに、この時期の有名 RPG といえば、(「頭脳戦艦ガル」ではなく)「ファイナルファンタジー」(以下「FF」)があったが、FF シリーズの音楽は、豊かなビブラートが特徴で、私は、音の強弱による響かせ方よりも、音程変化のビブラートの音色の方が好みだ。また、ゲームボーイの「Sa・Ga2 秘宝伝説」(以下「サガ2」)のタイトルの音楽のビブラートが、本当に気持ちよかったこと!
FF3Opening.mp3
Saga2Title.mp3
ということで、以上を踏まえ、ここにファミコン版と MSX版の《Love Song 探して》のサンプル(やや長め、高音質)を掲示するので、違いを聴き比べていただきたい。
FamDQ2Love_L.mp3
MSXDQ2Love_L.mp3
このように、同じ楽曲の同じピコピコ音でも、楽曲に対するアプローチの違いで随分と曲の雰囲気が変わるのも面白い。
2つを聴き比べるとそれぞれに良さがあり、それぞれに魅力があるのが分かると思う。さて、みなさんはどちらがお好みだろうか……? 私自身は、ファミコン版の三角波の魅力も捨てがたいのだが、やはり、より音作りに豊富で風格も感じられる MSX版の方を聴き入ってしまう。
⑥(参考)テンポの違い
これは、《Love Song 探して》についてではないのだが、ドラクエ2の戦闘シーンの音楽について、ファミコン版と MSX版とで、テンポが異なって聞こえたので、ここに参考として残すものである。
以下、私の個人的な計測だが、ファミコン版が4分音符=130 に対し、MSX版は4分音符=138だった。要は、MSX版が、わずかに速いのだ! これは、ファミコン版をずっとやってきた世代なら違和感を感じられる程度だと思う。
FamDQ2Battle.mp3
MSXDQ2Battle.mp3
○おまけ
さて、ここまでいろいろなドラクエ音楽をサンプルとして掲示してきたが、こんな中途半端なサンプルじゃなくちゃんとした作品として最後まで聴きたいというアナタへ。ここに、私がオススメするドラクエ音楽の動画を紹介したい。私はもうここ3年以上、毎日彼のリコーダーの音色に浸りながら、毎晩自然と眠りについている……。
リコーダーという楽器は、多くの方が小学校で触れるので、なじみのある楽器だと思うが、そんなリコーダーでここまでの音楽を作り上げていることに、非常に感動したし感動できる仕上がりになっている。
私もまさか、こんなリコーダーというシンプルな楽器で、ここまで豊かなビブラートがかけられるとは知らず、
(これは本当に小学校で触れたあのリコーダーと同じ楽器なのか?)
と思ったのだが、そんなリコーダーでも極めてしまえばここまでの音色が出せるようになる、ということらしい(まあ、プラスチック製と木製の違いもあるとは思うが……。)。
加えて、上の動画は1人の奏者による多重録音なので、怖いくらいに息がピッタリ合っている。それだけでなく、音が複数重ねられているため音圧もすごい。決して「え? 単なるリコーダーでしょ?」を侮るなかれ。
ちなみに、この Rexさんが吹く《Love Song 探して》も、残念ながら……ピチカートアレンジがベースとなった編曲だ。ぜひ、東京弦楽合奏団による演奏を元にした編曲で、演奏していただきたいものである。
ということで、気がつけば、相変わらずダラダラととりとめのない文章が続いてしまったが、ここに、ここまで読んでいただいたことに大きく感謝したい。
【関連記事】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
