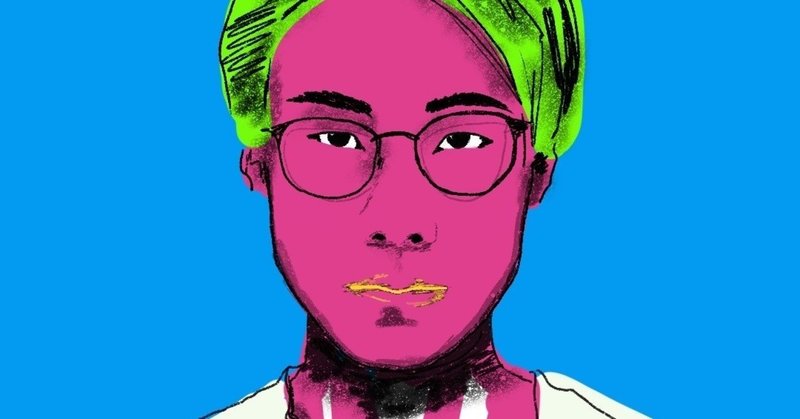
インターネットメディアを通じた感情との付き合い方を考えなければならない。
日も暮れようか暮れまいか、夕刻。ガラスの向こうで幼稚園帰りの園児が走る。買い物袋を下げた母親が追いかける。園児は目の前の「何か」に興奮して走り出し、母親はその先にある「何か」に危険を感じて引き留めようとしている、と勝手に妄想する。
まさに、これはインターネットなのではないかと思う。ガラスはスクリーンであり、外を行き交う人々は何千キロも離れた土地に暮らす人なのではないか。
このスクリーンの向こうで起きていることを「鑑賞する」ことは出来ても、僕には「通じる」ことは出来ないのだ。
エピローグ
8月30日から9月6日まで、僕はとある国際学生交流プログラムにオーガナイザーとして参加していた。バングラデシュと日本の大学生が、貧困と教育についてディスカッションとリサーチをする、実にお堅いプログラムである。
もちろん、このご時世海外に行くわけでないに、企画から運営まで全てオンラインでやってのけたのだが、僕はこのプログラムの「お堅さ」故に、「何も、面倒な感情のいざこざなんて起きやしない!」と高を括っていたが、それがどうにも間違いであったらしい。
言うなれば、この1週間は実に動物らしく、「感情」に苦しめられた。ただこれが普段の「感情」と違うことは、どこまで道を辿っても自分にたどり着いてしまうことらしい。
相手という目標を定めて出発したはずのそれらは、どんな険しい道を行っても、回り道をしても、どうやら最後には出発地点、つまりは自分という巣に還ってきてしまう。例えばそれはつもるところ、次のようなことである。
スクリーンの恐怖
プログラム開始の前夜(否、恐らくあれは既に正子を過ぎていたから「当日」が正しい)、バングラデシュ側のオーガナイザーに呼び出されて、緊急会議を開いたことがあった。内容は、プログラムの流れが理解出来ないということだった。
僕は突拍子もなしに言われたその事を、どうにも処理出来なかったと思う。
プログラムは明日(今日)始まるし、今更全てを一から説明するなど骨が粉砕するような作業である。万が一、修正を提案された日には、僕は首を吊ってやる!墓は要らねえ。粉々になった骨を海にでも撒いといてくれや!
その後は多分、必死に誰かが説明してくれたと思うが、記憶はあまりない。そのくらいの焦燥と悲憤と非情と滑稽さを感じていた。
さて、普段なら、この相手に向かって放出された僕の感情たちは、僕の使命のもと、何らかの形でもって終着点へと行き着く。それは必ずしも当初目指したところではないにしろ、少なくともどこかへは行き着く。一度旅に出たものが戻ってくることはない。
しかし、奇妙なことに今回は違うのである。どういうわけか、全てはまわりまわって僕の下に還ってきた。スクリーンのガラスによって跳ね返された感情たちは、行き場を失い、還ってくる他なかったに違いない。
こんなことは経験したことがなかった。いつだってどこかに道はあって、時間はかかれど、僕のために仕事をしてくれる彼らは、突如現れたスクリーンガラスによって道を遮られ、手土産なしに還ってくるのだ。もちろん還ってきたからと言って、彼らが休息に入るなんてことはなく、しっかりと僕の中で駆けずり回るのが厄介である。
僕はその夜、追い出すことも出来ない感情たちを抱えながら、一晩中目を開けていた。
ネオ・ヒューマン
これは、僕が今、口に含んだコーヒーを通行人に向かって吹きかけても、ガラスに遮られて、彼らには一向に届かないのと同じだ。もちろん、そんなことをする義理も動機もないのだけど、感情ばかりは義理や動機しかないのだから、はて困った。
「僕」に辿り着いてしまった感情たちは、静かにその生涯を終えるのを待つしかない。また旅に出ても無駄なのだ。スクリーンの向こうにいる、何千キロも離れた人々にはこのやり方では通じないのだから。
決して僕は、オンラインでの人との繋がりをやめようという話はしていない。むしろ、インターネットメディアを通した、感情との付き合い方を考えようと、あくまで楽観的に問いかけたいのだ。
僕らは知らず知らずの間に、スクリーン越しに顔を見、声を聞くだけで、二次元の人間を、三次元の人間だと認識してしまう性があるらしい。三次元人間のコミュニケーションは、新人類20万年の歴史が裏付けてくれるから、何も心配することはない。でも、これが落とし穴かもしれないことに、我々は気づくべきである。
つまりは、スクリーン越しで覚えた感情を、従来通りの伝達方法でやって良いわけがないのだ。何故なら、それのほとんどはガラスに遮られ、向こう側には通じないからである。自身に還ってきた感情と向き合うのは辛い。
オンラインは便利だ。現に、バングラデシュの学生と貧困・教育問題について深い議論を持てたのは何よりの財産であろう。しかし、我々がそこに発生する感情をさばけないのなら、オンラインがフィジカルを超えることは無い。我々が真に、インターネットに移行するならば、それは我々が「ネオ・ヒューマン」に移行した時だ。
果たして、スクリーンに抜け穴があって、実は感情は向こうに通じるのか。はたまた、還ってくるそれらを上手く飼いならすことでもって、上手く付き合ったことにするのか。僕にはさっぱりわからない。
しかし少なくとも、その議論をもう少し真剣に行う時が来たのではないかと思う。2020年を生きる一人の「ヒューマン」からの提案である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
