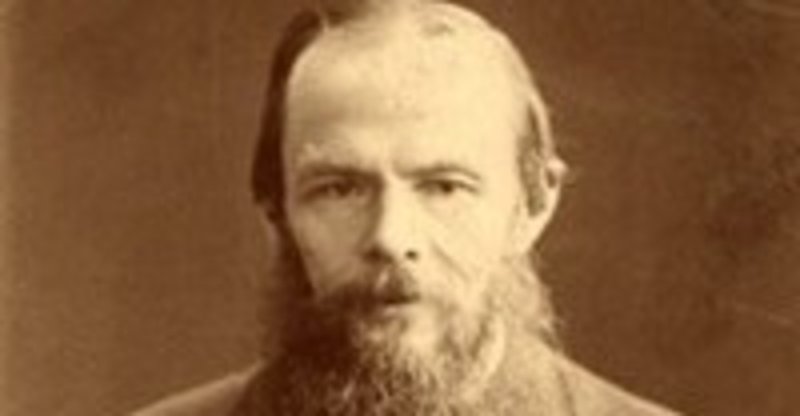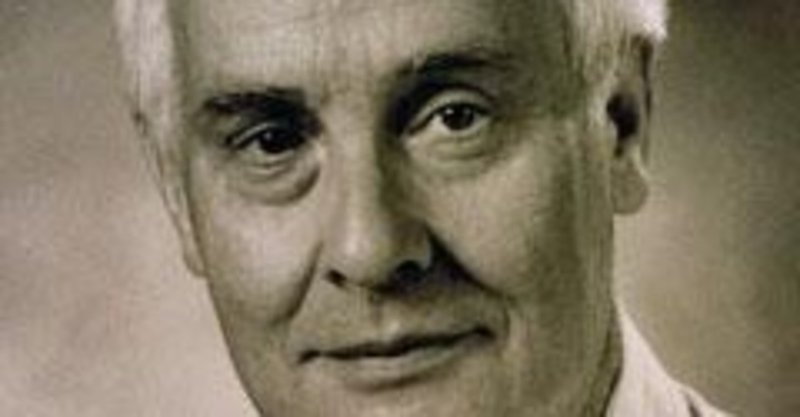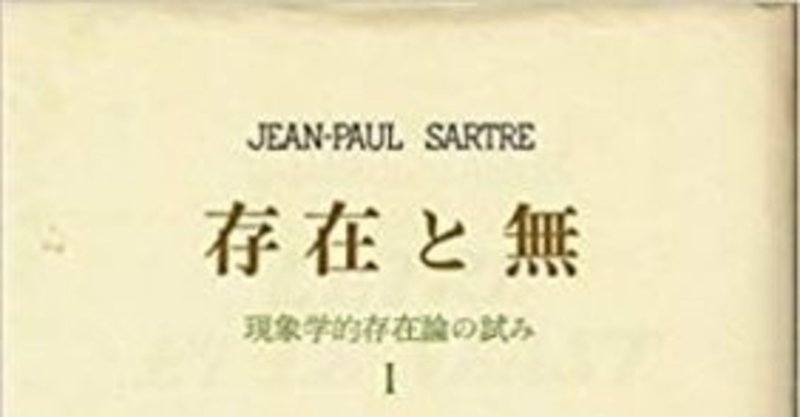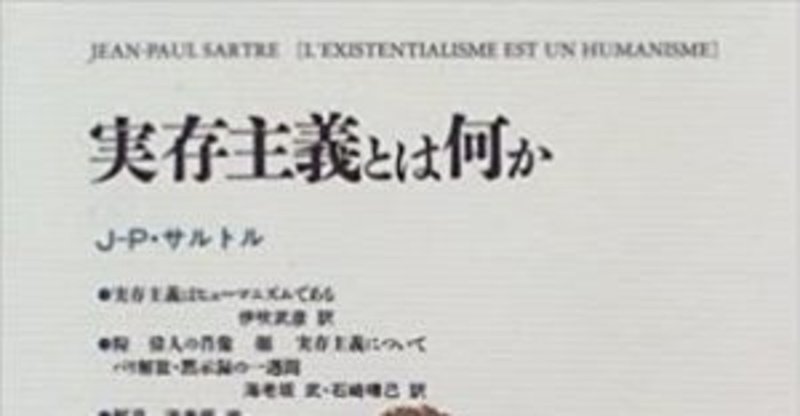2020年4月の記事一覧
ヒョードル・ドストエフスキー「罪と罰」(7)
予審判事がラスコーリニコフの自宅を訪ねてきた。彼は「老女殺しは病的な頭脳が生み出した事件だ」と話し始めた。ラスコーリニコフは動揺する。
『じゃあ…一体、だれが…殺したって?…』
ポルフィーリーは、あまりにも唐突な質問に驚いたかのように、思わず椅子の背にもたれかかった。
『だれが殺したか、ですって?…』
信じられないとでも言いたげに、ポルフィーリーはラスコーリニコフの言葉を繰り返した。
『
ヒョードル・ドストエフスキー「罪と罰」(6)
ラスコーリニコフは疑いを晴らそうとして、自分から予審判事を訪ねた。「ぼくを疑っているなら、訊問してください。なんなら、逮捕してもいい。証拠があるならね」
予審判事は答える。「その必要はありませんよ。この事件は放っておくのが一番です。そうすると犯人は不安になって、自分からボロを出しにやって来るんです。火に飛び込む蛾のようにね」
しかし、思いもよらないことが起こる。事件当日、同じ建物にいた職人が、
ヒョードル・ドストエフスキー「罪と罰」(5)
ある日、ラスコーリニコフのもとを一人の中年男性が訪れてくる。スヴィドリガイロフである。彼は多額の借金を肩代わりしてもらった代償に、マルファという女性と結婚していた。しかし、ラスコーリニコフの妹ドゥーニャに好意を抱き、邪魔になったマルファを殺害したとの噂が流れていた。
スヴィドリガイロフはラスコーリニコフに対して、ドゥーニャが成金弁護士との婚約を破棄してくれるなら、金を出すからドゥーニャに会いたい
ヒョードル・ドストエフスキー「罪と罰」(4)
ある日、ラスコーリニコフはソーニャという女性に出会う。ソーニャは信心深く、美しい娘だったが、貧しい家族のために娼婦をしていた。彼女は父親を馬車の事故で亡くし、悲しみに沈んでいた。途方に暮れていたソーニャのために、ラスコーリニコフは母が送ってくれていたなけなしの金を父親の葬儀代としてソーニャに渡した。
その帰り際、ソーニャの妹がラスコーリニコフに駆け寄ってきて、お礼とともにキスをした。すると、ラス
ヒョードル・ドストエフスキー「罪と罰」(3)
家賃滞納の件で警察に出頭したラスコーリニコフは、そこで高利貸しの老女と義理の妹殺害が話題になっているのを耳にして、その場で卒倒してしまう。
警察で不審がられながらも、なんとかその場を離れたラスコーリニコフは、自宅に隠していた老女から奪った金品を人気のない資材置き場の石の下に隠す。その後、自宅に戻ったラスコーリニコフは高熱を発し、丸3日間意識を失って、眠り続ける。
ラスコーリニコフは、頭ではこの
ヒョードル・ドストエフスキー「罪と罰」(2)
ラスコーリニコフは殺人の下見のために、高利貸しの老女のもとを訪れる。父の肩身を質草に入れて、1ルーブルちょっとを老女から借りる。ラスコーリニコフは強い嫌悪を感じながらも、老女と話しているうちに彼女を殺すことに躊躇いを覚えるようになる。
『本当に、どうしてあんな怖ろしい考えが頭に浮かんだんだ?それにしても、俺の心はなんて汚いことを受け入れることが出来るんだ!何より、汚いこと、汚らわしいこと、下劣な
ヒョードル・ドストエフスキー「罪と罰」(1)
ヒョードル・ドストエフスキー(1821〜1881)の代表作「罪と罰」は、1866年に「ロシア報知」に連載されるかたちで発表された。ドストエフスキーが45歳の時の作品で、全6部とエピローグから成る哲学・心理小説である。7月7日から7月20日までの2週間の物語だ。ちなみに、「ロシア報知」にはほぼ同時期にトルストイの「戦争と平和」が連載されていた。
「罪と罰」の主人公は、学費が払えず、大学の法学部を除
ベネディクト・アンダーソン「想像の共同体」
ベネディクト・アンダーソンは1936年に中国の昆明で生まれた。父はアイルランド人で、母はイギリス人だった。ケンブリッジ大学を卒業後、アンダーソンはコーネル大学でインドネシア研究者となった。
アンダーソンは1983年に出版した「想像の共同体」で著名である。アンダーソンは「想像の共同体」において、ナショナリズムあるいはネーションがいかにして構築されるかを研究した。
ネーションは複数の意味を持つ言葉
サルトル(4)「アンガジュマン」
第二次世界大戦前のサルトルは、生きることの不条理や無意味性を繰り返し説いていた。政治とは距離を置き、哲学や文学に没頭していた。
サルトルは第二次世界大戦で徴兵された。そして1940年にサルトルは前線に出ないまま、ドイツ軍の捕虜となってしまい、収容所に入れられた。ここでサルトルはさまざまな階級の人と触れ合い、それまでの個人主義的な哲学から人間の行動や連帯を重視する哲学に目覚めていく。やがて収容所を
サルトル(3)「地獄とは他人のことだ」
サルトルの実存主義にとって最大のテーマは「自由」であるが、それを脅かすのは「他人のまなざし」だと彼は主張している。サルトルは他者との関係を「地獄とは他人のことだ」と表現した。
1943年に出版された「存在と無」では、他人のまなざしがもたらす危機について「見る」か「見られる」かの決闘だとされている。対人関係はまなざしの闘いだとサルトルは主張したのだ。
人は「見る」ことによって世界の意味をさまざま
サルトル(2)「人間は自由の刑に処せられている」
サルトルの著書「実存主義とは何か」のテーゼのひとつが「人間は自由の刑に処せられている」である。人間は自由な存在であるがゆえに、孤独や不安から逃れることはできない。
『人間は自由である。人間は自由そのものである。一方において、神が存在しないとすれば、我々は自分の行いを正当化する価値や命令を眼前に見いだすことはできない。我々は逃げ口上もなく孤独である。そのことを私は、人間は自由の刑に処せられていると
サルトル(1)「実存は本質に先立つ」
ジャン・ポール・サルトル(1905〜1980)はフランスの哲学者、文学者で、生きることの不安と不条理、そして自由を論じた。第二次世界大戦後、価値観が大きく揺らぐ時代において、人はどのように生きるべきかが問われた。サルトルが掲げた実存主義はフランスを中心に世界を席巻した。日本でもサルトル全集が300万部を超える大ベストセラーとなった。
1944年のパリ解放後のフランスでは、自由と解放感とともに失業