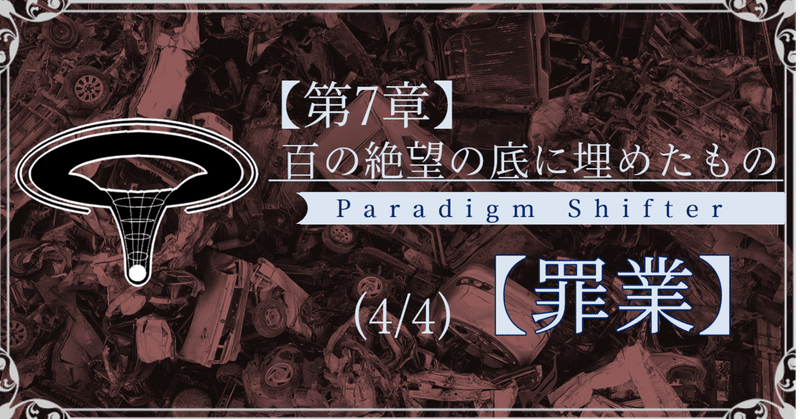
【第2部7章】百の絶望の底に埋めたもの (4/4)【罪業】
【三様】←
「よおし、それで完了かナ。流石だ、リンカくん。見事な手際だ」
リンカはドクター・ビックバンの指示に従って、自らが破壊した正面ゲートに仮設シャッターを取り付けていた。彼女の刀から生じる超常の炎が、金属同士を溶接する。
「のんべんだらり……おだてられたところで、なにも出ないのよな」
灼眼の女鍛冶はフェイスガードとガスマスクをはずしながら、作業台のはしごを降りていく。白衣の老人は、こめかみに手を当てる。
「む、ワッカくんのトラクターが戻ってきたようかナ。調度良い。仮設シャッターの動作チェックを兼ねよう」
「見なくても、わかるのものなのよな?」
「ミュフハハハ。このワタシは、セフィロト社製のシステムであれば容易にリンクして、操作することができるのだよ!」
かくしゃくとした老人は、己の技術を自慢するような子供じみた笑いをこぼす。リンカは、肩をすくめてみせる。
ドクター・ビックバンなる老人が言うには、発掘作業は一人二人で済むレベルではない大規模なものらしい。その人足をそろえるため、ワッカは自分の集落にすむ一族を迎えに行った。
重苦しい音を立てながら、仮設シャッターが上方向に開いていく。目で見てわかるほどの汚染空気がドーム内に流れこむ。
大規模な仮設隔壁が開ききると同時に、ほとんどタイムラグなくホバー走行のトラクターが施設内に入ってくる。
「女王サマ! ただいまだらー!!」
運転席から、ワッカが元気よく飛び降りてくる。もっとも、輸送車両の操縦自体はAIによる自動運転だ。
リンカは、しわだらけの少年を迎えようとする。トラクターとともに流れこんだ汚染空気がまだ残っており、せきこむ。
荷台からワッカの一族たちが、ぞろぞろと出てくる。皆、小柄で、肌はしわとしみだらけで、頭髪の一部かほとんどは白髪になっている。
「おお、なんと清浄な空気か……!」
「ワッカ、よくやった……伝説の『開かずの扉の城』を見つけ出すとは!」
「へへへ……この女王サマが、開かずの扉を壊してくれたおかげだら!」
ワッカは、誇らしげにリンカを指し示す。荷台の奥からは、他の仲間たちに支えられて、一族の長らしき老いた小人が降りてくる。
「なんとなればすなわち。諸君は、このワタシの依頼を了承してくれた、という認識でかまわないかな?」
長老らしき小人のまえに歩み出たドクター・ビックバンが、問う。白衣の老人とくらべて三分の一ほどの身長の小人は、深々とうなずく。
「細かい話は、ワッカから聞かせてもらった。わしは、見てのとおり老いぼれで役にたたんが、若いものたちは違う。発掘で生きてきた者たちだ」
長老の言葉に応じるように、ワッカの同族たちが誇らしげに腕をあげる。ドクター・ビックバンは、満足げにうなずいてみせる。
「これからおこなう発掘作業は、おそらく諸君らが初めて経験する大規模なものになる。なんとなればすなわち……」
ドクター・ビックバンは白衣をひるがえし、背後を仰ぎ見る。無数のビルを収めたドーム状施設の中央広場に視線を向ける。
そこには、格納庫からひっぱり出されて整備されたショベルカー、ブルドーザー、クレーン車といった重機車両がずらりと並んでいた。
「まずは、この発掘機械の操縦に慣れてもらいたい。皆、思い思いの車両に乗ってくれるかナ? AIがナビゲートとチュートリアルをしてくれる」
「おぉぉーッ!!」
ドクター・ビックバンの背後で、ワッカを戦闘に小人たちが歓声をあげる。すぐさま。それぞれの発掘重機の操縦席に乗りこんでいく。
「ふむ……手作業ではなく機械を使うのなら、わしでも力になれるかもしれん」
「なら、長老! オイラと一緒に乗るだら!!」
最後に一人残った長老を、ワッカが自分の車両の助手席に招き入れる。扉がしまると、重機たちはてんでデタラメに動き始める。
「さもありなん。だいじょうぶなのよな、これは?」
「致命的な事故や衝突は、AIが自動的に抑止してくれる。心配は無用かナ。とはいえ、邪魔にならないよう、我々は少し離れようか」
ドクター・ビックバンに促されて、リンカは中央広場に背を向ける。重機同士がニアミスし、急ブレーキと金属のこすれる不快な音が頻繁に響く。
しかし、灼眼の女と白衣の老人が距離をとるに連れて、危なっかしい音の発生頻度が減っていく。
二人が十分な間隔を置いて振りかえった頃には、車両群の動きは少しずつ統制を獲得しはじめている。
「これは驚いたかナ。かなりの習熟速度だ。訓練だけでも三日ほどはかかると思っていたが、今日中に作業に取りかかれるかもしれん」
「のんべんだらり。そのまえに、ワッカたちやこの世界はなんなのよな。地獄の底だってんなら、棲んでいるのは鬼と相場が決まっているが……」
「地獄の住人が何者かは、文化圏によって異なるものだが……なんとなればすなわち、説明せねばならないかナ」
ドクター・ビックバンは、右手で己のあごをなですさる。口元が無表情になれば、老人がなにを思考しているか、リンカには想像もおよばない。
「この次元世界<パラダイム>は、セフィロト社の廃棄物投棄場……ようは、ゴミ捨て場と言えば通じるかナ。地獄のような、という環境は、廃棄物による汚染によって生じたものだ」
白衣の老人は、抑揚のない言葉で淡々と説明する。灼眼の女鍛冶の胃袋が、いやな予感にもぞもぞとうごめく。
「そして、彼らはこの次元世界<パラダイム>の現住種族。もとは、ドワーフと呼ばれる種族かナ。もっとも汚染による変異と奇形化で、もとの種族とはかけ離れた存在となっている」
「──貴様ッ!」
リンカの脳裏に、一時暮らしていた世界に暮らしていた獣人の子供たちの姿がフラッシュバックする。それは、ワッカの屈託笑顔と重なりあう。
気がつけば、灼眼の女の右手は刀の柄に伸び、居合いの構えをとっていた。
「さもありなん! アンタたちが……セフィロトの連中が、この世界を地獄に作り替えたということよな!?」
その気になれば、首だろうが胴体だろうが両断できる距離にも関わらず、白衣の老人に動じる様子はない。
「なんとなればすなわち、まったくそのとおりであることかナ。弁明をするつもりはない。斬りたくば、斬ればいい。ただし……」
リンカの刀をにぎる右手に、いっそうの力がこもる。いつでも抜刀に移れるよう、女鍛冶の腰が沈む。白衣の老人は、微動だにしない。
「……このワタシを斬れば、リンカくん。キミは、この次元世界<パラダイム>から転移<シフト>することはできないかナ」
「さもありなん……」
リンカは、刀から手を離す。深く呼吸して、臓腑の奥から燃えあがる義憤の炎を鎮めようとする。
「なんとなればすなわち、そこまで肩肘をはる必要はないかナ。いまはまだ明かせないが、キミと、このワタシと、あの少年たちとの利害は対立しない」
「のんべんだらり……殺しあいの始まる理由が、理屈で説明できるなら苦労はしないのよな」
「イクサヶ原の出身者の言うことは含蓄があるかナ。デズモントも愚痴をこぼしていたよ。あの次元世界<パラダイム>のサムライは手に余る、とね」
気がつけば、広場で慣熟訓練をしていた重機車両たちは等間隔を保ちながら、規律正しく前進と後退を繰り返している。
「見たところ、リンカくん。キミは、絶望していない。それは、あの少年たちもそうだし、このワタシとてそうかナ。なんとなればすなわち、だ──」
車両群の先頭に立つショベルカーの運転席の扉が開く。ワッカが顔を出し、声を張りあげる。
「女王サマ、賢者サマ! この機械の扱いには、慣れただら。いつでも発掘にいける!!」
「よし、ならば早速シャッターを開けるかナ。ナビゲート用にドローンを同行させよう。細かい指示は、内蔵の導子通信機を使う」
若き発掘者<スカベンジャー>に対して、ドクター・ビックバンは簡潔な指示で応える。ワッカは、にい、と笑うと操縦席に潜りこむ。
「──絶望していない我々は、いまこそ、その旗印を城壁に掲げるのだ!」
かくしゃくとした白衣の老人は、己を鼓舞するように声をあげる。その横で、鞘に収めた刀を肩に担いだ女鍛冶が目を細める。
大型シャッターが開いていく。流れこむ汚染空気を押し返すように、エンジン音を響かせる重機たちが走り出した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
