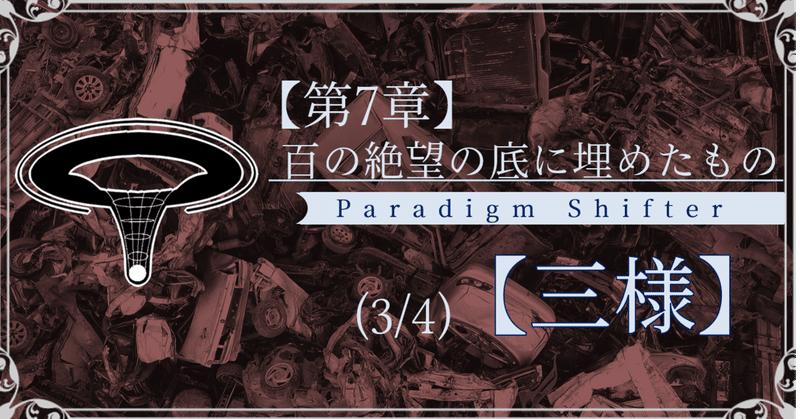
【第2部7章】百の絶望の底に埋めたもの (3/4)【三様】
【三者】←
「のんべんだらり。ずいぶんとよい風呂をしつらえてやがるのよな!」
すりガラスの扉を開けたリンカは、歓声をあげる。白衣の翁が言っていた『リラクゼーションスペース』に浴室を見つけた彼女は、勝手に利用することにした。
複数人が同時に利用することを想定しているのか、ずいぶんと広い浴槽が複数ある。かつて『淫魔』の部屋で見たシャワーや液体ソープも設置してある。
バスルーム全体に湯気が満ち、オートメーションシステムによりバスタブにはすでに湯が満ちている。
すでにリンカは入浴のためにいつもの着流しは脱ぎ捨て、一糸まとわぬ裸体をさらし、普段はさらしにの下に抑えつけられている豊満な乳房が揺れる。
「どんがらだった……なんてこった……」
リンカの背後で、防護服を脱がされ同じく全裸になった小人が震えた声をこぼす。男女が肌を見せあうことに緊張しているのかと思ったが、どうも違う。
そもそもドーム施設の外で出会ったこの男の年齢が皆目、見当もつかない。
身長は子供ほどだが、全身の肌は老人のようにしわとしみだらけだ。かと思えば、瞳と口調からは少年のような若々しさも匂わせる。
「のんべんだらり、なにをもじもじしているのよな。あんな地獄のような空気のなかにいたんだ。まずは、肌を流さにゃ」
「水だら……きれいな真水が、こんなにたくさん……」
黒髪灼眼の女の裸体にも声にも気がつかない様子で、しわだらけの小人は感きわまった声をこぼす。リンカは、怪訝な表情を浮かべる。
「そういえば、お互い自己紹介がまだだったのよな……アタシの名前はリンカ、アンタは?」
「……ワッカだら。それよりも、この水は……」
「風呂に入ったことがない……どころか、見たこともないって様子よな。お近づきのしるしに、アタシが身体を洗ってやるよ」
「どんがらだった……!」
リンカはワッカの手首をつかんで引っ張り、バスチェアに座らせる。ボディソープをしみだらけの全身に塗りたくり、泡立て、シャワーを流す。
「水! 水が……あばばば!?」
「さもありなん。目を閉じていないと、染みるのよな。まあ、手遅れか。すぐに終わるから我慢、我慢」
しわだらけの小人の身体を洗い終えると、浴槽のなかに放りこむ。リンカは手短に自分の身を清めると、ワッカのすぐ横に身を沈める。
「汚染されていない真水が、全身で浸かってもあまるくらいあるなんて……信じられないだら……」
あごまで湯のなかに沈んだワッカのつぶやきを聞いて、灼眼の女はようやく小人の境遇を察する。なるほど、あの地獄のような世界にはろくな水もないのだろう。
(イクサヶ原といい、獣人たちの世界といい……アタシは、水には恵まれてきたものよな)
リンカは、後頭部で腕組みして浴槽のなかで身体を伸ばす。『淫魔』の部屋の湯船も悪くなかったが、こちらのほうがはるかに広い。
「イクサヶ原にいたころの湯治を思い出すのよな……ま、竜宮城に来たと思って、せいぜい骨休みしていけばいいさ、ワッカ?」
しわだらけの小人の返事はない。リンカはまぶたを閉じ、しばし、湯のなかに身をたゆたわせる。よく考えてみれば、しっかりとした入浴はひさしぶりだ。
長湯としゃれこもうと思っていた灼眼の女は、ワッカがのぼせかけていることに気がつき、あわてて浴槽からひっぱり出す。
「さもありなん……すまなかったよな。風呂になれてなきゃ、まあ、そうなる」
リンカは、ワッカの手を引いて浴室から脱衣所へと戻る。空調装置からは、涼風が吹き出している。戸棚から適当にバスタオルをひっぱり出す。
「……のんべんだらり」
白髪まじりのワッカの頭をふきながら、黒紙の女は灼眼を細める。
適当に脱ぎ捨てたはずの着流しとさらしが、几帳面にたたんで置いてある。洗濯したてのように清潔な状態だ。その横には、ワッカの着替え用と思しき、子供用のパジャマが用意されている。
自分たちが入浴しているあいだに何者かが手を加えたことは明らかなだが、そのわりにはリンカの持っていた刀は壁に立てかけられて、そのままだ、
(さもありなん……白装束の爺さんには敵意を感じなかったし、他のセフィロト連中はそれどころじゃないだろうと高をくくっていたが……)
こうまで至れり尽くせりだと、わざと泳がされているのではないか、という懸念が強くなる。はたまた、武器を奪うまでもない、ということか。
ワッカにとっては慣れない服を着せ、自分もさらしと着流しを身につけると、リンカは納刀された鞘をつかみ、脱衣所の外に出る。
「なんとなればすなわち、セフィロトの最新型バスシステムはいかがだったかナ? VIP用とまではいかないが、それなりに快適だったはずだ!」
緊張感のみじんもない快活な声が聞こえてくる。コミュニケーションスペースと思しき大広間には、コック帽をかぶった例の老人の姿があった。
「諸君のおかげで、元社員たちの退避はスムーズに完了した。時間があまったので、洗濯、乾燥をすませ、ついでに軽食の用意をしているところかナ」
刀の柄に手を伸ばそうとしたリンカを意に介さず、義眼の老人は友好的な仕草で両手を広げてみせる。子供用の寝間着に身を包んだワッカが鼻をひくつかせる。
「なんだか……旨そうな匂いがするだら!」
「そうとも! なんとなればすなわち、すぐに用意しようかナ。そこのテーブルについて待っていてくれたまえ!!」
パジャマ姿の小人は、うきうきとした様子でいすに向かい、腰をおろす。小さくため息をつきつつ、リンカもそのあとに続く。
いったんキッチンスペースに下がった老人は、すぐに二人分のサンドイッチとポタージュを持って戻ってくる。ワッカは目を丸くして、輝かせる。
「これ……食べていいだら?」
「もちろんだとも! このワタシ、こう見えて料理の腕には少しばかり自信があってね……ぜひ感想を聞かせてくれないかナ?」
リンカが制止する間もなく、ワッカはサンドイッチを手でつかみ、口に運ぶ。ただでさえ丸く見開かれた双眸は、眼球が転がり落ちそうなほどになる。
「ンまいッ! こんなうまいもの、オイラ、初めて食っただら……!!」
「そうか、それは良かった! ときに……リンカくんは食べないのかナ。キミは確か……イクサヶ原の出身か。味噌仕立ての米料理のほうが好みだったかナ?」
「のんべんだらり。アタシは、まだアンタの名前も聞いていないのよな。それに……話がある、とも言っていた。先に、聞いておきたい」
いすの背もたれに刀を立てかけて、腕組みしたリンカが言う。白衣の老人もまじめな表情となり、対面の席に腰をおろす。
「なんとなればすなわち、これは失礼した。このワタシは、ドクター・ビックバンと名乗っている。セフィロト社では、単に『ドクター』と呼ばれていたかナ。まあ、好きに呼んでくれたまえ」
自らの肩書きを名乗ったドクター・ビックバンは、自分用のコーヒーカップを口に運び、舌をぬらす。
「単刀直入に行こうかナ。外に広がるガレキのなかに埋めたものがある。ワッカくんにはその発掘を、リンカくんには掘り出したあとの組み立てを頼みたい」
灼眼の女は、腕組みしたまま微動だにせず、けったいな名を自称する老人を凝視する。赤い光を放つ義眼から、その本心を読みとるのは難しい。
「これは、ビジネスの依頼と思ってもらってかまわないかナ。報酬に関しては要相談だが、このワタシが用意できるものであれば善処しよう。無論、仕事が完了するまでの衣食住は保証する」
「どんがらだった! こんな旨いメシが、毎日、食べられるだら!?」
リンカが返事を思案している間に、サンドイッチとポタージュを平らげたワッカが前のめりに応答する。
「ああ、その通りだとも! この拠点に残された福利構成施設も自由に使ってもらってかまわないかナ!!」
「それなら、断る理由はないのだら! なあ、女王サマ!?」
「さもありなん、アタシは女王なんかじゃないのよな。いや、それよりも……」
きらきらと瞳を輝かせるワッカに対して、ドクター・ビックバンは人なつっこい笑みを口元に浮かべる。
リンカは頭痛をおさえるように左手を額に当てつつ、右手でサンドイッチをつまむ。ワッカが言ったとおり、なるほど、これは美味だった。
→【罪業】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
