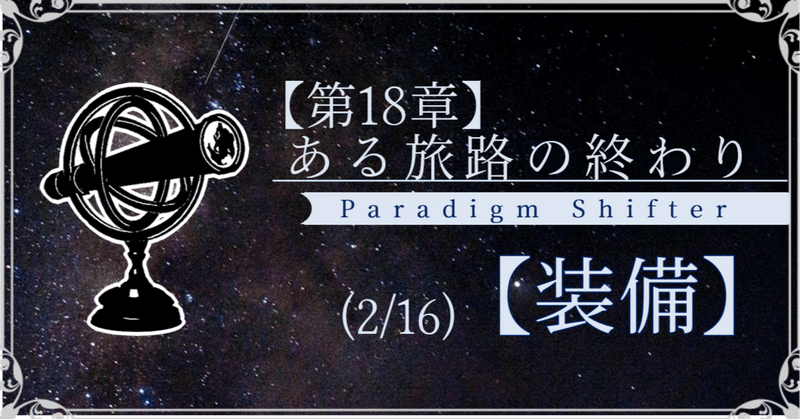
【第2部18章】ある旅路の終わり (2/16)【装備】
【棲家】←
「なんとなればすなわち、出撃まえに軽食を用意した。メニューは、このワタシの独断だが、かまわなかったかナ?」
「その点は、ドクのことを信頼しているよ」
カイゼル髭の伊達男が一瞥した長テーブルのうえには、オートミール粥、ベーコンとオムレツ、シーザードレッシングをかけられたフレッシュサラダが並んでいる。
「ふむ……これは?」
いすに腰をかけ、キャスケット帽を食卓のうえに置きながら、『伯爵』は『ドクター』に尋ねる。レタスとクレソンとルッコラにラディッシュをあえたサラダのことだ。
料理が趣味だという老博士に食事のことは任せきりにしていたが、この拠点の飲食は資源循環システムによる合成食料によって支えられていることは、壮年の男性も把握している。
「さすがに、生野菜は用意できないはずだ。どこぞ、ほかの次元世界<パラダイム>へ買い出しにでも行ってきたのかね?」
「ミュフハハ、よくぞ聞いてくれた! 実は、片手間で拠点内に農業工場を造っていたのだよ。ようやく初収穫を迎えたので、ぜひデズモントにも食べてもらいたくてね」
「ふむ……農業工場? 我輩たちは、この拠点を今日のうちに引き払うのではなかったかね。ドクの趣味、というのであれば止める理由はないが」
「リンカくんの強い要望かナ。我々ではなく、ここに残ることになる原住民の小人たちのために是非、とね。まったく、ただでさえ強行スケジュールのデスマーチだったというのに!」
コーヒーを満たしたマグカップをふたつ手にした老博士は、『伯爵』の対面の席に腰をおろす。グチのような言葉とは裏腹に、『ドクター』の声音はどことなく楽しげだ。
オートミール粥を口に運ぶ手を取め、カイゼル髭の男は伊達老博士の差し出した黒い液体を受け取る。コーヒー豆に関しては、旧セフィロト社の在庫がわずかに残っていた。
「リンカ……あのミズ・ブラックスミスかね?」
箸休めにすするコーヒーのような色合いの黒髪を伸ばしたイクサヶ原出身の女鍛冶の姿を、『伯爵』は脳裏に思い浮かべる。
「なんとなればすなわち、リンカくんはじつに優秀な技術者かナ。今回のプロジェクトにおける彼女の功績は、原住民の小人たちと並んで欠かせないものだった」
「ふむ……ときに、もうひとりのご婦人はどうしたのかね? いつもなら、リビングでくつろいでいるだろうが」
カイゼル髭の男の問いに、白衣の老人は肩をすくめてみせる。
「そちらの女性なら、ヘソを曲げて昨晩から戦車のなかに引きこもったままかナ。キミが怒らすからだぞ、デズモント」
「仕方あるまい。我輩がこれから向かう戦場では、戦車をまともに運用することはできないだろう。同行をいくら強く要望されても、断らざるえないかね」
「その点に関しては、完全に同意するが……キミは、このワタシよりも女性の扱いに慣れていると思っていたかナ、デズモント」
老博士が、少しばかりあきれたようにため息をつく。『伯爵』はなにも言い返さず、マグカップを卓上に置き、ふたたび食器を手に取る。
「ときにドク。食事をとりながらで行儀が悪いのは重々承知だが、頼んでいた装備についてのブリーフィングを願えるかね。お互い、時間がないはずだ」
にやりと笑ってうなずいた『ドクター』は、すぐとなりの座る者のいないいすのうえに置かれていた導子兵装を、テーブルのうえに並べてみせる。
「なんとなればすなわち、もちろんかナ。まずは、『ベクトル偏向クローク』だ!」
自慢の発明品に対する昂奮を隠せない様子で、白衣の老人は黒い布を広げてみせる。小さめのピクニックマット、あるいは闘牛士のマントほどのサイズだ。
「これは、表面に触れた物体の運動ベクトルの向きをずらすものだ。残念ながら十分な強度を確保できず、銃弾などを防ぐことはできないが……それでも、キミならば白兵戦の補助武器として活用できるはずかナ」
ビロードのような光沢を放つ黒い布の表面を節くれだった指でなでる老博士に対して、カイゼル髭の男はベーコンを咀嚼しながら、うなずきをかえす。
「続いてはこちら、『重力波観測ゴーグル』! 本来であれば、デズモントの使い慣れた片眼鏡<モノクル>サイズにまで小型化したかったのだが……」
無念そうに口元をゆがめる『ドクター』の手元には、ベルト固定式の眼帯型カメラがある。『伯爵』は視線をそらさず、シーザーサラダを黙々と口のなかに運ぶ。
「それでも、今回の戦場で必要となるであろう性能は満たしているはずかナ。半径およそ100メートルの範囲の引力および斥力をリアルタイムで計測できる。もちろん、いままでの多機能片眼鏡<スマートモノクル>の機能も搭載してある」
生野菜に続いてオムレツまで平らげたカイゼル髭の伊達男は、ナプキンで口元をふきながら老博士の説明に耳を傾け、やがて自分から口を開く。
「ふむ……いずれも十分な代物かね、ドク。ときに、メインディッシュのほうは?」
『伯爵』が尋ねたのは、主武装となる刀剣のことだ。いままでは愛用のステッキに仕込んだサーベルを用いていたが、いま、『ドクター』の手元にその姿はない。
白衣の老人は、よくぞ聞いてくれた、とばかりに大きなうなずきをカイゼル髭の伊達男に対してかえす。
「なんとなればすなわち、セフィロト型の高速振動サーベルでは要求水準を確保できないと判断した……そこで、とっておきのものを用意した! リンカくん!!」
かくしゃくとした老博士は、元気のよい声でイクサヶ原の女鍛冶の名前を呼ぶ。やがて、リビングの奥から着流しに身を包んだ黒髪に灼眼の女が鞘に納めた太刀を持ってくる。
リンカは卓上、『伯爵』のまえにいささか乱雑に刀を置くと、大きな音を立てながら不機嫌そうに隣のいすに座った。
→【業物】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
