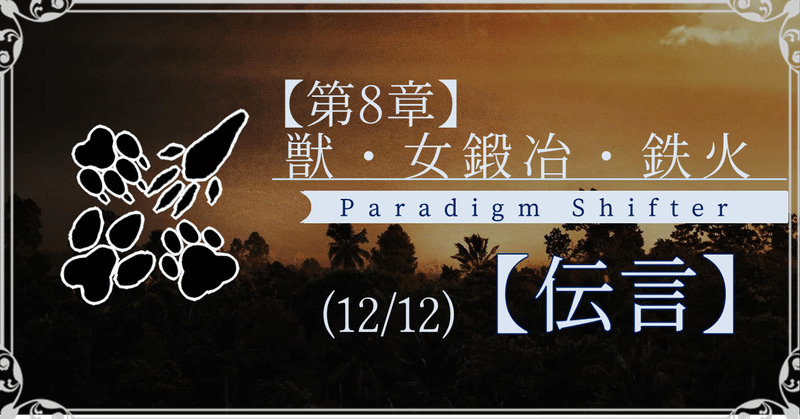
【第8章】獣・女鍛冶・鉄火 (12/12)【伝言】
【花魁】←
「アサイラが『龍剣』を使えば、次元障壁を破壊できる可能性があるのだわ。必要なものがあれば、なんでも、私たちが用意する」
前のめりになり、畳みかけるように、『淫魔』が言う。リンカは、困惑の表情を浮かべつつ、花魁装束の部屋の主を見つめ返す。
「待って欲しいのよな。アタシだって、造りたくないってわけじゃあない……ただ、『龍剣』を打つってのは、難儀なことなんだよ」
女鍛冶の深いため息が、円形の部屋に響く。
「故郷にいたころ、アタシも『龍剣』造りに参加したことはあるが……あれは、一族一門総出の大仕事なのよな。人手と、なにより大量の『気』が必要になる」
リンカの説明に対して、向かいに座る『淫魔』はもちろん、長いすに腰をおろすアサイラとシルヴィア嬢も食い入るように耳を傾ける。
「そして、一番難儀なのは、材料……龍の骨を用立てることなのよな。まがい物じゃなくて、できるだけ良質な本物の龍の骨……アタシの故郷には、あるかもだが……」
「えーと。それじゃあ、ひとつずつ整理させてもらうのだわ」
女鍛冶が言葉を濁し始めたのを察したのか、『淫魔』が引き継ぐように口を開く。
「まず、人手の問題。これは、マイスター・リンカ……あなた自身の『龍剣』を使えば、解決するんじゃないかしら?」
リンカは、腰かけに立てかけた己の刀を見やる。一族から持ち逃げした家宝の『龍剣』が、いまは鞘のなかに納められている。
「まあ、できなくはないと思うが……」
「次! 龍の骨は、アサイラが探しに行く。そして最後に、あなたの言う『気』……導子力の問題ね。これも、解決するいい方法があるのだわ」
渋る女鍛冶をさえぎるようにまくし立てた『淫魔』は、自分の席から立ちあがる。ぽかん、と見あげるリンカのそばに、花魁装束の女は周りこむ。
「むちゅ……」
「……ッ!?」
不意打ち気味に、女鍛冶は『淫魔』から接吻を施される。蕩けるような柔肉の感触が、唇に押しつけられる。反射的にふりほどこうとするが、身体に力が入らない。
「んーッ! んむ──ッ!!」
「ぢゅむ、じゅるっ、んちゅう……」
左右に頭を振ろうとするリンカの頬を、『淫魔』の両手が抑える。女同士にも関わらず、舌肉を咥内へと侵入させられ、唾液を流しこまれる。
「むちゅう……んっ」
しばしの後、ねっとりとした口づけから、ようやくリンカは解放される。二人の女の口元に、銀色の輝きを放つ唾液の橋が架かる。
全身が、熱い。心臓が、早鐘のように高鳴る。強い酒気にあてられたかのように、頭のなかが揺れて、思考がまとまらない。
「シルヴィア! アサイラのほうは、お願いするのだわ」
「ひょこっ!」
「おい、シルヴィア! やめろッ!?」
花魁姿の女の声が、どこか遠くに聞こえる。狼耳の娘は、尻尾を振りながらアサイラを無理矢理立たせると、部屋の中央の台座へ向けて、ぐいぐい押していく。
「むふふ……さあ、リンカも立つのだわ」
「はあぁ……あっ、あぁぁ……」
女鍛冶は言われたとおり、ふらふらと腰かけから立ちあがる。肉体が、勝手に『淫魔』の言葉に従っているかのような感覚だ。
「心配しなくても、だいじょうぶだわ……痛いことは、しないから」
リンカの心の中を見透かしたかのように、『淫魔』は妖しい声音でささやく。
───────────────
「遅い遅い……リシェ、急ぐんだもな!」
「マノが早すぎる……また転んでも、知らないんだよ!」
二人の獣人──猿耳の少年と、リスの尾の娘は、全速力で草原を駆けている。二人の視線の先には、勢いを弱めながらも、未だくすぶる黒煙が見える。
猿の獣人、マノの手には研ぎ澄まされた山刀が握られ、リスの相を持つリシェは、薪を棍棒がわりに手にしている。
マノとリシェは、一度はリンカの洞窟まで逃れたが、残してきた女鍛冶のことが心配になり、ふたたび彼女のもとへと急いでいた。
「はあ、はあっ、はあ……ッ」
やがて、二人は、草原の真ん中に位置する野牛の獣人の集落に到着する。村を囲む柵は破壊され、住居は粉砕され、人の気配はまったく感じられない。
「女神さま──ッ!」
「リンカさまあッ!」
マノとリシェは、大声をあげて女鍛冶の名前を呼ぶ。返事はない。二人は互いの顔を見て、うなずきあうと、武器を構えながら倒れた柵を踏み越える。
しん、と静まりかえった集落を、マノとリシェは背中をあわせながら、おそるおそる進んでいく。二人の脳裏に、草原で遭遇した異様な獣人の姿がよみがえる。
「リンカさま、無事かな……」
「だいじょうぶもな。女神さまは、強いから!」
巨大な生き物が暴れまわったあとのように踏み荒らされた家屋からは、人の気配はおろか、下敷きになった住民の息づかいすら感じられない。
墓場のように不気味な静寂に浸る住居のあいだを抜けて、マノとリシェは集落の中心の広場にたどりつく。
「……なんなのもな?」
「わからないんだよ……」
広場の地面は、巨大な炎が燃えさかった跡のように黒く焼け焦げている。その中央には、大きな岩が安置してあったが、二人にその意味まではわからない。
「リンカさまは見つからないけど、化け物もいないみたいだよ……手分けして探してみよう、マノ!」
「わかったもな、リシェ……それに、けがした人がいたら、助けてあげないと!」
マノとリシェはうなずきあい、二手に分かれて、野牛の獣人の集落を探索する。
リスの尾の娘は、廃墟のなかに焼け焦げた土塊の山を見つけたが、二人ともそれ以外に探し人はおろか、生存者すら見つけることはできない。
二人の獣人は、それぞれ集落を一周し、ふたたび広場へと戻ってくる。
「だめだ……誰も、いないんだよ」
「う、うぅぅ……女神さま、女神さまぁ!」
うなだれるリシェを前に、マノは嗚咽をこぼし、やがて泣き声をあげ始める。
「女神さま。オイラたちを助けるために、どこかに行ってしまったもな……もう、きっと、戻ってこないもな──ッ!」
猿耳の少年の嘆きが、集落中に響きわたる。大粒の涙が、マノの頬を伝って、ぼろぼろと滴り落ちる。
「もう、マノ……泣かないでよ。そんなひどい顔、リンカさまに見られたら、笑われちゃうんだよ?」
「だって、だって……リシェ!!」
猿耳の少年は、リスの尾の友人の声音が、意外にも落ち着いていることに気がつく。手の甲で涙をふき、赤くはれた眼で前を見る。
リシェは、手招きする。マノは、ゆっくりと歩み寄る。
リスの尾の娘は、広場に設置された井戸の影を指さす。石積みのすぐ横の地面には、刀の切っ先のようなもので、なにかが刻み込まれている。
「これは……なにもな?」
「マノ、リンカさまから文字を習っていなかったの?」
リシェは、猿耳の少年に対して小さく笑いかける。
「これはね。『いつかもどってくるよ』って、書いてあるんだよ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
