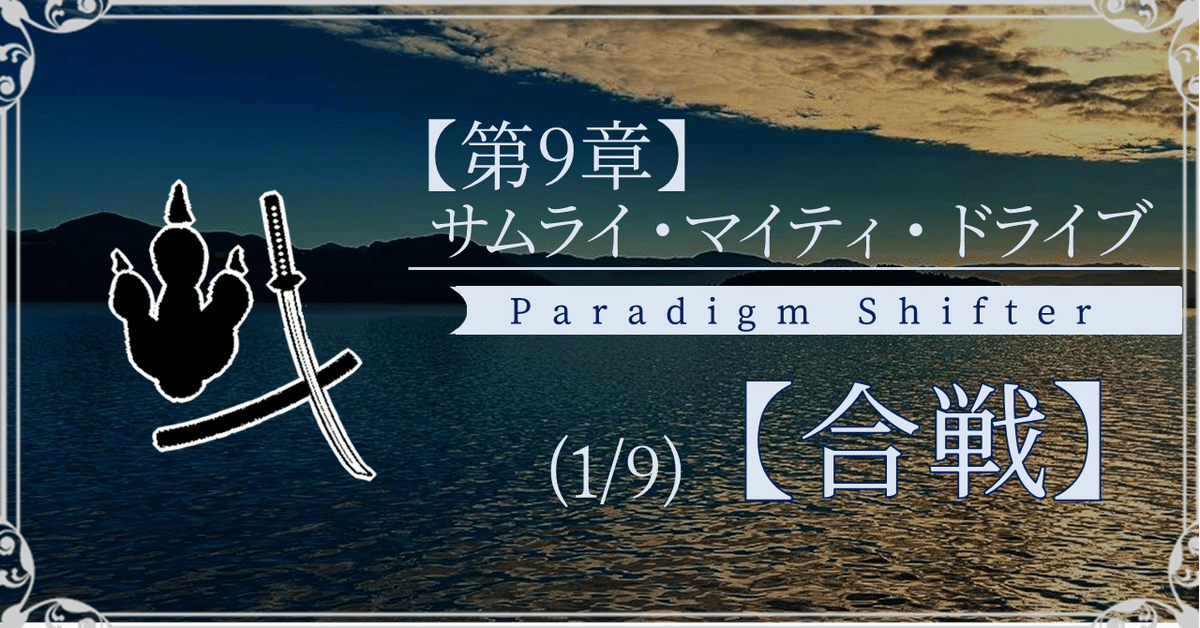
【第9章】サムライ・マイティ・ドライブ (1/9)【合戦】
──ブオオォォォ……
乾いた平原に、法螺貝の音が響きわたる。少し遅れて、恐竜たちが吼えたぎる。人間の叫び声は、地を踏みにじる巨竜たちの足音にかき消される。
荒野に対峙していた両軍の最前列が、接触する。陣笠をかぶった足軽たちの長槍がぶつかり合い、そのあとから続く恐竜が有象無象を踏み砕く。
「グルオォアアァァァ──ッ!!」
血の臭いを嗅ぎとり、大型肉食竜たちがひときわ大きな咆哮をあげる。
後方の兵たちが弓を放つ。恐竜は、針のような矢を物ともせず、長大な尾を振り回して群がる雑兵たちをなぎはらう。
人と恐竜の混成部隊がぶつかり合い、前線が混濁していく。長槍が敵兵を貫き、恐竜の脚が足軽を踏みつぶす。
剣戟と絶叫が響きわたる戦場を、小型の恐竜にまたがり、大槍を手にした一人の若武者が駆け抜けていく。

「単身斬りこんでくるとは、その意気やよし! いざ尋常に勝……ぐブぁ!?」
若武者と同じ種の小型竜にまたがった下級武士ののどを、大槍が易々と貫く。指揮者を失い混乱する足軽たちを、長物を回転させて遠ざけつつ、さらに前進する。
「テメェのような小物に用はないだろ」
若武者の操る小型恐竜が、稲妻のごときじぐざくの軌跡を描きつつ、敵陣へと斬りこんでいく。
またがっているのは、『迅脚竜』とも呼ばれる速度に優れた種だ。だが、それを差し引いても、若武者の駆る竜は、見るからに疾い。
横切る足軽や下級武士たちが手をこまねいているなか、若武者は敵陣の一翼を担うと思しき敵将のもとへと肉薄する。
「グウゥゥルアアァァァ──ッ!!」
小山のような大型肉食竜が、耳をつんざかんばかりの咆哮をあげる。その頭部には、精緻な装飾の施された武者甲冑と派手な旗指物を身につけている。
若武者は、己の騎竜のうえで身を屈めつつ、兜の影から舌打ちする。主君を守ろうとする周囲のサムライたちの放った矢が、肩口をかすめる。
「馬鹿となんとかは、高いところが好き……ってやつか? それに、どうせ壊れ物だ。鎧だって、そんな芸術品みたいに仕立てなくてもいいだろ」
不機嫌そうにつぶやきながら、若武者は大槍を振るい、敵兵たちをなぎ倒していく。
武将の格は、騎乗恐竜の大きさに比例する傾向がある。しかし、この若武者の感覚から見ればいいマトだった。
「……さて、どう料理してやろうか」
若武者は、騎竜の脚を一度、止める。眼前には、敵将の鎮座する巨竜がそびえ立つ。
鼻のうえに特徴的な角の生えた『鼻角竜』などと呼ばれる種だが、本当の武器はノコギリのように荒々しい牙と、刀のように鋭い爪だ。
敵将の大型竜は、眼前の獲物に狙いを定め、人を一呑みにするほどに顎ををひろげる。同時に、側近のサムライたちが騎竜を駆って、集まってくる。
「ものども! 殿を守れェーッ!!」
「いくぞ、『薙鳥<ちどり>』ッ!」
若武者は、己の騎竜につけた名を呼ぶ。小型恐竜は、応えるように自慢の脚力を活かして、前方へ跳躍する。敵将たちが狙いを定めた場所から、若武者が消滅する。
「……べガふッ!?」
サムライの一人が、若武者の代わりに、敵将の騎竜の牙によって犠牲となる。若武者は、相手の大型竜の股間をすり抜け、荒れ狂う太尾をかわし、背後に出る。
「チョコザイな……ッ!」
壮年の敵将が、声を張り上げる。山のような騎竜の巨体が、ゆっくりと若武者のほうを振り返る。
当の若武者は、周囲の武士たちを牽制しつつ、本丸へ向けて大槍を突き出す。隊列に生じた一瞬の間隙をついて、騎竜とともに突撃を敢行する。
「──ギャオォウウゥゥゥ!?」
刹那、敵竜が悲鳴をあげ、身をよじる。乗り手である武将が、慌てた様子で手綱を操る。若武者の大槍は、巨木のごとき脚のふくらはぎに突き刺さっている。
「攻めること、火の如し……だろ」
騎竜の鞍のうえから、若武者が跳躍する。巨竜に穿ちこんだ大槍を踏み台にして、再度、跳ぶ。蝶のように宙を舞う若武者の姿に、敵陣のサムライたちは恐慌する。
若武者は、滞空しながら、腰に携えていた縄状の道具を手に取る。恐竜の革をなめしたもので、先端は投げ縄のように輪になっている。
「喰らいなッ!」
巨竜の頭部に向かって、若武者の手から投げ革鞭が投擲される。
「……おグッ!?」
敵将が、のどを抑える。竜革製の輪が、壮年のサムライの首にからみつき、締めあげる。若武者は、革鞭の逆端を握りしめて、振り子のように巨竜の背へと着地する。
「グッド……」
兜の影で、若武者が小さくつぶやく。どちらか片方の腕を捕らえられれば御の字と考えていたが、首を絞められたとなれば理想的だ。
若武者に対する地上からの妨害が少ないのも、好都合だ。乗り手不在に関わらず、『薙鳥<ちどり>』が素早く立ち回り、敵兵を攪乱している。
「ウチの相棒は、賢いだろ。こっちも、負けちゃいられない」
革鞭で体重を支えつつ、若武者は、しゅらっ、と太刀を引き抜く。白刃を巨竜の背に深々と突き刺し、柄を足場にして、頭上めがけて一気に駆けのぼる。
「おグぅ、ぐブぬぬ……ッ!」
騎竜の頭上で手綱を握る敵将が、首を抑えながら、もがく。若武者が、投げ革鞭をたぐり寄せて恐竜の背を登るほどに、その体重でますます喉が絞めあげられる。
やがて、若武者が巨竜の頭に設えられた鞍のもとにたどりつくまでに、乗り手である武将は窒息して、半死半生となっている。
「……フンッ!」
「げブほ……ッ!?」
投げ革鞭を短く握りなおした若武者は、手甲におおわれた拳を敵将の顔面に叩きこむ。脇差しを抜き放ち、気絶した相手の首を躊躇無く切断する。
若武者は、敵将の兜を地面に放り投げ、鬟をつかんで首級を確保すると、鮮血が噴き出す首無し死体を巨竜の頭上より蹴り落とす。
「殿がやられたァーッ! ものども、仇をとれェーッ!! こら、なにをしているッ、逃げるんじゃない──!?」
地上より、指揮官を失った敵兵たちの狂乱の声が聞こえてくる。結局、反撃らしい反撃もないまま、足軽と武将たちは、四方八方へと散っていく。
最後まで暴れていたのは、乗り手を失った敵将の騎竜だった。若武者が手綱を奪うと、それも、すぐにおとなしくなる。
巨体の鼻角竜は観念したのか、若武者の意に従うように身を伏せて、頭を垂れる。迅脚竜の『薙鳥<ちどり>』が、乗り手のもとへと駆け寄ってくる。
「グッド」
若武者は、地面に降りつつ、戦場全体へと視線を向ける。趨勢は、自軍に傾いていることが見て取れる。
──ブオッ、ブオォオオォォォ。
敵陣の方角から、法螺貝の音が聞こえてくる。撤退の合図だ。敵兵たちが、引き潮のように後退していく。
若武者もまた、己の騎竜にまたがると、自陣の方角へ向けて走り出す。鞍のうえで兜を脱ぎ、額の汗をぬぐう。
赤毛の短い髪が、風に揺れる。灰色の瞳が、陽光を反射する。なにより、若武者の線の細い顔立ちは、女性のものだった。
───────────────
「あっぱれ、あっぱれ! 快勝じゃ! 皆のもの、よくぞ戦った!!」
左右に武将たちが並び、腰をおろすなか、上座には荒武者たちを統率する『大御所』が豪快な笑い声をあげる。
白髪で、頭頂ははげあがり、鬟も結えないほどの高齢だが、陣羽織を着こんだ体躯は筋骨隆々であり、いまだ、一流の武人としての覇気をみなぎらせている。
赤毛の女武者は、自陣営の武将たちに混じって腰をおろしている。男所帯のなか、彼女の性別はもちろん、髪と瞳の色も、ほかの者たちとは明らかな異彩を放っている。
「ときに、ナオミ御前! 此度も、首級を挙げたそうだな?」
「……ハッ」
少し間をはずして、女武者は頭を下げつつ、返事をする。ナオミ・ベティ・レイ。それが、彼女の名前だった。
「近うよれ。恩賞をとらす!」
「……ハッ」
周囲の武将たちが、どよめきだす。ナオミは、大御所の前に出て、あらためて頭を下げる。大御所は満足そうに、うなずく。
老主君があごで合図をすると、側仕えのものが女武者の眼前に黄金の大判を重ねていく。サムライたちのざわめきが、いっそう大きくなる。
「ありがたく、頂戴……いたします」
「うむ。次も励め!」
女武者は、いささかぎこちない動きで金貨を受け取ると、自分の座へと戻っていく。己へと注がれる敵愾心に満ちた男たちの視線が、刺さるようにわかる。
ナオミは、このような形式ばった礼儀作法が苦手だ。不作法もあるだろうに、大御所は寛容だった。それが、ほかの武将たちは余計に気に入らないのだと思う。
大御所は、女武者に続いて、手柄をあげた家臣の名前をあげていき、領土や銘刀といった褒美を与えていく。
機械仕掛けのような動きで主君に頭を下げ、決まりきった感謝の文言を返すサムライたちを、ナオミはどこか遠くのことのように見つめていた。
やがて、戦勝の報告は終わり、上機嫌の大御所が席を離れるのを待って、他の武将たちも各々、立ちあがる。
夜には宴も開かれようが、それまでにはいささかの時間がある。ナオミもまた、広間から退出しようと立ちあがる。
「おい、ナオミ御前!」
廊下に踏み出た女武者は、背後から声をかけられる。振り返ると、にたにたとした笑みを浮かべる、壮年の武将の姿があった。
「ツバタ……さま」
露骨に不快な表情を浮かべて、舌打ちしそうになったナオミは、すんでのところでポーカーフェイスを保つ。そんな自分をほめてやりたいと思う。
ツバタ・タダスグ。大御所に仕える武将のなかでは、家臣筆頭を競うほどの大物だ。赤毛の女武者よりも、はるかに高い地位にある。
「聞いたぞ、また大金星を挙げたそうだな──ン?」
「いえ。皆の奮戦のおかげ……で、ございます」
なれなれしく肩をたたいてくるツバタに対して、ナオミは嫌悪感を覚えつつ、呑みこむ。社交辞令のひとつも口にできるとは、自分も順応したものだ。
「おい、おい! 謙遜することはない。ときに、こなたも良い歳であろう。なんなら、身どもが縁組みを世話してやってもよいが──ン?」
ツバタの口角はゆるんでいるが、目元は笑っていない。赤毛の女武者は、反吐が出そうになるのを必死にこらえる。
この男の考えることは、だいたい想像できる。自分の家の三男坊あたりと結納を挙げさせて、ナオミを飼い殺しにしようという算段だろう。
「せっかくだが、ツバタ、さま……ウチは、独り身が気に入っているので……」
女武者は、自分が知る限りの穏便な言葉を選び、己にできる限りの丁重な態度で、重臣の申し出を辞退する。
「……ヌッ」
返事を待たずして背を向けたナオミの耳に、ツバタの小さなうめき声が届いた。
→【祝宴】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
