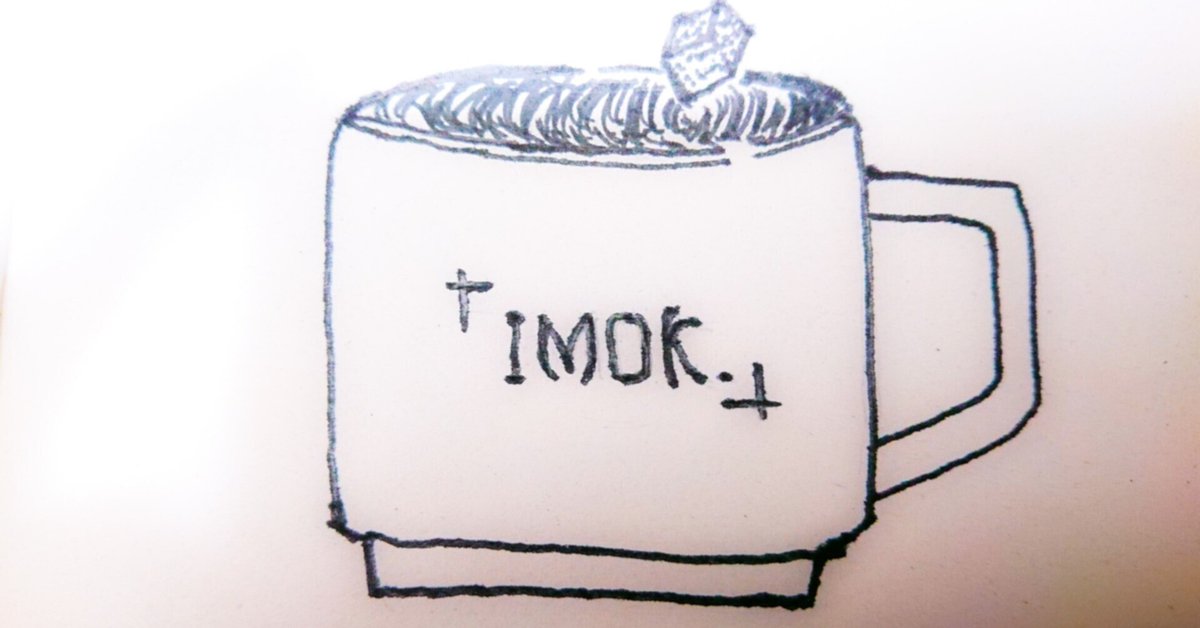
アイム・オーケー
冬の朝をバスが走る。
最後列の真ん中に彼女は座っていて、聞き流すだけで身につくと話題になった韓国語の教材アプリを聴きながら眠っていた。彼女は春の終わりに地元の女友達二人と一緒にドラマの聖地巡礼をする予定だ。
声が小さく聞き取りずらい運転手のアナウンスが、偶然耳に入ってきた彼女は慌てて降車ボタンを押す。古びた赤紫色のランプが灯って、バスは高校の前に止まった。
校門へと続く登り坂を女子バドミントン部が走っている。それを眺めながらストップウォッチを押し、機械のように淡々と記録を取る女子マネージャーが彼女の彼女だった。
今日は後ろで結んでんだ。へぇー、かわいいじゃん。
バスの扉は開いていて、扉の向かいに座る親子が彼女を見ている。だが彼女は気づかない。車内に苛立ち交じりの静寂が漂い始め、運転手が心配を装いながら彼女を急かした。
やっと気づいた彼女が席から跳び上がるように立ち上がる。
「すみません。もう大丈夫です、降ります!」
もう、ってなんだ?
という疑問が同乗したまま、バスは次の停留所に向かって走っていった。
彼女が高校教師になった理由はただの口実だった。
幼いころ両親が共働きだったため、彼女は放課後、児童館にいることが多かった。そこで彼女は自分より小さい子に読み聞かせをしてあげたり、人形遊びを手伝ったりするのが得意だった。
そんな記憶が高校受験の時にふと過って、彼女は親を説得することに成功し、上京した。
確かに得意だった。テストやレポートの評価はまずまずだったが、実習の評価は良かった。就職先もそれほど苦労せずに決まった。
だが好きではなかった。彼女の夢は世界中を渡り歩いて自分がかっこいいと思う女性を撮り収め、個展を開くことだったりする。
「ユイコ先生大丈夫ですか? 目赤いですよ」
音楽教師として今年から入ってきた彼女の後輩のユカは、小鳥みたいに小さな顔をしていて、美容系youtuber並みにコスメに詳しい。隣に座るユカの机の上はいつも整頓されていて、授業用のノートにも、教材にも、レザーのブックカバーがついていて、そのままInstagramに載せても違和感がない。対して彼女の方は、机の上はそれなりに整頓されているが引き出しの中とパソコンのデスクトップは散らかっている。
生徒の答案のチェック、小テストとクラス便りの作成、その他の雑務。それらに優先順位をつけていくことから彼女の一日は始まる。
彼女がまだ教科担任だった時、早く起きた朝は少し歩いた先にある個人経営のカフェに行き、働いているバイトの女子と話しながらよくモーニングコーヒーを飲んでいた。そこで彼女は、彼女の彼女であるエリと知り合った。
だが、クラスの副担任になってからは仕事の量が倍に増え、疲労に追われるようになり、朝どころか休日にすら、顔を出せなくなった。
好きな人と一緒に過ごせないのに、なんでわたしは働いているんだろう。
そう思いながら彼女はまず小テストの答案用紙のチェックから入った。なんかなめられている気がした彼女は後輩の目を見て、満面の笑みで応戦した。
「ユイちゃんさ、『わたしは大丈夫』ってよく言うけど、大丈夫って口にした時点で、大丈夫じゃない気がするんだよね。それってあたしだけ?」
野球部の顧問とクラス担任を両立する男性教師に変わって休日出勤した日、担任ってそんなに偉いのかよ、と小言を言いながら頼まれていた仕事を片付けた。
その後、彼女は久々にカフェへ向かった。
店内は若い男女がテーブル席を埋めていて、彼女はカウンター席に座った。見回したが、エリがいない。思わず彼女はカメラロールに保存したエリのシフトを確認していると、俯いて顕になった項にエリが息を吹きかける。彼女が半休だったと知っていたエリはもし来たらそこから1時間の休憩にして欲しいと頼んでいたのだ。
そんなことを知らない彼女はいきなり私服姿で隣に座ったので驚きつつも、猫舌のエリがコーヒーを啜っている姿をスマホのカメラでちゃんと撮った。画角にもこだわった。ネットで知り合った友達だけのアカウントに、写真を投稿するといいねがすぐに着いた。だが彼女にとってはどんなリプライよりも、エリの言葉が沁みわたった。
たったの一時間だったが、その一時はブラックコーヒーの中に溶かした角砂糖のようで、色は変わらないにしても、微かに、確かに、甘くなった。彼女はエリをより好きになった。
そして、飲んだ後に感じる酸味のように、エリが落とした一言が自宅に帰ったあとも彼女の胸中を濁らせていた。
シンクに山積みになっている食器を洗いながら彼女は思い返す。
数年前に比べて何倍にも膨れ上がった仕事量。いつでも笑顔。行きたくない飲み会と潰れる恋人との予定。愛想。そもそも子供が好きじゃないということ。今でも板書中は背中が張り詰めてしまうこと。チャイムが鳴ると開放されたと思ってしまうこと。
300円均一ショップで購入した食器を干す用の籠に、ほぼコンビニで済ませてるはずなのになぜこんなに溜まるのだろうと思いながら、彼女は皿を並べていく。独りぼっちだから皿を立てかける音がやけに響く。
幼いころ、彼女は机の脚に小指をぶつけただけで声を上げて泣いていた。家ならば母親が大丈夫と気にかけてくれたが、学校では嘲笑われるだけだった。だから彼女は常に元気でいないといけない気がしていた。
誰かに両指で無理やり口の端を吊り上げられているみたいな感覚があった。だが、笑った。おかげでバカにされずに済むようになった。いつも元気だねと言われることが増えた。
なんだ、わたし生きていけるじゃん。そう思う日もあった。
あっただけだった。
「わたし全然大丈夫じゃないじゃん。もう、自分のことで精一杯じゃん」
その時彼女の頭には、学年主任の顔が浮かんでいた。何か言われたことに対して彼女が、全然大丈夫ですと返したことがあった。思い返せばその日も全然大丈夫じゃなかった。だが、学年主任の女は現代文の教師の性なのか、全然大丈夫という言葉はないと、彼女を指摘した。端が吊り上がった赤色のフレームの眼鏡をかけたババアだった。
洗い物をしていたため、彼女は涙を拭えなかった。情けなかった。彼女は久々に声を上げて泣いた。
その後、エリが卒業を機に別れを切り出してきて、彼女は受け入れた。
悔いは不思議となかった。
翌年、彼女は離任する教師の紹介で、ユイコ先生は自分探しの旅に出掛けられますと紹介され、会場をざわつかせた。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
