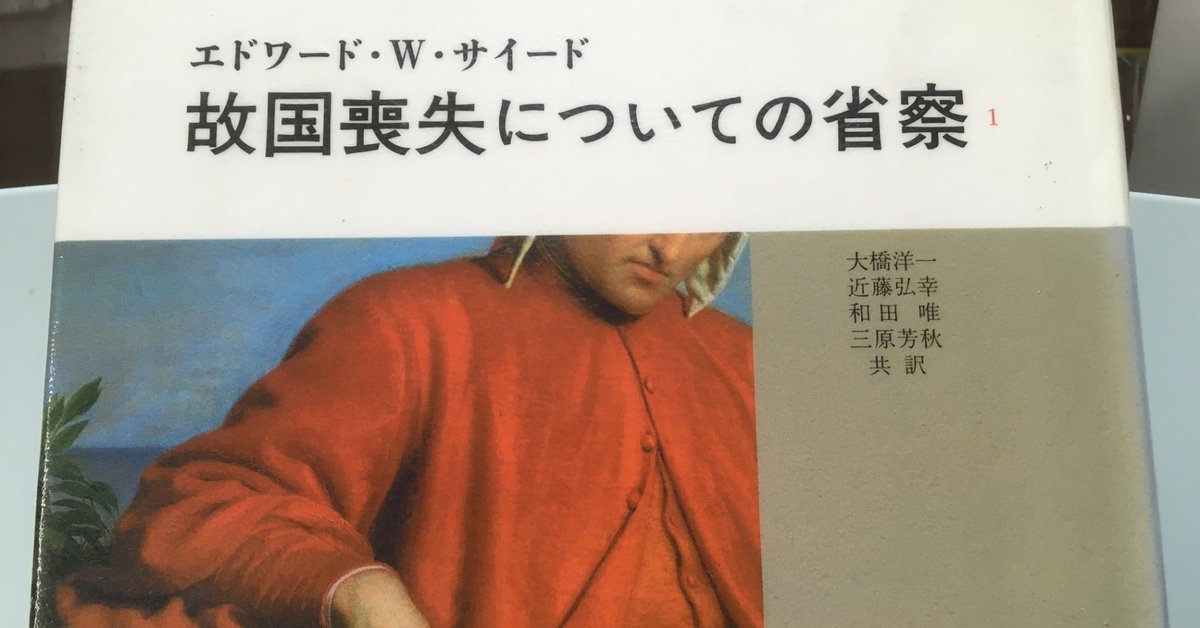
『故国喪失についての省察 1』より〈12 故国喪失についての省察〉エドワード・W・サイード
「故国喪失(エグザイル)は、それについて考えると奇妙な魅力にとらわれるが、経験すると最悪である」という感傷的な一文から始まるこの表題作は、文学作品などで英雄的にあるいはロマンティックに描かれることが多いエグザイルだが、それを経験した者にとっては癒しがたい亀裂と根元的な悲しみにあふれるという矛盾が指摘される。コンラッド、アドルノ、あるいはマフムド・ダルウィッシュの詩などを論じながら、サイードはエグザイルのネガティブな一面を描いたものとして文学を擁護し、同時にそれは説得力のある感情表現となっている。
しかしながら、エグザイルには肯定的な面もあるという。エグザイル状況にいない者は、ひとつの文化・環境・故郷しか意識できないのに比べ、エグザイルは同時存在という意識を持つことができる、と。それゆえ「奇妙な魅力」なのだ。「自分の家でくつろがないことが道徳の一部なのである」とするアドルノ『ミニマ・モラリア』のアイロニーもまた「奇妙」この上ない。
コンラッドの中編小説『エイミー・フォスター』は、東欧出身の農民ヤンコが生きるためにアメリカ移住を夢見て乗った船が難破し、漂着したイギリスの田舎町で異邦人として孤独に死んでいく絶望的な話である。かたや、ジェイムズ・ジョイスは芸術的使命によってエグザイル状態を自ら選び取る。彼の手紙に記される「孤立して友人もいない」状態も、ジョイスは試練として受けとめ理解する。これら極端な例示に対して、サイードは歯切れが良くはない。エグザイルについての「奇妙な魅力」を列記するこの「省察」は、肯定的な側面と否定的な側面を堂々巡りする。明快な結論はない。だからこそエッセイとして面白い。
エグザイルには文字通りの意味と隠喩としての意味がある(『知識人とは何か』)とするならば、その両義性について考えてみたい。『エイミー・フォスター』は、田舎町に「外国から戻ったばかりの私」がケネディという医者から聞いた話という構造をとる。「私」はいわばエグザイル状態から故国に戻ったところである。故国喪失とはいえないが、一度去ったその地に戻ったところで、そこが故郷として居心地がいいとは限らない。一方のケネディはその土地に住み続け、エグザイル状態を知らずにすんできたし、おそらくその後もそうであろう。しかも医者というステイタスを持つ余裕のある状態にいる。両者とも、生活の困窮状態から抜け出すために故国を喪失し異国で孤独死するヤンコに対し、「上から目線」である(ケネディは町では例外的にヤンコに対して同情的であるが)。
語り手の「私」はヤンコに対し、必ずしも態度を明らかにしているとはいえない。では、「私」とケネディの間でヤンコについて語り合うことで、二人はどんな感情を共有しようとしているのか。それも明らかではない。そもそもこの中途半端な立場の「私」とは誰なのか。医者のケネディから話を明かされるということから「私」がある程度の「知識人」であることが想定される。「私」は「知識人」でありエグザイル状態から「故郷」に戻ってきた、居心地が定まらない者として表象される。
おそらくコンラッドの似姿である「私」はエグザイルとして中途半端であるがゆえに、完璧に絶望的なエグザイルであるヤンコを投影することが、説話論的に必要であった。ヤンコは文字通りのエグザイルで、「私」は隠喩としてのエグザイルといえる。そうすると、「私」がヤンコに変異する(不)可能性という主題がみえてくる。その隠された主題を無意識に読むことが、『エイミー・フォスター』を読むということであり、サイードのいう「奇妙な魅力」を感知することでもあろう。
『故国喪失についての省察 1』より
〈12 故国喪失についての省察〉
著者:エドワード・W・サイード
発行:みすず書房
発行年月:2006年4月6日
関連記事
『故国喪失についての省察 2』より〈23 知の政治学〉エドワード・W・サイード
『故国喪失についての省察 1』より〈17 被植民者を表象する━━人類学の対話者たち〉エドワード・W・サイード
『ポスト・オリエンタリズム』〈第1章 亡命知識人について〉ハミッド・ダバシ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
