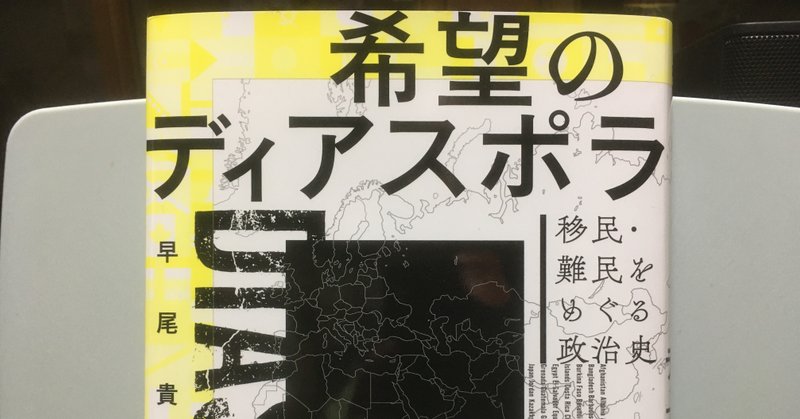
『希望のディアスポラ 移民・難民をめぐる政治史』早尾貴紀
第1章で「難民」と「移民」の差異は自明だろうかと問われる。「純然たる」避難と「不純な」労働という区分けを、私たちは無意識にしている。しかし、「もう故郷では人間的な家族生活をする収入を得るほどの仕事の機会がないというときに、故郷を離れる決断をしたとする。それは「不純」なことなのだろうか」(48ページ)と問われれば、その線引きの力は弱まる。あるいは強制性が強い「難民」と自発的な「移民」という峻別にしても然り。その間にはどちらとも取れる人間の「移動」が無限に存在するのだから。その両義的な越境を、本書では「ディアスポラ」(離散)と呼び、その語彙の歴史的変遷と政治史的なアクチュアリティが吟味され、そこから今日的な意味が照射される。
とりわけ読ませるのが、現代の移民・難民の排斥という、我が国を含む今日の全世界的課題を古代・中世のディアスポラへと遡行する第6章である。地中海世界にひとたび目を向ければ、古代から中東・南ヨーロッパ・北アフリカの間で人の行き来と移住があり、「植民」もあった歴史があり、それはユダヤ人迫害とは別の話である。そもそも「ディアスポラのユダヤ人」という表現は、19世紀シオニズム運動によって人工的につくられたものである。
著者の専門であるパレスチナのディアスポラとクルド人ディアスポラが同根であるとする歴史的・政治的記述の第7章も興味深い。「パレスチナ/イスラエル問題」は、一般には聖書時代からの宗教紛争や、ヨーロッパ近代の反ユダヤ主義が原因として語られるが、それは正しくない。その起源は第一次世界大戦後のオスマン帝国の解体過程におけるイギリスの介入にあるとする解説には目を覚まされれる。
ここで著者は、ディアスポラ化したクルド人とパレスチナ人は、故郷を取り戻すことができるだろうかと絶望的な問いを発した上で、両者の民族主義は、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアといった諸帝国による分断統治に対する「抵抗」として発生した思想と運動である、つまり、ディアスポラとナショナリズムは矛盾しないと述べる。であればこそ「そのナショナリズムは領土主義的な国民国家のみに回収されるものではない」(191ページ)のだ、と。
第8章では、「パレスチナ/イスラエル問題」が宗教対立でも民族対立でもなく、「労働経済」という移住労働問題であるという、現場を目撃した者ならではの視点を提示する。分断・占領・抑圧されているはずのパレスチナ人であるとしても、賃労働のためイスラエルへ日々出入りする姿は決して珍しくないという。
ここまできて序章にたどり着く。イラン出身でアメリカ合衆国在住の批評家であるハミッド・ダバシのモットー、「異郷にいながらもくつろぐこと」「故郷にいながらもくつろがないこと」へ。at home すなわち、「家(故郷)にいる」ことと「くつろぐ」ことの両義性である。故郷にいてそこに完全に同化してしまうことも、異郷にいて一切溶け込まないことも拒否する亡命知識人の取るべき態度として、ここでは紹介される。この言葉に導かれながら私がむしろ交感したいのは、知識人のそれというよりも、「労働経済」によって移動した、それこそ強制性と自発性の意識が当人にもあいまいで、言葉がみつからない、ふと途方にくれる、ある「感情」についてである。
『希望のディアスポラ 移民・難民をめぐる政治史』
著者:早尾貴紀
発行:春秋社
発行年月:2020年1月20日
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
