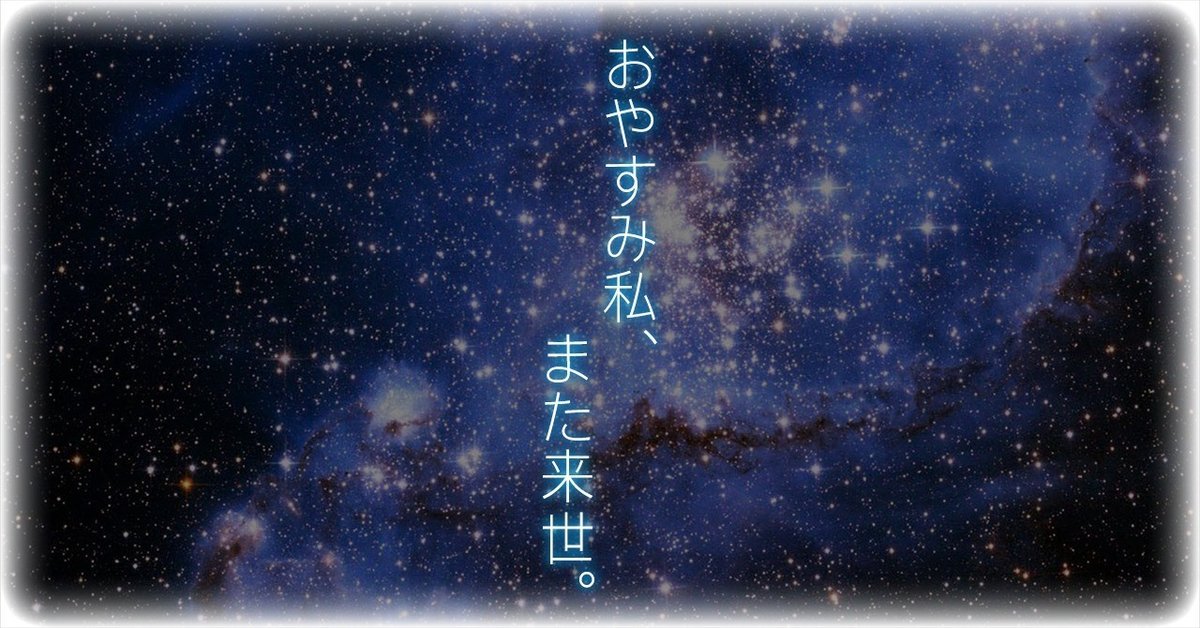
おやすみ私、また来世。 #2
あおり@aoriene・2010/1/6
新しいシングル好き。
「アワーミュージック」が特に好き。
いいね1
神@zinjingin・2010/1/7
相対性理論の作曲じゃないけど確かに良い。
聴けば聴くほど味の出るスルメ曲。
いいね1
┃あおり@aoriene・2010/1/8
┃『アワーミュージック』のリリースイベント、
┃どんなセトリになるのか楽しみ。
┃
┃神@zinjingin・2010/1/8
┃単独ライヴでは観たことないから
┃行こうかな。
僕はSNS上で、彼女のツイートに“いいね”したり、彼女の方から“いいね”されたりしていた。それでも彼女がツイートに言葉で返信することは決してなく、そのつぶやきは相変わらず一方的で、何処か感情が欠如しているようにも思えた。とても細い繋がりではあったが、興味深い彼女との関係性に満足し、そのやりとりが僕の楽しみになっていた。
そんなある日、彼女から僕宛てにDMが届いた。ダイレクトメールなんて、それまでに届いたことがなく何事かと驚いた。たった一文『リリースイベントを一緒に観ませんか?』というものだった。ネット上でのやりとりは頻繁にしていたものの、知らない相手から会おうと誘われたことは初めだった。それとも僕が単に保守的なだけで、世間ではSNSを通じて知らない人間同士が接触するなんてことは、日常的だったのかもしれない。
二〇一〇年三月一三日──相対性理論 + 渋谷慶一郎”名義のトリプルシングル『アワーミュージック』の発売を記念したイベントライヴは、SHIBUYA-AXで行われる。僕が去年の夏に初めて彼らを目にしてから、それまで小さなイベントや競演はしていたものの、本格的なライヴは久しぶりのようだった。もちろん僕はすぐにチケットを取り、彼らの演奏を初めてフォロワーとして聴いてみようと思った。あまり公にヴィジュアルを出さない彼らの姿を、この目で観てみたいという気持ちは強かった。
それまでの彼女のツイートから、彼女が誰かと一緒に何かをすることがあるなんて想像もつかなかった。同じ会場に来ていても、お互い顔を知らないままに観覧し、帰宅したあとに何事もなくネット上で感想を言い合うのだろうと思っていた。それが秘密めいた彼女らしいような気がしていたから、まさか彼女の方からイベントを一緒に観ようという提案をしてくるなんて思いもしなかった。そのお陰で、彼女は本当はネットオカマで、僕をずっと騙していて、最後には何かを売りつけたりするんじゃないだろうかと、余計な心配をすることになった。
あおり@aoriene・2010/1/5
サン・ジェルマン伯爵やジョン・タイターとお友達になりたい。
あおりさんがリツイート
神秘ニュース@sinpinews・2010/2/16
東北の何処か。深い森の奥に別の次元に行くことができるという場所がある。
ただし、帰ってきた者は誰もおらず、謎に包まれている。
編集部では引き続き、この噂の情報提供を求めている。
あおり@aoriene・2010/2/20
久しぶりの単独ライヴ楽しみ。
いいね1
──当日の待ち合わせはSHIBUYA-AX。開場の一時間も前に到着した僕は、正直時間を持て余していた。妙な緊張を感じながら僕は辺りを伺う。入口の前には、すでにたくさんの人たちが、イベントのはじまりを待っていた。僕と同じくらいの年代の男女が多かったが、一人であろう三〇代くらいの男性も目についた。ブレイク直後のバンドなだけあって、その筋の目利きの客も多いのかもしれない。
彼女は学校の制服で行くと伝えてきたので、僕はそれらしい姿を探してみるが一向に見当たらなかった。ひょっとしたら、すでに彼女だという人物はすでに到着していて、物陰から僕のことをじっと観察しているのかもしれない。やはり“あおり”なんていう人物は存在せず、架空の女子高生の虚言に引っかかった僕を、何処かから面白可笑しく嘲笑っているのかもしれない。僕は少し軽率だったかもしれないと、今更になって後悔した。
隣りにいたデザイン専門学生風の男が、連れの女の子に相対性理論についてコアな話をしていた。どうやら同じコンポーザーが手掛ける、別のアーティストの話をしていたようだが、ヴォーカル以外のメンバーの名前もはっきり記憶していない初心者の僕には、その熱心なフォロワーたちの話は半分も理解できなかった。ただ、これから更にバンドが盛り上がっていくだろうという勢いは十分に伝わってきた。かつて僕の母親が聴いていた渋谷系の音楽シーンも、こんな感じだったのだろうか。
──フリッパーズ・ギターの熱狂的なフォロワーの母親は、バンドが解散してからもう二〇年近くが経つというのに、それぞれがソロ活動を続ける今も彼ら追い続けていた。幼い頃から母親の好きな音楽を聴いて育った僕も、多少なりともその影響は受けていた。だから今でも、母親とは最近の音楽の話をすることができた。
初めてのフェス参加で勝手がわからないし、どうせ彼女もいなくて暇なんでしょ──ある日、母親が僕をフェスに誘った。何も言い返せないまま、僕はそれを承諾した。
そのWorld Happinessという音楽フェスは、YMOが一九九三年の再生以来、実に十数年ぶりのHASYMO名義ではない、本来のYellow Magic Orchestraの名で出演するということで、開催前から各方面で話題になっていた。世代的にハマっていない僕であっても、YMOがどれだけ日本の音楽シーンで神格化されているのかぐらいは知っている。どうやら母親は、そのYMOよりも、サポートとして元フリッパーズ・ギターの小山田圭吾が出演をするのを目当てにしていたようだった。会場も都内で近かったし、親孝行のつもりで付き添うことにした。
そこで僕は、相対性理論というバンドに耳を奪われた。ポストYouTube時代のポップ・マエストロと言われる彼らの音楽に、新しさの中に懐かしさも感じた。どこかとぼけた不思議な歌詞と、口ずさみたくなるポップなメロディ、か細くも良く届くその声に惹かれた。本人たちの意向で、会場のモニタに彼らが映し出されることはなかったが、僕はすぐにネット検索し、相対性理論が出しているCDをその場で全て購入した。それから彼らの情報を集めるうちに、僕は彼女に行き着いた。
──すでに開場し、長く続く待機列が作られていた。オールスタンディングの公演は、チケットに記された整理番号の順に早く入場することができる。初めての単独イベントに参加ということもあり、前の方で観たい気持ちもあったが、B793という良くないチケットを持つ僕には、それは叶わないことだった。
長々と待機していた列が、次々と会場に飲みこまれていく。僕はなかなか現れない待ち人に、やはり騙されたのかもしれないと思い始める。一人、列の流れに逆らい、会場に背を向けてそれらしい人物がいないか目を凝らす。
──制服姿の女の子が会場前の坂を上り、近づいて来るのが見えた。僕はそれをじっと目で追う。彼女がそうなのかもしれない。そして、そんな僕の視線に気づいた彼女は、何の躊躇もなく、僕の目の前まで来ると、「──あおりです」と名乗った。
お互い自己紹介もそこそこに、慌ただしく彼女と会場に続く列の最後尾に並ぶ。僕が「ジンです。折原神です」と名乗ると、彼女は「──お互い真名だったんだ。それに既視感すごくある」と言った。その言葉を信じるのなら、どうやらハンドルネームと思っていた“あおり”は彼女の本名のようだった。
──熱気に包まれたフロアは七割方埋め尽くされていた。僕らはどちらからということもなく、ドリンクコインをそれぞれ飲み物に引き換えると、ステージの前方は目指さずに、フロア最後方の壁に背をつけた。わかってはいたけれど、あまり他人とのコミュニケーションが得意でない僕が、こうして初めて会う人と二人で居ることが落ち着かない。
僕はプラカップのビールを一気に煽り、喉を潤して彼女に話し掛けた。
「──すぐにわかった?」
彼女が真っ直ぐに僕の目の前に来て、自分の名前を名乗ったことを訊いた。
「うん。私、そういうのわかるの」
言葉足らずだったにも関わらず、彼女は僕の問いに応えてくれた。
「それは何か、霊的なものだったり?」
「霊かどうかはわからないけど、特殊な力──人の考えてることがわかったり、普通は見えないものが見えたりする」
「そうなんだ」
それが事実であるかはどうであれ、僕はそんな能力があるという人間に会うのは初めてだった。僕は科学で解明できない物事を否定も肯定もしない。ただ、オカルトに興味はある方だし、実際に自分の目で確認することができるなら、霊の存在もすんなり受け容れると思う。
「──でも、あれだけきょろきょろしてれば誰でもわかるよ」と、彼女は少しだけはにかんだ。そして、その笑顔を隠すようにして、彼女は両手を添えたペットポトルから水を一口飲みこんだ。
僕はそんな彼女を目にして安心していた。ネット上に自撮り画像の一枚も上げなかった彼女が、本当に実在するのか半信半疑だった。
紺のブレザーに赤いネクタイ、緑のタータンチェックのスカートの制服──どこの制服かはわからなかったが、彼女に良く似合っていた。小柄なせいか、背中に広がる茶色がかった髪の毛が、とても長く見えた。ネット上と変わらないため口も、年の割に落ち着いたその雰囲気から嫌味を感じさせなかった。それまで彼女の姿を想像することはできなかったが、こうして目の前にしてみると、ここに居るこの娘が、あの不思議なツイートをした本人だと納得する。そして、素直に可愛いなと思ったのは、そんな言動のギャップからだけではなかったことに、僕はすぐに気がついてしまった。
開演を待つ間のSEが流れる中、僕はただ彼女の傍に居るだけだった。色々と訊いてみたいこともあったが、秘密主義者である彼女が、それに素直に応えてくれるとは思えなかった。
「──今日で観るのは何回目?」
「まだ一〇回くらい。観れるのなら全部観たいけど、東京から離れると金銭的にちょっと厳しい」
「まぁ、そうだよね、学生だもんね──今、学校は春休みじゃないの?」
「来週から。今日は学校に用事があったから」
「だから制服なんだ」
いくつかそんな他愛のない質問をした。それに対して彼女は、感情の起伏もなく、まるで義務のように淡々と応えてくれた。しばらくすると、やくしまるえつこ本人のアナウンスが流れ、ライヴが始まった。すると彼女は目を輝かせて、ステージに見入った。それは何処にでもいる同年代の女の子と変わらないように見えた。
渋谷慶一郎の心地良いピアノが流れる中、僕の視線はステージに半分あり、残りの半分かそれ以上は、彼女の横顔にあった。
終演後、僕らはすみやかに会場を出た。後ろの方で観ていたお陰で、割とすぐに場外へ出ることができた。辺りはすでに暗くなっていた。
これからどうしようと思案する僕を横目に、彼女はたった今聴いていた曲を小さく口遊んだ。始まる前とは打って変わって、ご機嫌な様子だった。確かにすごく良いライヴだった。今回はコラボレーションライヴということで、いつもとは違うセットリストのようだったが、元々の楽曲の力と演奏の心地好さに満足した。そしてこの日の公演が、それ以降は演奏されない楽曲の貴重なライヴになるということに気がつくのは、かなりあとになってのことだった。
そして彼女は、何かを思い出したように僕の方に向き直ると、黒目勝ちの大きな瞳で真っ直ぐに僕を見つめた。
「──そうだ。ジン君、私の秘密結社に入らない?」
その眼差しは、光さえ吸い込むブラックホールのように、有無を言わさない力強さに溢れていた。僕は彼女に捕らえられ、その視線を外すことができなかった。そしてそれが、僕が宇宙の秘密に触れる、はじまりの言葉になった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
