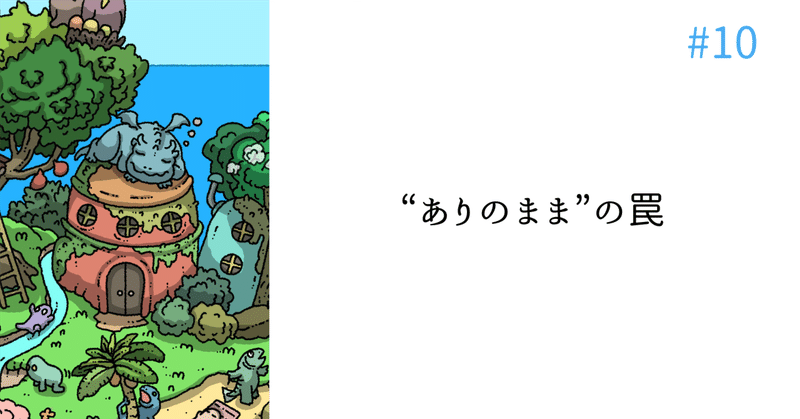
【期間限定全文無料】#10 “ありのまま”の罠
“ありのまま”
教育現場にいる時、この言葉を聞くことは多いのではないでしょうか?
“ありのまま”は、人の“よい姿”として表現される時に使われることの多い言葉だと感じています。
しかし、この“ありのまま”という言葉は、どのように“よい教育”の中で位置付けることができるのでしょうか?
こちらのnoteでは、「先生にとっての“ありのまま”」をテーマにして文章を綴っていきます。(1800字程度の短めの記事になっています!)
先生は、『先生』としてではなく、『1人の人』として生徒と接することが大切だ。
これは、無花果として大切にしている考え方の1つです。
“よい教育”の定義から辿ると、先生自身が「自身の自由」を大事にすることが大切なことは自明です。
だからこそ無花果では、『1人の人』として生徒と接するようにしよう!という言葉を先生間での共通言語にしているのですが、この言葉が持つある意味での「危険性」に気がつきましたので、その「危険性」にこのnoteでは触れていきます。
“ありのまま”で抜け落ちてしまいがちなもの
「しんどいから、生徒の話を今は聞きたくない。」
と
「先生として、生徒にとって“よい存在”で在りたい。」
これらはどちらも、先生の中で確かに生まれ得る想い。
だけど、1人の人間としてありのままにって話になると、前者だけの気持ちに従うのが大切なのかって考えてしまいがちになる。
これが“ありのまま”という言葉を使うときに抜け落ちてしまいがちなものの結論だと感じています。
(このお話は、以下の#8で簡単に触れさせていただきました!)
例えば、先生として生徒と関わっていると、
「自分は先生だから今この子とお話をしているけど、もし先生って立場じゃなかったら、お話を聞きたいと思っていないだろうな…。」
などと感じてしまう瞬間は、先生も人間だからこそきっとあるのではないかと思います。
そう感じている時に、頭をよぎる「ありのまま」という言葉。
「ありのままに子どもと接するなら、自分は生徒の話を聞きたくないって伝えるのではないか、それがいいのかな…。」
このように感じてしまう瞬間を、想像できる方も多いのではないでしょうか?
結論で述べた通り、ここで抜け落ちてしまいがちなのが、
「先生として、生徒にとって“よい存在”で在りたい。」などという想いです。
「自分は先生だから今この子とお話をしているけど、もし先生って立場じゃなかったら、お話を聞きたいと思っていないだろうな…。」
こう感じてるのも自分だし、
「先生として、生徒にとって“よい存在”で在りたい。」
と感じているのも自分。
どちらも確かに自分が感じていること。
このどちらの想いをも大切にして生徒と接することこそ、無花果で大切にしている『1人の人』として生徒と接するということです。
「ありのまま」という言葉は、「ある自身の感じていること」を見つけやすくする反面、「また別の、ある自身の感じていること」を見にくくし得る。
この“ありのまま”の罠に自覚的であるからこそ、実践していける“よい教育”がありますので、今日はその罠についてまとめてみました。
あなたにとっての何かの発見になっていましたら幸いです!
ちょこっと余談 〜そもそも“ありのまま”って存在する?〜
ここからは少し余談ですが、そもそも“ありのまま”ってなんなんでしょうか?
現象学的に考えると、「“ありのまま”を存在するものとして、それを見つけようとする」という態度は現象学的態度とは言えません。
「“ありのまま”を存在するものとして、それを見つけようとする」
と
「これこそが“ありのまま”って自分が最も感じる瞬間を探す…」
の差。
この差に自覚的であることは、“よい先生”の土台として大切なことです。
現象学については以下のnoteでまとめていますので、よろしければご覧ください!
“よい先生”の在り方に関しても以下にまとめていますので、まだ読まれていない方はぜひご覧ください!
以上で本日のnoteは終わりになります!
このような“よい教育”に関する記事を毎月1万字程度で執筆中ですので、よろしければ以下よりメンバーシップにご加入いただけますと嬉しいです!
(初月無料なのでぜひお気軽に!!)
ではまた次回のnoteでお会いしましょう!!
「スキ!♡」は誰でも押すことができますので、この投稿を「素敵だな!」と感じてくださった方は、ぜひ気軽に押していただけますと嬉しいです!
(フォローもいただけると、めちゃくちゃ喜びます!)
「いちじくlabo」のメンバーシップ加入は以下からできますので、ぜひよろしくお願いいたします!
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
