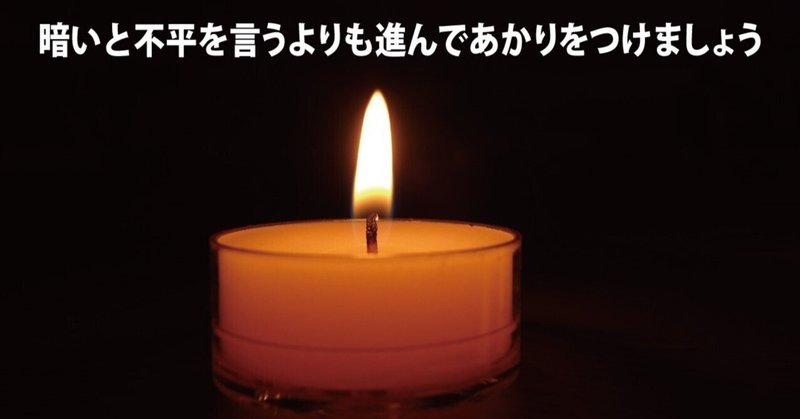
暗いと不平を言うよりも・・・
「心のともしび」というカトリック布教番組
ときどき思い出す言葉がある。それは「暗いと不平を言うよりも進んであかりをつけましょう」。記憶にあるのは、子どもの頃にテレビ番組で流れたナレーションだ。内容は覚えていないが、この言葉だけは残っている。
子どもの記憶だから曖昧だが、週末早朝の15分ほどの番組だったような気がする。調べてみると、宗教法人「カトリック善き牧者の会」による「心のともしび」というタイトルのカトリック布教番組だった。
1966年から日本テレビ放送網で流され、ラジオ番組もあったようだ。その番組のスローガンが先ほどの言葉だ。何度も耳にしているうちに、子どもだった僕の頭に刷り込まれた訳だ。それがときどきひょいっと顔を出す。
不平が集団の力になると、攻撃の対象を探し出す
出元がわかったところで、言葉の意味を考えてみよう。人生というのは思い通りにならないことの方が圧倒的に多い。そんなときに不平が口をつく。今年の猛暑のように、言っても仕方ないと思いながらもつい出てしまう。
不平がすべて悪いわけではない。一種のガス抜き効果がある。仕事帰りに飲み屋で「ああだ、こうだ」と言って酒を飲むのもガス抜きだ(最近は見かけなくなったなあ)。しかし、厄介なことに、不平は伝播すると力を持つ。
さらに不平の力が集団になると「みんなが言っているから正しい」が生まれる。「あいつが悪い、こいつのせいだ」と糾弾の声が上がり始める。集団の力学は、不平を作り出していると思える誰かや何かを攻撃の対象とする。
不平は小さなうちに自分ごとで解消する
力の制御が不全に陥ると、後半の「進んであかりをつけましょう」は意味をなさなくなる。「誰かがつけてくれるのが当たり前」になるわけだ。つまり、起きていることが、自分ごとではなく、他人ごとになってしまう。
多くの不平の背後には億劫な気持ちが潜んでいる。後回しをしてるうちに、小さな不平がどんどん大きくなっていく。わかっていながら、自分でそうしているのだ。不平は小さなうちに、自分ごとで解消するに限る。
僕はイライラしたときには場所を変える。そこで深呼吸するだけで気持ちが落ち着く。リセットすると、「すぐにできることなら、すぐにやる」「できなければ、誰かに頼む」「どうしようもないことは、きっぱり諦める」。
他人の不平を受け止める「不平の聞き役」になる
僕には上手にできないが、他人の不平を受け止める人がいる。どういうことかというと、「不平の聞き役」になるのだ。効果は大きい。誰かに不平を聞いてもらっているうちに、大したことはないと思えてくるから不思議だ。
不平を取るに足らないと一蹴するのはいいが、何の解決にはならない。「進んであかりをつけろ」というのも逆効果だ。不平の要因に本人が気づくことの方が大事だ。自ら気づけば、先ほどのようにリセットできる。
子どもの頃の記憶から妙な話になってしまったが、まずは不平を自分ごとで片付ける。できれば、不平の聞き役になる。そんなことが大事だと思う。「暗いと不平を言うよりも進んであかりをつけましょう」いい言葉だなあ。
こちらもお読みいただければうれしいです
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
