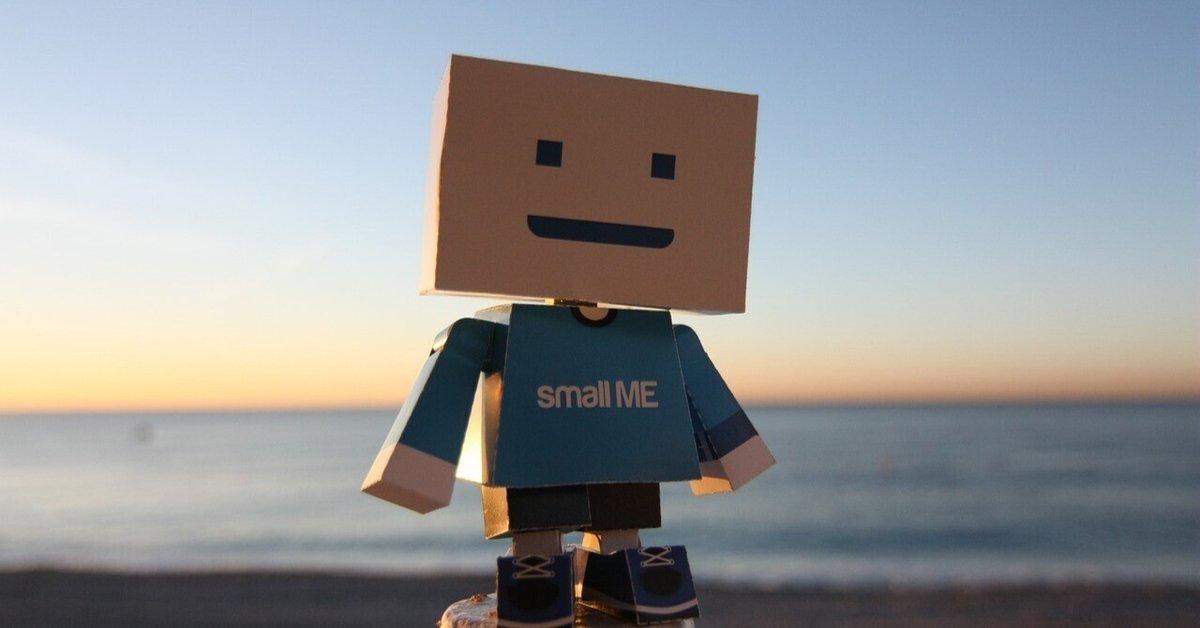
当事者意識を持ったチームづくり
「当事者意識って何だろう」と考えた一日
休み前の昨日は社内で仕事、何やらわさわさとした一日だった。朝から原稿や資料の作成、連絡業務に追われた。連絡はメール、Fbメッセンジャー、Slackがほとんど、電話は本当に少なくなった、来るのは営業ばかりだね。
今日は「おおっ」というようなうれしい知らせ、「うん?」と首をかしげるような連絡もあった。いくつかの連絡から感じたのは「当事者意識」だ。と書きながら「当事者意識ってなんだろう」・・・これがなかなか難しい。
起きていることに自分もかかわっているという意識
僕が当事者意識を考えるようになったのは『「当事者」の時代』(佐々木俊尚著)という本を読んでからだ。お読みいただければと思うが、多くの学びと同時に心の痛みを感じる一冊だ(とくに西口バス放火事件のところ)。
当事者意識には「相手がどう感じるのかを察知する」という気遣い的な面もあるが、実はもっと奥が深い。「起きている(あるいはすでに起きた)ことに自分もかかわっているという意識」・・・これが当事者意識の本質だ。
「他人ごと」ではなく、「自分ごと」にとらえられるか?
人によって当事者意識のとらえ方はさまざまだが、シンプルにいうと「他人ごと」ではなく「自分ごと」にとらえられるかだ。といっても、別に非難することでもない。「ああ、そういう人なんだ」で済ませればいいだけだ。
でも、仕事となると、結構厄介なことだね。どうしたら当事者意識を持ったチームがつくれるか。経営者やリーダーなら、ここは悩むところだ。これまでの経験では、当事者意識の強いチームや組織はブランド力が強い。
主語を自分にして話す文化が当事者意識を育てる
当事者意識の強いチームや組織に共通しているのは、主語を自分にして話す文化だ。「私はこれをやりたい」「これはこう思う」・・・こんな風に経営者自身が、自分を主語にして語り合うことで当事者意識は育っていく。
読んだ本のことや誰かに聞いた話を語る人がいる。そのこと自体は悪いことではないが、内容が咀嚼できていないと本や人物が主語になる。「○○○と書いてあった、□□□といっていた」・・主体がない話は共感を生まない。

多様な意見が飛び交うことで、当事者意識が育っていく
経営者がこうした借り物の内容を語っていたらダメだ。社員は本気にしない。どうせ、自分には関係ないと思う。自分を主語にして話すということは、自分の考えをまとめることにつながる。
稚拙と思われてもいいじゃないか。自分の言葉で思いを込めて語ることだ。社長が自分を主語にして語れば、社員は自分ごとで考え、自分を主語にして返してくる。多様な意見が飛び交うことで、当事者意識が育っていく。
こちらもお読みいただければうれしいです
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
